| |
|
|
| |
農経しんぽう |
|
| |
令和7年10月13日発行 第3571号 |
|
| |
|
|
| |
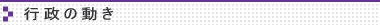 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農業サービス事業の普及拡大へ/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は、ドローンの作業受託やスマート農機のシェアリングなどを行う農業支援サービス事業の普及拡大を図る。現在、執行中の令和6年度補正予算では、「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業」に100億円を投入、8年度予算では9億8000万円を概算要求するなど対策を強化している。農林水産省では、同事業により、特に地域のニーズ調査やドローン、スマート農機などの現場でのデモ実演、機械オペレータの育成、サービスの品質確保に向けた「標準サービス」の策定などに定額支援し、推進していく方針。今年9月には「農林水産航空・農業支援サービス協会」(農サ協)が発足(6日付既報)するなど、体制整備も進み、取り組みが加速しそうだ。
「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業」は、農業者の高齢化・減少が進む中においても農業の持続的な発展を図るため、農業支援サービス事業者の人材育成や活動の促進、サービスの提供に要するスマート農業機械等の導入などの取り組みに対して支援するもの。
「農業支援サービス事業育成対策」では、サービス事業の立ち上げ当初のビジネス確立や事業拡大の際に必要となる、地域のニーズ調査や現場でのデモ実演、機械オペレータなどの人材育成等に必要な経費を支援(定額)。「スマート農業機械等導入支援」では、機械作業受託等のサービスの提供に必要となるスマート農業機械等の導入に必要な経費を支援(2分の1以内)する。
「農業支援サービスの土台づくり支援」として、サービスの標準的な作業工程や作業精度等を定めた「標準サービス」の策定等を支援(定額)する。
「標準サービス」については、現在、ドローン散布、水稲収穫作業において検討が進んでいる。今後、サービスの質の向上を推進するため、「標準サービス」に基づいた認証制度も視野に検討されている。
農林水産省では、サービス事業を(1)専門作業受注型:播種や防除、収穫などの農作業を受託し、農業者の作業の負担を軽減するサービス(2)機械設備供給型:機械・機具のリース・レンタル、シェアリングにより、農業者の導入コスト低減を図るサービス(3)人材供給型:作業者を必要とする農業現場のために、人材派遣等を行うサービス(4)データ分析型:農業関連データを分析して解決策を提案するサービス―の4類型に分類している。
特に、専門作業受注型は高度な技術提供と人材供給の面から注目している。取り組み事例として、JA新すながわのドローン防除・追肥・直播、オヤマ・アグリサービス(精米事業者)の耕起・田植え・収穫などをあげている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
「みどり脱炭素海外展開コンソーシアム」セミナー開催/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は9日、都内の同省7階講堂にて「みどり脱炭素海外展開コンソーシアム」第1回セミナーを開催した。
同コンソーシアムは、我が国が有するGHG(温室効果ガス)排出削減技術の海外展開を後押しする「農林水産分野GHG 排出削減技術海外展開パッケージ(通称:MIDORI∞INFINITY)」の実行ツールとして、6月に設立。日本企業と国内外のパートナーとのマッチングを図り、二国間クレジット制度(JCM)にもつながる脱炭素プロジェクトの形成を推進していく。10月9日現在、(株)クボタ、ヤンマーアグリ(株)、井関農機(株)といった農機メーカーをはじめ、農研機構や農林中央金庫等の関係機関・金融機関・スタートアップなど105の構成員が参画している。
設立後初となる本セミナーは、構成員間のマッチングを図ることで案件形成を促進し、11月のCOP30などに向けた機運を高めるため、直近の政策動向や構成員による関連取り組みが紹介された。
冒頭、農林水産省大臣官房技術総括審議官兼農林水産技術会議事務局長の堺田輝也氏が挨拶。参集した大勢の構成員に謝意を述べ、この分野への関心とコンソーシアムが果たす役割への期待が高まっていると説明。主役は脱炭素化と食料安保を両立させるイノベーションを有する民間企業だと述べ、本日が新たなビジネス展開を創出する機会になり、農林水産分野の脱炭素技術の国際展開を後押しすることを祈念するなどと語った。
その後、セミナー趣旨説明を経て、(1)今秋の主な政策動向(2)農業分野の金融資金の増大に向けた金融機関の取り組み(3)COP30に向けた動向と当面の取り組み―の3セッションが行われた。
(1)のうち、農林水産省輸出・国際局国際地域課の米田立子課長は「日ASEAN間での脱炭素関連の取組」を紹介した。みどり戦略を通じて日本が有する技術を活用し、ASEANの食料安全保障に貢献する「日ASEANみどり協力プラン」について、今年改定した内容として、GHG削減技術(水田の推移モニタリングなど、JCM活用も視野)や、民間企業によるスマート農業技術の普及(高機能バイオ炭、農協のDX・GX化及びバリューチェーン連携支援)などの新規プロジェクトが追加されたと説明。
今後の日ASEAN連携では、Win―Winとなるビジネス展開を支援していくとし、官民学の効率的な連携を図り、我が国発の社会イノベーションを巻き起こしていくなどと語った。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
前年比63万4000t増/農林水産省・令和7年産水稲の予想収穫量 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は10日、令和7年産水稲の作付面積及び9月25日現在の予想収穫量を公表した。それによると、生産者が使用しているふるい目幅1・85ミリ、1・90ミリ等ベースの予想収穫量(主食用)は715万3000トンで、前年産に比べ63万4000トン増加と見込まれる。前年産に比べ作付面積が10万8000ヘクタール増、単収が5キロ増となったことから、予想収穫量は平成29年以来、最高となる見込み。
令和7年産水稲の作付面積(青刈り面積を含む)から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた主食用作付面積は136万7000ヘクタールで、前年産に比べ10万8000ヘクタール増加が見込まれる。これは、新規需要米や備蓄米などからの転換等があったため。
9月25日現在における全国の10アール当たり予想収量(生産者が使用しているふるい目幅ベース)は、524キロ(前年産に比べ+5キロ)と見込まれる。これは、一部地域で5月上旬から6月中旬にかけての気温や日照時間が前年を下回る地域があったものの、多くの地域で総じて天候に恵まれたため。
これを地域別にみると、北海道においては6月上旬までの日照不足により全もみ数がやや少なくなったことなどから、550キロ(前年産に比べ△12キロ)と見込まれる。北海道と沖縄県を除く各地域では、6月中旬までの低温、日照不足により、東北、関東等では穂数が少ない地域がみられたものの、6月下旬以降おおむね天候に恵まれ、多くの地域で全もみ数が前年以上に確保された。東北は556キロ(同±0キロ)、北陸は516キロ(同+6キロ)、関東・東山は524キロ(同△5キロ)、東海は493キロ(同+19キロ)、近畿は504キロ(同+16キロ)、中国は516キロ(同+18キロ)、四国は489キロ(同+18キロ)、九州は479キロ(同+13キロ)と見込まれる。
主食用作付面積に10アール当たり予想収量(生産者が使用しているふるい目幅ベース)を乗じた予想収穫量(主食用(生産者ふるい上米))は715万3000トン(前年産に比べ63万4000トン増加)と見込まれる。
新たな指標である全国の作況単収指数(前年産までの5カ年中3年平均)は102、前年産比は101と見込まれる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
食料自給率38%で前年同/農林水産省・令和6年度食料自給率 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は10日、令和6年度食料自給率について公表した。6年度のカロリーベース食料自給率は前年度と同じ38%、生産額ベース食料自給率は前年度に比べ3ポイント高い64%となった。また、今年度から併せて公表された摂取熱量ベース食料自給率は同1ポイント高い46%となった。
食料自給率は、長期的に見ると、米の消費が減少する一方で畜産物や油脂類の消費が増大する等の食生活の変化により、低下傾向が続いてきたが、2000年代に入ってからは概ね横ばい傾向で推移している。
6年度の結果について同省の見解は次の通り。カロリーベースについては、米において主食用米の消費量が増加したこと及び、砂糖において、国産テンサイ・サトウキビの生産量が増加し産糖量が増加したことがプラス要因となる一方で、小麦の単収減少により生産量が減少。この他、大豆、野菜、魚介類の生産量も減少したことがマイナス要因となり、前年度並みとなった。カロリーベース38%は4年連続となっている。
生産額ベースについては、国内生産額の増加により、前年度比増の64%となった。特に、米、野菜、畜産物の国内価格上昇に伴い、それらの国内生産額が増加した。生産額ベースは4年度の58%を底として、2年連続で上昇している。
摂取熱量ベースの食料自給率は、平時において国民の日常生活に必要な摂取熱量のどの程度が国産で賄われているかを示す指標で、7年食料・農業・農村基本計画で設定された。「1人1日当たり国産供給熱量÷平時における国民の日常生活に必要な摂取熱量(1850カロリー)」で計算し、6年度は860カロリー÷1850カロリー=46%となった。
一方、飼料自給率については前年度より1ポイント下落して26%となった。輸入飼料による畜産物の生産分を除かない食料国産率については、カロリーベースが47%、生産額ベースが69%となった。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
井関農機・タイショーなど3件認定/農林水産省・基盤確立事業実施計画 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は9月26日、みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画を認定し公表した。今回計画が認定されたのは(1)井関農機(株)及び(株)タイショー(2)OATアグリオ(株)(3)(株)WAKUの3件。井関農機及びタイショーの、可変施肥が可能な直進アシストトラクタ及び高精度ソワー、OATアグリオの養液土耕栽培システムは、みどり投資促進税制の対象機械に追加された。また、今回の認定により、累計97事業者の事業計画が認定された。認定計画の概要は次の通り。
▽井関農機・タイショー=営農支援システム「ザルビオ」を活用し、生育データに基づく可変施肥が可能な直進アシストトラクタ及び高精度ソワーの普及拡大を図る。これらは化学肥料の使用低減に寄与。両社で連携し、パンフレットの作成や現地説明会の開催、展示会への出展を実施する他、井関農機が運営するポータルサイト「Amoni」による農業者への情報発信を行う。計画実施期間は7年9月〜11年12月、みどり投資促進税制の対象機械に追加。
▽OATアグリオ=土壌の養分や水分量に合わせて自動で潅水施肥を行い、化学肥料の使用低減に寄与する養液土耕栽培システムを普及拡大。製品の普及拡大に向けて、地方自治体の農業試験場等と連携して、作物や地域に合わせたマニュアルを整備。また、全国の営業所でのフォローアップ体制の構築、契約代理店との連携による拡販活動やシステムメンテナンスを実施するほか、展示会への出展や自社試験農場等で見学会を実施する。計画実施期間は7年9月〜12年3月、みどり投資促進税制の対象機械に追加。
▽WAKU=植物の成長促進効果があるグルタチオン含有肥料及びグルタチオン含有有機質肥料を安価に製造する方法を開発するとともに、化学肥料の使用低減と収量向上を両立させる施用方法を開発する。計画実施期間は7年9月〜12年8月。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
令和8年度農林予算概算要求をみる③/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は8月29日、令和8年度農林水産関係予算概算要求を取りまとめて公表した(既報)。「米の需要に応じた増産実現予算」と銘打ち、令和7年度より3882億円(17・1%)増の2兆6588億円を要求。なかでもスマート農業技術の開発や活用への期待は高く、スマート農業技術活用促進集中支援プログラムは前年度比124億2800万円増の大幅な増額要求となっている。ここでは「Ⅱ 農業の持続的な発展」の項に関連した主要事業概要のうち、特にスマート農業に関係の深いものをピックアップする。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
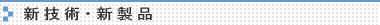 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
大型アッパーローター発売/松山 |
|
| |
|
|
| |
松山(株)(松山信久社長・長野県上田市塩川5155)は、アッパー回転とスクリーンの効果で二層構造の土づくりが可能な大型アッパーローター、BURシリーズとDURシリーズをモデルチェンジ、20シリーズとして、BUR20シリーズは12月、DUR20シリーズは11月から新発売する。50〜100馬力対応のBUR20シリーズと、北海道専用で100〜170馬力対応のDUR20シリーズの2機種をラインアップ。従来機と比較して耐久性と使いやすさが向上している。
BUR20シリーズは、フランジ爪タイプのBUR2020U(作業幅2・0メートル)、2220U(作業幅2・2メートル)、2420U(作業幅2・4メートル)の3型式に加え、ホルダー爪タイプで畝立て仕様のBUR2220H(出荷時3畝立て仕様)の4型式をラインアップ。対応馬力は50〜100馬力。
今シリーズより、フランジ爪は従来モデルより板厚と幅を広くした新型爪A301Gを採用、耐摩耗性が向上。また、土の付着を抑える均平板下部のアンダーステンはボルト留めを採用し簡単に交換できることに加え、板厚も1・5倍となり耐久性が向上している。更に、均平板らくらくアシスト採用で均平板持ち上げ時の負担を50〜70%軽減した他、耕うん軸のチェーンケース側につなぎ軸を採用したことで、メンテナンス性能が向上している。
装着方法はJIS標準オートヒッチの4L/3L/0Lを採用。また、フランジ爪タイプではマストがハイトップ仕様の2Lを用意し、車高の高い大型トラクタにも対応している。
北海道向けのBUR20シリーズは、全型式フランジ爪タイプとなっており、BUR2020U=作業幅2・0メートル、2220U=作業幅2・2メートル、2420U=作業幅2・4メートル、2620=作業幅2・6メートル、2820=作業幅2・8メートルの5種類の作業幅を用意。外爪タイプ(爪両端が外向き)の標準仕様に加え、作業幅2・0/2・2/2・4メートル幅には内爪タイプのU仕様を用意している。作業幅2・6/2・8メートル幅にはリアサブソイラー付きのR仕様を用意し、顧客のニーズに合わせて選択できる充実の10型式をラインアップ。
BUR20シリーズの対応馬力は50〜100馬力となっている。従来機より採用のリアサブソイラー付きのR仕様では、作業機後方に取り付けたリアサブソイラーにより、砕土作業と同時に硬盤破砕を行い、圃場の排水性を高める。
装着方法は作業幅2・6メートルまでの型式はJIS標準オートヒッチの4L/3L/0Lと2点クイックヒッチの2Lを用意。BUR2820とR仕様は2Lを用意。発売は12月。
北海道専用となるDUR20シリーズはDUR2820(作業幅2・8メートル)、DUR3020(作業幅3・0メートル)、DUR3320(作業幅3・3メートル)、DUR3620(作業幅3・6メートル)の4種類の作業幅に、それぞれリアサブソイラー付きのR仕様を用意した8型式をラインアップ。対応馬力は100〜170馬力。
DUR20シリーズにおいても、耐摩耗性が向上した新型爪(BA121G)を採用。更に、100馬力に対応するためミッションギアを強化、PT0は1000回転仕様となっていることに加え、チェーンケースの重みに対して左右のバランスをとるためのカウンターウエートを標準装備するなど、安定した作業を行う機能を装備している。
装着方法は2点クイックヒッチの2L仕様を採用。ハイトップ仕様のマストはCAT2/3兼用仕様となり、大型トラクタに対応する。11月発売。
なお、BUR/DURシリーズともに作業幅2・4メートル以上の型式には、公道走行部品付型式(型式末尾Z)を用意している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
新型クランプ「T―Earth」を発売/タカミヤ |
|
| |
|
|
| |
(株)タカミヤ(高宮一雅社長・大阪府大阪市北区大深町3の1)は、高張力軽量パイプの安全基準をクリアした新型クランプ「T―Earth」(以下、T―Earth)を開発。10月1日より同社の機材委託サービス「OPE―MANE(オペマネ)」で取り扱いを始めた。クランプとは足場のパイプ同士やパイプと鉄骨を連結・固定する金具のこと。各種の建設、農業用ハウスや農機の格納庫の組み立て時にうってつけの部材である。
T―Earthは、ボルトが突き出さない構造とパイプを安定して保持し、荷重や振動でもずれにくい業界最高水準の滑り止め性能を持つ。これにより作業者がボルトに接触することや、足場が変形することによる事故リスクを低減し、作業者の安全と負担軽減に寄与する。
クランプは建設現場では不可欠な部材だ。しかしこれまで「壊れたら買い替える消耗品」という扱いが一般的だった。そして新品のクランプは、製造時の試験で品質が保証されている。しかし一度現場で使われた経年品は管理された事業所を除き、再び強度試験が行われることはない。この慣習は「業界の非常識な常識」となっており、安全性への懸念が常に存在している。
また近年、足場の運搬や組み立ての負担軽減のため、鋼材を薄くした軽量パイプが普及している。しかし軽量パイプに対する従来クランプの締め付け基準が明確でないことから、過度な締め付けによりパイプの変形や結合部のずれが生じ、事故につながるリスクがある。この状況に対処するため、同社は軽量パイプでも安全性と強度に優れたT―Earthを開発した。
T―Earthの主な特徴は以下の3点。
(1)ボルト不突出デザインでひっかかりを抑制=従来のクランプはボルトが外側に突出している。そのため作業者の衣類や資材が引っかかったり、通行時のつまずきを誘発する恐れがあった。従って人が通る場所にはプラスチック製の「クランプカバー」を装着する運用が一般的だった。
そこでT―Eartはボルトの突出を抑えた外観設計を採用。カバーに頼ることなく、製品自体のデザインを変えることで、現場の安全性向上と作業負担の軽減に寄与する。
(2)業界一滑らない設計で結合部の滑りを抑制=T―Earthは直径48・6ミリに特化することで、接触面を最適化。パイプ全体を均一に掴むことができる。これにより過度な締め込みによるパイプの変形を防ぎながら業界一の保持力を安定して発揮する(新基準〈単品承認〉により、安全基準がなかった軽量パイプ〈引張強さ700ニュートン毎平方ミリメートル以上〔外径48・6ミリ、肉厚1・8〜2・0ミリ〕の溶解亜鉛メッキ、電気メッキの防錆処理を施した鋼管〉に使用しても滑らないことが証明されている。今年7月時点、一般社団法人仮設工業会にて確認)。
加えて、T―Eartは、仮設工業会の安全基準「仮設工業会認定品」および軽量パイプの安全基準「仮設工業会単品承認品」を緊結金具業界で初めて同時取得。従ってこれまで安全基準がなかった軽量パイプにおいても、高い安全性を担保することが可能となった。
(3)人と地球に優しい設計=クランプカバーが不要な設計により、プラスチックの廃棄物と、その製造や廃棄に伴うCO2を削減する。また、今後はリサイクル過程において電気炉を利用し、さらにCO2排出量を削減していく予定である。
さらに、錆を防ぐための表面処理(メッキ)では、従来使用されていた製造過程で人体に有害性の高い六価クロムメッキから、多くの環境規制対象とならない三価クロムメッキへ変更。これにより、メッキ作業者の安全確保を実現する。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
大容量非常用発電機を商品化/ヤンマーエネルギーシステム |
|
| |
|
|
| |
ヤンマーホールディングス(株)のグループ会社であるヤンマーエネルギーシステム(株)は、データセンターや大型設備に対応する大容量の非常用発電機「GY175」を商品化し、シリーズ第1弾として今年度中に2000kVAクラス対応機種の販売を開始する。今後、26年度以降に3000kVAクラス、28年度以降に4000kVAクラスへの展開を計画している。
近年、クラウドサービスの普及、AIの普及・高度化に伴い、データセンターのニーズが急増している。2030年度の日本のデータセンター新増設の電力需要規模は、2025年度想定値の約9倍で、今後も増えていくと想定されている。
ヤンマーエネルギーシステムでは、昨今の電力需給逼迫や災害時における停電への事業継続計画(BCP)対策として、データセンターをはじめ工場やビル、病院など幅広い業界からのニーズに対応すべく、2000kVAクラス以上の大容量非常用発電機を開発した。
今後の需要拡大に対応するため、同シリーズの新たな生産工場を増設し、供給体制を強化していく計画。
本機に搭載しているエンジン「GY175シリーズ」は、ヤンマーパワーソリューション(株)が舶用エンジンで培った技術に基づき開発した新しい高速エンジン。また、発電装置に対するISO規格で最高水準に当たるClass G3(ISO8528―5)への適合に加え、短時間始動や遠隔監視サービスにも対応しており、万一の停電でも、サーバー機器などを停止させることなく、データ損失や通信サービス停止のリスクを最小限に抑えることができる。
【主な特徴】
(1)短時間起動実現、発電装置に対応する動作性能のISO規格で最高水準にあたるClass G3(ISO8528―5)に適合(2)A重油対応による安定稼働(3)黒煙、白煙の発生を大幅に低減した環境配慮設計(4)遠隔監視サービス。バッテリー劣化診断、警報の緊急連絡などのほか、定期的なレポートを発行し、災害時に備えた管理体制作りをサポート(5)メンテナンスの容易性。フィルター類などのメンテナンス部品は片側に配置し、GY175シリーズで部品の共通化することによる部品供給の安定。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
環境性能高い油圧ショベル発売開始/ヤンマー建機 |
|
| |
|
|
| |
ヤンマー建機(株)(工藤龍社長・福岡県筑後市大字熊野1717の1)は、10月から、エコモードによる燃費向上を実現した油圧ショベル「ViO45―6C」「ViO55―6C」の発売を開始した。
同機は従来モデルから搭載していたエコモード使用時において、エンジン回転数の最適制御により従来機比「ViO45―6C」11・8%、「ViO55―6C」11・1%の燃費向上を実現した。これに伴い、法人税および固定資産税の優遇税制措置も適用対象となる。
低燃費で高い環境性能を誇る自社製エンジンに加え、こうしたエコ機能を搭載・活用することにより、CO2排出量の削減や環境負荷低減にも貢献する。
ヤンマーグループでは、脱炭素社会の実現に向け「YANMAR GREEN CHALLENGE 2050」を推進している。今後も建設作業の効率化、環境性能の向上を目指し、ユーザーの課題解決に貢献していく。
〈商品概要〉
▽商品名=ViO45―6C
商品価格=817万4000円
▽商品名=ViO55―6C
商品価格=892万7600円
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ビッグフードシリーズ「霧花(KIRIKA)」を発売/永田製作所 |
|
| |
|
|
| |
農業用噴霧機などを製造販売する(株)永田製作所(田中寿和社長・大阪府大阪市西淀川区千舟1の5の41)はビッグフードシリーズ「霧花(KIRIKA)」を発売した。260グラムの軽量なノズルで高所から低所まで使用しやすい。また、ビッグフードが後方から空気を大量に吸い込むため、霧が長く遠くまで達し、果樹園やハウスでの使用を想定している。(※到達距離などは性能表参照)
その他の特徴は、直射と円錐の切り替えができ、低木などの防除、また広範囲の作業や長尺の散布竿に取り付けて高木の防除にも効率的だ。軽量なので竿に取り付けやすく、消費者テストでは女性から好評であったという。噴口はステンレス製で、耐久性にも優れている。
〈製品仕様〉▽全長=245ミリ▽重量=260グラム▽孔径=2・0ミリ▽最高使用圧力=3・0MPa
▽希望小売価格(税込み)=1万4850円
▽製品問い合わせ=同社TEL06・6473・0835
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
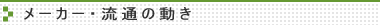 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
北大教授・野口伸氏が脳のデジタルツイン展望/農業WEEK |
|
| |
|
|
| |
1〜3の3日間、千葉市美浜区の幕張メッセで開催された「第15回農業WEEK(通称J―AGRI TOKYO)」では連日様々な特別講演が開催された。1日に開催された北海道大学大学院農学研究院農学研究院長・野口伸氏による「スマート農業技術の今後の展望」の概要をみる。
野口氏は、日本がアジア・モンスーン地域に適用するスマート農業技術のトップランナーであり、日本政府は2030年までにスマート農業技術を活用した面積を50%にすることを目標に掲げていることを踏まえ、スマート農業の普及拡大に求められる技術と社会システムについて論じた。
日本の食料自給率は2022年度にカロリーベースで38%、生産額ベースで58%となり、G7内でも最低水準。さらに日本農業は農業人口の高齢化と減少が最大の問題となっており、今後の食料安全保障の確保のためにも食料の安定供給が欠かせず、この難題に解決する術としてスマート農業が貢献すると語った。
野口氏はスマート農業のポイントとして、圃場のフィジカル空間において農作業履歴や気温などの環境状況、農作物の生育状況などのデータを収集し、サイバー空間にデータを飛ばしてビッグデータをAIで解析、そこから有用情報を抽出してまた生産現場にフィードバックして営農に活用するというSociety5・0の実現を目指していると指摘。
2050年におけるスマート農業の姿は、人工衛星やドローン、各種センサーで収集したフィールドデータをAIに学習させて、サイバー空間に農業現場を構築し(バーチャルファーム)、シミュレーションや生育モデルの作成を経て、現実の農地にフィードバックする「農業デジタルツイン」の構想が重要になると説明。デジタルツインによりAIとロボットを共進化させて現場適応能力を高めて、AIロボットが最適な農作業を実現するとした。
その一例として、▽小型AIロボット群を利用して24時間作業▽リモート農業により1人で5倍の作業量▽大変な作業はAIロボットが行い、人は楽しみながら農作業を行う。将来にわたりウェルビーイングの高い社会を構築する―などを示した。
そして、それに向かう道筋として野口氏らが取り組んでいる研究について紹介。北海道大学のスマート農業教育研究センターにロボット農機の遠隔監視システムを設置し、北大圃場にてロボットトラクタ2台、岩見沢市の水田にてロボットトラクタ1台、羅臼町のワイン用ブドウ畑にてEVロボット2台を監視・操作するリモート農業を実証。ロボットトラクタは無人作業を基本とするが状況に応じて遠隔操縦も可能。農業支援サービス事業者がロボットを所有し、レンタル・作業受託する想定で、実証の結果、生産コスト・作業時間が減少し営農利益改善の効果が見られたと述べた。昨今は複数の無人・有人ロボット農機による協調作業で何台で行うと最も効率がよいかをサイバー空間のシミュレートで検討し、岩見沢圃場においては9台が最も効率的であったと報告。
一方、羅臼町のブドウ畑のEVロボットは電動式見回りロボとなっており、運搬・防除なども行える。LiDAR技術により周囲環境を調べてAIで精緻に認識し、障害物などを検出。8つのノズルをコントロールして可変防除ができ、夜間作業も可能という。また、野口氏らは糖度などの品質を認識し、それに基づいてAIで収穫を判断し自動収穫するブドウ収穫ロボットの開発に取り組んでいる。
そして、こうした技術の現場実装に必要なこととして、スマートアグリシティの構想を紹介。スマート農業は自動化とデータ利用がポイントであり、特にサイバー空間の利用拡大が重要となる。スマートアグリシティの構築を通して、デジタルインフラを整え、地域内に効率的に時空間データを蓄積・分析できるデータセンターを整備することが必須であるとした。また、ロボット農機は自動化から知能化に進化し、これまで以上にAIが重要になると指摘。今後は農作業を請け負っていく農業サービス事業者が利用できる技術が必要であり、リモート農業やデジタルツインは農業に大きな変革をもたらしていくなどと展望した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農業WEEKで木製ハウスをPR/オムニア・コンチェルト |
|
| |
|
|
| |
(株)オムニア・コンチェルト(東京都港区高輪3の11の3・イハラ高輪ビル6階)は、農業WEEKにおいて、画期的な農林業用木製ハウスシステム「さえずり」を中心とした同社製品各種を展示。2×5メートルの木製ハウスで小間全体を覆い、来場者の注目を集めた。
木製ハウスは、鉄骨ハウスと同強度で低コスト化を実現しており、耐風50メートル/秒、耐雪50キロ/平方メートルをクリア。高断熱設計の住宅建材技術を採用し、鉄骨ハウスよりも効率的なエネルギー利用を実現する。有孔ボード床、壁面ブラインド、床下ボイラーなど、同社独自の技術による高付加価値なハウスを実現。自由度の高いカスタマイズで様々な要望に柔軟に応え、小規模から大規模まで対応する。太陽光、風力、バイオマス発電など自然エネルギーを活用し、エコで低コストな運用をサポートする。遮光・採光制御(自動ブラインド)と換気制御による温度管理、潅水管理などを同社の環境制御盤に統合し、ほとんどの自動化要求に対応。同社の3D遠隔監視システム「スフマート」や環境統合制御システム「コンチェルト」とスムーズに連携できる。ハウスの屋根や側面に取り付けたソーラーパネルにより、ハウス内の環境制御機器やLED、天窓側窓の開閉、換気用ファンなどの電力も賄う。木のぬくもりを感じさせる景観を損なわないデザインで、地方創生にも役立つ。木製のため環境負荷の低減にも貢献する。
その他、新製品となるUFO型LED照明やウエアラブルカメラを含めた監視カメラシステム等も出品展示。ウエアラブルカメラを搭載したゴーグルを作業者が装着することで、作物の状況を作業者の目線で、ZOOM等のサービスを活用しながら遠隔での指示や相談、教育、作業確認などができるようになる。
小間でウエアラブルカメラの展示を担当した同社技術部の大和田勝徳副部長は「将来はゴーグルをスマートグラスに替えることで、PC画面を観る替わりに、作業者がバーチャル映像を見ながら作業することができるようになる。そうすれば完全ハンズフリーでの作業を実現できるようになる」と述べている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
果樹の散布ロボットを農業WEEKに出品/韓国・HADA社 |
|
| |
|
|
| |
韓国のHADA社(大韓民国全羅北道益山市銀基キル329―34)は、10月1日から3日間、千葉市の幕張メッセで行われた第15回農業WEEKに無人果樹園散布ロボット「PURIDA」を出品した。同社は、ニンニク栽培の全行程を機械化したメーカーで、スプレヤー工程だけが遅れていたがこのほど完成し、同会場で披露した。電動化に取り組む企業には国から補助金が出ており、それを活用した。
来年から韓国で発売する予定という。
同社によると、PURIDAは、農村地域における労働力不足と従来の農薬散布作業の非効率性の両方を解決する次世代型スマートの農業ソリューションとして開発された無人自律型果樹園散布ロボット。高精度な自律ナビケーション技術と高性能散布システムを統合することで、このロボットは果樹園内を自律的に移動しながら、樹木間の農薬散布を高精度かつ確実に行うことができる。
機体寸法は全長1383×全幅2397×全高2841(折りたたみ時は1840)ミリ。重量は773キロ。
主な特徴は、(1)電力は59・5キロワットから11・5キロワットに削減。重量は既存品1395キロに対しPURIDは773キロと軽減、大幅な省エネ、機器寿命の延長、稼働時間の延長を実現(2)500リットルの大容量タンクを搭載し、1000坪を最長30分間散布できる。左・中・右の散布制御で正確な散布を実現(3)ワンタッチカプラで取り付け、取り外しが可能。メンテナンスを簡素化(4)独立送風システム+8台の送風機を様々な角度に調整可能、多軸・トンネル式果樹園での散布が可能(5)静電ノズルを使用して噴霧された水粒子が散らばらず、木の表面にしっかり付着して農薬使用量を40%削減―など。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
みやぎ林機展で「つかむっちシリーズ」紹介/ユタニ工業 |
|
| |
|
|
| |
ユタニ工業(株)(湯谷友章社長・大阪府東大阪市稲田新町2の32の18)は、10月5日に宮城県石巻市で開催された「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」で産業廃棄物の分別や積み込みに最適なフォーククラブ「つかむっちシリーズ」を紹介した。
「つかむっち」と「つかむっちミニ」は3点止め機械式。独自のリンゲージ機構で過酷な現場でも大活躍。ストロークが短いので開閉作業がスムーズ。シリンダー推力を分散することにより、つかむっち各部のピン部にかかる負担を軽減。製品自体の耐久性を高めた。
油圧式の「ふりふりつかむっち」は、バケットシリンダーでつかむっちの首振りを操作。内蔵シリンダーで爪を開閉。ピン2本で脱着できる。
「ぐるぐるつかむっち」は油圧旋回式。油圧モーターで対象物を自由自在に回して、あらゆる方向から掴んだり離したりすることが可能。作業効率が大幅にアップする。
この他、油圧ショベル用草刈り機「カルンダモン」を出品。ハンマーナイフ方式でパワフルに粉砕。生い茂る草木を細かいチップ状にすることができる。平面はもちろん斜面や法面でも楽々。作業の効率化を実現する。
また、バケットロックをはじめ、重機の横滑りを防止するゴムクローラチェーンや「滑らんバー」をPRした。
つかむっちシリーズは愛らしいネーミングも特徴の一つ。公式マスコットキャラクター「つかむっち君」のグッズを同社のオンラインショップで販売。いつでもどこへでも連れていきたくなるぬいぐるみやバッグ、Tシャツなどがあり、好評を博している。グッズの購入はこちらから。https://yutani.jp/item/
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
10月からコロンビアに現地法人設立、製品販売を開始/丸山製作所 |
|
| |
|
|
| |
(株)丸山製作所(内山剛治社長・東京都千代田区内神田3の4の15)は、コロンビアに現地法人「MARUYAMA COLOMBIA S・A・S」を設立、10月から製品販売を開始した。
同国はコーヒー豆、生花、バナナ、パーム油などで世界的な競争力を持つ農産物生産国ながら、生産現場は中小規模の家族経営農家が大部分を担っており、それぞれにおける生産性向上、機械化が喫緊の課題となっている。
同社は、こうした現状に同社製品や技術力が貢献できる余地は大きいと判断、今回の事業を進めるに至った。
現地法人は今年1月9日に設立、所在地はCarrera11A No.93―52 Office404、Bogota、COLOMBIA。
同社は、「長年にわたり培ってきた防除技術と現場の声を反映した製品開発力で、成長ポテンシャルの高いコロンビア市場のニーズに応えることを目指す。現地法人が主体となり、製品販売後のきめ細かなカスタマーサポート体制を構築、お客様が製品を安心して長く使えるようにサポートする」とし、同国農業の発展に貢献する意欲を示している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
PONSSE55周年を祝う/新宮商行 |
|
| |
|
|
| |
(株)新宮商行(坂口栄治郎社長・北海道小樽市稲穂2の1の1)は4日、「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」の開催にあわせて、仙台市内のホテルJALシティ仙台で、PONSSE55周年記念パーティーを挙行し、PONSSE関係者や販売店、ユーザーなど約80名が参集、共に成長を期した。会は前半のPONSSE社によるプレゼンテーションと後半の祝賀パーティーの2部制で行われた。
冒頭、主催者を代表して同社坂口社長が挨拶し、「PONSSEとの関係は30年以上。PONSSEは1970年の創業当初から現場に近いところで機械開発を行ってきた非常に現場を大切にする会社。当社も現場の声を常に身近に感じながら仕事をすることを心掛けており、その姿勢に共感している。本日はご参集の皆様と率直な話をし、PONSSEファンを一人でも多く作っていきたい」と述べた。
プレゼンテーションでは、始めにアジア・オーストラリア・アフリカ担当のユッシ・ヘントゥネン副社長が会社紹介を行った。まずPONSSEの由来が動画で紹介された。フィンランドの北サヴォ地方のヴィエレマ村に住み、村人から愛された雑種の猟犬「ポンセ」。夏の暑さにも、冬の嵐にも湿地もぬかるみも茂みでも動きを止めることなく、己の道を進み続けた。その名前を受け継いだのが運材フォレストマシン「PONSSE」だった。創業者はエイナリ・ビドグレン氏。林業を生業としながら、機械製造を開始。1969年に1台目の機械を製造し、これまで2万1000台を超える機械を世に送り出してきた。現在は息子のヤルモ・ビドグレン氏が取締役会会長としてその意思を引き継いでいる。創業当時数人だった従業員も今や2083名となり、2024年売上高も1300億円に拡大。12カ国に会社を保有し、30社のディーラーと取引し、欧州を中心に南北アメリカ、アジア、オーストラリアなど40カ国で事業を展開するまでになっている。
全世界で稼働する機械は1万6000台。創業者の言葉でもある経営理念は(1)お客様のために働く(2)心からのケア(3)正直である(4)革新に前向きの4つで、PONSSE―SPIRITとして掲げられている。同社が最も重視するのがアフターサービス。売上高の21%を占め、世界中に2200人以上のサービスマンを配置。業界で最も近代的な工場や常時2万種類の部品を在庫する物流拠点についても説明した。
続いて商品や技術についてハーベスタヘッドの製品開発を担うマルック・サヴォライネンプロダクトマネージャーが登壇。製品はハーベスタの固定キャビン型と同旋回キャビン型、フォワーダ、ハーベスタヘッドの4群。それぞれ用途によって大小6〜8機種程度を取り揃える。加えて、それらをつなぎ、管理するデジタルソリューションの開発も行う。同社は林業、木材生産に特化した製品作りに注力し、それ以外の産業向けの機械は生産していないのが特徴である。中軽量タイプのフォワーダ2機種をモデルチェンジし、高耐久化、荷台配置の自由度向上を成し遂げた。
また、アクティブキャビンというオプションによりキャビンの振動を軽減し、作業環境を快適化している。さらにポンセスケールというフォワーダ用の全く新しいワイヤレス計量システムを開発。掴んで積んだ材と、下ろした材の重さを計測し、記録できる。その他、アタッチメントを動かしたい方向に動かしたいスピードで操作できるアクティブクレーンや新たなハーベスタヘッド2機種なども紹介した。
次にシミュレーター担当で林業学校への協力にも携わるユッシ・ユルバネンプロダクトマネージャーが、オペレータの育成に欠かせないものとなりつつあるシュミレーターについて説明。同社は20年以上前からオペレータ教育に着目し、2007年に育成部署を設置。このチームはたくさんの知識と技術を身につけることのできるサービス提供に尽力している。機械の説明書を無料アプリ化したアクティブマニュアルについてや、林業に関する教科書を出版したこと、実際のシミュレーターの内容などについて伝えた。
休憩中、取材に応じたユッシ・ヘントゥネン副社長は「日本は非常に重要な市場だと捉えている。まずは日本に合った商品を提供すること。次に生産性の向上やトレーニング。3つ目のアフターサービスも重要。新宮商行と一緒に顧客を訪問し、どういったことを重要視しているか見極めていく。明日からの展示会ではシミュレーターを実際に体験してその良さを実感していただきたい」と話した。55周年の今年、「LOGGING TOGETHER WORLDWIDE」のスローガンを掲げ、40カ国を回っている。直訳すれば「世界中で一緒に伐採する」といったところか。これからも顧客ニーズを大切に共に成長していくことを念頭に製品開発などを進めていくとした。
祝賀パーティーには、ヤルモ会長が到着。「55周年の今年、このようにして20カ国以上を回ってきた。各地のお客様より直接お言葉を頂くことを最も大切にしている。ご来場の皆様に心より感謝する」などと55周年に込めた思いを語った。
また、取材に応じた坂口社長は「新宮商行の精神はPONSSEのメンタリティに非常に近しい。そのため我々とPONSSEの経営陣は一体感を持って、これからの林業をどう活性化させるかを考え行動している。当社は林業の川上から川下まで対応している。これからもいかにして木材を最終のお客様のもとにお届けし、使っていただくかという基本を忘れず、後世につないでいきたい」と語った。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
電動歩行台車を農業WEEKで参考出品/みのる産業 |
|
| |
|
|
| |
みのる産業(株)(生本尚久社長・岡山県赤磐市下市447)は第15回農業WEEKに出展し、来春頃発表予定で開発中の電動歩行台車「ECN―1」を参考出品した。
狭い圃場やハウス内での収穫、管理作業をサポートする同製品は、最大積載量100キロ程度で、簡単に収穫物などの運搬ができる。前進・クラッチ切・後進の切替スイッチで方向を制御し、隣接するつまみで簡単に速度調整できる。走行ブレーキもハンドル部分に付帯し、各操作ともワンタッチでできる。積載部の縦横のガード伸縮が可能。農業用コンテナ(みかん用)を横向きで2個搭載、スタッキング金具付きプラスケットも横向き2個搭載できる。凹凸面でも水平に保つ機構で安定走行を実現。一点旋回も可能だ。バッテリー着脱も手軽にでき、残量表示付きのため一目でバッテリー残量が把握できる。後輪の回転止めによる直線作業での利用も可能で、駐車ストッパ付き。機体重量は36キロ、全長1050ミリ、幅が440ミリ、タイヤ幅は400ミリとコンパクトで軽量となっている。
主要諸元は次の通り(開発中のため予告なく仕様変更の場合あり)。
▽名称=電動歩行台車▽型式=ECN―1▽機体寸法=全長1050×全幅440×全高865ミリ▽機体質量(重量)=36キロ(バッテリー含む)▽荷台寸法=長さ780〜940ミリ、幅400〜605ミリ▽最大積載荷量=100キロ(未定)▽車輪=前輪:エアタイヤ(外径300ミリ×幅92ミリ)、後輪:ノーパンクタイヤ(外径200ミリ×幅56ミリ)▽輪距=前輪310ミリ、後輪340ミリ▽軸距=560ミリ▽バッテリー=やまびこ(ECHO)製、型式:LBP―50―250G、種類:Li―ion、重量:1・8キロ、容量:4・5Ah、電圧(定格):50・4ボルト▽充電器=やまびこ(ECHO)製、型式:LCJQ―560D、電源:AC100ボルト、50/60ヘルツ、充電時間:約89分▽作業目安=最高走行速度=前進:1・3メートル/秒、稼働時間:4〜5時間程度(バッテリーの新品満充電での収穫作業時)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
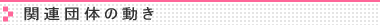 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農機具まつり盛況、スマート農機を提案/愛媛県農林水産研究所 |
|
| |
|
|
| |
愛媛県農林水産研究所の農業・果樹部門の研究成果を広く公開する農林水産参観デーが1、2の両日、松山市の農林水産研究所と果樹研究センターで開催された。両会場では同県農機具協会が協賛する「農機具まつり」が開催され、最新型の農業機械や農園芸関連資材が多数出品され、多くの来場者で賑わった。
農機具まつりは、愛媛県農機具商業協同組合(冠範之理事長)が開催する毎年恒例の行事である。
期間中は晴天に恵まれ、暑いくらいの陽気にもかかわらず、会場には最新の農機や情報を求める農家が来場した。
今回はスマート農機・農業DX関連機器の展示・実演会が中心に行われた。最新のトラクタ及び田植機、コンバインなど各種農機が展示され、会場中央に設けられた実演会場では、直進アシスト機能付きトラクタの実演が行われ、多くの農家が注目した。
今年は果樹研究センターにおいて、ヤンマーアグリジャパンによるドローンの実演が行われた。
実験圃場となっているミカン畑を実際に使い、水を農薬に見立てて散布するデモンストレーションが行われた。山間地域にあるミカン畑は、足元が悪く、重い噴霧機を担いでの農薬散布は大変な重労働で、ミカン農家にとっては大きな課題となっている。実演では、エリアを決めコースを設定して散布するモードや、樹木にピンポイントで散布するモードなどを披露し、多くの農家が関心を寄せた。
また愛媛県農機具商業協同組合のブースでは、恒例の農機安全講習会が開催された。今年はトラクタ、コンバインのほか、最近利用が増えているリモコン草刈機も加え、それぞれの機械に関するメンテナンスや運転技術、安全な使い方、日頃の心構えや服装などの注意点を分かりやすく説明し、農作業事故防止を訴えた。講習会には多くの農家が参加し、関心の高さが伺えた。
冠理事長は「両日とも天候に恵まれ、6700人余りの方に来場いただいた。果樹研究センターの実験圃場を使用したドローンの実演には、多くの方が集まり注目された。また、直進アシスト付きトラクタにも多くの関心が寄せられた。スマート農機を用いて、愛媛農業を省力化できることをアピールできた2日間だった。協力いただいた組合員やメーカーの方々に深く感謝します」と総括した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
テクノフェスタを11月7日に開催/農業食料工学会 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人農業食料工学会(飯田訓久会長)は11月7日11時より、さいたま市西区の農研機構農業機械研究部門において、同学会シンポジウム「第30回テクノフェスタ」を開催する。
テクノフェスタは農業機械に関係する技術者、研究者の技術力の向上ならびに交流と親睦のために平成8年からスタートし、今回は節目の30回目に当たる。「スマート農業におけるモデルベースデザインの活用」をテーマに掲げ、基調講演では同技術を活用した自動車及び乗用トラクタの安全性に係る事例発表を行う。同学会では今後のスマート農業技術の開発を加速化するための新たなツールとなり得る技術であり、産学の取り組みを深める契機となることに期待を寄せている。また、今年度の開発特別賞・開発賞の受賞講演や、分科会も開催される。
シンポジウム内容は次の通り。
(1)基調講演=自動車におけるモデルベースを活用したスマート安全の取り組み(東京農工大学大学院工学府スマートモビリティ研究拠点・教授・ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク氏)、農業のスマート安全におけるモデルベースデザイン―トラクタ用ドライビングシミュレータの活用―(東京農工大学大学院農学研究院・特任教授〈名誉教授〉・酒井憲司氏)
(2)受賞講演=開発特別賞/「アグリロボコンバインDRH1200A―A」((株)クボタ)▽開発賞/「コイン精米機CP420,CPH420の開発」(井関農機(株))、「スピードハローソニックSHV280」(小橋工業(株))、「ラジコン斜面草刈機YW500RCの開発」(ヤンマーアグリ(株))
(3)分科会=農業機械分科会(農業機械部会)、生物資源分科会(生物資源部会)、自動運転分科会(IT・メカトロニクス部会)
参加費は会員4000円、非会員5000円、海外・学生参加者は無料。参加申し込みは同学会ホームページから。申し込み期限は10月24日。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
国産国消フェスが盛況/JAグループ |
|
| |
|
|
| |
JAグループ(全国農業協同組合中央会)は4日、都内千代田区のKITTE丸の内1階アトリウム・テラスにおいて、「食と農でつながる国消国産フェス」を開催した。国消国産は私たちの国で消費する食べ物は、できるだけこの国で生産するという考え方のことで、日本の食と農について知って、国産農畜産物をさらに味わってもらうきっかけを提供したいという想いから、国産農畜産物について楽しく学び、美味しく味わうイベントを提供した。
会場の特設ステージではJAグループサポーターの林修氏が登壇し、全国農協青年組織協議会(JA全青協)会長や、東京農業大学の学生とのトークショーを実施したほか、タレントのギャル曽根さん、QuizKnockの鶴崎修功さん・東問さんをゲストに迎えた国消国産クイズ大会、JAグループキャラクターの笑味ちゃんとハローキティがコラボしたグリーティングなども行われ、若者から親子連れ、お年寄りまで大勢の観覧者で賑わった。
また、会場ではJA全青協及び東京農業大学による自慢の農産物・加工食品を集めたマルシェが行われたほか、JA全農による和牛試食会、秋の食材を使ってちょうど1キロを量るゲーム「触って感じる重量感覚チャレンジ」、国産和牛や各地の味覚が当たる「スタンプラリーガチャ」なども開催され、参加者が楽しみながら各小間をまわっていた。和牛試食会は、国内でもっと和牛を食べてもらうために、JA全農が令和7年度和牛肉需要拡大緊急対策事業の一環で実施したもの。今回は佐賀県産・福岡県産のサーロイン・リブロースをその場で焼いて提供し、「ちょっといい日に和牛をたべよう!」と呼び掛けていた。通りがかった観光客や買い物客らは和牛が焼ける独特の香ばしい匂い(和牛香)に引き寄せられ、柔らかくて美味しい焼肉を堪能。さらにゲームやステージイベントを通して国産農畜産物について楽しく学び、お土産に全国各地の新鮮な野菜や果物、加工食品などを買い求めていた。
林修氏とJA全青協・北川敏匡会長のトークショー「国消国産レッスン」では、日本の食料自給率は約4割で年々低下していることを踏まえ、このままでは国産の美味しい食材が食べ続けられなくなるかもしれない危機的状況だと指摘。この緊急課題を解決するには国民が国産を選んでいくことが必要だとし、「ちょっと高くても美味しくて安全な国産食材を食べることが自己投資にもなる。最近は推し活が流行しているが、ぜひ国消国産を推しにしてほしい」(林氏)、「作る側としても、消費が減ってしまうとまわらない。国産食材を1つでも多く選んでもらえると生産者も心置きなく作れるので、国産の良さを理解して食べてほしい」(北川会長)などとコメントした。
また、マルシェにてご当地の食材・加工食品を出品していたJA全青協の会員らに話を聞くと、「自分たちが作っているものを直接販売することで、消費者と生の声をやり取りして、相互理解を深めたい。農産物は交流のツール。米や農産物がなぜ値上がりしているのかといった事情を伝え、また、消費者の声も聞いて生産に反映していきたい」、「ここにあるのは見た目も綺麗に揃っている農産物のエリートばかり。手間暇をかけ、想いをこめて作っている。価格だけでなくそうした背景も見て、美味しい国産を選んでほしい。そして、産地にも来てもらって、もっと様々な食を味わってもらえたら」などと想いを語ってくれた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
加工・業務用レタス現地検討会でデリカなど講演/野菜流通カット協議会 |
|
| |
|
|
| |
野菜流通カット協議会(木村幸雄会長)は9月30日、長野県において加工・業務用レタス現地検討会を開催した(既報)。レタス収穫機の普及や国産の加工・業務用レタスの生産・流通の拡大を図るため、国内で初めて実用化に成功した(株)デリカのレタス収穫機DX―121の実演及びセミナーを行った。
セミナーでは、5講演と総合討論が行われた。そのうち、(有)トップリバー代表取締役・嶋崎隼人氏は「加工・業務用レタスの機械化とデータ連携による次世代産地経営の実践と課題」を講演。
同社は長野県でレタスを中心に200ヘクタールの面積で高原野菜を栽培・販売しており、農業経営を軸に社内で生産・販売・組織マネジメントを徹底。独自の生産・販売管理システムを開発し、野菜サプライチェーンのDX化を行っている。レタス収穫機の導入は法人として日本初。レタスの手収穫は畑業務の約6割を占めることから、生産性向上には収穫の効率化が必須とし、デリカと共に収穫の機械化に取り組んだ。 収穫機の導入で切り業務を機械化し、人間が1玉当たり6秒で切るところを機械は8倍速で切れると述べ、労働力削減と業務分配による安定出荷につながるとした。取り組み目標として、現在は1時間当たり15ケースの収穫を30ケースにすることを掲げ、今後は▽削減経費や効率性を鑑み費用対効果を考察▽切り込みにより褐変箇所の拡大もみられ、褐変を防止する方法の模索▽コンベア導入による箱詰めまでの流れの円滑化▽現場収穫体制の構築▽出荷規定の決定―を進めていくなどと語った。
また、デリカの開発技術部課長・胡桃沢隆氏は「レタス収穫機への取り組みと現状の課題から今後の展望について」講演。長野県松本市を本拠地とする同社は国内6、海外1の拠点を構え、マニュアスプレッダなどを主力製品として、循環型有機農業に資する農業機械を供給し続けている。ラインアップをみると、良質堆肥づくりをサポートする堆肥切り返し機や籾殻粉砕機、土づくりを支援するマニュアスプレッダシリーズ、様々な野菜苗の移植機、肥料の少量散布が可能な肥料散布機、マルチ剥ぎ機、収穫作業ではベビーリーフ収穫機や高所作業台車など、農作業体系別に各機を提供しており幅広い。
今回実演を行ったレタス収穫機は片倉機器工業などが進めてきた開発を受け継ぎ、2019〜2023年にスマート農業機械社会実装加速化支援事業で長野県とデリカで「同時2条刈、損失10%以下、1秒当たり1・5個を目標に刈り取りのみの機能を持つ」現状機のベースを構築したもの。2024年に市場投入し、開発に参画していたトップリバーが導入。24〜25年はトップリバーとデリカで協議しつつ、実際の圃場で課題出しを行い、稼働フォローを進めているという。
胡桃沢氏は同機の課題として、▽収穫時間25%削減の目標達成(手作業の1人1時間当たり20ケース↓機械収穫で同40ケース)▽オペレータの育成(直進などオペレータの技術により収穫精度に差が発生)▽栽培方法の検討(畝の中心に植えるなど機械収穫に適した栽培)▽機械による収穫品の評価(機械収穫を許容・評価してもらい改善などのフィードバック)―などを提示。中でも、稼働を経て浮かび上がった収穫時の課題として(1)ガイド円板が畝にもぐってしまう(2)切断位置の安定化―をあげ、(1)についてはオペレートによる改善やガイド円板の形状・重量の見直し、畝形状の改良などを、(2)については刃の剛性や適正作業速度の見直し、畝形状や移植位置など栽培の安定を図ることなどで対策を進めているとした。
今後については、現状機の活用・普及を進めて機械化に向けた栽培方法の確立や安定供給に向けた課題へ取り組むとともに、他地域を含む稼働・検証も進めて意見を吸い上げ、さらに現場にマッチした機械へステップアップしていきたいなどと展望した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
食の意識・環境などを国際分析/農林政策研が成果報告会 |
|
| |
|
|
| |
農林水産政策研究所は7日、オンラインにて研究成果報告会「食環境と持続可能な食料消費に関する国際分析」を開催し、これには全国から約120名が参加した。
今回は健康的な食とエシカル消費に着目し、世界8カ国(セネガル、ケニア、中国、インド、アメリカ、アルゼンチン、フランス、ドイツ)の都市住民の食意識と食環境に関する多国間分析の結果を報告した。
会では、(1)食環境と社会・経済的環境が持続可能な食料消費に及ぼす影響評価―8カ国比較による考察―(丸山優樹氏・農林水産政策研究所食料領域研究員)(2)持続的食料システムの構築に関する国際比較研究―アルゼンチン編―(田澤裕之氏・全国農村振興技術連盟企画部長)(3)ドイツにおける健康的な食品摂取と食意識(飯田恭子氏・農林水産政策研究所国際領域上席主任研究官)(4)ケニアにおける農業開発・食料消費の現状と課題(伊藤紀子氏・拓殖大学政経学部准教授)―などの6件の報告とまとめ、質疑応答が行われた。
そのうち(1)では、総論として研究全体の背景や目的、調査概要と結果、分析結果などを説明。
持続可能な食料システムの構築には先進国と途上国の両者において「食料増産」「環境配慮」「健康増進」の3要素を同時に成立する必要があり、生産者、加工業者、流通業者、消費者の全主体の取り組みが必要であることから、今回の研究では消費者の意識や行動の変容を促す第一歩として、8カ国の都市部に住む消費者にアンケートを行い、消費者の食品摂取に至る食意識や食環境などについてデータを集め、どのような食料摂取がなされているのかを把握した。
各国の調査結果を総合したところ、先進国や途上国に関係なく、食意識については「安全性・栄養重視」に属する消費者が多いという。この消費者は有機食品の消費を求めるが経済的・物理的アクセス環境に障壁があるため、各国共通の持続可能な食料消費に向けた取り組みとしては、所得の向上及び該当する食料品店舗の拡充によって消費行動の更なる向上が見込めるとした。
また、「価格と食味を重視」する消費者グループについては、すぐに食べられるように加工された油脂や糖分を多く含む「ウルトラ・プロセスド・フード(UPF)」を好み、生活習慣病のリスクも高いことから、食育教育の実施や、関連する食品ラベルの表示による行動変容の必要性が示された。
「原産地と伝統性を重視」する消費者グループについては、物理的なアクセス環境の改善によって、さらに当該食品の消費が伸びる可能性があるなどと示唆された。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
水稲直播の技術パンフをHPに掲載/農研機構 |
|
| |
|
|
| |
農研機構は7日、技術紹介パンフレット「水田直播栽培における難防除雑草の防除」をホームページに掲載した。
昨今導入が求められている水田直播栽培において、多年生雑草などの難防除雑草対策が困難になっている状況を踏まえ、農林水産省委託プロジェクト研究「直播栽培拡大のための雑草イネ等難防除雑草の省力的防除技術の開発」(2019〜23年度)で開発・実証した技術と成果を生産現場で取り組めるように取りまとめたもの。
難防除雑草を防除するにあたって、(1)防除上重要な生態的特性(2)推奨する防除体系の事例と防除のポイント(3)推奨防除体系による防除効果と防除コスト(4)推奨防除体系に組み入れ可能かつ有効性が確認された除草剤―を解説している。
同資料で取り上げる難防除雑草は、オモダカ(湛水直播栽培)・クログワイ(湛水直播栽培)・グリホサート抵抗性ネズミムギ(不耕起V溝乾田直播栽培)。
目次をみると、除草剤の効果的な使い方を解説したのち、これら3種の難防除雑草における生態と防除対策について、▽生態▽防除体系▽防除体系の導入効果▽有効性が確認された除草剤―などの項目に分けて、それぞれ詳しく紹介している。
このうちオモダカの解説について一部をみると、防除のポイントとして(1)オモダカは発生期間が長いため、有効な除草剤を複数回使用する体系処理での防除が基本(2)移植栽培に比べ、生育期間中の発生が遅れる傾向があるため、処理適期を逸しないよう、早期に発生した個体の生育程度を見極めて除草剤を散布(3)1回目の除草剤は、稲の平均葉齢が1葉に達した時期以降に散布し、2回目の除草剤はオモダカの生育程度に気を配りながら、播種後40〜50日に散布(除草剤によってオモダカに有効な処理時期が異なるので、農薬ラベルの使用上の注意事項で確認)(4)通常はノビエなどオモダカ以外の一般雑草も発生するので、播種前後に一般雑草対象の除草剤散布を推奨―などと説明している。
同パンフレットは農研機構ホームページから確認可能。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
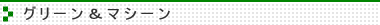 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
チェンソーの妙技競う/鳥取でJLC開催 |
|
| |
|
|
| |
18、19の2日間、鳥取県鳥取市の鳥取砂丘オアシス広場で、「第4回日本伐木チャンピオンシップin鳥取」が開催される。これまで日本伐木チャンピオンシップ(JLC)は、2014年の青森県会場を皮切りに、昨年の第5回大会まで連続青森県で実施され、世界伐木チャンピオンシップ(WLC)の日本代表選手を選考してきた。この間、鳥取県でも独自に大会を催してきたが、今回初めて日本代表を決定する公認の場となり、JLC全体の広がりを印象づけている。
大会には全国から約80人のチャレンジャーが参加。うちジュニアクラス、レディースクラスは各10人で、若い世代、女性にも着実にチェンソー技術者は増えている。
初日の予選会、2日目の決勝大会を経て、プロフェッショナルクラスの上位3名、ジュニアクラス、レディースクラスそれぞれの優勝者は、来年3月にスロベニアのシェンチェルネイで開かれるWLCに日本代表として参戦する。
近年、WLCでは種目別で金メダル、総合で銅メダルを獲得するなど、日本人選手は目覚ましい活躍をみせ、世界の注目度も一躍上がっている。
森林は国土や環境を健全に保つための不可欠な要素であり、その適切な管理を担う林業は、まさに日本を維持発展させていく上で欠くべからざる産業になる。
ただ、職場環境の視点で林業の現場をみると、過酷ともいえる状況にあり、事故率ではワーストランク。特にその大きな要因となっている立木伐倒の作業については、基本事項の励行、正しいチェンソー操作、安全装具・用具の装着など、安全を確保する様々な要件を満たす必要があり、JLCにおけるルールには、そうした安全要素が数多く含まれている。
加えて、競技者はカラフルかつデザイン性の高い防護具に身を固め、颯爽とツリーマストや丸太に対峙してスピーディーに技を繰り出し、技術の高さはもちろん、見た目のカッコよさでも観客を魅了する。大会会場は、林業に若い世代を引き込む好適な空間にもなる。
「鳥取でNo1を決めようぜ!」と戦いに挑む選手たちは、そのままで日本林業の明日に貢献しているといえる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
通信機能備え安全なスマートヘルメット発売/和光商事 |
|
| |
|
|
| |
和光商事(株)(池村圭史社長・東京都品川区西五反田8の7の11 アクシス五反田ビル)は既報の通り、林業関連「杣(そま)」シリーズの新製品として、通信機能や電動ファンを備えた「スマートフォレストヘルメットWHF001」を新発売した。林内通信やヘルメット内への送風機能など、作業の安全性を高める高機能ヘルメットで、林業関係者からはすでに高い関心が寄せられている。
人里離れた林業現場での伐倒作業は、万一トラブルが発生し事後の時間経過が長い場合は重大事故にもつながる可能性がある。こうしたリスクを解消するため、「スマートフォレストヘルメット」にはインターコム通信機能(通信距離はオープンエリア200メートル、森林内150メートル)を備え、作業中の仲間との連絡を確保。また、Bluetooth(接続距離5メートル)により電話による発着信、あるいは休憩中の音楽鑑賞と、外部との通信によって異常発生時の迅速な対処に寄与する。さらにヘルメット後部には3段階に調節できるファンを搭載、特に猛暑の夏場はヘルメット内の環境を快適にする。
使い方は、使用前にバッテリー残量を確認し、(1)イヤーマフ調整(左右および上下)(2)フェイスシールド調整(上下4段階)(3)フェイスシールド交換(ノブを回して外すと元のフェイスシールドとPCマスク取り付けや交換ができる)(4)アウトシェル、インナーシェルの締め付け具合の確認(5)あご紐のバックル確認(6)ヘッドバンドの調整―を行った後、パワーボタンを3秒間長押しすると全ての機能がON。BluetoothがONになり、自動的にマッチング、インターコム、ファンの電源がONになる。
レッド、ホワイト、ブルーの3色があり、カラーラベルでカスタマイズでき、自分の好みに合った外観を得られる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
コンパクト木質チッパー「REX―One」をみやぎ林機展で初披露/緑産 |
|
| |
|
|
| |
緑産(株)(小菅勝治社長・神奈川県相模原市中央区田名3334)は、かねてより自社開発を進めていたコンパクト木質チッパー「REX―One(レックスワン)」の限定数量先行販売を開始した。5日に宮城県石巻市で開催された「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」で初披露し、実演で来場者の注目を集めた。
国内製造の同機は、228PSのエンジンを搭載したクローラ自走式。シンプルな機構、移動性の高いコンパクト設計、リーズナブルな価格帯などが特徴だ。
〈開発の経緯〉
緑産はこれまで、最新技術を搭載した欧州製木質破砕機を幅広く取り扱い、木質バイオマス燃料製造現場の効率化や省力化に貢献してきた。
林地はもとより、街路樹の剪定枝や河川敷の伐採木など、都市部にも多くの木質バイオマス資源が存在しており、これらを活用する上でも小型・中型機のラインアップの必要性が高まっている。
こうした背景を踏まえ、従来から定評のある大型チッパーに加えて、導入のしやすさと現場での扱いやすさを両立させた国産コンパクトチッパーの開発に至った。
〈製品の特徴〉
新開発の「REX―One」は、コンピュータ制御システムを排除し、手動式機構を採用することで、シンプルでメンテナンスのしやすい機構を実現させた、緑産の技術陣による独自設計の国産モデル。
内蔵スクリーン付きオープンドラム式切削ローターを採用し、安定した品質の方形チップ(G100)を効率的に生産。
クローラ自走式とブロアー排出方式を採用しており、重量も最小化。山土場での現地破砕に威力を発揮し、狭小地や未整備の現場でも活躍する。
扱いやすいシンプル設計。高度な電子制御をあえて避け、マニュアル制御を採用した。ユーザー自身での修理・メンテナンスも可能。国産開発なのでユーザーにとって導入しやすい価格帯を実現している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
過去最多の91社が先進技術を披露、バリエーション豊かな展示/みやぎ林機展 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人林業機械化協会(島田泰助会長)と宮城県の共催による「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」(林機展)が5日、宮城県石巻市の仙台塩釜港(石巻港区)雲雀野(ひばりの)地区で開かれた。国土緑化推進機構の令和7年度「緑と水の森林ファンド」事業の助成を受け実施された同展には、過去最多の91社が出展し、1日目は晴天に恵まれ、林業関係者や家族連れなど多くの来場者で賑わった。会場内にはハーベスタやフォワーダといった高性能林業機械がずらり。チェンソーや木材破砕機、防護服・ヘルメットなど安全用品の他、今年は車両関連やドローン、仮設トイレ、燃料、通信機器等の出展もあり、各社がそれぞれのブースで自慢の製品をPRした。2日目は前夜からの雨の影響で会場に水溜まりができ、状態が悪いため、開催中止となった。
開幕に先立ち行われた開会式では、主催者である林業機械化協会の島田会長が挨拶し、「過去最大規模の展示実演会となり、最新の林業機械や関係資材が並んでいる。地球温暖化問題などを背景に、森林林業への関心が高まっている。安全かつ効率的な林業を実現するための原動力とし、これからも機械化を進めていきたい」と意気込んだ。
続いて、来賓として林野庁研究指導課技術開発推進室の塚田直子室長が祝辞を述べ、同庁の小坂善太郎長官のメッセージを代読。「展示実演会は災害に強く、地球環境の保全を担う未来の林業の姿を示す貴重な機会。地域の森林資源の価値を再認識し、持続可能な社会の実現に向けた一歩となってほしい」と呼びかけた。
また、石巻市の工藤均副市長が「人口減少や担い手不足による森林資源の適正管理・活用が課題。作業の効率化・省力化を進めて、林業・木材産業を持続的に発展させていかねばならない。展示実演会は最新機械や技術を体験できるまたとない機会。宮城県内の名物も楽しんで」と挨拶。
さらに、昨年10月の福井林機展で実施した来場者アンケートで、「関心の高かった展示・機械」として最も多くの票を集めたコベルコ建機日本(株)を表彰し、島田会長が同社の荒木治郎社長に記念品を贈呈した。
荒木社長は「大変光栄な賞をいただいた。遠隔操作システムK―DIVEへの関心が高かった。人手不足や働き方改革によって、林業においてもDX化の動きが進んでいる。これからも安全確保や移動距離の削減など効率化の提案をしていく」と話した。
約6ヘクタールの広大な会場内には未来の林業を担う最新鋭の機械が勢ぞろい。高性能林業機械を中心に、重機の遠隔操作システムや無人伐倒作業車、木材破砕機などが並んだ。各機種の実演や試乗体験には多くの人が集まり、注目されていた。チェンソーのデモンストレーションではWLC(世界伐木チャンピオンシップ)に出場した日本代表選手が匠の技術を披露し、来場者の目を釘付けにしていた。
島田会長は、「林業機械への関心の高まりを実感した。プロのみならず家族連れも多く見られ、来場者だけでなく出展社からも良い反応をたくさんいただけた。日本の森林・林業における機械化は重要なキーワード。遠隔操作や無人化の取り組みがどんどん進歩している。今後の動きにも大いに期待したい」と総括した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
省力・低コスト造林技術の普及に向けた研修会を開催/日本森林技術協会 |
|
| |
|
|
| |
令和7年度林野庁委託事業「省力・低コスト造林及び森林整備事業のデジタル申請・検査等の普及調査事業」の事業実施主体として事業を進めている一般社団法人日本森林技術協会(小島孝文理事長)は、委託を受けている(1)ゾーニング支援ツール(通称:もりぞん)(2)省力・低コスト造林事業(3)森林整備事業における補助金の申請・検査のデジタル化のうち、(2)の「省力・低コスト造林技術の普及に向けた研修会」を10月1、2の両日、徳島県下で開催し、有識者による省力・低コスト造林技術の講演や、林野庁がこの春制定した「造林に係る省力化・低コスト化技術指針」の解説及び具体的に省力・低コスト造林技術を導入している事業体での現場視察などを実施した。
徳島会場では、徳島県立農林水産総合技術支援センター資源環境研究課専門研究員の藤井栄氏による有識者講演「省力・低コスト造林技術を計画するために知っておくべきこと」の他、技術指針についての解説が行われ、また、2日目に現地検討会を開催。
徳島県美馬郡つるぎ町内のつるぎ木材協同加工組合の施業地でフォワーダによる苗木運搬等の実際の作業を見学しながら、効率的な作業のあり方などで議論し、意見を交換。この先より問われてくる省力で低コストな造林技術への向き合い方などを共有した。
この研修会はこの先、10月24日の東北会場をはじめ、11月13日に和歌山、12月9日に熊本の3カ所での開催を予定し、省力・低コスト造林技術の周知、浸透を図っていく。問い合わせは、同協会事業部森林保全第2グループ(TEL03・3261・9157)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
第61回全国林材業労働災害防止大会の会長表彰受賞者/林災防 |
|
| |
|
|
| |
林業・木材製造業労働災害防止協会(中崎和久会長)はこのほど、11月21日に山形県山形市内の山形テルサにおいて開催する第61回全国林材業労働災害防止大会における会長表彰受賞者を決定、公表した。それによると、事業場進歩賞が5事業場、また、個人功労賞が11名、個人功績賞が5名の計16名となった。この他、西間薫、外久保蔦雄、江連比出市、榎本長治の4名に感謝状が贈呈される。
受賞者は次の通り。 (氏名敬称略)
【事業場賞(進歩賞)】
▽荒生木材(有)(山形)▽東北ウッドカッター(株)(山形)▽岡部材木店(埼玉)▽木村木材フォレスト(株)(埼玉)▽(株)村山土建(新潟)
【個人賞(功労賞)】
▽佐藤里美(山形)▽渡部伸也(山形)▽水野武雄(福島)▽荒井勇雄(栃木)▽小森正秀(栃木)▽奥野宏幸(埼玉)▽田渕和正(千葉)▽八木寿昭(千葉)▽鶴巻潔(東京)▽野村一芳(東京)▽西川健治(愛媛)
【個人賞(功績賞)】
▽五十嵐茂一(山形)▽村上行治(群馬)▽小林貞信(群馬)▽佐久間雅哉(山梨)▽澤野誠(和歌山)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
国有林野の令和6年度実施状況/躍進2025林業機械(37) |
|
| |
|
|
| |
既報の通り農林水産省が9月30日に公表した令和6年度の「国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況」。令和5(2023)年12月に定めた管理経営基本計画に基づき、推進した取り組みをとりまとめたものだ。公益重視の管理経営の一層の推進をはじめ、民有林に係る施策を支え、森林・林業施策全体の推進へ貢献、「国民の森林(もり)」としての森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等の推進、国有林野の林産物の安定供給が行われている。以下、概要をみる。
トピックスとして「相次ぐ災害への対応」と「地方公共団体と連携した森林経営管理制度の推進への貢献」を取り上げた令和6年度の実施状況では、併せて事例としてウェブサイト掲載分とを合わせ40の取り組みを紹介している。
このうち技術に関連した事例の取り組みと実施森林管理署などは次の通り。
▽育成複層林施業を普及するための現地検討会の開催(四国森林管理局 徳島森林管理署)▽都市近郊での花粉発生源対策の推進(関東森林管理局 千葉森林管理事務所)▽治山事業でのドローンによる資材運搬の効率化(四国森林管理局 嶺北森林管理署)▽災害時に代替路として活用可能な林道の整備(近畿中国森林管理局 三重森林管理署)▽CLTパネルを活用した庁舎新築工事(関東森林管理局)
▽スギ特定苗木の安定需給協定の締結による生産拡大支援(九州森林管理局)▽林地保全に配慮した簡易架線作業システムの導入の推進(東北森林管理局 三陸北部森林管理署)▽樹木採取権制度による林業経営体の経営基盤の強化(中部森林管理局 東信森林管理署)
▽新規就業者育成研修へのフィールド提供(九州森林管理局 佐賀森林管理署)▽職員考案のカードゲームを活用した森林環境教育(東北森林管理局 三陸中部森林管理署)▽関係機関と連携したナラ枯れ被害対策(北海道森林管理局 檜山森林管理署)▽「受け流す柵」による獣害対策(中部森林管理局 愛知森林管理事務所)
▽地方公共団体のシカ被害対策への支援(近畿中国森林管理局 滋賀森林管理署)▽小笠原諸島森林生態系保護地域における観光客による外来植物の駆除体験(関東森林管理局 小笠原諸島森林生態系保全センター)▽倒伏した弥生杉の取扱いに係る検討会の開催(九州森林管理局 屋久島森林管理署・屋久島森林生態系保全センター)
▽町有林と連携した木材販売(北海道森林管理局 上川北部森林管理署)▽モバイル端末を用いたLiDAR計測による現地測量作業の効率化(四国森林管理局)▽林道等の路網計画に係る技術研修(森林技術総合研修所)▽クマ被害の予防に向けた関係団体と協働した森林整備活動(中部森林管理局 富山森林管理署)▽放射性物質を含む土壌の流出を防ぐための森林整備(関東森林管理局 磐城森林管理署)
【ウェブサイト掲載事例一覧】
▽シマフクロウの生息に配慮した森林施業(北海道森林管理局)▽人材育成に係る担い手機関との連携の強化(近畿中国森林管理局)▽国有林モニターを対象とした現地説明会(四国森林管理局)▽グリーン・サポート・スタッフによる保全管理(九州森林管理局 屋久島森林生態系保全センター)▽ドローンによるナラ枯れ被害の早期把握・早期対策(東北森林管理局 青森森林管理署)▽大規模災害発生を想定した職員の防災訓練の本格化(北海道森林管理局)▽国有林野の活用を通じた東日本大震災からの復興への貢献(関東森林管理局 福島森林管理署、磐城森林管理署)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
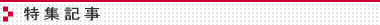 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
米価上昇で販売に手応え/佐賀県特集 |
|
| |
|
|
| |
佐賀県の農業は温暖な気候と肥沃な土壌、恵まれた自然条件を活かして、県南部から県東部にかけて広がる佐賀平野では米や麦といった土地利用型農業が盛んだ。2024年産水稲作付面積は、2万2400ヘクタールで、品種別にみると「さがびより」と「夢しずく」で55%を占める。また、モチ米「ヒヨクモチ」は20%を占め、全国でも有数のモチ米産地だ。24年産米は価格が高騰し、その適正価格に注目が集まった。25年になっても続く米の価格上昇は農業資機材の売上げにも影響を与える。現地の農機販売の動向などを取材した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
市場の概況:農業産出額1284億円/佐賀県特集 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省が発表した、2023年の佐賀県農業産出額は1284億円となった。22年に比べ23億円減少した。耕種部門が70%(901億円)、畜産部門加工農産物部門が30%(383億円)となっている。耕種部門において、米、果実、麦類など概ね増加傾向だったが、野菜の減少が響いた。特にタマネギの減少は顕著で、22年の172億円から101億円減少した。
農業産出額の上位10品目は、米が245億円で1位。以下順に肉用牛(185億円)、ミカン(139億円)、ブロイラー(101億円)、イチゴ(91億円)、タマネギ(71億円)、豚(55億円)、キュウリ(40億円)、アスパラガス(26億円)、小麦(22億円)。同年の生産農業所得は609億円で、22年に比べ21億円減少した。
また、佐賀県中古農業機械流通実行委員会主催の「中古農業機械Web展示会」が10月1日から開かれている。1日の時点でトラクタや田植機、作業機など49台が出品されている。会期は来年2月25日までの約5カ月間。1980年から対面イベントとして開始した中古農機展は、新型コロナ禍の2020年にWebイベントに移行した。始まった当初の会期は1カ月半程度であったが、終了してからも問い合わせが増える傾向があるとして24年から会期を延長している。製品は主に福岡九州クボタやヤンマーアグリジャパンなど、販売会社の各支店から出品されており、展示会の担当者は「ただ販売するだけではなく、その後のメンテナンスなども含め、安心感をアピールしたい」と述べた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
各社の動向:米関連製品の需要高/佐賀県特集 |
|
| |
|
|
| |
(株)福岡九州クボタ(久保雄司社長/佐賀県下17拠点・102人)の24年度実績は、前年をわずかに下回った。佐賀県担当の成清等部長は「23年はトラクタ『SL33L』が牽引したが、24年は同機の終売に伴い売上げが減少した」と説明する。 24年度には「MIRAI農業サポートセンターSAGA(通称:みらさぽ)」が開設され、RTK基地局を設置。これを活用し、後付け自動操舵システムやRTKアンテナキットなどを実演した合同イベントを4月に実施した。7月の価格改定までは順調に推移したものの、その後は伸び悩んだ。
主要機の動向としては、トラクタは50〜60馬力が主力。田植機は品薄の影響で6条植えが減少し、4条植えが増加。コンバインは前年並みで、4条刈が好調だった一方、23年には伸びた2〜3条や5条は減少した。米価上昇の影響で色彩選別機など米関連機器の需要が増加。草刈機関連は特に自走式の伸長が目立った。
25年度も、7月の価格改定を見据え4月に合同展示会を開催。多数の顧客が来場し、GSトラクタや自動操舵システムの実演は高評価を得た。春先から価格改定の周知を徹底したことで駆け込み需要にも対応でき、6月まで売上げは堅調に推移。前年に見られた改定後の落ち込みも、今年は納品ベースで抑制できた。さらに8月には中古農機展を実施し、こちらも盛況となった。
今後は、精度を高めた「GS3」搭載のトラクタを軸に実演活動を強化し、位置情報の正確さや安全性を訴求。廉価版自動操舵システムにも注力する。米価上昇を背景にライスセンター設立の引き合いも増えており、色彩選別機、穀物乾燥機、保冷庫など関連製品の提案を推進していく。次回のイベントは11月、福岡での合同展示会を予定している。
今回の取材は「みらさぽ」で実施した。同施設は27基の整備ピットを備え、県内各地から点検や修理依頼が引っ切りなしに持ち込まれる。サービス売上げはすでに24年度比で2倍に拡大。スタッフの熱中症対策としてスポットクーラーやスマートウォッチ型体温計を導入し、営業とサービスの混成チームによる休日確保や人材育成にも取り組んでいる。成清部長は「ここから九州の働き方モデルを発信したい」と意気込みを語った。
ヤンマーアグリジャパン(株)九州支社(増田広次支社長)北部九州営業部、佐賀ブロックの2024年度の実績は前年並みで推移した。小柳裕弘エリアマネージャーによれば、米の価格上昇などで顧客の購買意欲が高まりつつあった市場の雰囲気に乗じ、トラクタと作業機の実演回数を増加したことで売上げを維持できたという。同年度7月に佐賀・長崎合同の展示会を2日間開催した。4年ぶりとなった合同展示会には多くの来場者が訪れたといい、ムードの良さを感じ取れるイベントになったようだ。
主要機の動向は、トラクタは25〜45馬力が主流。平野地域では60馬力がよく動いた。田植機は中山間地域で4条植えが、平野地域では6、8条が伸長した。コンバインは4条刈が主流で、3条は減少。その他、ドライブハローやあぜ草刈りなどの作業機が伸長した。自走式草刈機が堅調だった。
25年度については、価格改定を4月に実施したが、米価のさらなる上昇で、継続して市場のムードは良い。様子見だった顧客からの問い合わせも増え、大手担い手から助成金を活用しての相談なども増加したという。トラクタに加え、穀物乾燥機や色彩選別機、保冷庫など米関連製品の引き合いが多い。
今年度、後半の推進機種はトラクタに加えて直進アシスト田植機。実演での販促をさらに強化する。また、シーズンが終わる草刈機もラストスパートをかける。乾田直播の提案で播種機も推進している。
アフターサービスでは、シーズン前の農機点検や「安心パック」などパッケージ商材を積極的に販促している。また、農機をモニタリングできるスマートアシストを活用し、すぐに客先に駆けつけるべきか否かの判断をしている。限られた人材では、非常に有効なシステムだ。
(株)ISEKI Japan 九州カンパニー(中谷清社長)北部支社・佐賀系統SSの24年度の実績は前年対比減で推移した。3月に価格改定を実施。駆け込み需要の対応策として2月、JAグループの合同展示会「さが農業まつり2024」に出展。続いて九州カンパニー全体の展示会「初春感謝市in九州」でも実績を維持したが、それ以降は調子を落とし、「例年にないほど厳しい年だった」と岡健太所長は振り返った。米価上昇の影響は少なく、様子見の顧客が多かったようだ。
24年度の主要機動向は、トラクタは23〜25馬力が主流だが、中山間地域の顧客の評価が良い「RTS5」シリーズが振るわず減。田植機は前年並みで5条植え低コスト機が主流。次いで4、6〜8条。コンバインは4条刈が主流。その他、後付け自動操舵システム「CHCNAV」が伸長した。
25年度は7月に価格改定を実施した。駆け込み需要の対応策として2月、JAグループの合同展示会「さが農業まつり2025」に出展したことを皮切りに、拠点別の展示会も開催。9月までの実績は、トラクタ、コンバインの売上げが非常に良く、昨年の不振を払拭できた。「価格改定の時期に合わせたプロモーションが奏功した」と同所長は分析した。
また、米価上昇の影響から、20〜30石の穀物乾燥機や保冷庫など米関連製品も伸長した。24年度は慎重だった顧客も、今年は購買意欲が戻ったようだ。この追い風に乗り、後半はコンバイン「HFR4050」や、新製品のコンバイン「フロンティアマスター」シリーズの実演に注力する。後者は、キャビンの広さや静穏性が顧客から好評だという。
また、レベリングシステム「CHCNAV IC100」と、タカキタの簡易レベラー「マルチグレーダ」を連携した実演も強化。乾田直播の提案にも力を入れているが、播種機の品薄が続いている状況だ。
三菱農機販売(株)九州支社(松尾秀二支社長)佐賀支店(長崎系統含む5拠点・16人)の24年度の実績は前年比減で推移した。これについて香田和磨支店長は、米価上昇の影響で米関連製品やトラクタの動きは良かったが、雨が多かったことなどが影響して二条大麦などの不作や、製品の品薄が続き、実績が落ち込んだとした。
主要機の動向は、トラクタは18〜25馬力「X(クロス)S」が、顧客の需要にマッチして伸長。田植機は4条、6条植えがよく動いた。コンバインは前年比増で、2〜3条刈が主流。その他では、農業用倉庫「ガルックスガレージ」(旧・ダイヤハウス)が伸長した。
今年4月から、業務効率化などを目的として組織改編を実施。佐賀(長崎系統含む)と福岡の拠点は「北九州支店」として統合された。これに伴って九州支社は、それまでの佐賀県鳥栖市から小城市に移動した。
9月までの成果について聞くと、米価上昇の影響で、例年にないほど米関連製品の需要が高まっていると同支店長。特に保冷庫や精米機は引き合いが多いといい、この追い風に乗じて、来年の田植えシーズンに向けて田植機の推進を強化している。
また、10月末〜11月にかけて収穫後の圃場で、ディスクハロー「KUSANAGI MDH1820」と、60〜105馬力トラクタに対応するディスクハローの新製品「KUSANAGI Plus MDH2022」、両製品の実演にも力を入れる予定だ。
その他、紙マルチ田植機「LKE60AD」に関し改めて性能を確認した。1997年の発売以来、「みどりの投資促進税制認定機」として脚光を浴びた同製品を軸に、「今後は有機農業の提案にも力を入れていく」と前向きに語った。
アフターサービスの取り組みは、佐賀の3拠点にサービス専門のスタッフを配置。また、熱中症対策としてスポットクーラーを導入した。セールスも含めてスタッフ全員が農機整備技能士の有資格者であることを活かし、顧客への点検呼びかけを徹底している。スタッフに対してはフレックス制を導入し、労働環境の整備にも取り組んでいる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
JA系統の動き:2024年度、計画上回る実績/佐賀県特集 |
|
| |
|
|
| |
佐賀県農業協同組合(生産資材部農業機械課10拠点・147人)の24年度の実績は、目標を上回り、23年度の実績と同水準で推移した。犬塚智博次長は、主な要因として価格改定前の大型農機の駆け込み需要や、各展示会の成功などをあげた。25年1月末にJAグループ佐賀の展示会「さが農業まつり」を九州佐賀国際空港の特設会場で4日間にわたり開催し、約9万人が来場。農機だけでなく自動車や生産資材なども展示し、キャラクターショーや演奏会なども開催された。
24年度の主要機の動向は、共同購入の4条刈50馬力コンバイン「YH448AEJU」が伸長した。トラクタは40〜50馬力が、田植機は5条植えが主流だった。
25年度は、7月の価格改定に合わせ、駆け込み需要に対応できるよう各地で展示会を開催し、各メーカーからの改定告知を徹底。前年同様に大型農機の実績を伸ばした。 今年後半の推進機種は、前述の共同購入コンバイン。その他、自動操舵システム、直進アシストトラクタ・田植機、ラジコン草刈機などを推進する。また、栽培管理支援システム「xarvio(ザルビオ)」を活用したドローンや可変施肥田植機の実証実験を実施。新規就農者や女性農業者、行政の担当者などを対象に直進アシストトラクタなどを実演する「ICT農機研修会」も実施している。今後のイベントとしては「さが農業まつり」を26年1月末に開催予定。今回も多くの来場者を見込んでいる。
農機サービスの動向は、今年度は農薬散布などドローンのサポート体制を構築。整備・点検内容などを充実している。大型農機の売上げが伸長した影響で、整備修理の依頼は小型農機が中心となったことも特徴だと同次長は話した。
熱中症対策として、工場内にサービススタッフ用のスポットクーラーを導入。農機指導員に対しては「熱中症処置応急セット」やクーラーボックスなどを支給。24年度から変形労働時間制度を導入し、働きやすい労働環境の整備や、技術向上を支援する取り組みも推進している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
県内企業ピックアップ:サンキ工業・麦踏み作業を省力化/佐賀県特集 |
|
| |
|
|
| |
播種機や施肥機を製造販売しているサン機工(株)(相良豊社長・佐賀県杵島郡大町町大町1287)が発売した折り畳み式麦ふみ・鎮圧ローラー「ふみふみ号 スイングローラーRXGS」は、トラクタに装着し3畝を同時に鎮圧する省力化作業機だ。幅広く鎮圧するので折り返す回数が減り、何度も枕地を踏み固める必要がないため、排水が良くなり立ち消えも少なくなるという。作業幅は4270ミリと3270ミリの2展開で、前者なら作業時間は1ヘクタール27分、後者は1ヘクタール40分(どちらも時速5キロの場合)となっている。
サイドローラーは独立構造で、隣の畝に角度違いや段差があっても、一様に鎮圧作業が行える。鎮圧力は2本のスライドロッドのバネ圧で調節し、左右同じ力に設定が可能だ。力が不足しているときはオプションの「RXG用ウエイト」を使用して調節する。サイドローラーは折り畳み式でコンパクトに収納でき、スムーズな移動を実現した。
麦ふみローラー両側の取り付けパイプに、オプションの「スイングローラー用溝切刃セット」を装着すると排水対策が行える。また、本体ローラーとサイドの間に踏み残しが発生する場合は、オプション「スイングローラー用フロントローラー」を装着すれば均等に作業が可能だ。
〈製品仕様〉(1)RXGS―4300:作業時寸法=全長660×全幅4330×全高890ミリ▽移動・格納時寸法=全長1170×全幅2380×全高890ミリ▽重量=390キロ▽作業幅=4270ミリ▽ローラー幅=本体2010ミリ×1/サイド1000ミリ×2▽トラクタ適応馬力=30〜(2)RXGS―3300:作業時寸法=全長660×全幅3420×全高890ミリ▽移動・格納時寸法=全長1170×全幅1870×全高890ミリ▽重量=320キロ▽作業幅=3270ミリ▽ローラー幅=本体1510ミリ×1/サイド750ミリ×2▽トラクタ適応馬力=30〜
問い合わせ=同社TEL0952・71・4007
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
炭素化の取り組み進む/土づくり特集 |
|
| |
|
|
| |
「みどりの食料システム戦略」を踏まえた地球温暖化の防止や生物多様性保全の取り組みの重要性が増している。脱炭素化の取り組みの1つとして、堆肥を使ったり、カバークロップを栽培して土づくりを行うことは、慣行農法と比べて農地の土壌に有機炭素がより多く貯留し、地球温暖化防止に効果があることが認められている。農林水産省の「環境保全型農業直接支払交付金」でも、堆肥散布や炭散布などによる土作りを支援している。土づくりに関連する話題を集めた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
環境保全型農業直接支払いで支援/土づくり特集 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は、化学肥料、化学農薬を原則5割以上低減する取り組みを推進している。令和8年度予算概算要求では、環境保全型農業直接支払交付金等28億7100万円を盛り込んだ。農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るとともに、みどりの食料システム戦略の実現に向けて、農業生産に由来する環境負荷を低減する取り組みと合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全などに効果の高い農業生産活動を支援する。
このうち「環境保全型農業直接支払交付金」は27億5300万円。対象者は農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等。対象となる農業者の要件は、主作物について販売することを目的に生産を行っていること、環境負荷低減のチェックシートによる自己点検に取り組むこと、環境保全型農業の取り組みを広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)を進めること。支援対象活動は、化学肥料、化学農薬を原則5割以上低減する取り組みと合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動。取組拡大加算として、有機農業の新規取組者の受入れ・定着に向けた活動を支援。
「環境保全型農業直接支払推進交付金」は1億1800万円。都道府県、市町村等による環境保全型農業直接支払交付金事業の推進を支援する。支援対象の取り組み・単価は上表の通りで、堆肥の農地への施用などを支援する。また、肥料の国産化・安定供給には8400万円を要求。堆肥等散布機、土壌分析機などの導入支援を行う。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
取り組み事例:炭を土壌に施用/土づくり特集 |
|
| |
|
|
| |
土壌炭素貯留量を増加させ、間接的に大気中のCO2削減に貢献する技術として、土壌へ炭を投入する取り組みがある。木材やもみ殻等を炭化した炭を土壌に施用することで、植物が生育中に吸収したCO2を難分解性の炭素として土壌中に蓄積。炭に含まれる難分解性の炭素は、作物残渣や堆肥等の有機炭素と比較して土壌中で分解されにくく、長期間にわたり土壌中に貯留される。
農林水産省がまとめた「環境保全型農業直接支払交付金取り組み事例」から、炭の投入の事例を拾った。
〈北海道・地域特認〉
令和5年度実施状況は、実施面積:33ヘクタール、実施地域:オホーツク。令和5年度から地域特認取り組みとして、推進。初年度の令和5年度はオホーツク地方の北見市で取り組みが行われている。対象品目は、イモ、野菜類で、タマネギで取り組まれている。
主作物タマネギの栽培期間の後、10月頃に、購入した木炭、もみ殻くん炭など、植物を炭化して製造した炭50キロ/10アールを圃場に投入。植物由来の炭を圃場に施用することで、土壌中に炭素が留まり、大気中に放出される二酸化炭素が減るので、地球温暖化の防止に貢献できる。
北海道では、「北海道クリーン農業推進計画(第7期)」等に即し、土づくりを基本に、化学肥料や化学合成農薬を必要最小限に留めるクリーン農業の取り組みを推進している。この取り組みの普及とともに環境保全意識が向上したことをきっかけに、炭の投入の取り組みが進んだものと考える。今後も、クリーン農業の普及と本交付金を活用した炭の投入の取り組みの推進を図っていく。
〈山形県・地域特認〉
令和5年度実施状況は、実施面積:63ヘクタール、実施地域:鶴岡市。本交付金の創設以前から当該取り組みは実施されていたが、本交付金の普及が進んだことで、取り組み件数及び取り組み面積が拡大している。県内の取り組み面積は、令和2年度3ヘクタール、令和3年度8ヘクタール、令和4年度49ヘクタールと増加傾向で推移しており、庄内地方の水田地域において、主作物は水稲において取り組みが行われている。県内で取り組みの多い庄内地域では、鶴岡市を中心に取り組みが行われている。耕起前の4月頃に、ブロードキャスタ等を用いて、炭(もみ殻くん炭等)を50キロ/10アール施用している。
この取り組みにより、地力の維持や土壌の物理性の改善、ケイ酸補給による生育の向上などの効果がみられている。
県では有機農業の推進のため、県内の熟練有機農業者を「やまがた有機農業の匠」として認定し、新たに有機農業に取り組む農業者に対して、栽培技術や経営指導などのサポートを行う体制を設けている。本交付金における県内の有機農業取り組み面積は、令和2年度626ヘクタール、令和5年度726ヘクタールであり、増加傾向で推移している。特に、ソバにおける取り組み面積が増加している。
〈滋賀県・地域特認〉
令和5年度実施状況は、実施面積:96ヘクタール、実施地域:長浜市、甲良町、彦根市等。平成24年度から地域特認取り組みとして、推進を行っている。県内では、湖東地域、湖北地域を中心に取り組みが行われている。対象品目は水稲、野菜、果樹、茶で、多くは水稲において取り組まれている。
甲良町では環境にやさしく食味の良い米づくりを目指し、町内の7つの農業法人により、「甲良集落営農連合協同組合」を設立。土壌の有用微生物の増殖効果等が良食味米生産につながることを期待し、炭を圃場に投入している。
炭は木炭を用い、12〜2月頃に1500リットル(150キロ)/10アール前後の量を投入している。現在、5つの農事組合法人が共同生産に取り組み、安定した供給量を確保している。地元企業と連携して、炭と堆肥を混ぜた資材を開発。良食味と安定供給によって、独自の農業ブランドとしてPR。大手量販店と契約を結び、需要に応じた生産・販売を実現している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
日本土壌肥料学会が新潟大会開催/土づくり特集 |
|
| |
|
|
| |
日本土壌肥料学会(信濃卓郎会長)は9月、新潟市西区の新潟大学五十嵐キャンパスにおいて日本土壌肥料学会2025年度新潟大会を開催した。大会では土壌肥料学における最新研究成果が口頭発表やポスター発表にて発信され、シンポジウム等を通じて広く知見が共有された。
大会では2025年度日本土壌肥料学会賞等授賞式ならびに記念講演も行われた。各賞の受賞者と受賞業績は次の通り(敬称略、受賞者、受賞業績題目)。
〈第70回日本土壌肥料学会賞〉▽大津(大鎌)直子(東京農工大学農学研究院)、「グルタチオン分解経路の解明を通じた植物のイオウ代謝制御研究」▽程為国(山形大学農学部)、「土壌・植物系における炭素・窒素の動態に及ぼす土地利用管理と気候変動の影響に関する研究」▽三宅親弘(神戸大学大学院農学研究科)、「光合成の酸化障害回避メカニズムの解明と植物栄養診断法の開発」
〈第30回日本土壌肥料学会技術賞〉▽徳田進一(農研機構中日本農業研究センター)、「茶園・野菜畑における環境保全型土壌管理技術の開発」▽林哲央(道総研酪農試験場天北支場)、「積雪寒冷地の施設栽培における土壌診断および肥培管理技術の高度化とその利活用」
〈第43回日本土壌肥料学会奨励賞〉▽佐藤匠(ナガセケムテックス(株)播磨事業所)、「アーバスキュラー菌根菌の有機態リン酸可給化機構と農業利用に関する研究」▽鈴木一輝(新潟大学農学部)、「農耕地における土壌微生物生態に関する研究」▽西垣智弘(国際農林水産業研究センター)、「サブサハラアフリカにおける土壌保全と作物生産性向上に資する肥培管理に関する研究」▽Nguyen Thanh Tung(山形大学農学部)、「耕畜連携水田における養分収支と土壌肥沃度維持に関する研究」▽Raj Kishan AGRAHARI(東京大学大学院農学生命科学研究科)、「遺伝子発現データを使ったゲノムワイド関連解析と化学遺伝学による新規アルミニウム応答機構の発見」
〈第14回日本土壌肥料学会技術奨励賞〉▽鈴木基史(愛知製鋼(株))、ムギネ酸類誘導体の実用化研究▽和田巽(岐阜県農業技術センター土壌化学部)、「土壌診断に基づく適正施肥を推進するための生産現場適用技術の開発」
〈日本土壌肥料学雑誌論文賞〉▽宇野功一郎、中尾淳(京都府立大学大学院)、奥村雅彦(日本原子力研究開発機構)、山口瑛子、小暮敏博(東京大学大学院)、矢内純太(京都府立大学大学院)、「放射性セシウム捕捉ポテンシャルから推定されるKd値と実測Kd値との誤差要因の解明」▽森下瑞貴、石塚直樹(農研機構農業環境研究部門)、「ドローン空撮画像の教師なし分類による圃場内土壌区分図の作成」
〈SSPN Award〉略
また、同大会で特別招待講演をする予定だった国際土壌科学連合(IUSS)のVictor O.Chude会長は急遽来日取りやめとなったものの、後日、日本土壌肥料学会ホームページにて、同会長による講演動画「土壌学における国際的課題と若手研究者への期待」、「国際土壌科学連合の役割と現在の活動」が公開された。ここでは前者の一部概要をみる。
土壌は地球上の供給、調整、支持などを含む幅広い生態系サービスを提供しており、人類の生存はこれらの重要なサービスを提供する健全な土壌に依存している。土壌の劣化は目に見えずゆっくりと進行し、農業生産量を低下させ、生物多様性の喪失を加速して、環境ショックに対する地域社会の回復力を弱める。世界的な食料安全保障、生態系の健全性、持続可能な開発は全て人為的・自然的要因の両方による土壌劣化のリスクにさらされている。健全な土壌は、生産力や生物多様性、貯水、炭素回収などの生態系の機能を備えており、土壌の健全性は農業生産と生態系サービスの提供の両方を継続的に支えるものである。
土壌科学は持続可能な農業や環境管理、気候変動へのレジリエンスの中心として長い間認識されてきたものの、健全な土壌の保全に対する現在の行動は不十分であり、土壌専門家を育成するためのパイプラインは弱く、断片化されている。人口増加や食料不安など世界の変化に対応するために若手専門家への投資が緊急的に必要である。若手専門家に高度な科学的知識を身に着けさせ、教育を行うことで、将来を見据えた解決策が見いだされ、より持続可能で回復力のある未来を創造する世代の可能性が切り開かれるだろう。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
安全な技術を林業へ/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
「鳥取でNo.1を決めようぜ!」のキャッチフレーズで開催される第4回日本伐木チャンピオンシップin鳥取。18、19の両日、鳥取市内の鳥取砂丘オアシス広場を会場に開かれるこの大会は、文字通り、腕に自信のある全国各地のチェンソーマンがエントリー、一堂に集う。チェンソーの使い手No.1を決めるとともに、世界に伍して競い合う日本代表を選出する場でもある。日頃磨いた技術を惜しみなく披露し、林業現場での安全作業や段取りの重要性、正確性、スムーズな展開などを確認するのにまたとない機会として、歴史を重ねているJLC。林業のポテンシャルを高め、可能性を引き出す役目を担おうとしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
日本代表を選出、林業界が後押し/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
鳥取でNo.1を決めようぜ!―18、19の両日、鳥取県鳥取市の鳥取砂丘オアシス広場で、「第4回日本伐木チャンピオンシップin鳥取」が開催される。来年3月にスロベニアで行われるWLC(世界伐木チャンピオンシップ)に参戦する日本代表(プロフェッショナルクラス3名、ジュニアクラス、レディースクラス各1名)の選考大会となるもので、2014年の第1回大会から2024年の第5回大会までは青森県で実施され、この間、鳥取県でも競技会が継続的に開かれてきたが、今回は初めて日本代表を選出する公認大会となった。
参加希望者が定員を超えたため、抽選で出場者を決定し、プロフェッショナルクラス59人、ジュニアクラスおよびレディースクラス各10人のチャレンジャーが競技にのぞむ。初日の午前9時40分から予選会がスタートし、簡易伐倒、接地丸太輪切り、枝払いの3種目で獲得したスコアをもって翌日の決勝大会への参戦の可否が決まる。
決勝大会は、午前中にマストツリーを使った伐倒の技を競い、午後はソーチェン着脱、丸太合わせ輪切り、接地丸太輪切り、枝払いと、WLCと同じ種目をこなす。枝払い競技は、それまでのスコア順で2人同時に競い合う形式となるため、1位、2位の選手が最後のチャンピオンの座をかけ白熱の戦いを繰り広げる、まさに見ものの場面が展開される。
JLCは林業界にとっても自己アピールに有用なイベントであり、今回は地元・鳥取県で合板の製造・販売を進める(株)日新をはじめ、チェンソー供給企業のハスクバーナ・ゼノア(株)(埼玉県)、(株)やまびこ(東京都)、(株)スチール(栃木県)、林業機械をレンタルする(株)レンタルのニッケン(東京都)、そして全国森林組合連合会とそのグループ企業の組合林業(株)、農林中央金庫をメーンスポンサーとし、そのほか数多くのサポーティングスポンサー、後援団体が後押しする。また、森林環境譲与税の活用、森と水の森林ファンドの助成を受けて実施される。
会場は県内有数の観光地である鳥取砂丘の東側に位置する多目的広場(左図)で、JR鳥取駅からの所要時間は車で約25分、山陰近畿自動車道福部ICからは同じく約6分。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
JLCの歴史を振り返る/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
今回で第6回目を数え、鳥取県で行われてきた「日本伐木チャンピオンシップin鳥取」を公認大会として認定、初めて青森県以外での大会開催と歴史を積み重ねている日本伐木チャンピオンシップ(JLC)。当初、プロフェッショナル部門だけだったものが、U―24のジュニアクラスと女性を対象とするレディースクラスを加えるなど門戸を広げている。
大会としては、技術レベルの向上が図られるとともに、出場する選手の数も回を重ねるごとに増加、名実ともに日本を代表するチェンソーの競技会としての地歩を固めている。ここ2大会は、出場選手を抽選で選出する事態となっている。
これまで開かれた5回の大会を振り返ってみよう。
記念すべき第1回大会は、平成26年5月11、12の両日、青森県青森市にあるモヤヒルズで開かれた。大会の名称は「WLC2014第1回日本伐木チャンピオンシップin青森」。8県から20名が出場した。歴史に名を刻む初代のチャンピオンに輝いたのは、青森県の前田智広氏((有)前田林業)、5種目の合計得点は1376点だった。
第2回大会は、2年後の平成28年5月21、22の2日間、同じモヤヒルズで開かれた。出場選手は31名。前田智広氏が見事連覇を果たした。合計得点も1537点と前回を大幅に上回り、技量のアップを示した。
この第2回は女性が初めて出場した大会として記録される。現在、一般社団法人林業技能教育研究所の所長として安全講習・研修の講師として全国を駆け巡っている飛田京子氏が参戦した。
そして回を重ねるごとに出場選手、規模も広がっている。平成30年5月19、20の両日、モヤヒルズを会場に開かれた第3回大会には、22都道府県から68名が参加。この大会からプロフェッショナルとともに24歳以下のジュニアクラスが設けられた。エキシビジョンで韓国から2名が参加するなど国際色も帯び始めた。また、参加選手の増加に伴い、大会初日に決勝出場選手を決める予選制度が採用された。
第1位は、青森県の(有)マル先先崎林業に勤める先崎倫正氏。前田氏の大会3連覇を阻んだ。この両名と青森県森林組合連合会の秋田貢氏の3名、そしてジュニアクラスでトップの横山大蔵氏(当時は岡山県の(株)岡田林業所属)の4名がWLC日本代表として出場した。
この大会で特筆すべきは、優勝した先崎氏の得点が過去最高だったのをはじめ、上位4名の得点が1500点を突破していることだ。出場選手の競技力が明らかにレベルアップし、出場選手全体の技能レベルも向上していることを示すものといえる。
そして新型コロナウイルスがあって延期を余儀なくされた第4回大会が令和4年5月21、22の2日間、モヤヒルズを会場に開催された。まだ5型に移行する前とあって、新型コロナウイルス対策を講じての大会となったが、24都道府県から97名が参加し、出場選手数としては過去最高となった。
この第4回大会は、初めてレディースクラスが独立し行われた大会。プロフェッショナル、ジュニアと並ぶ3クラス体制となった。世界大会であるWLCがレディースを設けていることを受けて設置したものだが、優勝した青森県ウッドホープ(株)の岡田望氏は男子のジュニアクラスでも第2位に相当する1441点を獲得した。世界大会でも種目別とはいえ、金メダルを獲得する快挙を達成した。
そして前回大会となる第5回は2024年6月1、2の両日開催。それぞれプロフェッショナル57名、ジュニア9名、レディース10名が出場した。優勝したのは、ジュニアクラスでWLCに出場した経験を持つ高山亮介氏((有)矢守産業)。横山大蔵氏(下仁田森林組合)第2位、杉本和也氏(岐阜県立森林文化アカデミー)第3位。U―24のジュニアは山岡空氏((有)矢守産業)、レディースは武藤唯氏が第1位となった。この5名が同年9月開催のオーストリアの第35回WLCに日本代表として出場した。
ちなみに高山選手の種目別の得点は、伐倒640点、ソーチェン着脱130点、丸太合せ輪切り185点、接地丸太輪切り226点、枝払い416点の計1591点。過去4回に比べて最も高い得点となった。
このようにJLCは回を重ねるごとに規模、質ともに充実してきており、世界を目指すレベルの高い大会に成長している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
正確性、スピード競う競技5種目/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
JLCは、伐倒、ソーチェン着脱、丸太合せ輪切り、接地丸太輪切り、枝払いの5つの種目で競技が行われる。
競技内容と得点配分はどのようになっているのか。実行委員会がまとめた競技概要からみた。5種目の最高得点を合わせると、1690点に達する。
【伐倒】
自分で定めた標柱(標柱)にできるだけ接近して倒せるよう、選手は3分以内に木を伐倒する(3分を超えると減点)。5種目の競技の中で最も配点が高く、安全作業を意識しながらの正確性が求められる。林業の事故で最も多い“かかり木(倒す木が隣の木などに引っ掛かってしまうこと)を防ぐことなどを想定し、狙った場所への正確な伐倒技術、伐倒後の退避が重要なポイントとなる。
競技最高点:660点
【ソーチェン着脱】
選手はソーチェンを外し、バーの上下を入れ替えて取り付け、別のソーチェンを装着し、0.1秒単位で測定され、採点。次の2競技である「丸太合せ輪切り」と「接地丸太輪切り」の間はチェンの調整ができないため、着脱のスピードだけでなく正確さも求められる。なお、次の2競技でソーチェンやバーカバー、ナットが外れた場合は、この競技の得点は0点になる。
競技最高点:約134点
【丸太合せ輪切り】
選手は地面から7度に傾いた2本の丸太を垂直に上下から切り出し30〜80ミリの厚さに輪切りにする。切り出す順番は下側から半分、残りを上側と順序が決まっており、赤いラインの中で合わせなくてはならない。林業では、傾いた状態で木を輪切りする作業になりがちのため、チェンソーの角度を巧みに変えて、丸太を垂直に切る技術が試される。
競技最高点: 200点
【接地丸太輪切り】
地面に接地している2本の丸太を上から垂直に30〜80ミリの厚さに切り出す。丸太が接地面の表面とどこで接しているか分からないように、接地面の上は薄くおが屑で覆われている。チェンソーで接地面にキズを入れると、この競技のポイントは0点。採点は、垂直の正確さとスピードで競う。
競技最高点:約250点
【枝払い】
6センチの丸太にまっすぐ差し込まれた30本の枝を切り払いする。どの選手も共通のパターンで枝払いを競う。枝払いの跡が5ミリ以上残ったり、丸太に深さ5ミリ以上または長さ35センチ以上の傷がつくと減点対象となり、また、チェンソーのバーが立ち位置にある時に歩いた場合も減点となる。スピードと安全性、正確性が求められる競技。
最高点:約450〜460点(スピードと正確さが加算ポイント)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
白書でも世界大会での躍進紹介/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
JLC(日本伐木チャンピオンシップ)は林野庁がまとめている森林・林業白書に取り上げられるようになっている。令和5年度の森林及び林業の動向では、林業労働力の動向のコーナーで「高度な知識と技術・技能を有する従事者育成」の一環として「チェーンソー作業の正確性や安全性を競う日本伐木チャンピオンシップが開催されている。林業技術や安全作業意識の向上、林業の社会的地位の向上、新規就業者数の拡大等を目的としており、優秀な成績を収めた選手は世界伐木チャンピオンシップの代表として選出されている」と言及し、事例Ⅱ―1に「世界伐木チャンピオンシップでの日本人選手の活躍」を取り上げ、写真入りで次のように紹介している。
「世界伐木チャンピオンシップ(WLC)の第34回大会が令和5(2023)年4月にエストニアで開催され、我が国からは5名の選手が参加した。
国別総合順位(プロクラス3名の合計点により判定)では、前回の第18位から大きく順位を上げて第6位に入った。ジュニアクラスでは「丸太合せ輪切り」(丸太を上下から垂直に切る種目)で高山選手が第2位の成績を収め、さらにレディースクラスでは岡田選手が同種目で第1位を獲得した。
日本人として初めて金メダルを獲得した岡田選手は、平成26(2014)年の第1回日本伐木チャンピオンシップ(JLC)の見学をきっかけに林業に就業しており、全国各地で開催される競技大会は、林業の社会的地位向上や新規就業者数の拡大にも寄与している」。
そして令和6年度の森林・林業白書でも、JLCの開催に触れており、「優秀な成績を収めた選手は世界伐木チャンピオンシップ(WLC)の代表として選出されている。令和6(2024)年9月にオーストリアで開催された第35回WLCにおいても、日本人選手が活躍した」と伝えている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ロガーズ例会で技術確認/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
2023年にエストニアで行われたWLCに日本代表として参戦した今井陽樹氏は、我が国のチェンソー競技会を牽引してきた1人であり、NPO法人ロガーズ(群馬県)の代表を務め、海外遠征を含めて自ら技量アップの鍛錬を重ねるとともに、林業者らの連携、仲間づくりにも意をおき、毎月、競技会に向けた練習会、勉強会を実施している。ちなみに同氏は、鳥取県で開かれたJLCで第1回、第2回と優勝を飾り、鳥取とは相性がいい。
9月14日の例会には、2018年のノルウェー大会にジュニアクラス代表で参戦、以降、プロフェッショナルクラスで2023年(エストニア)、2024年(オーストリア)と連続して世界大会を経験している横山大蔵氏をはじめ、星野智也、川村岳、畠山直樹、黒岩英高の各氏、合計6氏が出席。黒岩氏以外は前回のJLC参戦者だが、星野氏は残念ながら抽選に外れ、今回のJLC参加の権利は得られなかった。「もっと過去の実績に配慮したやり方があれば」とは周囲の声。
会場は、埼玉県神川町の農地に囲まれた場所に設置されている。午前9時半、準備が整ったところでジャンケンで順番を決め、ソーチェン着脱からスタート。使用チェンソーは今井、横山の両氏はやまびこ・エコーCS7330P、黒岩氏は同・シンダイワE3073DP、星野、川村の両氏はハスクバーナ572XP、畠山氏はスチールMS500i。各々の愛機を自分で最もスピーディーかつ確実に扱える方法で操り、スコアを稼いでいく。
今井、横山の両氏は、やまびこ(エコー)のアンバサダーを務めており、機会を捉えJLCを模したデモでその技術を披露し、安全作業の大切さを伝えている。先に宮城県で開かれた林業機械展示会の同社ブースのもようは別掲の通りだ。
丸太輪切りや簡易伐倒、枝払いと、使う材の調整あるいはルールに則った条件づくり、また、ジャッジは全員が交替で進める手づくり感あふれるものだが、基本・規則はしっかりとおさえ、JLC本番さながら。さらに冗談を交えながら今井氏、横山氏が指摘する改善点は、皆真剣な表情で受け止め、温かさの中に進歩・進化を目指すまさにアスリートの空間を形成していた。
今井氏は、若い人の参加が増え、その技術のレベルアップが早くて楽しみと話す一方、仕事人・家庭人世代としての練習の場づくりや時間確保の難しさを指摘。さりながら自身の技術力に関しては「伸びしろしかない。これまでの色々の経験を踏まえ、変化の中で自分の引き出しも増えたので、掘れば掘るほど出てくるというか、それだけこの競技は奥深い」とし、加えて海外遠征を含め、共通の志を持った仲間との交流により多くの価値を見出してもいる。
JLCに関わった当初は独身。その後家庭を持ち子供が生まれと、大きな環境変化とともに競技者人生を送ってきた横山氏は、「どううまく競技と関われるか模索しているところ」としつつ、「いままでは大会自体少ないこともあり、とにかくいい結果を出そうとやってきたが、心持ちを変えて丁寧にやろうと臨んでも、結果はさほど変わらない。練習は本番のように、本番は練習のようにといわれる通り、ふだん通りをいかに再現できるかどうかが大事」と強調。「そこに行きつくために、技術はもちろんだが、それ以上に精神の持ちように重きを置いている」と。
長野県から参加した川村氏は毎月例会に参加し、今回のJLCは3回目のトライで、本番でその成果を出したいと。大会に向けては、「まず接地丸太輪切りで切り込みすぎないこと」と課題を示し、「やはりふだん通りにやることを自分に課して、決勝大会に残りたい」と目標を示した。
岩手県で林業・バイオマス関連企業に勤める畠山氏は、県内の競技経験者に誘われてから4年が経過した。「最初の頃に比べれば、技術的には雲泥の差」といい、「目標はもちろん優勝」と。毎回例会に参加し、また勤め先や自宅敷地内での練習と、世界を目指し情熱を傾ける日々を過ごす。
黒岩氏は群馬県環境森林部林業振興課に勤務し、林業担い手の研修や農林大学校の学生指導などに当たる。「学生の頃から安全な作業を認識してほしいですし、競技への参加で仕事に活きることは多々ある」と述べ、県内林業の安全性向上を願いつつ初の競技会にのぞむ。
星野氏は抽選で鳥取大会を逃したが、所属する森林組合の仲間は参加。後進の指導でも競技会の内容は活きると話し、自らの技量を高めながら現場への還元を進める。ちなみに今回の例会では3位のスコアをつけた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
みやぎ林機展でやまびこ、ハスクバーナがデモンストレーション/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
宮城県で開かれた森林・林業・環境機械展示実演会の会場では、(株)やまびことハスクバーナ・ゼノア(株)の2社がJLCを模したデモを展開、見事なチェンソー操作技術を披露するとともに、安全・的確な作業の重要性をアピールした。
(株)やまびこのブースでは、今井陽樹、横山大蔵の両氏が「エコーCS7330P」を使用して3競技に挑んだ。同製品は本格伐倒作業から伐木競技まで兼用できる国産大排気量チェンソー。73・5立方センチエンジンの大排気量を引き出すドライブトレインは、最大70センチガイドバーも余裕でこなせる。高出力と高効率燃焼を新設計の6流掃気で実現。理想的な混合気が燃焼室内に生成され、最適な燃焼によって高出力と低排出ガスを両立した。
ソーチェン着脱で今井氏は「落ち着いて、ゆっくり動きを確認しながら取り組むことが上達の近道」と説明。また、デモを終えた横山氏は「大勢の人の前で披露することの難しさを感じた。自宅で練習している環境とは大きく違うが、楽しい瞬間でもある」と振り返った。
ハスクバーナ・ゼノア(株)の小間では、高山亮介、山岡空の二氏がデモ。使用機種の572XPは強力な4・3キロワットエンジンを搭載していながら重量はわずか6・6キロ。優れたパワーウェイトレシオを実現しており、従来機よりも鋸断性が12%向上。圧倒的なパワーとハイレスポンスを実現している。
仕事でも休日でも毎日チェンソーを触っているという山岡氏は、林業の魅力について「自然の中で作業をして1本ずつ特徴が違う木を切り倒すことの楽しさを痛感している」と話した。
また、高山氏は、572XPは、仕事でも競技でも最適な機種。チェンソーは縦だけでなく、横や斜めに使うこともあり、その際のバランスが良い。狙ったところに木を倒せる楽しさ、機械を思い通りに動かせる嬉しさを日々の仕事で感じていると話し、競技については、「丁寧にやることを意識し、本番で最大限の力を発揮したい」とコメント、鳥取大会への意欲を示した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ハスクバーナ・ゼノア 白川英夫氏に聞く:安全な林業の一助に/JLC in 鳥取特集 |
|
| |
|
|
| |
ハスクバーナ・ゼノア(株)(パウリーン・ニルソン代表取締役・埼玉県川越市南台1の9)は、スウェーデン本社から講師を招き、理に適いかつ安全な立木伐倒・枝払い・造材のポイントを指導する伐木造材講習会を独自に実施、併せて安全装具・用具の重要性をアピールし、各地で安全意識を醸成してきた。長年の取り組みは、地域の林業者と結びついてWLCに日本選手を送り出すまでに成長、JLC立ち上げにもつながった。JLCメーンスポンサーでもある同社の白川英夫マネージングダイレクターにこの間の経緯やJLC、WLCに向けた同社の考え方を聞いた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
