| |
|
|
| |
農経しんぽう |
|
| |
令和7年1月20日発行 第3536号 |
|
| |
|
|
| |
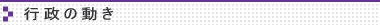 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
「海外から稼ぐ力」強化へ/政府・関係閣僚会議 |
|
| |
|
|
| |
政府は10日、総理大臣官邸で第21回農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議を開催し、輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化について議論が行われた。林内閣官房長官は、地方創生2・0を強力に進めるためには、農林水産業を儲かる産業にしていかなければならないとした上で、「新たな食料・農業・農村基本計画において、『海外から稼ぐ力』の強化を新たな柱として位置付ける必要がある」と述べ、各省庁の連携を求めた。農林水産省からは、米輸出の最大化に向けた施策を強化することとし、スマート農業の導入と低コスト生産技術の定着や、輸出産地の規模拡大等に伴う精米施設、乾燥調製施設の整備などの方針が示された。
林官房長官は会議で、「農林水産業は地方の成長の根幹であり、地方創生2・0を強力に進めるためには、農林水産業を儲かる産業にしていかなければならない。このため、新たな食料・農業・農村基本計画において、『海外から稼ぐ力』の強化を新たな柱として位置付ける必要がある」とし、「稼ぐ力を強めるためには、農林水産物・食品の輸出拡大を加速化することに加えて、食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費の拡大の取り組みを強化し、双方の施策の相乗効果を高めることが重要」だと指摘した。
その上で、農林水産物・食品の輸出拡大を加速するための4つの取り組み強化を要請。
まず、先般決定した経済対策では、前回の本閣僚会議での指示を踏まえ、輸出向けの供給力の向上、国内外の流通体制の構築、非日系など新市場の開拓のための施策が盛り込まれた。これらの施策を迅速・適切に執行し、幅広い品目で、国内から現地まで一貫してつなぐサプライチェーンを構築する。
次に、輸出の再開・拡大に向けた協議を前に進めるため、昨年9月に、日中間で、ALPS(多核種除去設備)処理水の海洋放出と日本産水産物の輸入回復について認識が共有されたが、関係閣僚は、中国による水産物の輸入停止措置の解除始め、諸外国・地域による輸入規制の早期撤廃の実現に向けて、政府一丸となって取り組んでほしいと指示。
また、優良品種をしっかりと守っていくため、海外における無断栽培を抑止しつつ、海外からの稼ぎにつなげるため、海外でのライセンス生産を戦略的に推進するとともに、厳格な国内管理を進めるため、制度的枠組みの整備を検討するなど、対策を強化を求めた。
最後に、ブランド化等による高付加価値化に向けて、地理的表示(GI)保護制度について、現在、登録数は148産品まで増えており、2029年の200産品目標の達成に向け、更なる活用を進めるとともに、加えて、外国人の関心が高い日本のアニメやキャラクターなどのコンテンツ、「伝統的な酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録などを絡めたブランディングの促進を提示した。
また、食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費は、それ自体、稼ぐ力の強化につながると同時に、日本食・食文化の浸透や日本食ファンの増加を通じて、農林水産物・食品の輸出拡大にもつながるもの。このため、海外展開や食関連消費を拡大するための効果的な施策について、施策の効果を検証するための目標のあり方とともに、具体的な中身の検討を開始。これらの施策の強化・検討に当たっては、民間の知見を活用するとともに、農林水産省のみならず、経済産業省、外務省、観光庁、国税庁始め、関係省庁の連携を強める必要があると述べた。
農林水産省から提出された資料によると、米輸出の最大化に向けた施策の強化の方向として、米の大規模輸出産地拠点を形成することとし、農地の大区画化やスマート農業の導入等を通じて生産コストを削減し、輸出用米の生産を拡大を図る。具体的には、ドローン・直進キープ田植機などのスマート農業技術の活用により、農薬散布や田植え作業が省力化。労働時間の抑制や施肥量の低減によりコストを削減。
また、フラッグシップ輸出産地(年間の米輸出1000トン超)を、現在の2産地から拡大することを目指し、輸出産地の規模拡大に対応し、精米施設、乾燥調製施設を整備する。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
未来のコメづくりシンポジウム開催/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は15日、都内霞が関の同省会議室及びWebで第2回未来のコメづくりオンラインシンポジウムを開催した。令和5年度より実施している低コスト・低メタン国産米の生産・輸出実証事業の一環。同省は昨年2月より乾田直播・節水灌漑(マイコスDDSR)による「超低コスト・低メタン輸出米」の栽培体系確立に向けて、全国の8つの農業法人、国内外の資材メーカー及び研究機関が参画する「超低コスト・低メタン輸出米官民タスクフォース」を発足し、栽培・輸出実証事業を進めている。今回は同省及び同タスクフォースのメンバーから、昨年行われた生産実証の結果共有をはじめ、除草体系、農業資材、GHG測定状況等、輸出に向けた取り組みなどについて情報提供が行われた。
まず同省が昨年実施した生産実証について説明した。昨年は仮説「菌根菌+土壌改良資材(ビール酵母等)を用いて、乾田直播と不耕起で水稲多収米を栽培し、慣行に比べ生産コスト6割削減」を実証するべく、全国の北海道から中国・四国の6地域にて、8生産者が全54パターンの生産実証を行った。パターンは耕起・不耕起や湛水・節水・天水、バイオスティミュラント資材のあるなしなどの形で、様々な品種を地域特性等を加味した上で栽培したもの。その結果、収量が多く取れた箇所を中心に、1キロ当たりの生産コスト100円未満を達成した生産者が出たという。また、収量が低い箇所についても、1反当たりの生産コストは大きく下がっている結果が得られたとした。
次いで、栽培実証を行った生産者3人が昨年の結果を報告。埼玉県杉戸町のヤマザキライスは節水型マイコスDDSRを昨年4月30日にドリルシーダーで乾田直播。出芽後も順調に生育し、酷暑の夏となったが、乾いた時に入水する形で通水は5回のみで、無事収穫を迎えたという。耕起・播種・育苗・代かき・田植え・水管理が不要となり、同社比較で慣行に比べ設備機械コストは6割減、投下労働時間7割減を達成した。これにより、昨年産は1キロ当たり生産コスト120円、売上高のうち生産原価は40%を実現。将来的には同75円、同32%に達する見込みとした。バイオスティミュラント資材の登場により出芽後の水張りをほぼしなくても良くなり、パワーハロー↓ドローンまたはブロードキャスタによる散播↓ケンブリッジローラーまたはニプロスリップローラーシーダによる覆土という簡素な播種体系で、小中規模の農家でも取り組めるという。一方で、場所によっては収量が取れない、枯れてしまった箇所もあったとし、適地適作の水の使い方が重要となることや、雑草の管理、連作障害などが問題になるなどと語った。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
第1弾の生産革新計画を認定/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は15日、スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定第1弾を発表した。今回は(株)おしの農場(山形県天童市)ならびに(株)山正(山形県天童市)の2事業者の計画が認定された。
計画概要をみると、両社とも「栽培管理システム」から得られた圃場ごとの地力・収量等のデータを他の生産者と共有し、その分析結果を用いて翌年度の圃場ごとの最適な施肥設計を実施。また、当該データは労働力の平準化のための作業計画にも活用するとともに、施肥に当たっては、農業用ドローンによる可変施肥を利用することで、省力的に圃場ごとの施肥作業を実施し、収益性を向上―としている。これにより、補助事業の優遇措置の活用を計画。
昨年施行されたスマート農業技術活用促進法では、スマート農業技術の活用及び併せて行う農産物の新たな生産方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)を農林水産大臣が認定し、認定を受けた事業者は、金融・税制等の支援措置を受けることができる。今回の計画認定により、スマート農業技術の活用や農産物の新たな生産の方式の導入を通じて、農業の生産性が向上していくことが期待される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
スマート農業開発供給計画を初認定/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は昨年12月24日、「スマート農業技術活用促進法」に基づく開発供給実施計画を初めて認定し公表した。
同法は昨年10月に施行され、農業にて特に必要性が高いと認められる「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」を農林水産大臣が認定し、計画実施事業者は金融・税制等の支援措置を受けられるというもの。今回、(株)Root、(株)アクト・ノード、(株)NTT e―Drone Technologyの3社が計画を申請し、全て認定された。これが認定第1弾となる。各計画概要は次の通り。
(1)Root(申請代表者)=スマートグラス用のAR(拡張現実)技術を用いた農作業補助アプリについて、適用場面の拡大に向けた機能拡充や改良を行うとともに、アプリ搭載グラスのレンタルサービスを行う。これにより、播種、移植作業等の畝立てに要する作業時間を20%削減。活用する支援措置は日本政策金融公庫の長期低利融資。
(2)アクト・ノード(申請代表者)=柑橘栽培において、育成環境や果樹の育成状況をデータ収集し、灌水や施肥の最適化や自動化を実現する「デジタルデータ統合型マルドリ自動潅水システム」の開発と供給を行う。これにより、柑橘の潅水・施肥の労働時間を60%削減。活用する支援措置は登録免許税の軽減。
(3)NTT e―Drone Technology(申請代表者)= 傾斜地の柑橘防除における労働時間の削減や、衛星やドローンで取得したセンシング結果に連動した可変施肥等による作業の効率化及び環境負荷の低減に係る国産大型ドローンの供給を行う。これにより、柑橘の防除作業(手散布)の労働時間を80%削減。活用する支援措置は農研機構の研究開発設備等の供用等。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
最新スマート農業技術を発信/埼玉県、行田市など |
|
| |
|
|
| |
埼玉県、行田市及び北埼玉スマート農業研究会は昨年12月25日、埼玉県行田市の行田グリーンアリーナにおいて、「スマート農業技術実演・展示会」を開催した。県がスマート農業の普及推進のために実施している埼玉県スマート農業普及推進プラットフォームの取り組みの一環で開催したもので、今回で2回目。
同プラットフォーム会員企業31者によるスマート農業技術の展示をはじめ、関東甲信クボタやヤンマーアグリジャパン、トミタモータースなどによる実演会、はせがわ農園代表取締役・長谷川浩氏によるスマート技術導入事例発表講演会などが行われ、これには近隣農家など約300人が来場し、最新のスマート農業技術を熱心に確かめ、吟味していた。また、文部科学省副大臣・野中厚氏や埼玉県知事・大野元裕氏、行田市長・行田邦子氏も視察に訪れた。
講演会冒頭、開会あいさつした大野知事は、大勢の参加者に謝意を述べ、昨今のスマート農業をめぐる情勢は10月にスマート農業技術活用促進法が施行されるなど大きな変化を遂げつつあるとし、埼玉県としてもスマート農業技術活用促進資金などで普及促進に力を入れていると説明。農業現場に技術導入を図るには、農業者に実際にスマート農業技術に触れてもらうことが重要であり、本日の会でぜひ多くの技術を実際に見て詳細を聞いたうえで、導入を検討してほしいなどと語った。
また、行田市長は、行田市はギネス登録もされている世界最大規模の田んぼアートの取り組みを行っており、2024年は田んぼアートに市内の子供たちを招いて自動操舵トラクタの実演も行ったとし、そうしたスマート農業技術により集約・効率化を図り、市内農地で今後も美味しい農作物を作ってもらえるように、本日の会が実り多いものになることを願うなどと挨拶した。
会場では、31のプラットフォーム会員企業がスマート農業関連技術を展示。一部をみると、関東甲信クボタは営農管理支援システムKSAS及びクボタ農業用ドローンT25Sを紹介。クボタケミックスは水田の給排水を遠隔操作・自動制御できる圃場水管理システム「WATARAS」を展示した。また、ヤンマーアグリジャパンは最大45度の傾斜まで草刈り作業が可能なラジコン草刈機YW500RCをアピールした。
トミタモータースは後付け自動操舵システムと農薬散布ボート、農薬散布ドローンを展示し注目を集めた。JA全農は圃場情報をマップで見える化する営農管理システム「Z―GIS」をPR。サンホープは作物に応じた適切な埋設・敷設を行う新商品の点滴チューブ埋設敷設機を紹介した。ハタケホットケは農薬不使用の水田専用除草ロボット「ミズニゴール」を出品。GPS搭載で田を走らせるだけで水を濁らせ、除草作業を自動化する。
また、近隣圃場で行われた実演会では、関東甲信クボタは農業用ドローンT10を実演。スカイロボットが実演した同T25と合わせて、ドローンによる農薬散布の省力効果が示され、大勢の注目を集めた。ヤンマーアグリジャパンはラジコン草刈機YW500RCを実演し、力強い作業と快適な操作性を大勢の来場者に披露した。トミタモータースはFJDynamicsの後付け自動操舵システムをトラクタに装着して実演。改良を重ねた同製品は直進のみならず、枕地旋回や曲線作業にも対応し、ますます使いやすくなったとPRした。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
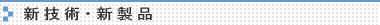 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
DX対応の業務用精米機/サタケが新発売 |
|
| |
|
|
| |
(株)サタケ(松本和久社長・広島県東広島市西条西本町2の30)は17日より、新型業務用精米機「ミルモアⅡ」の販売を開始した。1986年の発売以来、業務用精米機「ミルモア」は精米品質の高さが評価され、多くの精米工場で使われている。長年にわたるユーザーの声を反映した「ミルモアⅡ(型式名:HPR1500C)」を発売。同製品は、基本的な精米品質を継承しつつ、より安定した品質の確保やDX(デジタルトランスフォーメーション)対応を兼ね備えた次世代型精米機となっている。
同製品は原料供給部にロータリーバルブを採用し、原料の安定供給により精米品質にムラのない、連続精米を実現する。また、エア圧制御を搭載。精米中の負荷変動をリアルタイムで感知し、瞬時にエア圧を自動調整することで、精米作業のムラを抑えることが可能になった。
これらの機能により、従来機に比べ処理能力が10%向上し、作業の効率化や時間短縮の効果も期待できる。
DX対応では、モバイル端末で専用アプリをダウンロードし、精米機と連動させることで、運転状況や精米ロール、金網などの消耗部品の使用時間、異常通知をリアルタイムで把握できるようになった。
メンテナンス作業や現場の業務の効率化と遠隔管理の利便性が大幅に向上する。
価格は748万円(税込み・据付工事費別途)。
【特徴】
(1)精米品質の向上と安定生産▽ロータリーバルブで原料供給=常に安定した原料供給により、精米品質にムラのない安定加工が可能。原料特性による流れの変化や調整にも柔軟に対応▽ミルモアの精米品質を受け継ぐ精米室=ミルモアの精米品質を継承し、糠切れの良い精米を安定して生産可能▽エア圧制御による精米調整=精米中の負荷変動に対して瞬時に追従するエア制御を採用し、精米を自動コントロール。
(2)生産性を向上▽精米能力を最大10%向上=従来機(HPR25B)の最大精米能力1500キロ/時に対して、ミルモアⅡは1650キロ/時に向上▽残留米の自動排出を標準装備=原料が少なくなると、自動で終了工程に切り替え。最終原料まで精米加工し、機内残留米を自動で排出する。
(3)オペレータにやさしい操作性▽日常点検とメンテナンスを簡単に=動力制御盤と吸引ファンを内蔵し、カバーを最小限に。部品の脱着と安全性に配慮した設計で日常点検・清掃・メンテナンスの簡便化を実現▽カラータッチパネルを採用し誰でも簡単操作=タッチパネルのサイズは5・2インチ。操作や稼働状況の確認が視覚的にわかりやすく、直感的な操作が可能▽リモート監視で作業効率を向上=精米機とモバイル端末を連携すると、モバイル端末から精米機の運転状況や異常通知等をリアルタイムに確認できる。Wi―Fi環境と専用アプリ(Pro―face Remote HMI)有料ダウンロードが必要。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農業向け小型EVを披露/ヤマハ発動機 |
|
| |
|
|
| |
ヤマハ発動機(株)(渡部克明社長・静岡県磐田市新貝2500)は10〜12の3日間、千葉市の幕張メッセで開かれたオートサロン2025に出展、農業分野向け製品「C580 Fork1」を出品し、数多くの来場者の関心を引いた。
ヤマハ発動機の電動ユニットとホンダ着脱式可搬バッテリーを活かし、幅広い企業と連携・共創を進めて新たな商品を開発していく―同社が「DIAPASON」(音叉)の名を冠して多様なパートナーとともに製品開発にチャレンジし4年目を迎えた。農業分野に向けては、不整地の走行に強い電動3輪車とそれに装着する作業機、1人および2人乗りの圃場見回り車両など、これまで色々な製品が参考的に披露されてきたが、今回の「C580」は、最も早く市販が期待される2人乗りの汎用作業車になる。
バッテリー駆動の2人乗り作業車で専用のトレーラを牽引。その荷台には(株)丸山製作所のエンジン駆動噴霧機を搭載し、さらに作業車のフロントには三陽機器(株)が同機専用に開発したドーザーを新たに装着。圃場の見回りのほか、運搬、防除、除雪などの作業に対応できる機能を盛り込み、小型EVならではの持続可能な効率性と楽しい作業環境を提供する製品に仕上げた。
また、車両部には屋外でもクリアに聞こえ音楽本来の美しさを伝えるスピーカー(DIECOCK)、機能性と静寂を両立するルーフラック(PIAA)を備え、足回りはタフで快適な乗り心地のオールテレーンタイヤ(YOKOHAMA)、レーシングホイールのスピリットを宿したWORKのホイール、ラバー素材で機能性と美しさを兼ね備えたFEASTの専用フロアマットと、遊び心、楽しさが味わえる装備を施した。
開発に当たったEV設計1グループの小屋孝男マネージャーは、「今の農業におけるトレンドが分かっていなかったので、よくご存じの方に様々指導してもらいながら作業を進めてきた」とし、また、「小型特殊免許で公道走行できる製品を目指しており、そのためのレギュレーションに何があるのか。それに利用者にはカッコよく仕事をしていただきたいので、スタイリング、使い勝手などを考慮し、加えて価格も購入しやすい水準に着地したいなど、未経験の部分が多い中で開発をする難しさがあった」と振り返りながら、今後の試乗活動を踏まえた改良・玉成に意欲をみせた。
これまでの試乗や農家との意見交換では、YAMAHAブランドでの発売を望む声が多かったとのこと。さらなる機能の向上を含め、来年予定の市販に向けてこれからの動向が注目される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
凍結防止剤散布機ゼストで冬の路面を安全に/タイショー |
|
| |
|
|
| |
(株)タイショー(矢口重行社長・茨城県水戸市元吉田町1027)が供給する「凍結防止剤散布機ZEST(ゼスト)」は、ZM―Lシリーズ3型式とZR―110の4型式で構成しており、ZM―Lシリーズは無線リモコン搭載で運転席から降りずに散布作業を操作でき(散布量、散布幅の調整)、作業性の向上を図っている。作業幅調整はスピンナー回転による3〜7メートル範囲の1メートルごとの5段階設定になる。
今冬は、この数年耳目にすることが少なかった多雪の報が各地から届いており、合わせて雪道を走行する車両には適切な装備、滑りやすい道路における安全な運転法が絶えず呼びかけられている。こうした中、雪を溶かし凍結を防ぐ融雪剤や凍結防止剤の散布作業は、雪国に欠かせない安全対策になる。
「ZESTシリーズ」は、散布剤の詰まりを防ぐ独自技術の「ノッカー」と、シャッター負荷を減らす「締まり防止板」(特許取得)で散布剤をスムーズに流し、塩化ナトリウムの散布も可能にしている。また、ホッパーの前面に窓を付けることで散布剤の残量が運転席から確認でき、スピンナーユニットの跳ね上げが簡単で手入れがラク=メンテナンス性向上、電源は車載バッテリーを使用し配線の脱着が簡単―などの特徴がある。
オプションとして軽トラックなどへの積み下ろしや保管時に使う専用スタンド(手回しハンドルを回すとスタンドの高さ調整ができる)、トラックの電源を使わない場合に独立電源としてバッテリーを載せられるバッテリー台、24ボルトバッテリー車で使用する際に電圧を24ボルトから12ボルトに変換するZM電圧変換器を用意している。
ZR―110は、適量を均一散布するコストパフォーマンスに優れた製品で、散布・停止は運転席から手元スイッチ操作で簡単に行え、散布はローター繰り出し方式により1〜1・6メートル幅で調整が可能。また、散布量の調整はレバーで目盛りを合わせて行う。バッテリーへの配線は簡単に着脱でき、工具なしで取り外しできるワンタッチ着脱、掃除がラク―などの特徴を有する。
適応散布剤は塩化カルシウム(粒状)、塩化ナトリウム(同)、塩化マグネシウム(フレーク)、塩化マグネシウム(粒状)、7号砕石(ZR―110は不可)。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
装飾表示用フィルム「グランメッセ」の新製品/バンドー化学 |
|
| |
|
|
| |
バンドー化学(株)(植野富夫社長・兵庫県神戸市中央区港島南町4の6の6)はこのほど、装飾表示用フィルム「バンドーグランメッセ(登録商標)」の新製品の販売を開始した。
屋外のグラフィック広告物で使用されるフィルムは、昼夜や季節による温度差により看板下地材が収縮する影響でフィルムが看板下地材に追従できず、広告物への施工後に、割れ・裂け・剥がれといった不具合が発生することがある。そこで同社は「しなやかさ」「下地に対しての追従性」をコンセプトに、独自の配合技術による新設計を行った。
これにより従来製品の特徴である美しい作画性能はそのままに、施工後の寸法安定性能をさらに高めたインクジェット印刷用メディア「バンドーグランメッセGM―NSG、GM―LUG」と、メディアの耐候性を大幅に向上させるラミネートフィルム「バンドーグランメッセGM―SSG、GM―SSM」を開発。2024年12月から販売を始めた。
インクジェット印刷用メディア「バンドーグランメッセGM―NSG、GM―LUG」の主な特徴は以下の3点。(1)下地に対する高い追従性(2)糊面にエア抜け性能を向上した「エア・スイープ」を採用し、貼り作業時間短縮に貢献(GM―NSG)(3)材料への添加剤には非フタル酸系可塑剤を使用し、環境や安全性に配慮。
ラミネートフィルム「バンドーグランメッセGM―SSG、GM―SSM」の主な特徴は以下の3点。(1)屋外7年相当の耐候性能を実現(2)グロスタイプ(GM―SSG)とマットタイプ(GM―SSM)の2種類をラインアップ(3)材料への添加剤には非フタル酸系可塑剤を使用し、環境や安全性に配慮。
これらの特徴から、新製品2種ともに屋内装飾および屋外看板の使用に最適である。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
新型ロータリ2機種を発売/アグリアタッチ研究所 |
|
| |
|
|
| |
(株)アグリアタッチ研究所(笹岡弘和社長・静岡県富士市北松野1204)は1月より、トラクタ平高整形ロータリと小うね整形マルチロータリをモデルチェンジした。平高整形ロータリ「ラクーネロータリ ハイジ」は、整形でもマルチでも楽に最適な畝立て作業ができる。小うね整形マルチロータリ「ラクーネロータリ マルシェ」はより機能が充実し、イモ類に最適な畝立てと、同時マルチ作業が可能となる。両機ともグレーを基調にした新しいカラーリングを採用しており、作物に最適な畝作りを実現する製品として期待が高まっている。
「ラクーネロータリ ハイジ」は、18〜32馬力のトラクタに対応した平高整形ロータリ。従来機より伸ばした整形機と樹脂付き上面整地板の効果で、より締まったきれいな畝に仕上げることができる。
整形でもマルチでも楽に作業ができ、土質条件や畝サイズに合わせて標準仕様と砕土仕様の2形式で最適な畝立て作業を実現する。
振動が少なく砕土性に優れたナタ爪ローターを採用。畝サイズにより9本爪(片側)のATR―HT2(標準仕様)と、12本爪(片側)のATR―HT2―S(砕土仕様)の2形式を取り揃えている。マルチ部は両サイドのアーム構造変更でマルチフィルムの押さえを安定、畝上面に配置したローラーの上下位置調整により鎮圧作業も可能。予備マルチ置き台にも走行時の落下防止機能が追加されている。調整範囲を広げた角度可変ハンドルで微妙な土量調整が楽にでき、圃場に合わせた最適な整形ができる。また溝幅延長板を伸ばすことで、往復25〜40センチの通路残土が少ないきれいな畝を作ることができる。
ATR―HTM2(マルチ仕様)なら、高さ150〜300ミリのマルチ作業も簡単に行うことができる。
【仕様】
▽型式=ATR―HT2▽畝高さ=150〜300ミリ▽畝肩幅=600〜1020ミリ▽畝裾幅=900〜1200ミリ▽適応シート幅=1350〜1600ミリ
▽型式=ATR―HT2―S▽畝高さ=同▽畝肩幅=760〜1200ミリ▽畝裾幅=1100〜1380ミリ▽適応シート幅=1500〜1800ミリ
「ラクーネロータリ マルシェ」は、イモ類に最適な畝立てと、同時マルチ作業が可能となった。砕土性に優れたナタ爪ローターの採用で、振動を軽減する爪配列により長時間の作業でも低振動で疲れにくい。調整範囲を広げた角度可変ハンドルを搭載し、整形機の角度を徐々に変えることで、土量調整ができ、圃場に合わせた最適な畝作りができる。また、畝側面の整形角度可動機構搭載により、様々な畝形状(丸形状から釣鐘形状)に対応。マルチシートに一定のテンションをかける新機能でシート巻量に合わせて張力をかけ、安定したマルチ作業を実現した。管理機で好評を得ているクワホルダーも標準装備している。
【仕様】
▽適応馬力=18〜32馬力▽畝高さ=250×320ミリ▽畝裾幅450〜650ミリ▽適応マルチ幅=950×1200ミリ
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
史上最軽量モデルのワークシューズ/ミズノが新発売 |
|
| |
|
|
| |
ミズノ(株)(水野明人社長・大阪府大阪市住之江区南港北1の12の35)は、現場作業者向けに、同社のワークシューズ史上最軽量モデルの新商品「オールマイティLL11L(エルエルイチイチエル)」をミズノワーク品を取り扱う全国の作業用品専門店やホームセンター、同社公式オンラインなどで20日に発売した。過酷な現場で働く人が、足の負担軽減のため、長きにわたりワークシューズへ求める機能の1つが軽さである。しかし、軽さは安全性との両立が難しい機能といわれてきた。これまでも同社は軽量ワークシューズを開発・販売してきたが、さらなる軽さを求め研究開発を続けてきた。
新商品は作業の安全性を確保するために、耐滑性や耐久性などの機能は維持しつつ、シューズを構成するパーツ数を削減。従来の硬質樹脂先芯よりも軽い先芯を採用することで軽量化を図った。さらに、ミッドソールを薄くし、ラバーの領域も最小限に抑えたアウトソールを採用するなど、設計パターンや素材の見直しを行った。
その結果、同社の従来品である軽量ワークシューズ「オールマイティLSⅡ11L」より約17%軽い、26・0センチ片方で約295グラムという、まるでランニングシューズのような軽さを実現した。同社はこのワークシューズ史上最軽量モデルの新商品で、現場作業者を足元から支え、労働環境改善をサポートする。新商品の販売目標は発売から1年で3万足とする。
新商品の主な特徴は以下の3点。
(1)軽さに特化した設計のアウトソールを採用=耐久性や耐滑性など、JSAA規格A種の基準は満たしつつ、アウトソールのラバー領域を最小限に留めた。これにより従来アウトソールと比べて軽量化を実現した。
(2)アッパー部のメッシュ比率が高く、蒸れにくい=軽量化のためアッパー部のメッシュ比率を高くした。これによりシューズ内が蒸れにくい。また、傷つきやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強することで、アッパーの耐久性にも配慮した。
(3)クッション性に優れたソール設計で履き心地を追求=踵部のクッション性を高める「セル構造」を搭載したミッドソールを採用。セル構造は複数の独立した突起状設計で各セル同士に隙間を持たせた。隙間により荷重時に各セルがたわむことで、クッション性を高めた。
【オールマイティLL11Lの仕様】▽商品名=オールマイティLL11L▽品番=F1GA2502▽発売日=2025年1月20日▽価格=オープン価格(ミズノ公式オンライン販売価格=1万1880円)▽カラー=04(スノーホワイト×ブルー)、14(ディープネイビー×ゴールド)、62(レッド×ゴールド)、54(オレンジ×シルバー※ミズノ公式オンライン限定カラー)、99(ブラック×シルバー※同)▽サイズ(カラー04および14)=22・5〜28・0、29・0センチ(EEE)▽サイズ(カラー54、62、99)=24・5〜28・0、29・0センチ▽素材=甲材(合成繊維・人工皮革・合成皮革)、底材(合成底)▽質量=約295グラム(26・0センチ片方)▽原産国=カンボジア
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
硬盤破砕、収穫にもスーパーソイラー活用/川辺農研産業 |
|
| |
|
|
| |
川辺農研産業(株)(川辺一成社長・東京都稲城市矢野口574の4)が供給する「バイブロスーパーソイラーSV2/同3〜アタッチメント仕様〜」は、硬盤破砕や畑作物の収穫作業に仕様を変えて対応する作業機。同機独自の上下振動によって土壌の透水性改善などの効果をもたらすとともに、低馬力帯のトラクタで牽引できることから、水田地域における転作対応などに幅広く活用が図れる。
用途対応については、▽ダイコンなど=SV2―R/同3―R▽ゴボウなど=SV2―G▽サトイモ、ニンジンなど=SV2―D900/同D1300/SV3―D900/同D1300▽ウド、アスパラ、シャクヤクなど=SV2―UD900B/SV3―UD900B▽長ネギ=SV2―NGTK―V/SV3―NGTK―V▽転圧ローラ、麦踏など=SV2―T(ローラ幅1200ミリ)/SV3―T1500(同1500ミリ)/同―T1800(1800ミリ)―など多様な品揃え。
このうち長ネギの掘り取りに用いるSV2―NGTK―V型は、独特の構造のネギプラウと根切りカッターおよびリフティングロッドでネギを浮かせて畝の片側を崩すことにより、ネギの抜き取りを容易化。従来機よりも小型軽量化を図ったことで、20PS級のトラクタで無理なく使用できる。また、(1)移動時や格納時はワンタッチで内側に反転・収納できる回転スペース付き(2)トラクタの直進を保持する抵抗棒付き(3)アタッチメントの付け替えで畑の排水改善や他の作物の収穫にも使える―などの特徴がある。
また、ユーザーの中には硬盤破砕用のSV2―BDに加え、掘り取り用のアタッチメントD900およびゲージ輪を導入してカンショの収穫作業に用い、収穫専用機に勝る能力を発揮していると評価する向きがあり、バイブロスーパーソイラーはなお広い範囲での活かし方が期待される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
手押し台車、物流の現場で好評/テイモー |
|
| |
|
|
| |
物流機器専業メーカーの(株)テイモー(雄島耕太社長・大阪府大阪市鶴見区今津南3の4の10)は、ストレスフリーの運搬を実現する最大4センチの段差を乗り越える手押し台車「ロイターバウル」を提案する。 物流の現場では運搬時の段差がスムーズな作業を止めるだけでなく、作業者のストレスとなり、負担となっている。この課題を解決するべく、迂回時間や無理な乗り上げを防ぎ、業務効率化と作業負担を軽減する段差乗り越え台車「ロイターバウル」を同社は生産している。同品はキャスターサイズ125ミリ(Φ125)および100ミリ(Φ100)があり、シリーズは全4種を揃える。ロイターバウルはそれぞれ以下の特徴がある。
Φ125=(1)最大4センチの段差を乗り越える(2)通常の台車と比べ、取り回しが軽く、旋回始動力に優れる。
Φ100=(1)従来比約60%の軽さ(Φ125仕様の自重との比較)(2)質量に加え、サイズ感もコンパクトサイズ。
同社は「運ぶ・保管でお困りの際にはぜひテイモーまでご連絡・お問い合わせください」と呼びかけている。問い合わせは同社(TEL06・6961・5171)まで。
【ロイターバウルΦ125の仕様】
▽型式=TC906B(カッコ内はストッパー付き)▽外形寸法=奥行き915×幅600×全高905ミリ▽自重=16・5キロ(18・5キロ)▽最大積載質量=段差無し300キロ、4センチ以下の段差乗り越え時100キロ▽キャスターサイズ=125ミリ
【ロイターバウルΦ100の仕様】
▽型式=TC745B(カッコ内はストッパー付き)▽外形寸法=奥行き727×幅456×全高873ミリ▽自重=10・1キロ(11・8キロ)▽最大積載質量=段差無し150キロ、4センチ以下の段差乗り越え時50キロ▽キャスターサイズ=100ミリ
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
有機栽培米のパックを販売/みのる産業 |
|
| |
|
|
| |
みのる産業(株)(生本尚久社長・岡山県赤磐市下市447)は1月上旬、有機栽培米のパックごはん「みのるのごはん 有機の白ごはん」を発売した。同品は兵庫県産の「みどり豊」(有機JAS認証米)を有機JAS加工場認証を取得した加工工場で製造したもの。環境や身体に配慮した有機栽培米を電子レンジで温めるだけで手軽に食べることができる。
同品の販売個数は800個で、3個セット1360円(税込み・送料込み)から。楽天市場や同社のECサイト「みのるセレクション」で販売している。
有機栽培米(有機JAS認証米)は、2年以上化学肥料や化学合成農薬を一切使わず、周辺から使用禁止資材が飛来、流入しないように必要な措置を講じて栽培した米のこと。農林水産省が定めた有機JAS規格に適合した米のみが有機JASマークを貼付できる。そのため自然環境に優しい農法で栽培されており、SDGsの目標12および13に貢献している。
同社と米づくりの関わりは深く、日本で初めて動力の稲刈機を開発した農業機械メーカーである。1945年の創業以来開発した商品は500種類以上あり、特に1981(昭和56)年に開発した「ポット成苗田植機」は、田植え後の活着が早く、早期から機械除草ができる。
そのほか、苗箱と播種機および移植機を連携させたトータルシステム「ポット成苗システム」が、近年、「有機稲作・無農薬稲作に最適」として注目を集めている。なお、ポット成苗田植機は農林水産省が推進する「みどり戦略」の対象機械に認定されている。
同社の広報は「有機の白ごはん」について、「米づくりに係る企業として『未来を担う子どもたちや家族のために、安心安全で地球環境にも配慮した食を提供』することを目的に、製造に至りました。原料の『みどり豊』はコシヒカリの突然変異から生まれた新品種。粒が大きく艶があり、米本来の甘味とモチモチの食感がある。そのため冷めても美味しいお米です」とPRし、普及に期待を寄せている。
問い合わせは同社(TEL086・955・1123)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
1輪カート噴霧器など新製品を発売/永田製作所 |
|
| |
|
|
| |
農業用噴霧機などを製造販売する(株)永田製作所(田中寿和社長・大阪府大阪市西淀川区千舟1の5の41)はこのほど、新製品カート式噴霧機、フィーダー洗浄カートを発売した。
【1輪カートシリーズ】
磁石で噴霧の方向をワンタッチで切り替えられる「サイドターン」と、左右の畝に同時に噴霧できる「Wサイド」の2製品を発売。どちらも1350〜1800ミリで高さ調節可能、噴霧パターンは扇型でノズルの角度調節も可能なので、菊やトウモロコシなど背の高い作物に威力を発揮する。 その他の特徴は、1輪カートなので取り回しが容易で、作業時の腕の負担を軽減する。そして狭い畝でも走行可能なスリム設計。
〈製品仕様〉
▽1輪カートサイドターン=(1)3型=3頭口(2)5型=3頭口・上部2頭口(3)7型=3頭口・上部4頭口
▽1輪カートWサイド(1)6型=6頭口(2)10型=6頭口・上部4頭口
【フィーダー洗浄カート】
15方向から噴射し、養鶏場の給餌器や給水機の洗浄などに使用できるカート型の噴霧機。自在噴口を採用し、給餌器や給水機の位置に合わせて角度調節が可能。噴口を外側に向ければ鶏舎内の消毒にも活用できる。噴霧パターンは扇型で、各噴口の開閉可能なバルブストップ機能付き。カート型なので作業時の腕の負担を軽減し、移動時の運搬が容易な軽量設計。
▽製品問い合わせ=同社(TEL06・6473・0835)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
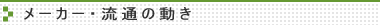 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
「命を支えるプラットフォーマー」実現へ成長加速/第78回クボタ機械グループディーラーミーティング |
|
| |
|
|
| |
(株)クボタ(北尾裕一社長)は15日午後、京都市の国立京都国際会館で、「2025クボタ新春のつどい・第78回機械グループディーラーミーティング」を開催し、今年度の経営方針を発表するとともに、特別優秀ディーラー、最優秀販売店、優秀セールス、優秀サービスなどの表彰を行った。北尾社長は、クボタグループの使命は「命を支えるプラットフォーマー」であり、地球にも人にも優しい食と農業の実現をリードしていくことであると指摘したうえで、農業経営者を支える最先端にいる販売店、営業・サービス拠点長の最前線基地の使命の大切さを強調した。新任の花田晋吾代表取締役副社長機械事業本部長は、2024年は売上計画を超過達成したことに謝意を表したあと、今年度の事業方針として(1)足元固め=短期対策(2)持続的な成長に向けた取り組みの2点をあげ、変化を恐れず、率先して進化していく必要があると訴えた。特別優秀ディーラーには新潟クボタ、関東甲信クボタ、北陸近畿クボタの3社が輝いた。 今回は昨年同様、農機国内事業に対象をフォーカスし、初めて全国の販売会社約800カ所の営業・サービス拠点の拠点長が参集し、「One Kubota」をさらに追求する運営を目指した(事務局)。参集者は本会場、オンライン参加合わせて2800名。海外からは韓国、台湾から代表が参加した。
新春の集いでは冒頭長野県松本蟻ケ崎高校書道部のビデオによるパフォーマンスで開幕。墨痕鮮やかな「智農革新」が完成すると拍手が沸いた。
北尾社長は挨拶でクボタグループの「使命」に言及し、「命を支えるプラットフォーマー」としてその使命を果たすには「本日出席の販売店、拠点長の役割が大切。その理由は(1)日本が課題先進国であること(2)食料安全保障や環境問題など、食を脅かす課題が増えていること(3)どんな時でも最重要情報は現場にある」と指摘したうえで、顧客の変化、真の顧客の声、課題を把握する「ファースト・ワンマイルは拠点の皆さんであり、一方顧客の成功へとつなげる最後のラスト・ワンマイルを担うのは拠点である」と強調し、農機だけではなく、農業全体を見てそれをOne Kubotaで支えていこうと訴えた(挨拶要旨は別掲)。
花田副社長は、持続的な成長に向けた取り組みとして、(1)事業運営体制への変革(2)経営体質の強化(3)成長ドライバー事業の加速化をあげ、とくに国内ではアフターマーケット事業のさらなる拡大を図るとした。
続いて、鶴田慎哉EO農機国内本部長が挨拶に立ち、変わる覚悟と勇気をもってビジネスモデルの変革を進めるとともに、課題や外部環境の変化をチャンスと考え、日本農業の生産性向上と持続的発展を支え、「日本農業を支える人を支え続ける」ことが使命であり、その使命を胸に、2025年も共に進んでまいりましょうと呼びかけた。 このあと技術向上委員はじめ、マーケティング戦略、アフターマーケットなどの領域でクボタグループをリードするメンバーの紹介が行われ、最後にディーラーを代表して吉田至夫全国クボタ農機連合会会長が決意発表に立ち、農業の現場を預かるディーラーは「地域の農家、農業にとって一番頼りになる存在であり続けること。2030年に地域を支えるプラットフォーマーになる、その実現に向けて、この1年を脱皮の年と位置づけることをここに決意する」と述べたあと、「連合会は1957年からの歴史があるが、このたび解散することになった」と報告、これまでの支援に謝意を表した。
このあと、表彰が行われ別掲のディーラー、販売店が栄誉に浴した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ISEKI Japanスタート!変革実行!/2025年ヰセキ全国表彰大会 |
|
| |
|
|
| |
井関農機(株)(冨安司郎社長)は16日、東京・港区台場のホテルで「2025年ヰセキ全国表彰大会」を開催した。これには前半から厳しかった2024年商戦で、最後まで執念と粘りで見事に計画を達成したトップセールスマン・サービスマン、優秀特約店代表約800名が出席したほか、全国の販売会社・関連会社の拠点を結び「You Tube Live」で配信、総勢4000名が参加した。また、海外からはこの度新たにISEKIグループに加わった英国の販売代理店であるプレミアムターフケア社のウィザース社長はじめ経営幹部が参加した。冨安社長は、2025年の成長戦略として海外では、ここ数年「Non―Agri市場」が牽引しているとし、特に欧州では景観整備用トラクタや乗用芝刈機を成長戦略の重要なセグメントと位置づけ、更なる商品競争力の強化を図ると強調。国内は「大規模」「先端」「畑作」「環境」に経営資源を投入することを明らかにするとともに、1月1日に設立した(株)ISEKI Japanに触れ、販売会社と営業本部が一体となり生み出されるエネルギーを成長分野に振り向け、地域を越えた人材交流を積極的に行い、さらなるレベルアップを図っていくと方向を示し、「本日出席の一人ひとりがプロジェクトZの担い手として『変革』を実行する年にしていこう」と呼びかけた。
大会には冨安社長、小田切元代表取締役専務執行役員はじめ、深見雅之取締役常務執行役員、神野修一同常務執行役員、谷一哉同常務執行役員海外営業本部長、石本徳秋執行役員営業本部長(ISEKI Japan社長兼任)、渡部勉執行役員開発製造本部長ら役員が出席した。
冒頭あいさつした冨安社長は、出席者に謝意を表した後、プレミアムターフケア社の役員に英語で歓迎の言葉を述べた。次いで日本農業の現状に触れ、農業人口の減少、大規模化、先端技術活用、畑作転換など構造的な課題を指摘。農機メーカーである同社の果たすべき役割は大きいとし、先端技術をベースに大型・畑作・環境への取り組みを強化するとした。
最後に、創立100周年のスローガンは「Your Essential partner」であることを紹介し、「これまでの100年、この先の100年もかけがえのない存在でありたいとの想いを込めている」とし、市場が厳しい今だからこそ、「食と農と大地」に関わる事業は、エッセンシャルビジネスとして継続させていく必要がある」と力を込め、ISEKIグループが、全てのステークホルダーにとってかけがえのない存在であり続けるためにも一人ひとりがプロジェクトZの担い手として、一丸となって「変革」を実行する年にしよう、と訴え挨拶を結んだ(挨拶要旨は別掲)。
続いて石本営業本部長、渡部開発製造本部長、谷海外営業本部長の3本部長が立ち、それぞれ本部方針を明らかにした(挨拶要旨は別掲)。
このうち、石本本部長は、ISEKI Japanは、国内広域販社6社と三重ヰセキ販売、井関農機営業本部の一部機能を残して統合し、売上高1000億円以上、社員数約3600名の販社としてスタートするとした後、役員を紹介。ここで新役員一人ひとりが登壇し決意、抱負を語った。
渡部開発製造本部長は、本部方針として「一人ひとりのアイデアと工夫で最適化を完達し、世界中で儲ける商品を創造する」と定めたと報告し、今年の干支である脱皮を繰り返しながら力強く成長を遂げる巳(蛇)のように、「新たな価値創造に挑戦する」と決意を披歴した。
谷本部長は、海外事業では中期経営計画の売上げ、収益とも最終目標を達成したといってよいとした後、「今後大きく変化する環境に素早く対応しながら、プロジェクトZの目標の1つである海外売上高800億円を確実なものにする」と決意を述べた。
この後表彰式典に移り、まず販売会社のエクセレントサービスマンクラブ(ESC)認定、スーパールートセールスクラブ(SRC)認定、スーパーセールスマンクラブ(SSC)認定が行われた。ここではSSC認定40回となるヰセキ中四国の永井義正氏の特別表彰が行われ、石本本部長から賞状・トロフィーが贈られた。
次いで来日したプレミアム・ターフ社の役員3人が紹介され、冨安社長、谷海外営業本部長から賞状・記念品が贈呈された。
特約店表彰では、金賞11店、銀賞13店、銅賞12店、努力賞21店がそれぞれ贈られた(表彰店は別掲)。
販売会社表彰では「最優秀賞」にヰセキ関東甲信越(瀧澤雅彦社長)、「優秀賞」にヰセキ北海道(土屋勝社長)、「敢闘賞」にヰセキ東北(加藤敏幸社長)が輝いた。 最後に、小田切専務が閉会のあいさつに立ち、プロジェクトZ担当の立場から、「Zはまだ十分に浸透・共有できていない。キーワードは実行。歴史に残るISEKI Japan初年度にふさわしい活躍、目標達成を」と呼びかけ、大会は終了した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
21日から下取りセール/空研 |
|
| |
|
|
| |
(株)空研(中川禎之社長・大阪府羽曳野市野々上3の6の15)は、中型エアーインパクトレンチ(19ミリ角)の「下取りセール」を始める。セール期間は2025年1月21日〜同年3月31日まで。下取りセールの対象機種は全10機種となる。
期間中にセール対象機種を購入すると、手持ちの19ミリ角以上のエアーインパクトレンチの下取り値引き(1台当たり5000円)を実施する。なお、下取り機のメーカーは問わない。また期間中に対象機種を購入すると、追加特典として同社のロゴ入りオリジナルニット帽が進呈(同梱)される。
対象品のひとつ「KW―2500―prо」は、(1)高能率消音機構の採用(86デジベル)(2)手にフィットする防寒・防振グリップ(3)重量バランスの良い設計(4)視認性の良い樹脂プロテクター(安全性)(5)操作性の良い各種レバー(操作性の向上)―といった特徴がある。
同品はトラクタの整備、ライトトラックおよび2トン車などのタイヤ、Uボルトの脱着作業、大型トラックのエンジン整備作業などで威力を発揮する。また橋梁や鉄骨の組立て作業、重機および建設機械などの分解組立て作業の際にも使われる。
問い合わせは同社(TEL072・953・0601)まで。
【セールの対象機種】ワンドッグ型=KW―20P、同―20PI、同―20GI―6▽N型=KW―200P、同―2500prо、同―2800PA、同―2000prоI▽D型=KW―230P▽ツードッグ型=KW―L17G、同―L17GV(防振型)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
取引先商談会「サカタフェア」で新商品や企画提案/サカタのタネ |
|
| |
|
|
| |
(株)サカタのタネ(坂田宏社長・神奈川県横浜市都筑区仲町台2の7の1)は9日、横浜市西区のパシフィコ横浜で取引先向け商談会「サカタフェア2025」を開催した。
サカタフェアは同社の仕入れ先や得意先が一堂に会し、新商品や企画の提案など活発な情報交換をする場で、会場には同社の各種資材関連商品、花、野菜のオリジナル品種などを展示した。
今回は121社が出展し、450人が来場。テーマは「サカタEXPRESS発進!皆さまと共に、みらいへ」。人と人のつながりを意識し、情報にアクセスしやすい環境をつくることが新たなイノベーションに結びつくという考えからこのテーマを掲げた。
会場では同社が「輸送」「省力化」「コスト」「病害虫」「豪雨・湿害」「猛暑・厳寒」などに関するブースを設け、新商品や取り組みをアピールした。この他に有光工業(株)、(株)スズテック、(株)誠和、(株)マツモトなどが出展し、各企業がそれぞれの強みをアピールした。
開催に先立って坂田社長が挨拶し、「種のビジネスには国境はない。世界中で争いが絶えない今の時代だからこそ、創業から現在まで私たちが心に抱いている種にかける情熱が重要だ。当社で働く一人ひとりがこの情熱で、人々に心の安らぎをもたらす花と、体に健康をもたらす野菜の種の開発を通して、世界の人々の生活文化向上に貢献していく」と意気込みを語った。
挨拶の後、同社コーポレートコミュニケーション部の濱田善之氏が「農園芸業界情報〜現場の課題とその対応策」と題して講演。低コストで始められる環境制御システムArsprout(アルスプラウト)や赤熟もぎり(ステージ4以降)で収穫しても輸送に耐えられる王様トマトなどを紹介した。
この他、今月9日にリリースしたハクサイ「初美月」の種子をPRした。耐寒性、在圃性、耐病性に優れており、暖冬でも安定した出荷を可能にするハクサイの新品種。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
JICAのビジネス化事業/山本製作所が展開 |
|
| |
|
|
| |
(株)山本製作所(山本丈実社長・本社=山形県天童市、東根事業所=山形県東根市大字東根甲5800の1)はこのほど、独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する2024年度の「中小企業・SDGsビジネス支援事業〜ビジネス化実証事業」において、同社が応募した案件「循環型乾燥機による収穫後処理改善に係るビジネス化実証事業」が採択されたことを明らかにした。JICAがホームページで公表した。JICAが政府開発援助(ODA)を通じて築いてきた開発途上国政府とのネットワークや信頼関係、ノウハウ等を活用し、価値の共創に取り組み、循環型乾燥機の有効活用を広げていく。
JICAは政府の開発援助を通じて築いてきた開発途上国政府とのネットワークや信頼関係、ノウハウなどを活用し、価値の共創に取り組んでいる。中でもJICAが進める民間連携事業「中小企業・SDGsビジネス支援事業」では、開発途上国の課題解決に貢献する日本の民間企業等のビジネスづくりを支援。今回、同社では「循環型乾燥機による収穫後処理改善に係るビジネス化実証事業」の案件で応募し、採択された。アフリカのタンザニアを対象国とする取り組みとなる。
JICAによると、アフリカの途上国では、米を収穫した後の貯蔵段階で多くの廃棄が起こっている。米は長期保存のために収穫後の乾燥調製を行う必要があるが、途上国では機械化が遅れているため、適切な乾燥調製ができずに腐敗させてしまい、その結果、多くの米が廃棄されているのが現状だ。
途上国の食品生産工程における廃棄を減らすことができれば、より多くの食料を確保することが可能になる。さらに、廃棄される食品が減ることで生産者の収益も増え、生活基盤の安定につながり、飢餓から抜け出すための一歩となる。
このため、同社は山形銀行と連携し、米の貯蔵に関する課題を抱えるタンザニアにおいて、長年にわたり国内外で培ってきた循環型乾燥機の技術を活用。性能実証や運営・維持管理、また現地代理店候補との協業の実現可能性の検証などを行い、現地精米業者などへの販売を目指していく。
これまで同社は、東南アジアを中心に乾燥調製機器の販売を通して、米生産における生産性向上および食品廃棄の削減に努めてきた。今後は最も人口増加が見込まれるアフリカ地域においても、同様の取り組みを展開して、農業生産の近代化に貢献していく、としている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
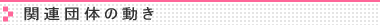 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
予防・予察に重点/日本植物防疫協会がシンポジウム |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本植物防疫協会(早川泰弘理事長)は16日、都内千代田区の日本教育会館一ツ橋ホールおよびWebにて、シンポジウム「農家にとってのIPM実践の意義を考える」を開催した。これには会場・Web計800名以上が参加した。
開会挨拶した早川理事長は「我が国の農業の生産力向上と持続性両立のためには、化学農薬だけでなく、様々な手法を組み合わせた総合防除(IPM)の取り組みを推進、拡大することが非常に重要だ」と、同シンポジウムに込めた思いを述べた。
当日は「現場目線でのIPM」をテーマに、国や県の取り組み、関連企業による最新技術の紹介、農業生産現場からの実践報告など8講演と総合討論が行われた。
最初に登壇した農林水産省消費・安全局植物防疫課の春日井健司氏は、持続的で強固な防除体系を構築するためには、予防・予察に重点を置いた総合防除の推進が欠かせないとし、地域の実情に応じた総合防除体系確立に向け、都道府県、研究機関、関係団体、農業者などの連携・協力が不可欠だと訴えた。
また、岐阜県の取り組みを紹介した同県農政部農業経営課の渡辺博幸氏は、IPMの推進はこれからの農業に必須だが、一方で、農家の経営の持続性を確保するため、収量、売上げ、労力、コストなど総合的な検討も重要だと指摘。県としては、農家のIPM意識の醸成や品目に合った技術の組み合わせの提案、指導者の育成などを継続的に進めていくとし、「生産者と行政がともにIPMへの理解を深め、切磋琢磨しながら進んでいくことが大切だ」と強調した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
今年の一字は「進」/JA全中・山野会長 |
|
| |
|
|
| |
JA全中の山野徹会長は9日、東京・大手町のJAビルで定例会見を行い、自身が選んだ今年の一字を「進」と発表した。物事を進展、前進させるという思いを込めた。
会見の要旨は次の通り。
令和7年、最初の会見にあたり、「今年の一字」を選びました。今年の一字は「進(しん・すすむ)」にいたしました。この文字には、いくつかの決意や願いを込めています。
まず一つ目は、「物事を『進展』させる年にする」という決意です。現在、我が国農業は、歴史的な転換点を迎えております。令和6年、四半世紀ぶりに「食料・農業・農村基本法」が改正され、令和7年は、この改正基本法に基づく、新たな「基本計画」の策定を通じ、施策の具体化を進めていく極めて重要な年です。
あわせて、JAグループは4月に、第30回JA全国大会決議の実践をスタートさせます。組合員・地域とともに、各地域の課題に応じた戦略にもとづき、「食」と「農」を支え、豊かなくらしと活力ある地域社会の実現を目指し、着実な実践を進めていきます。
そして二つ目は、「物事を『前進』させたい」という願いです。全中やJAグループとしても課題は山積ですが、JAグループ各組織、そして組合員とともに前を向いて進んでいきたいという思いです。
世界情勢など、大変厳しい状況下であり、ウクライナ情勢や急激な円安により端を発した、あらゆるものの物価高騰は、国民生活を直撃しています。農業に必要な資材価格の高騰・高止まりも、依然として続いております。この難局においても何とか前進し、持続可能な食料生産により、消費者の皆様に安定して食料を届けるため、生産者やJAグループは、あらゆる努力を続けてまいります。
あわせて、コスト増加分を販売価格へ反映していかなければならない状況にあることを、「国消国産」をキーメッセージに、消費者や関係者の皆様にご理解いただけるよう、取り組みを強化してまいります。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
補助金活用し設備投資を/日本食品機械工業会が賀詞交歓会 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本食品機械工業会(大川原行雄会長)は16日、東京都港区の東京プリンスホテルで令和7年新春賀詞交歓会を開催した。
会の冒頭で大川原会長が挨拶に立ち、「安心安全な食品の提供、労働力の確保、自動化、省力化、グローバル化への対応など様々な面でコストが上昇している。厳しい中だが、慢性的な労働力不足を解消するために中小企業省力化投資補助金を効果的に活用し、省人化や省力化、設備投資に役立てられている。日食工でも新たな設備投資につながるよう積極的に取り組みたい。多様化する中、エンドユーザーの問題が解決につながるよう努力していく」と意気込みを語った。
続いて来賓として経済産業省製造産業局産業機械課長の須賀千鶴氏が祝辞を述べ、同工業会の小林幹央副会長が乾杯の音頭をとった。
同工業会が主催する世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN2025」は6月10〜13の4日間、都内有明の東京ビッグサイトで開催される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
植物工場を宇宙へ/植物工場研究会が勉強会開催 |
|
| |
|
|
| |
特定非営利活動法人植物工場研究会は14日、第163回勉強会「宇宙農業の研究・開発動向と将来」をオンラインで開催し、「宇宙に活かす植物工場」(千葉大学園芸学研究院/宇宙園芸研究センター教授・後藤英司氏)、「宇宙農業の経済成立性について」(日揮グローバル(株)月面プラントユニットシニアエンジニア・田中秀林氏)の2講演を行った。
後藤氏は、月面に人が長期居住するためには、閉鎖型の基地にミニ地球のような人工生態系を構築することが必要だと指摘。続いて、2019年に検討報告書が公開されたJAXAの月面農場ワーキンググループの活動について報告した。現在は、農林水産省の「月面等における長期滞在を支える高度資源循環型食料供給システムの開発」戦略プロジェクトで「高度資源循環型の食料供給システムの開発」に取り組んでおり、同大の植物工場を活用して、月面農場での育成を目指した生産システムの研究を進めているなどとした。
続く田中氏の講演では、宇宙農業の経済性を考察した。宇宙活動において経済的な足枷となるのは輸送費であるとし、宇宙農場での食料自給による経済的メリットについて検討。月面農場で稲やトマトなどの作物を栽培するのに原発を使用した場合は8・5年で損益分岐を迎えるが、太陽光発電の場合は電源設備の質量コストが大きく、損益分岐を迎えられないなどの研究結果を報告した。その上で、今後、植物工場の面積効率や電力効率を上げることで、宇宙農業の経済成立性が向上する可能性を示した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
革新的新品種開発へ/農研機構生研支援センターが公募 |
|
| |
|
|
| |
農研機構生研支援センターは、農林水産省の令和6年度補正予算「革新的新品種開発加速化緊急対策のうち政策ニーズに対応した革新的新品種開発(提案公募型)」の公募を実施している。
水稲に関しては、温暖化に伴う白未熟粒の発生のみならず、減収、病虫害被害にも対応した業務・輸出向け水稲で、各地域の作期分散に対応する水稲品種開発を課題にあげている。
食料安全保障の確保やみどりの食料システム戦略の実現等を図るため、多収性や気候変動、環境負荷低減、高付加価値化等に対応した、今後の国内農業の基盤となる革新的な新品種の開発が求められている。
このため、生研支援センターでは、開発段階から生産者・消費者・実需者のニーズを踏まえた、高い性能や高度な特性を持った革新的な品種の開発を効率的に行うため、提案公募型の研究事業「革新的新品種開発加速化対策のうち政策ニーズに対応した革新的新品種開発」(令和6年度補正
予算)を実施することとし、提案型の公募により研究業務を委託するもの。
同事業で、今後の国内農業の基盤となる革新的な新品種として位置づけているのは▽環境負荷低減に資する耐病虫性品種▽急激な気候変動下でも生産性を維持する高温耐性品種▽生産性向上に資する多収性品種▽スマート農業の推進に資する機械作業適性品種▽国産への転換や輸出の促進に資する高付加価値品種▽輸入に依存する肥料の使用量低減に資するBNI(生物的硝化抑制)強化作物品種―などで、参考資料「農研機構が開発を進める新品種」に示されたもの。
この中で、水稲については、低コスト生産を重点課題とし、気候変動、輸出、化学農薬・肥料低減に対応した、温暖化に伴う白未熟粒の発生、減収、病虫害被害にも対応した、業務・輸出向け水稲で、各地域の作期分散に対応する品種開発を課題にあげている。
公募期間は1月8日〜2月5日まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
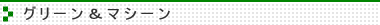 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
森林経営管理制度を改正/林野庁 |
|
| |
|
|
| |
林野庁は、制度の運用開始から5年が経過した「森林経営管理法(森林経営管理制度)」の改正案を24日から始まる今通常国会に提出、これまであまり進んでいなかった林業経営体への権利設定を増やし、林業経営に適した森林における木材生産の活発化を目指すとともに、民間の林業事業体が請けやすい仕組みを提供していく。改正案では、特に意向調査を踏まえた集積計画の策定や配分計画の策定等を行う現行のあり方に加えて、地域の関係者が協議し、集約化を進める区域・受け手となる林業経営体の方針などを決定する「集約化構想」の策定などを新たな仕組みとして追加し、安定した事業地確保を図っていく。令和8年の施行を目指している。
森林経営管理制度は、市町村が中心となって管理の行われていない森林の集積・集約を図るとともに、林業経営に適した森林に関しては「主伐後は、再造林を必ず実施する」との条件付きで、林業経営体に経営管理を再委託するなど、森林の適正管理と循環利用の推進を目的に平成30年に制定された。施行後5年が経過したことから、林野庁では、森林経営管理制度の取り組み状況や現場の声などを踏まえ、見直しに向けた議論をスタート。
林野庁のまとめによると、令和6年3月までの5年間に制度の活用を希望する市町村の94%に当たる1132市町村が約103万ヘクタールで意向調査を実施。回答があった約4割の所有者からは市町村への委託希望があり、未整備森林の解消に貢献。一方で、林業経営体への権利設定は低位な推移となっており、このため5年を経過した見直し論議では、(1)森林の集積・集約化を進めるための新たな仕組みの構築(2)制度推進を担う市町村の事務負担の軽減(3)林地開発許可制度の実効性強化―の3つに論点を絞り、検討を重ねた。
今通常国会に提出する改正法案では「林業経営に適した森林における木材生産につながらなかった」(林野庁)現状を踏まえ、特に新たな仕組みとして、集約化を図る区域や方針、受け手となる林業経営体を決定する「集約化構想」の策定を盛り込み、安定的に事業地確保ができるよう修正。
また、「集約化構想」の実現に向け、一括計画を作成・公告し、市町村と受け手とを同時に権利設定するなど、民間の林業経営体が仕事を請けやすく、使いやすい仕組みとするよう改善。安定的に事業地の確保ができるようにしている。
こうした森林経営管理制度の現場では、森林環境譲与税が活用されており、意向調査や再委託などに活用されている。林野庁では今通常国会での成立、令和8年の施行を目指している。改正案が通れば、林業経営に適した森林での生産活動の拡大が期待される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
安全推進ウェビナー、昨年実施分を再掲載/林業機械化協会 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人林業機械化協会(島田泰助会長)は、昨年9月26日〜11月30日の約2カ月にわたって行った「林業・木材産業作業安全推進ウェビナー」の映像及び資料をWebに再掲載、「ウェビナーの映像や資料を今後の安全活動に使用したい」という林業関係者の要請に応えている。
林野庁の補助事業である「林業・木材産業全国作業安全運動促進事業」の一環として取り組んだ「林業・木材産業作業安全推進ウェビナー」。再掲載する映像と資料は次の通り。
▽林業・木材産業労働災害の現状について(林野庁経営課林業労働・経営対策室課長補佐・西山靖之氏)=URL:https://youtu.be/LTcwPoXj2j0
▽林業労働災害ゼロを目指して 〜集材作業について〜(森林ヒューマン・ファクター研究所所長・山田容三氏)=同:https://youtu.be/7CMH2U-vttU
▽安全とは リスクとは(藤本労働安全コンサルタント事務所CSP労働安全コンサルタント・藤本吟蔵氏)=同:https://youtu.be/ycNUyI5MreA
▽伐木作業の安全対策としての技能教育の位置づけ(一般社団法人林業技能教育研究所所長・飛田京子氏)=同:https://youtu.be/BsDSfgAEUJE
▽製材工場に潜む危険とその対策(職業能力開発総合大学校助教・飯田隆一氏)=同:https://youtu.be/bFXUYIEMfo8
ウェビナー全体を通して見る場合は、https://youtu.be/bvGkohZFDWからとなっている。
協会のホームページには、資料も掲載している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
6年度のイノベーションシンポで新技術の開発成果/躍進2025林業機械2 |
|
| |
|
|
| |
既報の通り、2月5、6の両日、2会場で行われることとなった「令和6年度林業イノベーション現場実装シンポジウム」。林野庁と林業機械化協会が主催する同シンポジウムは今回「新技術が拓く林業の未来」と題して開催。林業の安全性や生産性の向上、魅力ある産業への発展を実現させていく上で欠かせない「林業イノベーション」の現状を、林業機械開発はもちろん、現場での実証、林業経営体の導入事例などを中心として掘り下げて、技術が変える林業の未来を展望していく。
最新の技術開発の動向や各地域における取り組みの紹介とともに、関係者の交流の場を提供していくことを目的に開催される令和6年度の「林業イノベーション現場実装シンポジウム」。今回は、2月5日が都内新木場の木材会館7階大ホール、6日が都内六番町の主婦会館プラザエフ7Fカトレヤの2会場に分かれての開催となっている。
森ハブ(林業イノベーションハブセンター)会員限定の情報交流会は参加費として1500円を徴収するが、それ以外は無料で開催する。新技術の開発・実証の成果や地域への導入実績などを広く発信していく。取り上げる成果報告等は、次のように決まっており、盛りだくさんの内容だ。
林野庁、林業機械化協会からの開会挨拶で始まる初日は、第1部として木質系新素材の開発・実証の現状を実施。森林総研と玄々化学工業が取り組んでいる「広葉樹ファインセルロースファイバー製造・利用技術の開発」、また森林総研がチヨダ工業、玄々化学工業とともに進めている「高柔軟性板材を用いた装飾性の高い立体成形品の製造技術開発」の現状報告が行われた後、日本大学生物資源科学部教授の木口実氏が「木質系素材の活用の現在位置と可能性」と題し講評する。
第2部の林業機械の開発・実証の現状では、現在、林野庁の補助事業で行われている4つの開発課題である、「ラジコン式伐倒作業車の遠隔操作技術・自動走行技術の開発・実証」(松本システムエンジニアリング、久大林産)、「自動集材・造材マルチワークシステムの実証」(イワフジ工業、中井林業)、「フォワーダ集材作業の労働課題を解決する自律走行マルチオペレーション技術の開発」(諸岡、パナソニックアドバンストテクノロジー、森林総合研究所、東京農工大学、国際電気通信基礎技術研究所)、「自動運転型下刈機械の植栽フィールドでの運用実証」(NTTドコモ、筑水キャニコム、千葉県森林組合)の成果報告。東京農業大学の今冨裕樹氏による講評「機械開発・実証の現在位置と可能性」が行われる。
「新しい林業経営の事例」の第3部では、柴田産業と住友林業が「ICTを活用したCTLシステムによる垂直統合型経営モデル」、林業機械化協会が「『新しい林業』経営モデル事業での12事例の成果と課題」について発表。
第4部は「技術は林業の未来を変えるか」と題し、パネルディスカッション。ファシリテーターである酒井秀夫氏とパネリスト5名とで現状を掘り下げていく。
また、2日目の6日は、森ハブ事業報告、デジタル林業戦略拠点構築推進事業報告、パネルディスカッション「林業のデジタル化はどこまで来たか」に続いて会員限定の情報交換会が行われる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
第58回森林・林業技術シンポジウム開催/全国林業試験研究機関協議会 |
|
| |
|
|
| |
全国林業試験研究機関協議会は16日、「第58回森林・林業技術シンポジウム」を東京都文京区の東京大学弥生講堂で開催した。テーマは「人と森林のより調和した関係を目指して」。
会の冒頭で同協議会の向川克展会長が挨拶に立ち、林業・木材産業の発展・活性化を願った。次に林野庁研究指導課長の安高志穂氏ら来賓がそれぞれ祝辞を述べた。この後、第37回研究功績賞及び第3回研究支援功労賞の表彰式があり、計15人の受賞者が向川会長から表彰状と記念品を受け取った。
続いて、代表者による研究発表があり、北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場主査の北橋善範氏が「循環型林業の理解促進に向けたゲーム型教材の開発」と題してスライドを用いて取り組みを紹介。木の伐採は悪いことだと思っている人が多い現状を説明したのち、「伐採は悪いことではなく木材利用の森林保護につながる」という正しい認識を普及させることの必要性を強調した。
さらに秋田県林業研究研修センター資源利用部長の田村浩喜氏が「人が利用する森林に拡大するニセアカシアとの調和を考える」、岡山県農林水産総合センター森林研究所専門研究員の三枝道生氏が「再造林に向けた少花粉種子の安定生産を目指して」、愛媛県農林水産研究所林業研究センター主任研究員の金子翼氏が「CLT建築物の室内環境評価と人への影響」と題してそれぞれ発表した。
この他、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の研究コーディネーター片岡厚氏が「木のエクステリアの普及(外構木質化)に向けて―経年変化を知り、活かし、調和する」と題した特別講演もあった。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
樹上作業用品を発売/ハスクバーナ・ゼノア |
|
| |
|
|
| |
ハスクバーナ・ゼノア(株)(パウリーン・ニルソン代表取締役・埼玉県川越市南台1の9)は15日、特殊伐採など樹上で行う作業に必要な用品16品目を新たに1月から発売開始したことを明らかにした。
国内の取り扱いは(株)ツリークライミングワールド(縣毅史社長・愛知県名古屋市守山区上志段味寺山1200、以下TCW)を総代理店として全国展開する。
TCWは、樹上で剪定作業や樹木のメンテナンスに当たるスペシャリスト=アーボリストのトレーニングに当たる国内唯一の組織・アーボリスト研究所を運営する企業で、同研究所はアーボリストの国際的組織・ISAから認定を受けている。
新発売する製品は、作業の性格上、安全を最優先に開発し高い品質を誇っているもので、(1)クライミングハーネス(2)プルージック(移動、固定のために使うロープ)(3)フリクションセーバー(樹木、ロープを傷めないためのアイテム)(4)マルチスリング・リング付き(5)ワークポジショニングランヤード(高所からの墜落を防ぐためのアイテム)(6)クライミングロープ(7)リギングロープ(扱いやすく摩耗しにくい構造で負荷に強いロープ)―などの合計16品目をラインアップ。
(1)については、耐荷重部はポリエステル、ポリアミド、アルミニウム、およびDyneemaでできており、長時間の過酷な樹上作業に必要な快適性と機能性を実現。背中部分にはクッション性の高いパッドを採用し、レッグループの調節も可能。身体への負担を軽減して快適にフィットする。
また、二重のブリッジと多層構造のウェビングにより安全性が向上し、作業やクライミング方法に応じて様々な調整ができるうえ、多くの小物を取り付けることが可能となるため、作業に必要なツールを常時携帯できる―などの特徴がある。
同製品に関する問い合わせはTCW(TEL052・768・7553)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
中型ローダ受注開始/日立建機 |
|
| |
|
|
| |
日立建機(株)(先崎正文社長・東京都台東区東上野2の16の1)は10日から、中型ホイールローダZW140―7(標準バケット容量2・0立方メートル、運転質量1万860キロ)および同160―7(同2・3立方メートル、同1万2570キロ)の受注を開始した。販売目標台数は2機種合計で年間250台。両機種ともに一般土木、除雪、産業廃棄物処理、畜産、林業、採石など幅広い業種で需要を見込んでいる。
同機には、積み込み作業時の走行速度を自動で制御する「アプローチスピードコントロール」を搭載、低燃費と操作性の向上を実現した。また、運転室(キャブ)のモニターから、周囲環境装置「エアリアル アングル」で車体周囲を俯瞰した映像の確認や、荷重判定装置「ペイロードチェッカー」でバケットの積載重量の計測を可能にしており、安全性と生産性の向上に寄与する。そのほか、油圧ショベルZAXIS―7シリーズと並び、遠隔で機械の状態診断やソフトウエアの更新が可能な「コンサイト エアー」や電気式フロント操作レバーなどの技術を盛り込んでいる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
墨出しロボットがモノづくり部品大賞で受賞/レンタルのニッケン |
|
| |
|
|
| |
(株)レンタルのニッケン(齋藤良幸社長・東京都港区東新橋1の9の1東京汐留ビル19階)は14日、同社と(株)竹中工務店、(株)未来機械が共同で開発した「墨出しロボット SUMIDASU」が2024年の超モノづくり部品大賞の生活・社会課題ソリューション関連部品賞を受けたことを明らかにした。
同機は、建築施工で墨出しといわれる部材の取り付け位置の情報を床や壁、天井面などに記していく作業を自動で行う自走式のロボットシステム。
(1)3次元レーザー測量機でロボット位置を正確に測量しミリ単位で床面に墨出し(2)建築現場に点在する多くの墨出し位置に対する作業順序を最適化し作業の効率をアップ(3)業務終了時にセットし夜間にロボットが作業を行うことで時間の有効活用が可能―などの特徴がある。
同社は、「今後もお客様の困ったに耳を傾けて、レンタル事業を通して安全・安心を提供し、環境対策に配慮した商品の開発にも率先して取り組んでいく」と、様々な産業分野に対する新規製品の開発意欲を示している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
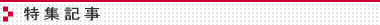 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
安定的な米供給に貢献/田植機・育苗関連機器特集 |
|
| |
|
|
| |
昨年の稲作は、作況指数101の平年並みとなった。品質面でも、1等米比率は昨年11月30日現在で76・1%と、5年産と比べておよそ15ポイントほど高い水準となっている。しかし、一部では、夏の高温による影響が散見される状況で、今後の安定的な米供給に向けては、高温・猛暑に対応した栽培技術や、新品種開発の必要性が高まっている。また、みどりの食料システム戦略に基づき、有機栽培への対応も重視されており、育苗段階からの減農薬や圃場における機械除草に対応した田植機の開発なども進んでいる。田植機・育苗関連の話題を集めた。
米価の高止まりが続いている。これまで低水準で推移していた米の小売価格は1・5〜2倍に跳ね上がり、この急激な値上がりで、消費者の米離れを懸念する声もあるが、生産資材の高騰などもあり、稲作農家にとっては、今後の営農継続に向けた追い風となっている。
昨年の田植機の動向をみると、肥料、農薬等の資材費の高止まりや価格改定等の要因により、稲作農家の投資意欲は低下しており、8条以上のクラスについては、堅調に推移することが見込まれたが、前年を下回って推移した。4条、5条クラスも、個人農家の高齢化、後継者不足による離農等の要因により、大きく落ち込んでいる。
一方、米の在庫がひっ迫したことによる米価上昇に伴い、今後の購買意欲向上に期待がかかる。スマート農機への関心の高まりにより、直進維持機能や可変施肥機能を搭載した田植機、ロボット田植機の導入が進んでいくと見込まれ、みどりの食料システム戦略による環境負荷低減に対応した田植機への関心の高まりにも期待が持てる。
環境負荷低減に対応した田植機・育苗関連技術としては、農薬削減に向けた種子温湯消毒、両正条田植機、化学肥料低減やプラスチック被覆肥料問題に対応した可変施肥、ペースト施肥、紙マルチなどの技術も注目されている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
2024農業技術10大ニュース・1位に両正条田植機/田植機・育苗関連機器特集 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省農林水産技術会議事務局が昨年12月20日に発表した「2024年農業技術10大ニュース」の1位は、農研機構構農業機械研究部門が開発した「両正条植えで縦横の機械除草が可能」となる、両正条田植機が選ばれた。同機の概要をみる。
◇
農研機構は、水稲苗を縦横2方向とも揃えて植える両正条植えが可能な植付位置制御機構を開発した。両正条植えをすることで縦横2方向の機械除草が可能となり、これまで除草率が低かった株間でも除草効率が向上する。植付位置制御機構を搭載した田植機の活用により、除草の手間が壁となっていた水稲作での有機栽培の取り組み面積拡大に貢献することが期待される。
SDGsや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国の食料・農林水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築することが急務となっている。持続可能な農業を目指す「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに耕地面積に占める有機農業の取り組み面積を25%(100万ヘクタール)に拡大する目標が設定された。一方、現状の有機農業の取り組み面積は2021(令和3)年度は0・6%(2万6600ヘクタール)であったことから、目標達成のためには栽培面積の大きい水稲作での取り組みが不可欠。
水稲の有機栽培において手間がかかる作業として「除草」があげられ、規模拡大を阻む1つの要因となっている。農研機構はこれまでに、水稲の除草作業の効率化を目的とした高能率水田用除草機を開発(農機メーカーから市販)し、この機械を活用すれば条間の除草は高能率で行うことが可能。しかし、株間にレーキ(熊手)などを作用させると苗を損傷させる恐れがあるため、条間と比べて除草率が上がらず、残った雑草を手取り除草しなければならない場合がある。機械除草により手間を大幅に減らすためには、株間も条間と同様に高能率で除草するための工夫が必要となる。
そこで、水稲苗を田植機作業方向(縦方向)だけではなく、その直交方向(横方向)の位置も列状になるように揃えて碁盤の目状に苗を植える両正条植えができる植付位置制御機構を開発し、これを市販の乗用型田植機に組み込んだプロトタイプ機を製作した。これにより、水田用除草機を縦横2方向に走らせる直交除草が可能となり、機械除草の効果向上につながることから、これまで困難であった大区画水田での有機栽培の実践を可能とするなど取り組み面積の拡大に貢献することが期待される。
研究の内容は、農研機構がこれまでに開発した田植機の電動植付部を活用し、両正条植えができる植付位置制御機構を開発した。
通常の田植機は同一方向に往復を繰り返しながら田植えを行うため、縦方向には苗の列の幅(条間)が等間隔に揃うが、その横方向には株の位置が列状に揃わなかった。 開発した植付位置制御機構を組み込んだ田植機は、田植機に備えた高精度なGNSS(RTK―GNSS)を用いて、横方向に仮想の基準線を設定して、それに合わせるように植付爪を回転させることにより、横方向にも苗が列状となるように揃えられるようになり、縦方向と横方向が碁盤の目状に揃った両正条植えができるようになる。
電動植付部を用いて両正条植えをした圃場で水田用除草機による除草効果の確認試験を行ったところ、従来の縦方向のみの除草(慣行除草)と比べて、縦横2方向の除草(直交除草)を行うことで株間の除草率が向上することを確認した。
さらに、将来的には、先述の電動植付部の採用が理想ではあるものの、現時点では市販化されていないことから、研究成果を早期に社会実装するため、既に実用化済みである無段変速機を搭載した機械式の植付部を装備する田植機をベースに開発を進めることとし、当該機に今般開発した植付位置制御機構を組み込むこととした。
農機メーカーから圃場内での車輪の滑りによる株間の変動を抑えることを目的として、植付部にHSTを搭載した田植機(クボタNW8S、みのる産業RXG―800、走行部は共通仕様)が市販化されたことから、これらに植付位置制御機構を組み込んだ。具体的には、田植機に備えたRTK―GNSSから取得した自機位置情報を基に、植付爪の回転を横方向の仮想基準線に合うようにHSTを制御する2つのECU(両正条制御ECUと株間制御ECU)を開発し、これらを搭載したプロトタイプ機を製作した。
現地実証にプロトタイプ機を供試した結果、秋田県大潟村の大規模水田圃場(1・25ヘクタール)などにおいても、高精度な両正条植えが実現できることを確認した。
プロトタイプ機はマット苗用田植機(クボタNW8S)をベース機として製作したが、同じ走行部を利用するポット苗用田植機(みのる産業RXG800)にも開発した植付位置制御機構を搭載することが可能。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
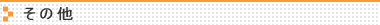 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ヤンマーアグリジャパン・田村裕己氏/欧州農機視察団員レポート |
|
| |
|
|
| |
この度は第77次農経しんぽう欧州農機事情視察に参加させていただき、心より感謝申し上げます。今回は、国内各メーカー17名にて7日間にわたりイタリアでのEIMA2024展示会とMaschio社工場視察、フランスでの農機販売店LE GOFF&GILLE、日本人農家の山下農園様の4カ所を訪問させていただきました。私自身、初めての海外ということもあり、見るもの全てが新鮮で、これまでの人生にはない新しい経験をたくさんさせていただきました。
イタリア視察初日に訪れたEIMA2024の展示会では、21の展示会場に1750の出展企業から6万点を超える出品があり、開催5日間での来場者は約35万人と、日本では感じることのできない規模の大きさや来場者の人数に驚きました。大規模農業の市場から各社300PSを超える大型トラクタやコンバインの展示が圧巻でしたが、欧州ならではの景観整備作業等に活躍する小型トラクタや、乗用モアの分野ではヰセキイタリア社のシェアが高く、クボタイタリア社ではM7以外は日本製の小型トラクタを主軸に2028年を目処に完全EV化を目指すとし、ヤンマーイタリア社は大型トラクタの野外ブースにてYT359での小回りを活かした旋回デモンストレーションを実施するなど、日本製トラクタの技術と強みにフォーカスを当てた販売戦略に学ぶべき点を感じました。また、欧州でも後継者問題は深刻だと聞いていましたが、来場者は家族連れが多く、子どもたちや次世代を担う若者にも楽しめる工夫が随所に散りばめられており、私個人の視点から見ても農業という職業は国を支える魅力的でカッコイイ職業だと感じられる部分が心に残りました。
2日目に訪れたMaschio社では、担当者による概要説明と2カ所の工場を視察させていただきました。ロータリーハローなどの土耕機のプロフェッショナルとして世界的に活躍し、1994年にはガスパルド社をグループに加え播種機やスプレヤーにおいても現在高い評価を獲得しているメーカーです。5つある工場では24時間シフト3交代制にて1つの工場で300以上の工程を踏んでいますが、工場内は生産性が高くムダのない動線が確保されており、安全かつクリーンな印象で驚きました。また、ロボットを使用し効率を上げる一方で、繊細な作業は全て人の手によって実施されており、品質へのこだわりとプライドが感じられました。今回急遽決まった視察でしたが、帰り際に現地ケータリングによる食事も提供してくださり、イタリアの人柄や文化にも触れることで、同業者として尊敬と感謝の気持ちで胸が熱くなりました。
3日目のフランスでは農機販売店LE GOFF&GILLEを視察させていただきました。郊外に位置する田舎の販売店といったイメージですが、約400世帯の顧客をもち、新品から中古まで幅広く扱い、修理も自社にて行われていました。社長は気さくな雰囲気で、町に欠かせない販売店という印象があり、店舗運営に関しても日本の販売店に共通する部分が多く親近感を抱きました。
午後からの山下農園様訪問では、農園主の山下朝史さんから、29年前にパリに来て独学で栽培を始め、パリに日本野菜を広めたパイオニアとしてのお話を聞かせていただきました。とても魅力的な方で、独自の発想力と人とのつながりを大切にすることで、全てがオリジナルでありオンリーワンであるのだと実感しました。今でもフランスのグランシェフが野菜を求める背景には、日本野菜というよりも、山下さんが作った野菜だからこその価値があるのだと理解できました。
今回の視察を終え率直に感じたことは、農業の形は違えど日本も世界も考え方のベースは同じであるということ。また、世界人口を支える食料は農業従事者を基盤に成り立っているのだと再確認しました。同行した他社メーカー様とも良い関係が築けたことで、今後は世界に目を向けた日本農業界の発展に少しでもお力添えできるよう業務に邁進していく所存です。この度はありがとうございました。
(九州支社谷頭支店)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農機販売会社視察/欧州視察から―伊仏の農業に浸る5 |
|
| |
|
|
| |
視察団一行はイタリアのボローニャを後にし、フランス入り。4日目の午前中はパリから西へ約100キロほどの場所に位置する農機販売会社のレ・ゴフ&ジルを訪れた。同社社長のレミ・ジルさんに対応していただき、拠点内の展示スペースや整備工場、小物販売用店舗などを案内してもらった。
同社の取り扱いメーカーは、マッセー・ファーガソンやアマゾーネ、クローネ、モノセム、キオティ、スチールなど大小様々な製品や部品を取り揃えている。
ここムソーヌーヴィルの本社を含め3拠点を構え、総売上げは800万ユーロ(約13億円)。新品販売が60%、修理整備が15%、部品が10%、中古が15%といった内訳である。
従業員は30名。そのうちセールス4、販売員4、整備士16、事務員が6。顧客は農家を中心に300〜400軒ほど。圃場規模は150〜300ヘクタールといった大規模農家。穀物栽培が中心で、畑作がメーンだ。扱うトラクタの平均馬力は200PS。その他に景観整備に使う芝刈機を役場や個人向けにも販売する。部品は在庫もしているが、KRAMPという膨大な部品が揃っているプラットフォームから注文すると、24〜48時間で届くとのことだった。
同社の繁忙期は春と秋だが、クリスマス休暇の2週間以外は常時仕事があるような状態である。マッセー・ファーガソンのトラクタは別の拠点で2、3台在庫していることもあるが、現在は在庫切れ。年間12台程度は売り上げる。韓国のキオティ社の小型トラクタも同程度販売する。
団員がフランスの農家について尋ねると、平均年齢は55歳で、日本に比べれば10歳以上若いが、それでも高齢化は問題だと教えてくれた。また、各農家の大規模化は進んでいるが、農業そのものが縮小しており、日本と同様の問題を抱えているとも話した。
視察団員が日本製についての印象を尋ねると、「昔からやっているのでクボタは有名。ヤンマー、ヰセキ、ホンダも良いですね」との回答。一同で盛り上がる場面もあった。
整備のニーズは日本同様に高まっているそうだ。整備費用は時間当たり72ユーロ(約1万2000円)。日本に比べればやや高めか。
同社でも技術者が足りないとのことで、「日本のメカニックがいたら、ぜひこちらに連れてきてほしい」というレミ社長の冗談に対し、「年収1000万円で雇ってくれませんか」と手をあげる団員もおり、「そこは交渉させてほしい」との答えだった。
中には、スマホの翻訳機能を使って、果敢に現場のメカニックとコミュニケーションを図ろうとした視察団員もいた。
出発時間ぎりぎりまで活発に質問が飛び、団員の好奇心の高さに、同行した添乗員の方も驚いていた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
EIMAが示す農の未来:人気のマキタ電動工具/イタリア・国際農機展レポート5 |
|
| |
|
|
| |
前回に続き、EIMA2024に出展した日本企業の出展概要をみる。総合電動工具メーカーのマキタは、EIMAの5つのテーマ別展示会のうち、「EIMAグリーン」に出展した。同社は1970年にアメリカに進出して以来、世界約50カ国に直営の営業拠点を設立。その中でマキタイタリアは2024年に50周年を迎えた。同国はじめ欧州にて、マキタは電動工具の人気ブランドとして根付いている。ブースでは、マキタイタリアの販売担当者が応対。新製品として、ハイパワー・長寿命・高耐久の「40Vmaxリチウムイオンバッテリー」を活用したXGTチェンソーの新シリーズ「UC021〜026GZ」をアピールした。同チェンソーは、本体重量がわずか3・4キロで1600ワットの出力を実現。これは、以前のモデルより40%高く、35立法センチガソリンモデルに匹敵するという。剪定から枝払い、大きな幹の切断に至るまで、様々な作業の効率と管理性を兼ね備えているとした。また、農業における新製品としては、ブラシレス手押し車「DCU601Z」を紹介。最大300キロまでの重量物を安定して輸送できる同製品は、12度の傾斜まで上れる能力を持ち、屋外にて農作物の運搬などに活用できる。また、電動リフトで荷物を地上1020ミリまで持ち上げることができるため、ユーザーの身体的労力を軽減する。同社担当者は今回の出展のテーマとしてマキタグループが目指す「ゼロエミッション」を示し、バッテリー駆動による低振動・低騒音なマシンによって、環境への影響を最小限に抑えながら安全に使用できる快適性を実現していると述べ、「親切で静か、パワフルに働く。これが日本式だ」と笑った。「イタリアでは習慣を変えることに抵抗があるが、新しいものが明らかに良いとわかればゆっくりと変えていく。マキタ製品の良さを時間をかけて周知した結果、今ではイタリアでも高い評価を受けている」と胸を張った。ブースでは、その他、電動のブロワや芝刈機、研磨機など同社が展開する様々な電動工具が並べられていた。一方、トプコンは、テーマ別展示会の1つである「EIMAデジタル」に出展。新製品の自動操舵システムのエントリーモデル「Value Line」シリーズ及び、今回のEIMA技術革新アワードで「佳作」を受賞した「SNIPER」をPRした。同社イタリア拠点でビジネスソリューションシニアマネージャーを務める横瀬早紀子氏が案内してくれた。食分野では農機の自動化など、農業DXソリューションを提供しているトプコンだが、EIMAでは目玉機種として自動操舵システムのエントリーモデル「Value Line」シリーズを出品。「これまでプレミアム価格帯の自動操舵システムを提供していたが、昨今は市場構造が変わり、エントリーレベルで精密農業をしたい要望が増えてきた。そうした声に対応した製品」だという。同シリーズはハンドル、7インチまたは10インチのディスプレイ、GNSS受信機で構成され、座席に座ってハンドルの操作ボタンを押すだけで、自動操舵のON・OFFやA―Bライン作成ができるという簡単操作。プレミアムモデルの約半額という求めやすさを実現し、イタリアでは主にワイン用ブドウ畑や野菜畑、果樹園など中小規模の農業者に提案している。シンプルながらもきちんとデータの収集・記録・通信を行うことができ、「特にEUでは規制が厳しく、肥料散布量などのデータ提出が必須となっている」とした。エントリーモデル発売を待ちかねていた顧客も多く、EIMAでは歓迎する声が多かったという。同シリーズは日本を含む世界中で販売されている。一方、EIMAアワードで佳作を受賞した「SNIPER」は、ワイン用ブドウ畑における精密農薬散布を実現するスプレーキット。超音波センサーとコントロールユニットで構成され、スプレヤーに取り付けて可変速度の噴霧制御を行う。センサーで実際の葉の量を自動で読みながら、葉の多い・少ないに合わせて散布量を自動調節する技術が今回表彰された。イタリア・フランス・スペインはワイン用ブドウ栽培が盛んだが、近年は資機材価格上昇で苦しい状況にあるため、生産コストや環境負荷の低減につながる同技術に注目が集まっている。取り付けるスプレヤーは汎用性が高く、様々なメーカーと連携しているが、日本においてもリンゴの防除用に連携の話を進めているなどと語った。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
