| |
|
|
| �� |
���Ф���ݤ� |
|
| |
����7ǯ3��17��ȯ�ԡ���3543�� |
|
| |
|
|
| |
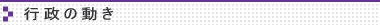 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�б�ͥ��ˡ��2025���ȳ�����ǧ��¿�����кѻ��Ⱦʤʤ� |
|
| |
|
|
| |
���кѻ��Ⱦʤ�������ܷ�Ĥ�10�����ַб�ͥ��ˡ��2025��ǧ��ˡ�ͤ��ɽ����������ϡ���Ĺ���Ҳ�μ¸��˸����ơ����Ȱ����η�����б�Ū�ʻ����ǹͤ������ݻ������ʤˤĤʤ������Ȥߤ���άŪ�˼�������бĤ�Ԥ�ˡ�ͤΤ������ä�ˡ�ͤ�ǧ�ꤹ���Ρ�
����ǯ���絬��ˡ�������3400ˡ�ͤ�ǧ�ꤷ���������500ˡ�ͤˤϡ֥ۥ磻��500�פδ����ղá��澮����ˡ�������1��9796ˡ�ͤ�ǧ�ꤷ���������500ˡ�ͤˤϡ֥֥饤��500�ס�501��1500��ˡ�ͤˤϡ֥ͥ����ȥ֥饤��1000�פδ����ղä�������ǯ�٤�Ʊǧ������Ф��ơ�ξ����Ȥ����������ä��ߤ�줿��
��Ʊɽ���Ǥϡ����ȵ����ȳ������¿�����Ф��줿��ǧ�ꤵ�줿��Ȥΰ�����ߤ롣��(����Ʊ)
�����絬��ˡ�������
����(��)���ܥ�(�ۥ磻��500��2ǯϢ³)�����ޡ��ۡ���ǥ���(��)(���ޡ����롼�פ�6ˡ�ͤ�������ǧ�ꡢ���롼��פ�17ˡ�ͤ�ǧ������)���������(��)����ɩ�ޥҥ�ɥ�����(��)��(��)������å��ۡ���ǥ���(���롼�ײ�Ҥ�(��)������å���(��)������å�R&D��ǧ��)�����Υ饤��(��)���Х�ɡ�����(��)��(��)�ݻ������(4ǯϢ³�����롼�ײ�ҤǤ������ܥ��饤��(��)���ޥ��ޥ�������(��)�������ݻ�(��)���ݻ�ʪή(��)��ǧ��)���ߤΤ뻺��(��)(2ǯϢ³�����롼�ײ�ҤΤߤΤ벽��(��)��(��)�ߤΤ르��ե�����(��)�ߤΤ륬���ǥ����ߤΤ�ۥƥ����(��)��ǧ��)��(��)��ޤӤ����桼�ԡ�������(��)(�ۥ磻��500)
�����澮����ˡ�������
����(��)��������ͭ������(��)����������(��)�������ͥĹ���(��)������������(��)��������(��)���Ų�����(��)��(��)����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���ޡ���������å��ʤɵ��ѾҲ����ӿ建�ʤ������� |
|
| |
|
|
| |
�����ӿ建�ʤ�6�������������Ķ��Ʊ��6�����������ļ��ڤ�Web�ˤơ���2��ߤɤ굻�ѥͥåȥ�������ĤŤ������֤ߤɤ�ο��������ƥ���ά���ѥ��������פˤޤȤ��줿���ߤɤ���ά�¸��˻뵻�ѤΤ���ʤ���ɤ�Ҳ���������¥�ʤ��뤿�ᡢƱ���ѤξҲ�˲ä������Ѥγ�ȯ�Ԥ�ºݤ˳��Ѥ��Ƥ������ȼ����ȤΥѥͥ�ǥ������å�����»ܤ���������ˤϲ�졦Web���700̾�ʾ夬���ä�����
������ˤ����갧���������ӿ建����ô�˼�������翳�Ĵ������ӿ建���Ѳ�Ļ�̳��Ĺ�����ĵ����ϡ����ϰ�Ǥߤɤ굻�Ѥ���ڡ����Ѥˤ�����Ω�ɤʼ���Ȥߤ�»ܤ��Ƥ���͡�������ȯɽ��Ԥ�����������Ƥ����ȸ�ꡢ����dz��ѤǤ����θ���ͭ���Ƥۤ����ʤɤȴ��Ԥ�����
�������ǡ�Ʊ�ʤˤ���������ߡ��ѥͥ�ǥ������å���Ԥ�줿�����Τ��������ޡ�������(��)��ȯ��������Գ�ȯ�������籦���ϡ��ж����Ȼ�̳�������ڲ���ڻ�Ƴ���������ҵ���ȤȤ�ˡֲ��������������Ԥ��������ǡ����Ȳ��ѻ����Ŀ����������ѡפˤĤ��ƹֱ顣�����Ϥޤ������ޡ������ȵ��Ѥ�Ϣ�Ȥ������ޡ��������γ��ѥ�����Ȥ��ƴ�����ѻ��β��ѻ����Ŀ�����������ѻ��β��ѻ���ɥ������Ϻ�Ȼ��μ��̥���Х������������PDCA����Ȥˤ��бIJ�������Ω�ƤƤ������Ȥ���ơ�����Ϥ��Τ��������ո������ԤDz��ѻ����Ŀ�������Ѥ����¾ڤˤĤ������̤���𤷤�������ӥ��ե�����ɥޥ͡����㡼�����ϥޥåפ��顢����ޥåפ������������β��ѻ����»ܡ����Զ�ȸ����2��(���Զ���15��4%����Ʊ17��6%��)����٤��Ȥ�����¦�����ԤäƤ���̸��ϳ�ǧ���줺��17��6%���ζ�Ǥ���������㸺�ȼ������ä���ǧ���줿�Ȥ���������˷������Ӥ����¦�������β��ѻ���Τߤ�10��������������600�ߤη���︺����ǽ�Ȥʤꡢ���˿��б�20�إ������롢¦�����θ���Ψ17%�Ȥ���ȡ�ǯ�ַ�����12���߸��ˤΤܤ�Ȼ���줿��
������¾�����ڤŤ���ȸ���Τ������������(�����������������ȸ��楻����������ڸ����ΰ衦���롼��Ĺ����߷��ɧ�ᡢ��Ʀ�ۤʤ��ӥ��ե�������ɽ�����Ҹ����)��͢����ʴ�˰�¸���ʤ���ʴ�ΰ��궡�륷���ƥ�(Ļ������������ڶ�������¼�����ᡢ��̸������������ӿ��������������ô���������Ӽ�Ǥ���ƺ갫��)������ͭ�����������Ѥ����ھ��Ը�����(���ҥ����ץ�����(��)���������������塼������������ѿ�ʲݡ��ڰ渦��ᡢʡ��Ȭ�����ȶ�Ʊ�ȹ��ݻ�Ƴ�ݷ�Ĺ�������չ���)���ʤɤΥǥ������å�����»ܡ�
���ޤ��������ˤϥݥ��������å�����Ÿ����Ԥ�졢(��)������å�R&D�Ͽ����ѽ���WEED��MAN�פ���������Ѥ��ʤ������ηϤȤ��ƾҲ𤷤Ƥ�����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Ȫ��Ǥ�ͭ��ʪ���ѡ����������ɤ��ߤɤ���ά�ٶ��� |
|
| |
|
|
| |
�����������ɤ�2��26�����ߤɤ�ο��������ƥ���ά�ٶ���(��28��)��饤��dz��Ť���������ϡ�Ʊ�����ɤ�Ʊ��ά�˴ط�����ơ��ޤˤĤ������Ť��Ƥ����Τǡ�1��3��Υơ��ޤϡ����Ω��!ͭ�����Ȥκ��ݵ��ѡס�����2���ܤȤʤ뺣��ϡ�������ˡ�ͼ�����ˡ��ݸ��泫ȯ���������κ縶����ϯ����Ť������ͭ�����ݤˤ�����ͭ��ʪ���ѵ��ѤˤĤ��Ʋ��⤷����
���縶��Ϻǽ�����ͭ�����ݤε���Ū�����Ȥ��ơ�ͭ�����ݤ����������ʤ����ᡢ�µ��䳲������к��ʤɤ��ܤ����������������������ڤ��˰�äƤ��ʤ���̤Ǥ���ȤȤ館���ޤ��Ϸ˰�Ƥ뤳�Ȥ����Ϥ��٤����פȶ�Ĵ�������ơ���ͭ��ʪ�γ����ʤ�������ȶ����Ǥ��뤯�餤�����Ϥ���ݤ��뤳�Ȣ��ɤ�����ɤ��ڤ�Ŭ���˺��դ��ơ�����������ݤ��뤳�Ȣ��Ƶ��Ѥ�ͭ��Ū��Ϣư���������ַϤ�����������ηϤ�Ĥ��뤳�ȡ���ռ������������������ΤǤϤʤ���������ɬ�פʤ����֤��ܻؤ����Ȥ����פǤ���ȽҤ٤���
���ޤ���ͭ�����ݸ������ʼ�����Ȥ��ơ������������ˡ��Ҳ𡣤���ϡ�Ȫ�ζ��ʤɤ˼���������ڤ����餬�����ˤʤ��礬���뤳�Ȥ��顢���ϴĶ��������ˡ�˹�ä������ʳ���������ȴ������������Ѥ����Τǡ�Ȫ����ڤδѻ�������Ū��³���뤳�Ȥ������ݤ��͡��ʥҥ�ȤˤĤʤ���Ȥ�����
��³���ơ����ϻ��֤ʤɤ�ͭ��ʪʬ��ˤϡ��ھ��β��١���ʬ�����ǡ���ʬ���θ����ɬ�פ�����Ȥ���������������ʤɤ���Ȫ�ξ����İ����뤳�Ȥ䡢�ھ���ʪ��ռ����ƿ����դ�������ͤ��뤳�Ȥ����פǤ���Ȼ�Ŧ������Ū�ʿ����դ������ˤĤ��Ƥϡ�����ڤϼ�ޤ����Ŀ����������٤�Ƥ��ʤ���������ξ���Ŭ���˿����դ���������֤���ݤ��뤳�Ȥ�˾�ޤ����ȥ��ɥХ���������
�������ͭ��ʪ�λ��ѤǤϡ����֡���ꡦ����(����)���̤��ݥ���Ȥˤʤ�Ȥ�����ʪ�κ����ն��̵����ͭ��ʪ�����ޤʤ��褦�ˤ��뤳�Ȥ䡢̤�Ϥ�ͭ��ʪ��������ϡ��߾�Ǥ�����꿢��90���ʾ����ˡ��ƾ�Ǥ�40���ʾ����˹Ԥ����Ȥ�侩������
��������ͤ���ͭ��ʪ�������ѤˤĤ��Ƥϡ�(1)��������������ͭ�������ΤߤǤʤ�������μ��ϻ��֤仨���ޤ�ͭ��ʪ��ʬ��ʬ�������Ϥ�ݻ�����ͭ��ʪ�γ���ʤ����Ƥ�����դ���(2)�����λ���鼡����դ��ޤǤ˽�ʬ�ʻ��֤����ʤ����ϡ����ϻ��֤�ʬ�����ؤ��Ĥκ�ĥ��ʬ��ʬ���뤳�Ȥˤ�ꡢͭ��ʪʬ��ξ㳲�ꥹ������Ĥġ����Ϥ�۴ġ��ݻ����ʤǤ���(3)���ϻ��֤�ɽ�ؤ������ߤϡ�ʬ���ؤ��������ͭ��ʪ���٤ߡ��ھ���ʪ�������⤤���ᡢ������̤����ԤǤ���(4)������ν�������Ű�줹�롽�ʤɤ�ݥ���ȤȤ��Ƥ�������
�������ơ����Ϥ��������پ夬�äƤ����顢���̹̤���ǤϤʤ���������ʪ��Ϣ³���ݡ����������ɽ�ػ��ѡ�ͭ��ʪ�ޥ����ޤ�ơ��������ַϤΰ����ݻ���������ؤȰܹԤ��뤳�Ȥ�����ǡ����ߤ�ޤ�������ݤǤϡ��ϲ����ھ���ʬ�ΰ��ꡢ������������ʤɡ��͡��ʸ��̤����ԤǤ��뤳�Ȥ�����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���Ƚ��Ҥ�͢�м���Ȥߡ����ӿ建�ʤ��ǽ����� |
|
| |
|
|
| |
�����ӿ建�ʤ�3����Web�ˤơ�GFP�����Ƚ���PJ͢��ȼ���ٱ�ץ������ǽ�����Ť�������������ӵ��ȼԡ����ʻ��ȼԤ�͢�Фγ����ٱ礹���GFP�פȽ������ȼԤγ�����ٱ礹������Ƚ��ҥץ��������ȡפ�Ϣ�Ȥ��ƺ�ǯ10���»ܤ��Ƥ�����Τǡ����Ƚ��ҥ��С���GFP�ˤ��͢��ȼ���ٱ������ʤ������Ū��͢���μ��ν������ͥåȥ�����ۤ���ȤȤ�ˡ��ºݤ�͢�����˼���Ȥ�Ǥ���������Ϥ����������Ȥ��ơ�(1)�ɥХ������ݡ������ξ��䡦�����������IJ�ʪ����͢�Ф��ܻؤ�������(2)���EC�����ȸ�����͢�Ф��ܻؤ��������ˤĤ��ơ�����Ȥߤγ��פ亣������ˤ��������줿��
������ˤ����갧������Ʊ����ô�˼���Ĵ�(��бĶ�)�ξ�����������ܻ��Ȥ˻��ä������Ƥ����Ƚ��ҥ��С��ȶ��Ϥ����ط��Ԥ˼հդ�Ҥ١���5����Ǥɤ��ޤ��ۤ����¸�������������ʾ��ʲ��⤢�ä��������������������˻��ȷײ��ľ���Ƥ���ʤ�ȯŸ���ܻؤ��Ƥۤ����ȴ��Ԥ����
�����θ塢�ץ��������������𤬹Ԥ�줿������ˤ��ȡ�����ϡ�͢�Фΰ����ܤȤ��ƾ����åȤǤ�͢�Ф��䤹���������ͥ�Ȥ��ƹ�鳰����EC�����ꤷ�������ǡ�GFP�Υѡ��ȥʡ����Ҥ�Ϣ�Ȥ����ƥ���͢�Хץ�������»ܡ�(1)��͢�а��ߤι⤤���Ƚ��ҥ��С����IJ�ʪ�ξ����ʳ�����ϩ��Ω���ܻؤ��ƥ�����������������ݡ����ɥХ���������֥�ͥ��ʤɤι�鳰��Ź��ۥƥ������͢�Ф�������������ʪ�Υ������ĥ�˥塼�γ�ȯ�����Ƚ��ҥ֥��ɤ�PR��»ܡ�͢�������Υݥ���ȤȤ��ơ������Ƚ��ҤϾ��ʥ饤�åפ�¿���Τ����ߢ�1�������ˤϡ֤��ġ�������ǡ����ɤ��ʼ��ǡ��ɤΤ��餤���̡פ�͢�ФǤ���Τ������뢦���ʥ���ץ��������ɤ�������롽�ʤɤ������줿��Ʊ������Ǥϥ����(��)������ब�濴�Ȥʤꡢ��³����Ȥߤ⸡Ƥ���Ƥ���Ȥ�����
���ޤ���(2)�Ǥϥ����̳��������å������顦����(��)���ƥ���������EC�Ȥ������Ƚ��ҥ��С��δ�̿��䥳���Ȥ����̤˽Ф������Ƚ������ߥ����Ȥ��ߤ������ܸ졦����������¥�ʡ�¿���ξ��ʤˤĤ��ƥ���ץ�����ۤ������̤��갷����ʤᡢ������ե�������ʤɤ�Ԥä������ϼҰ������Ԥ���������ե����ɥХå����ơ����դ��ʤɤΥӥ��ͥ���ˡ�ʤɤⶦͭ�����Ȥ����������ǡ������͢�������˸������ݥ���ȤȤ��ơ������ʤβ��ͤȤ�����Ф����в������������뢦���ͤ��в��μ¸��˸����Ʋ������Ϥ�³���뢦6�������ʤ���ϩ����Ǻ�������ΤϱĶ��ϡ��ʤɤ�������줿��
�����θ塢���ä������Ƚ��Ҥˤ�뿶���֤�ڤӡ����ӿ建��͢�С���ݶ�͢�л��Ϸ�����Ĺ���綶���ˤ�밧�����ġ������Ƚ��ҤؤΥե����ɥХå����Ԥ�졢���Ƚ��Ҥ����Ϻ���μ���Ȥߤ˰��ߤ���Ƥ�����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
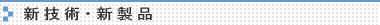 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
����Х����YH3/4R������ס����ޡ������꤬ȯ�� |
|
| |
|
|
| |
�����ޡ��ۡ���ǥ���(��)�Υ��롼�ײ�ҤǤ�����ޡ�������(��)(��ʥ��ޥ��Ĺ����������������蹾��428)�ϡ�ǽΨ�����٤���淿����Х����YH3/4R�ץ������쿷����4��1����ȯ�䤹�롣�ܵ���4��ǥ�ˤϡ�����滳���Ϥ�����絬�����Ȥ������˾��¿���ä�50�����Ӥ��ɲä����������®�٤åס����ѵפʥ�����ƹ+�磻����ư�Ĥˤ�ꡢ���̤�����Ψ�褯�����٤�æ�롣
��4��ǥ��YH4������Ǥϡ���˰��ꤷ�����Ϻ�Ȥ����ǽΨ�˹Ԥ���������52���ϥ������ܤ������ԡ��ǥ����ʴ�����ȤǤ�����٤�æ���������̤���ǽ�Ȥʤä���¾�ˤ⡢�ּ�ư���⤵����פˤ���ȼԤ���ô�ڸ��˲ä��������եƥ���ǽ�ˤ������������������������䤹�����ε����ˤ����ƥʥ�������夵�����ײ��̤�μ��Ϥ�¸����롣
���Ҿ��ʳ��ס�
��������̾������Х���YH325R/YH333R/YH440R/YH452R��ȯ������2025ǯ4��1�������ʲ��ʡ�589��6000�ߡ�933��9000��(�ǹ��ߡ��������˾�������)��
�������ħ�ϼ����̤ꡣ��(1);͵�Υѥ�ȥ��ԡ���=��YH452R�פξ�硢���®�٤�1��43��ȥ�/�äȤʤꡢ���赡����٤ƴ����®�٤����åס�®�٤��夬�äƤ���ѵפʥ�����ƹ+�磻����ư�Ĥˤ�ꡢ���̤�����Ψ�褯�����٤�æ�롣����ˤ����䤫����ƹ�����ä�����������⤬��ư�����Τ˳Ȼ����뤳�Ȥǡ���꤭�줤�����̤��Ԥ��롣
��(2)���ꤷ������ι⤵�Ǵ����ּ�ư���⤵�����=ʬ���Ĥ˼���դ������ꥻ�������α��̤��Τ��Ƽ�ư�Ǵ��⤵��Ĵ����������ι⤵�Ǵ�����Ԥ����Ȥ��Ǥ��롣���⤵Ĵ���ˤ�������ô�����ꡢ���ڥ졼���Ϻ�Ȥ˽��椹�뤳�Ȥ��Ǥ��롣
��(3)�����եƥ���ǽ�ˤ��������ȡ����������������䤹�����ƥʥ��������=���ή�����ߤ�����ꡢ�ꤳ�������ɤ�����Υ���ȼ�ư�ǥ����ɤ��夬�뿷��������Ѥ���Ϣ³��Ȥࡼ���˹Ԥ����Ȥ���ǽ�Ȥʤä����ꤳ����С��ȼꤳ�������å���Ʊ���˲����Ƥ���֤����ե����ɥ�������ư���뤿���Ȼ��δ��������Τ�̤�����ɻߤ��롣�ޤ������Ϻ�����˵��γ����ؤ���������ñ���μ¤˹Ԥ��뽸���������֤䡢�����Υȥ�֥�ȯ����������б��Ǥ���ޥ�������ץ��ʤɡ����ƥʥ������ɵᤷ����ǽ��ƽ�˼������Ƥ��롣
���һ��͡Ӣ����䷿��̾=YH452R����ʬ=EJU��������ˡ=��Ĺ4070������1895������2050�ߥꢦ���μ���(���å����դ�)=2435����������̾=4TNV86CT������=����4��������4����Ω���ǥ������륿���ܢ����ӵ���=2��091��åȥ뢦����/��ž®��=37��9������å�(51��5PS)/2600rpm��dz����������=43��åȥ뢦��ư����=���륹���������Хåƥ�=80D26R����������=��450������Ĺ1570�ߥꢦʿ�����ϰ�=16��9kPa(0��172���������f/ʿ�����������®����=HST̵����®(FDS)����®�ʿ�=�����̵�ʡ�����®3�ʢ�����®��=���ʡ���®0��0��75��ɸ��0��1��43������0��2��66��ȥ�/�á���ʡ���®0��0��65��ɸ��0��1��43������0��2��25��ȥ�/�â�������=4���ǥХ�����ü�ֳ�=1460��1510�ߥꢦ����=1450�ߥꢦ���⤵�ϰ�=50��150�ߥꢦ��®�ʿ�=��®ƱĴ+������2�ʢ���������Ĵ������=��ư�⡼������(��ư����ưʻ��)��æ������=��������ή��������ƹ=��420����810�ߥꡢ��ž®��520rpm��2�ֽ���ƹ=��170��240�ߥ�(�����䤫����������ž®��1600rpm)����ư������=��600��Ĺ��1350�ߥꢦæ���������=������������ӽТ���������=1000��åȥ�(������20��)��Ŭ����ʪ��Ĺ=550��1300�ߥꢦ����Ŭ����=����70�ٰʲ����ɤ���85�ٰʲ������ǽΨ=12��53ʬ/10������
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
����ư��ڰܿ�����ȯ�䡿���ޡ������� |
|
| |
|
|
| |
�����ޡ�������(��)��4��1����ICT���Ѥ���Ѥ��������٤�RTKľ�ʥ������ȵ�ǽ�ˤ��ľ�ʼ�ư���ʤɤ�����Ȥι��Ψ���������ٲ���¸������������ư��ڰܿ�����PW200R������פ�ȯ�䤹�롣
����ǯ�������Ը��������ˤ��ͼ����Ȥ��ä����������������ʬ��ˤ����ơ�ICT���ε��Ѥ���Ѥ�����Ȥθ�Ψ���������Ƥ��롣���ޡ�������Ϥ����β�����˸�������ư��ž������SMARTPILOT(���ޡ��ȥѥ����å�)�ץ�����Υ饤�åפ����Ƥ��롣
����������ư��ڰܿ�����PW200R������פϡ����ѷ�����ڰܿ����ˤ����ơ����ޡ�������Ȥ��ƽ���ľ�ʥ������ȵ�ǽ����ܤ��������ڥ졼���κ����ô��ڸ�����ȤȤ�ˡ������Դ���Ǥ��ñ�˹����٤ʿ��դ���Ԥ����Ȥ��Ǥ��롣
���Ҿ��ʳ��ס�
��������̾����������ư��ڰܿ�����PW200R('S)('RS)('G)��ȯ������2025ǯ4��1�������ʲ��ʡ�368���ߡ�456��6100��(�ǹ��ߡ��������˾�������)
���Ҽ����ħ��
��(1)��������������٤�RTKľ�ʥ������ȵ�ǽ(RTRKľ�ʥ���������ܡ�G����)=RTK��GNSS�����μ�ư���ɥ����ƥ����Ѥ��������˴������A����B������Ͽ���뤳�Ȥǡ��������ʿ�Ԥ˸���2��3������ι����٤ʺ�Ȥ�Ԥ������Τʤ����Ǥ⡢�ޤä��������դ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣����ˡ�ľ�ʥ������ȥȥ饯������Ѥ�����Ω�Ƥ���硢�ȥ饯�������̳Ѥ��PW200R�פ����Ϥ��뤳�Ȥǡ��ȥ饯����Ʊ��η�ϩ��Ȥ��Ǥ��롣�ޤ����ܿ���Ȥ���PW200R�פ����̳Ѥ�ȥ饯�������Ϥ��ơ��幩������̺���������Ѥ��뤳�Ȥ�Ǥ�����ں��������ηϤǺ�Ȥξ��ϲ��������ٲ���¸����롣
��(2)����®�١����ٸ���=�ǹ��®�٤�0��55��ȥ�/�äȡ����赡�������10%���塣�ޤ���®�٤θ���˹�碌�ƿ������ι�¤��ľ�����������Ѥ�������٤ˡ���Ψ�褯�����դ��롣
��(3)���Τ���ߤꤺ�����Ǥ���9�ʳ��Ρ�ʤ�ڰ�Ĵ����С���=�������٤ι⤤ʤ�ڰ�Ĵ����С������������˲ä�����ž�ʸ����ˤ⿷�����ߤ�����ž�ʤ���ߤꤺ�˥�С�����ǽ�ˤʤꡢ����Ԥ����ʤ�1�ͺ�ȤǤ��ΨŪ�˺�Ȥ��Ǥ��롣�ޤ�Ĵ���ʿ���9�ʳ���������ʤ���̤κ٤䤫��Ĵ������ǽ��
��(4)�͡��ʺ����ηϤ�Ŭ��=�������12����ɲ�ͽ��������˥��ץ�������ꡣͽ������(24��)+�ĺ���(4��)�Ǻ���28����ĥȥ쥤����ܤǤ����絬�����Ǥ�ȥ쥤����������㸺�Ǥ��롣�ޤ������վ�֤�45��66����������꤬��ǽ���ޥ���������������������dz������������90�ߥ��RS���͡��澮�̤���ڰܿ����б��������23��80�������û���ֻ���(S����)�ʤɡ�����������ηϤ��б����롣
���Ҽ�ʻ��͡�
����̾��=���ޡ����ѷ�����ư��ڰܿ�������ư����=4�ض�ư��������ˡ=��Ĺ3160������1835(ͽ�������Ǽ��1725)������2075(ͽ�������Ǽ��2225)�ߥꢦ�����Ͼ��=365�ߥꢦ����=666����������=����4�������륬��������ӵ���=0��391��åȥ뢦��ʽ���=5��8������å�(7��9PS)/3000rpm����ư����=���륹�������������������=��������(�ѥ���ƥ����)���ȥ�å�=����1200/1270�ߥꢦ����=1200/1300/1320�ߥꢦ��®�ʿ�=����2�ʡ����1��(HMT)�����վ��=2�����վ��=450/500/550/600/650/660�ߥ�(6��)��Ŭ�����⤵=0��300�ߥꢦŬ����ʪ=����٥ġ��Ϥ��������֥��å�������ǽΨ=0��5��0��9����/10������
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�ڥ�åȥ�������������������ȯ�� |
|
| |
|
|
| |
��(��)������(�����µ�Ĺ�����縩�칭�����������Į2��30)��3��顢�����̵��֥ڥ�åȥ����������פ�ȯ�䤷�����ץ饹���å��ڥ�åȤθ�����ι������忧γ�ʤɤ������ʤ������Τǡ�1�������������3�ȥ�θ���������Ǥ��롣������ʤϥ����ץ�����¤�������ץ饹���å��ꥵ������ȼԤʤɤ��оݤ˽�ǯ�٤�5����������Ǥ��롣
��Ʊ���ϡ�LED�����κ��Ѥʤ��߷פ�ľ����Ʃ��������Τ���ڥ�åȤ�������ǽ�������˸��夵��������˥�����ʬ��ǽ���赡��2�ܤ�0��03�ߥ�˹��������ι������忧�ڥ�åȤ�����٤����̡��ޤ��������ʤν���ˤ�Ʊ���ȼ��Υԥ����Х�֤���ѡ����ʤδ���ź�����㸺�������ʤΥ�����Ǿ��¤��ޤ��ʤ���ץ饹���å����ʤν��٤���뤳�Ȥ��Ǥ��롣
�����Τۤ���(1)0��1�ߥ����������������٤�����(2)1���Ʃ������Ʃ���ڥ�åȤ����̤���ǽ(�������Υ��åƥ����ѹ��ˤ�ꡢƩ������Ʃ���θ������̤�1��Ǽ¸�)(3)������LED����Ѥ��������μ�̿���赡����10�ܤ˱�Ĺ(4)�ӥ����Х�֤Ͻ�������1��7�ܤΥХ�ֳ���®�٤ˤ�����̻������ʤδ���ź����10%�㸺���Х�ֳ��������ü��Ǻ����ѡ���3�ܤ�Ĺ��̿����¸������������̤���Ӿ������Ϥ��㸺(5)�ӽХۥåѤμ�곰������ǽ�ˤʤ��������������˸��塽�ʤɤ���ħ�����롣
��Ʊ���μ�ʻ��ͤϼ����̤ꡣ
����������ˡ=��2200�߱���1400�߹�1656�ߥꢦ���μ���=1100����������Ű�=ñ��AC200��240�ܥ�ȡ�50/60�إ�Ģ�����ư��=2��3������åȢ�ɬ�ץ�����=500��750NL/ʬ(����ץ�å�5��7��5������å�����)������ǽ��=0��1��3��0�ȥ�/��
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���ѳ����ΰ�����ȯ�䡿ʡ������� |
|
| |
|
|
| |
��ʡ�������(��)(����������Ĺ�����縩ʡ���Ծ���Į3��1��63)�Ϻ�ǯ���顢�ѳ�����ͥ��������ȷ��֥��ƥ����ϥ��פ��ܳ�ȯ�䤷�����������åȤ�#300�ȥϥ����åȤ�#800��2���ब���롣�Ȥ��˷������ʬ�ˤϡ���ľ������ɤ���ʤ�ľ�Ф��Ƥ�������(�Ѹ��gecko)����¤�ͤ��ȼ���ȯ����������GG360(�����ϥ���åפ�G��gecko��G���Ȥ߹�碌��)����ѡ�360���������˥���å��Ϥ�ȯ�������ˤΰ��괶��ͭ���Ƥ��롣
��������Ĺ�ϡ��Ӷȵ����ʤɤ���¤�����䤹��(��)����(��������Ĺ����븩ζ�����)�Υ��ץ饤�䡼�ȿ����������ϲ������Ĺ��̳��Ƥ��ꡢ����ط�����Ʊ���ʤ��ܳ�Ƴ����1��Ȥʤä������Ǥϡ��ܼҹ����ǥ⥻���ν��Ȱ��ˡ֥��ƥ����ϥ��פ�ٵ뤷����
��������Ǥ϶�����ڤ뤿��˾��˿��դ���ܤ��Ƥ��ꡢ��ŷ���ʤɾ�����Ǩ�줷�Ƥ���ݤϳ��䤹�����ޤ�����ξ�����դ��ǵ��ξ���ư���롢���ȵ��Τξ��Ԥ��褹�����Ŵ�ľ���������䤹���Ȥ��ä�������β��꤬���ä�����Ʊ���ʤ��������Ȥǡ�����������ǰ���á���Ȥ������äƤ���Ұ��ϡ��֤��ΰ������ϥե��åȴ�������������餺�����ä��ꥰ��åפ��ư¿����⤢��פ��ä����ޤ�����¤�����ɾ������������̳�ϡ��ְ������ݤδ�������Ʊ���ʤ�Τ����졢���줫�����Ѥ����Ȥ���ɾ����ʹ�����Τǡ���ɤ�μ����ˤ�侩�����������Ӷȵ����Υ��ƥʥʤɤ������äƤ�������Ź�ˤ��Ŭ�����ʤǤϤʤ����ȹͤ��������̤˾Ҳ𤷤����ȻפäƤ����Ǥ��פȡ�
��ʡ������Ȥϡ���ʪ����ȡ����ȵ��������ߵ�������ξ�ط��ʤɤΥ�����ȼ���Τ��빩�����ʤ�2���������ǻ��Ȥ��ʤ��Ƥ��ꡢ��ʪ�����ô���Ԥϡ�������������ô���ԤȤ�Ϣ�Ȥ����Τ�ޤäƤ����ۤ���������������ή�̤˴ؤ���Ȥˤ��б����Ƥ��������Ⱥ���μ��ӥ��åפ˰��ߤ�ߤ��Ƥ��롣
��Ʊ�Ҥ���ʪ���ʤϡ�Ĺ��������������ȷ�����ʤꡢ����Ĺ���ǤϺǽ�������˥�å����Ǻ���Ѥ����ˤ�ˤ��������֥����ǥ��å��ס���ȷ��Ǥϥե����ʡ��դ��ϥ����åȤ�ߥåɥ��åȤ�·����ֿ����Ҥ���פʤɡ������Ϥ�褫������̾�٤ι⤤���ʤ����߽Ф��Ƥ��ꡢ����Ρ֥��ƥ��ϥ��פǤ�360�٤Υ֥�å��Ϥǿ����ʼ��פ��Ȥ�ª���Ƥ����ͤ�����
��Ʊ���ʤϥ������åȡ��ϥ����åȤ�2����ǡ����顼�ϥ��졼���֥�å���2������������25��25��5��26��26��5��27��28���������������ɽ��JSAA���ʤǤϡ������Ȥξ⥨�ͥ륮���ۼ�������ǽ�ϵۼ����ͥ륮��20J�ʾ塢�ѳ�����ư�������0��20�ʾ塣
���䤤��碌��Ʊ�ҥ��塼�������=TEL084��920��7111��
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
������������ȯ�䡿�ݵ������ |
|
| |
|
|
| |
��(��)�ݵ������(��ͦ���Ĺ����븩��������Ϥ1877)�Ϥ��Τۤɡ����ܥ��ȥ饯��TERAST��ST25/31(25/31����)��Ŭ�������ST�ѥ������פ�ȯ�䤷����Ʊ�ҤΡ֥ޥ��ƥ����������K950������פ���ܡ���Ȫ���ڤΰ�ư����ĥ��ΤλĴ��������ѥ�åȱ��¡�����ʤɡ����Ϥʺ�Ȥʤ�����Ū�˳��ѤǤ������ʤ���
��ƱK950�ϡ���եȥ����ॵ�������礭�����ƥȥ饯���ܥǥ����Ȥδַ�(���ڤ�����)��ʬ�ˤȤꡢ�¿����ƺ�ȤǤ���Τ˲ä�æ�����¿����ե���ȥ���ȥ�����Х�֤�ɸ�������������Ȥǡ���եȥ�����β��ߥ��ԡ��ɤ�Ĵ�����ǽ�ˤ������ذ¿����ƺ�Ȥ�ʤ�뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����å����Ȥο�ʿ���֤γ�ǧ�����������æ����Ȥ��ΥХ��åȳѤ��ǧ���뤿��Υ�٥顼�ϡ������ɤ���Ǥ������ǽ�ˤ��������Х�٥顼����ѡ��ɲå�٥顼���å�(���ץ����)�����夹��С������å����Ȥ���Ƥ�Ĵ���μ�֤�����ʤ��ʤ롣
�����Τۤ����������ʤ���Ӥ����͡��ʲ��ɤ�ܤ��Ƥ��ꡢ����եȥ�����ζ��٥��å�=�Ǻ������ѹ��������ද�٤�20%���墦�Х��åȥҥå������=��¤��ľ������˴��ʥҥå��ˢ�æ�她����ɤ����=����������ɡ�������æ����ΰ���������墦���ꥹ���åפ��ưפ�=���ꥹ�˥åץ�����ƥԥ���ߤ���������¦�̤���ε���Ȥ�����ʤɡ����ڥ졼����ͥ�����������߷פΥ������˻ž夲�Ƥ��롣
����ü�����å����Ȥ�˭�٤ǡ�������å����ͥХ��åȡ������ѡ��ޥ���Х��åȡ������ѡ��ĥ��դ��Х��åȡ������ѡ��Х��åȡ������̥����ѡ��Х��åȡ������ѡ��ѥ�åȥե��������ޥ˥��ե��������إ��ե������������ѡ����졼���������ƿ����������ȥҥå��ѥХ�������ȡ���·������
��Ʊ���λ����夲�ٽŤ�300��350�������ҥԥ�⤵��2200�ߥꡢ����ԥ��ꥢ���1605�ߥꡣ�������Ѥ�50�١�����׳Ѥ�58�١�
��Ʊ���䤤��碌TEL=0296��35��0611
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�����ͳ���������ȯ�䡿ENEGGO |
|
| |
|
|
| |
��ENEGGO(��)(�����˼�Ĺ�����츩��������ͭ��Į�ֺ�ʺ2842��2)��1������ͳ���ͭ���۹����֥������ʥ֥�פ�20���������פ����Ⱥ����ѤȤ���ȯ�䤷����Ʊ���ʤ��������������פ��顢��ʪ����������Ϥ˷礯���ȤΤǤ��ʤ�18����Υ��ߥλ�����Ф������ǡ������������3���Ǥ�ä���ͭ���۹�����������������ۤ����̻��ۤΤ��������ѤǤ��롣
����ħ�Ȥ��ơ��ۼ������ɤ���ʬ�ҥ��ߥλ������ˤ�ꡢ��ĥ���塢��Ĺ¥�ʡ�ŷ���Խ�˶������Ϥ����夹��ʤɤ����ԤǤ��롣���ΤʤΤǻȤ��䤹�����Ķ��ˤ�䤵�������������Хꥨ�������ϡ����Ӥ˱��������ǡ�������������۹���Ѥ���3���ࡣ
���ޤ�����������ư����ѤΡ֤��٤Ƥβ�������ѡסִ��տ�ʪ�ѡס֥Х顦���ѡ�(��800�ߥ��åȥ�)��3�����ۡ��ॻ���ʤɤ�ȯ�䤷�Ƥ��롣Ʊ�����פΥܥȥ�ˤ���̤�ú�����륷��������Ⱥ��礷�ƻ��ѡ�����ޤ��Ѵ�����Ƥ�������Ѥ��֥��åץ�������פ��뤳�Ȥǿ��������Ѳ��ͤФ�����
��Ʊ�Ҥϡ���̤�����硼�����������Хå��ʤɤ���¤���䤷�Ƥ���(��)�����ƥ���21(���츩�����)�����ΤȤ��Ƥ��롣�ȼ��Υͥåȥ�������ܳ��Ϥγ��줫���ӽФ������̤������뤳�ȤǸ�����Ĵã����Ʊ�Ҥ��õ����Ѥ��Ѥ��ƿ���Ϥ��ˤ�����������������ϲ������ߥλ���ʬ����Ф��뤳�ȤDZ���������ȯ���������ǡ������������ޤ�Ǥ����ΤΡ������ͳ���ͭ�����ߥλ����Ѥ��뤳�Ȥǡ�����β����������Ѥ��㸺�ˤĤʤ���ΤǤϤ�Ʊ�ҤǤϴ��Ԥ�Ƥ��롣
���������䤤��碌=Ʊ��TEL0955��25��9595
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�����������ۥɥ�����ȯ�䡿����ʥ����ꥵ���� |
|
| |
|
|
| |
��(��)����ʥ����ꥵ����(��������Ĺ�����ϸ����Ļ��縶Į2225��41)��2��27����2025ǯ�դ�ȯ���ͽ�ꤷ�Ƥ��뿷�����������ѥɥ�����֥˥塼������ե饤�䡼�פ�ȯɽ����ܼҤǹԤä���
���������������Ƭ�ˤ������Ĺ�������λ��üԤ˴��դ�Ҥ٤�ȤȤ�ˡ����ҤˤȤä��軰����Υɥ������ηи����Ȥˡ����Ȥ��䤹���������䤹�����ʤȤ������ץȤdz�ȯ��ʤᡢ�桹�Ȥ��Ƥ⡢��������äƤ�����Ǥ������ʤ��Ǥ��ޤ����פȰ���������
��³���ƱĶ�����ŷ�Ĵ�������դ�������������Ԥä���
���֥˥塼������ե饤�䡼(��)�פϡ��ַ��¡��϶�����������ʲ��Υơ��ޤˡ����ȥɥ�����Ȥ��Ƥ�ɬ��ǽ/��ǽ�����������㥳���Ȳ���ޤ����ʤǤ���פ���ħ�������������ȤΤ���Υɥ�����Ǥ��뤳�Ȥԡ��뤷����
���ڼ����ħ��
��������ǽ��������ʢ������Made��in��Japan���ޥ��ͥ����������ե졼��Ǵ�������ǽ���ƼKư���ԥ⡼�����(��ư���ԡ��������ȡ�AB�⡼��)���վ��դ��ץ��ݤǴ�ñ���ץ��ݥ����å�ư��Ǽ�ưΥ��Φ��ǽ
��Ʊ�Ҽ¸����ǤΥǥ�ե饤�ȤǤϡ�Ʊ���ε�ư�������������ǽ�ԡ��뤷����
�������Ĺ�ϡ֥˥塼������ե饤�䡼(��)�ϡ������䤹�����ʡ����˻Ȥ��䤹�����ѵפ�¸�����¿�������Ȥ������˻ȤäƤ������������ʤ��ܻؤ���ȯ���Ƥ��������ҤˤȤä��軰����ε���Ȥʤꡢ��������äƤ�����Ǥ������ʡ�����¿�������˼�˼�äƳ�ǧ���Ƥ������������פȡ�Ʊ���˴��Ԥ�����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�饸�������֥�����ܡ����䳫�ϡ�������֥��ޥ��� |
|
| |
|
|
| |
��(��)������֥��ޥ���(����ζ����Ĺ��ʼ�˸���������397)�ϡ��饸���ϥ�ޡ��ʥ�������AIRAVO(�������)��(��¤���������ͥĹ���(��))������Ϥ�����
����ħ�ϡ����ΥХ���ɵᤷ�ƥ����������ѡ�������30�٤ޤǤη��Ф��б����Ƥ��ꡢ�饸�������Τ��ᡢΥ�줿��꤫�����Ǥ������Ϥ�ʿ�Ϥ�ͤ�����������Τߤʤ餺�����Фʤɴ�����ȼ�����Ǥ���˺�Ŭ��
���ޤ����ϥ�ޡ��ʥ��դκ��Ѥǡ�150���������Ǥ⡢���ä���˿���������٤Υ��å���ʴ�դ��롣�����Ȼ����Ѥ路�����ä����ڤˤ�Ը�����䤹�������������餻����ˤ��뤳�ȤǴ�������ڸ��������ƴ������ϥ����ư���������ϥ⡼������ư�Υϥ��֥�åɼ�����ѡ������Ư�����ŵ������Ť���ɥ饤�ӥ�ȯ�Ťˤ�ꡢ������ʤ��ʤäƤ⤢�����٤����Ԥ���ǽ����
������¾�ˡ����ξ�����ǽ�ǡ��������Ǥ����ڤˤǤ��롣�ޤ������®�٤��®3��2������2������2�ʳ����ڤ��ؤ��뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ��饸������Դ���ʥ桼�����Ǥ�¿��������Ǥ��롣��ư�������4�����ޤ�®��Ĵ���ǽ��
�������ʻ��͡Ӣ���ˡ=��Ĺ1695������860������675�ߥꢦ�����Ͼ��=80�ߥ�(�����������)����������=260���������ڥȥ���ܲ�ǽ���Хåƥ������=�������ӡ�12�ܥ�ȡ�15Ah��4�����ӵ���=270Ω����������������=8��0PS������dz��=��ư����̵���������dz����������=4��1��åȥ뢦����®��=���ʻ�®0��4��0����(̵�ʳ�)/��ʻ�®0��3��5����(̵�ʳ�)
�����䤤��碌=(Ʊ�ұĶ���)TEL0795��42��1066
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
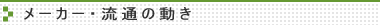 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
����˥��ब1�̡��͡��ߥ���� |
|
| |
|
|
| |
����35���ɼԤ����֥͡��ߥ����(��Ť��������ȿ�ʹ��)��ɽ������6��������η���Ϣ��ۤǹԤ�졢�ȳ�����ϥ���˥���(ʡ���������ϻ�)�ξ������֥ե롼�ƥ��ޤ����פ��ӥ��ͥ������1�̤�������ޤ��������ͥĹ���(��)(������������)�Υ饸��������AIRAVO(�������)�פϥ����ǥ��͡��ߥޤ���ޤ������줾����ԶѲ�Ĺ�����Ľ����Ĺ����ǰ�ν�������ä���
��19��Ϣ³���ޤ������뤲����Բ�Ĺ�ϡ�����ν˲�ѡ��ƥ����Ǥ������ġ��֥ե롼�ƥ����ޤ����ϡ��ޤ���������ˤ����õ������ơ��֤䤫�ʿ��ˤι����դ��ä����פ�̿̾�Τ������Ĥ�Ҳ𤷤ʤ��顢�͡��ߥۤɳڤ�����ȤϤʤ��ȡ�����ޤǤ�19ǯ��̾�Ť����פ�Ƨ�ޤ����ֻ�ˤȤä���ǯ��20��Ϣ³�Ȥʤ�Τǡ��������������ɥ���äȤ����͡��ߥ��Ѱդ����������Ǥ⤳���ˤ�äƤ��ޤ��פȼ���˸��������ߤ�����
�����ļ�Ĺ�ϡ�AIRAVO�Ϻǽ餫��̾����������ʲ��ˤΤ�����Ȥ�����AI�ϰ����äƽź�Ȥ�ڤˤ������Ȥ�����������ɽ�����ۤ�������AI(����ǽ)���Ȥ߹������Χ��������Ф��Ƥ�����Ǥ�AI�ΰ�̣�⤫���Ƥ���פ�������ǯ��ȯ���ͽ�ꤷ�Ƥ��뼡�����ʤϡֲ��Ρ�MAIRAVO(�ޥ����)�פȤ��Ǥ˷��Ƥ��뤳�Ȥ������������Ⱦ��ϲ��ؤι����Ϥ�����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
����ʬ�����ư����®�ؿ������ȿ���Ω�����ޡ��ۡ���ǥ��� |
|
| |
|
|
| |
�����ޡ��ۡ���ǥ���(��)(������ͼ�Ĺ)�ϡ������η��ߵ��������ȵ���ʬ��Ǥ���ư�����ʤ��뤿�ᡢ2025ǯ4��˿������ȿ�����Ω���롣���ȿ��Ǥϡ����ޡ��֥������ʡ�OEM���ʡ�����ݡ��ͥ�Ȥ����e�ѥ�ȥ쥤���3�ĤΥ��ƥ�������Ϥ����ߥ˥���٥롢�ۥ��������������Ϥ���Ȥ������ȵ�������ư���˼���Ȥࡣ���ޡ����롼�פˤ�������פ����ʷ�����ư���ο�ʤ��®���뤳�Ȥǡ����ʻ��ѻ��ˤ����벹�����̥����κ︺��ʤ�Ƥ�����
�����ȿ��ϡ���������Eleo��Technologies��B��V�ʤɥ��롼�ײ�Ҥ���ư���˴�Ϣ�����¸�ΰ����ȿ���ޤ�ǹ�������롣��Ǥ�ԤϤ���ޤǼ�ư�ֶȳ��ʤɤ���ư�����ɤ��Ƥ���Marko��Dekena��(�ޥ륳���ǥ�����)��
�����ȿ�����Ω�ϡ���YANMAR��GREEN��CHALLENGE2050�פǼ�����³��ǽ��̤��μ¸��˸���������Ȥߤ�1�ġ�
�����ޡ����롼�פ���ư���˲ä������Ǥ䥢���˥��ʤɤ�����dz���γ��Ѥ�۴Ĥˤ��Ѷ�Ū�˼���Ȥ�Ǥ��롣�����Ѥ�Υ��ϥ�����Ѥ����������Х�Ǥ�æú�ǼҲ�μ¸��˹����Ƥ�����
���ҥ��ޡ��ۡ���ǥ���(��)��ɽ������COO������ů���Υ����ȡ�
��������ȿ����ߤϡ��֥��ɥ��ơ��ȥ��Ȥ˷Ǥ���A��SUSTAINABLE��FUTURE���ƥ��Υ������ǿ�����˭�����ء����μ¸��˸���������Ȥߤ�1�ġ�
����������ư�ѥ�ȥ쥤��γ�ȯ�ϡ����Ҥ��ǥ������륨����Ѥ߾夲�Ƥ����Υ��ϥ�����ߵ��������ȵ���ʬ��ˤȤɤޤ�ʤ�����깭��ʬ���Ŭ�������������ܥ�˥塼�ȥ���¸����뤿��˽��פʥޥ��륹�ȡ�������ư������������³��ǽ�ʼҲ�μ¸��˸����������ľ�̤��Ƥ��뺣�����ʤ���ǽ����夵��������Ǥʤ�����ꥯ���ǻ�³��ǽ��̤��˹�������ư�ѥ�ȥ쥤��γ�ȯ��Ƴ�����®������ɬ�פ����롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�դ���Ÿ������ɸ�礭�����ꥢ�����͵���Ź |
|
| |
|
|
| |
��(��)���͵���Ź(���ݼ�Ĺ�����ո����ĻԾ����849)��7��9��3���֡�Ʊ��������������ˤƽդ���Ÿ����Ť��������褽800�ͤθܵ����Ȥˡ��ǿ��ε���ڤӾ����ȯ������ȤȤ�ˡ����㤤������Ÿ��������Ǥ����±鵡�ǻ��Ѥ����ȥ饯�����Ŀ���������Х���ʤɤ��ò������ꤷ�����٥�Ȥ��ܶ̾��ʤȤ�����
��������ϸ��⤪��Ӹ�����������Ȥ���줷�����������緿�ޤǽ��¤����饤�åפ���������ơ����ޡ����ʤ�4���β��ʲ������ˡ��Ǹ����Ƥ�Ԥä���
��������ˤϥȥ饯��YT3���������·���������Ԥ�зޤ������ˤ��Ŀ���YR8DA������Х���YH6135��Ϥ��ᡢ�̤�������������ȵ����żﵡ�ʤɡ���¿�������ʤ���·��������������˸������Ԥ�ľ�ܥ��ԡ��뤷����
���ޤ���������Ǥϡ�̩�ĵڤӥ��ޡ�����������ˤĤ��Ƥιֽ����Ť��졢¿�������Ȥ����ܤ�����
��ƻϩ�����ŵ������ʡ��α��ˤϲ����ڱ��������������θ������ʡ����ߤ���졢��������¿��Ÿ������ȤȤ�ˡ����Ԥ����Ǽºݤ˵�����ư��������θ����Ƥ�������������������ǽ�ʤɤ�����å����ʤ���ô���Ԥ˼��䤹��Ǯ�������Ȥ⤪�ꡢ���ܤ���Ƥ�����
�����͵���Ĺ�ϡֺ����ͽ����饷�����ۡ���ʹ�ޤ���ߤʤɡ����Τ����Ƥ�����ī���餪�����ξ��ʤ���뤪���ͤ�¿�����Ʋ��ι�ƭ�ˤ�������ߤι⤵���Ƥ���פȡ�������Ω�λ���Ž��줿������¿����������줿��
�����������ޡ����ʤβ��ʲ���ˤĤ��Ƥ����Ԥ�ȿ���ϡ��פä����������Ȥ�����Ʊ�ҤǤϡ�����äƥ��饷�����ۤ������ʲ���ˤĤ��ƸܵҤ������Ƥ�����������������������Ĥ��οͤ�¿�����ᡢ������פ�¿���ΤǤϤʤ�����ͽ�ۤ��Ƥ��롣
�����ݼ�Ĺ�ϡֽ�������¿����������줤����������3���֤���夲��ɸ�ϡ������˥��ꥢ������4���β��ʲ���˸�����Ÿ����θ��ɤ�ˬ�����פȤʤ롣��ꤳ�ܤ��Τʤ��褦�ˤ��Ƥ���������������ϰ�ξ���ȯ�����Ȥʤꡢ�ϰ����Ȥ˹����Ƥ��������פȺ���ΰյ����ߤ��ä���
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�϶�100��ǯ��ǰ��ŵ����ǰ�˲�����Ų����� |
|
| |
|
|
| |
���Ų�����(��)(����ľ��Ϻ��Ĺ���Ų����ް�Խ���1300)��6�����;��ԤΥ������饢���ȥ��ƥ��ۥƥ��;��ۥƥ�˹��⳰����δط���120̾;������϶�110��ǯ��ǰ��ŵ����ǰ�˲��פš��ʾ塢���ڼ�Ĺ��110ǯ�֤�Ĺ���ˤ錄�봶�դΰդ�������ȤȤ�ˡ֤��줫���100ǯ�����������äȤʤ뵻�ѳ������ܻؤ����ϰդ�ȯ�Ȥ������פȰ���������Ʊ�Ҥϡ�����3ǯ(1914ǯ)�˽��塦�����绰Ϻ���诵�����¤����ǥ������ȡ������ܡ����ڽ������28ǯ�˼�Ĺ�˽�Ǥ���������絡����Ѥ���˳�ȯ��ʿ��6ǯ�˸�������ľ��Ϻ���Ĺ�˽�Ǥ����������ǯ��ȯɽ�����ڸˤϡ������㲹��¢�ˤ���̾��Ȥ�ʤä����ҡ��������������������������䤵�졢�������Х��Ÿ����ʤ�Ƥ��롣
����ǰ��ŵ����Ω�������٥�ȥۡ���ˤ����ơ����絡������ˡ��Ƽ�¬���ʤɤ��������硢���������ŵ��ҡ������ʤɻ������硢�ޤ�������ʪľ��ΤȤ줿�ƿ�������Ÿ��������ˡ�Ʊ��110ǯ�ˤ錄���ұ�פ��Ҳ𤵤줿��
����ǰ��ŵ�ϡָ�������Ǯ�פε��Ѥǿ�����̤��ؤ�ơ��ޤˡ������̳������γ����ǻϤޤꡢ110ǯ���֤ä��ӥǥ���å���������Ǥ��줿��
��³���ơ����ڼ�Ĺ���϶�110��ǯ�����ΰ���(�̹�)��Ԥä���³�������н˼��˰ܤꡢ�ް�ԡ���쵬Ƿ��Ĺ���������ȵ���������ɩ�µ��ײ�Ĺ�����줾�줪�ˤ��θ��դ�Ҥ٤���
������Ĺ����ϡ��϶�100ǯ��Ķ�����ȤϾ��ʤ����Ų���������ϡ��ϸ�����ɽŪ�ʴ�ȤȤ������Ѥʸؤ�ȤʤäƤ��롣����ˡ�ȯŸ����뤳�Ȥ��ꤹ��פȴ��Ԥ��ۡ�
���ޤ���ɩ�²�Ĺ�ϡ��϶Ȼ����顢�ϰ�ȯ�Ȥδ�ˡ�����ޤǡ���˥ȥåץ�٥�ε��ѳ�ȯ��ʤ�Ƥ���줿���϶�110ǯ�ˡ�����˿����ʥ��Υ١���������ޤ�뤳�Ȥ��Կ����夲��פȽҤ٤���
����ŵ�˼����ǡ����饰�ӡ�������ɽ�θ�Ϻ�����ˤ������������ϡ�̴�ؤζ�ƻ�פ��ꤷ����ǰ�ֱ餬�Ԥ�줿��
�����θ塢��깯����̳������ˤ�볫��ΰ����ˤ�국ǰ�˲��˰ܤä����˲��Ǥϡ���������ȶ�Ʊ�ȹ硦������Ӳ�Ĺ��ȯ���ˤ�봥�դ�Фơ��ϸ��Х�ɤˤ�른�㥺���դ��Ԥ��������夲�������ڹ�����Ĺ����Ĺ���IJ�ΰ����ˤ�ꡢ���������ä���
����2015��2024���ƻ�������10ǯ����ߡ�
����������=�絬�ϡ����ޡ��Ȳ��οʤ����ܤ����Ȥ��б��������ʥ饤�åפ�Ƚ�����ݻԾ���ưʳ��ι�ʪ�ʤɿ��Ծ�ˤ��ܤ�������Ѷ�Ū�˿����ʤ�Ÿ����
����������=���ȴĶ��ǤΥ桼�����ˡ����˱������ǥ������쿷�����緿��������饤�åס�Ǯ����Ǥ��ŵ��ҡ�����WPS������������������ŵ��ޤǤ���·���¡�
����������=�����Ҳ�Ҥ���ƻ�˾�ꡢ��������ؤ����䤬���á�����ꥫ��Φ�ǤλԾ쳫����Ϥ˿���档
��ʪή��������=�桼�����ˡ������б�����٤���¨Ǽ������������ؤνв���������ߤȡ��ݼ����ʺ߸˴��������ƥ�Ƴ���ˤ�ꡢ�ܵ����٤θ�����礭�����档
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
��ȯ�˽դ�Ÿ���ۥ��� |
|
| |
|
|
| |
��(��)�ۥ���(�ϸ��Ҽ�Ĺ����̸���������8��1593)��7��8��2���֡��ܼҤˤ����ơ�2025�դ�Ÿ����פŤ�����
�����ˤϥȥ饯�����Ŀ���������Х���ʤ���30�椬Ÿ�����줿¾���������30�Ҥκǿ��������������ȯ������ʤɡ����Ȥ�Ω���Ω�ä���Ƥ�Ԥ��������δ��դ����赤���դ��Ÿ����Ȥʤä���
����������ò�����������Ǥ������к��˸������Ƽ������Ʋ���ƭ�ˤ��ⲹ�㳲������ॷ�к��ʤɤ����ܤ���Ƥ��뿧�����̵��ʤɤ������������䤷����ɾ�������
��Ÿ������̴ܶ��Ȥ��Ƥϡ������������ò�������š��ȥ饯�����Ŀ���������Х����Ϥ��ᡢ��ȵ������������������Ƶ����⤹�굡�ʤɤ���ŵ���50��ʾ���·������Ÿ����2����������ŹƬ��Ÿ������ï�Ǥ��ǧ���뤳�Ȥ��Ǥ���������˾�Ԥ�Ÿ��������˴�˾��Ф��������Ȥʤä�����ŵ�������Ʊ�Ҥ�����ꤷ������������������Ρ���������⸫�����ͤ�����ʤɡ��ܵҤ���ι⤤��������Ƥ��롣
���ϸ�������̳�ϡ��Ʋ��ι�ƭ�ˤ�ꡢ������ư������ȯ�ˤʤäƤ��롣¿����������줷�Ƥ���������褦�����ò����������ŵ�������ʤɤ��褷����Ÿ�����ˤϥ��ե����ե������ä���ȹԤ�����ꤳ�ܤ��Τʤ��褦�ˤ��Ƥ��������פȽҤ٤���
�����߲��Ǥϡ��ȥ饯�����Ŀ����Υ��ƥʥֽ���Ť����պ�����˼�ʬ�ǤǤ����ñ���ƥʥΥݥ���Ȥ�Ҳ𤷤����ֽ����Ω�������Ф�ۤɤ������֤�ǡ�����ե��ƥʥؤδؿ��ι⤵���Ǥ�����
���ϸ���Ĺ�ϡֺ�ǯ�����Կ���¿�����������dz赤�ˤ��դ줿Ÿ����Ȥʤä����桹�Ͼ�ˡ��٤������ȡ��ڡ����ȡ�³�������Ȥ�ơ��ޤ˳�ư���Ƥ��롣�����ͤΤ���ˤʤ���Ƥ��³���Ƥ��������פȡ�����������˸������յ����ߤ��ä���
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�ե����ޡ��������å��ե������˽�Ÿ��������� |
|
| |
|
|
| |
���������(��)(�ڰ»�Ϻ��Ĺ)��1��2��ξ�����������ë����塹�ڸ��।�٥�ȹ���dz��Ť��줿�֥ե����ޡ���&���å��ե������פ�ͭ�ʹƻ뷿�緿���ܥåȥȥ饯����TJW1233�ס�����Х����HJ6130�ס����ܥå��Ŀ�����PRJ8DR�פʤ��緿�������Ÿ�����ܤ����ȡ�����٤����������Υѥե����ޥ����ԻԤξ���Ԥ˥��ԡ��뤷�����ޤ���5���ȯ��ͽ���EGO��(���)����ư���ѼǴ�������ư�ⰵ����������ư�֥�������ư������Ÿ�����Ķ�����ʤɼҲ����ؤδؿ����⤤�Ȥ����Z������Ф��ƴĶ��ؤμ���Ȥߤ�PR������
��Ʊ�ե������ϡ�������ˡ����������ˡ�Ͷ���Ť����θ������٥�Ȥǡ������ܤΥץ����ȼԤ��������Ҥɤ�����Ȥ�Ĥʤ��ͤ����Ȥ����Բ�λҤɤ⤿���˸����ʥ˥åݥ����Ȥ�ȯ�����륤�٥�ȡ�(��ż�)�����ӿ建�ʡ��кѻ��Ⱦʡ�ʸ���ʳؾʡ���̳�ʡ������ģ������ԡ�����GAP����ʤɤ���礷�Ƥ��롣�����Ϲ�ŷ�˷äޤ졢�������鵤�����徺��20��C��Ķ���ư쵤�˽դ��褿�褦���۵��ǡ������æ���Dz�����ͤ���Ω��������λҤɤ⤿����Ⱦµ�ѤǸ��������Ӳ�äƤ�����
�������ˤϡ��ڰ¼�Ĺ������������������Ķ�����Ĺ((��)ISEKI��Japan��Ĺ)������ˬ�졢�����åդ���夷��������ϥ����åդ�Ʊ�ҤΥ����ݥ졼������μҰ���¿�����ä����Ȥ�����
������Ի��Ȥ��Ƥ��ä������夷���ȥ饯����ǰ���ƥ����ʡ�(����ϥ֥롼���å������Υ��ܥåȥȥ饯����TJW1233��R��)�ˤϿƻ�Ϣ�줬�¤ӡ���ˤ���㤭�����Ļ��⤤�ơ��Ҥɤ�λ������륹���åդϤ̤�����ߤοͷ��ǡ֤Ϥ��������פ�Ϣ�ơ�
������Ÿ�������ʡ��ϡ������ʤ���ȥ饯��������Х����Ŀ����μµ���ΤϽ��ƤοͤФ���ǡ��Ҥɤ����ͤ�������ɽ��Ǽ̥���ǧ���Ƥ�����
���ޤ����������ʤ���EGO����ư���ʤϡ����ơ������ǥҥåȤ��Ƥ���ȤΤ��ȡ�Ʊ�ҤǤϡ����٤Ƥε���Ŭ��ޡ����������Ǥ������������ͽ��ǡ����߹ĵﳰ������Ϥ��߽Ф��ȤäƤ��äƤ���ȤΤ��Ȥ��������ʡ���ô�����Ƥ���Ʊ�Ҥι���Ź�����������Ĺ�ϡ����ԤϴĶ�������Ҵ��ʿͤ�¿�����ݡ�����ޤ���ư�����ʤ�Ǥ��뤳�Ȥ⤢��ޤ������Хåƥ꤬�ɤ줯�餤��Ĥ��ʤɴؿ����⤫�ä��פ��ä���
��������ISEKI�ε������о줹�뤳�Ȥ�����Υ�����֥ե����ߥ���ߥ졼����2025��(�ץ졼�䡼�����ȼ�Ȥʤäƹ�������Ϥǥꥢ����絬�������θ�����ǽ�����ȥ���ߥ졼�������Ȥ���������ǿ͵��Υ����ࡣ�ºߤ�������������μ�ξ�����������Ѥ������Ȥ����Ǥʤ��ܻ����ӶȤ��濴�Ȥ������������ȷбĤ��θ��Ǥ���)�λ�ͷ�����ʡ��ϡ�1��20���ͽ�������դ�������2���Ȥⴰ�䤷�������������˥ȥ饯����TJW1233�ס��Ŀ�����PRJ8D�ס�����Х����HJ6130�פ��о줹�뤬����ͤǤ����Ȥ�������äѤ���ä���
������Ϻ�������¤�����ư���ޤ���«���Ƥ��ʤ����������ˡ����üԤ���ϡ������ȡ����Ƥ�����ʤ�����ˤʤ뤳�ȤϤ��ޤꤤ�����Ȥ���ʤ��Ǥ��衣���ʤ������Ȥ����ڤ������Ȥؤδ��դ�˺��ƤϤ����ʤ��Ǥ��礦��(����ë�衦30��Υ����ޥ�)���ּ���褬�ե����ޡ����ޡ����åȤ˽��ʤ��Ƥ���ΤǸ�����ޤ������ȶ�ʤȤ����������꤬�����ꡢ���������˼�����뤳�Ȥ��������ǤϤʤ����Ȥ˵��Ť�����ޤ�����(���ջԡ�30�������)�ʤɤ����������ä���
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�ʥ��ͤǷл���Ĺɽ����ISEKI��M&D |
|
| |
|
|
| |
��(��)ISEKI��M&D(���������Ĺ����ɲ������������Į700)�ϡ�2��7���˳��Ť��줿����6ǯ�پʥ��ͷ�ֻ��϶�ɽ����(���̼���ˡ�������ŵ������������������ϳ��Ѷ��IJ���)�ˤ����ơ����ͥ륮������ͥ�ɹ������Ȥ��ơֻ�кѻ��ȶ�Ĺɽ���פ���ޤ�����
����ɽ���ϡ����ͥ륮����ͭ�����Ѥ˸����ʸ��ӤΤ��ä����졦���Ⱦ줪��ӸĿͤ��оݤˡ����������ϳ��Ѷ��IJ��Ĺ����ӻ�кѻ��ȶ�Ĺ�����ʥ��ͥ륮����֤�ɽ�������Ρ�
������μ��ޤϡ�(��)ISEKI��M&D�ˤ�����A������LPG����LNG�ؤ�dz��ž�������������ͥ졼������ƥ�Ƴ���������٤˱����������ηײ�������θ��Ӥ��Τ���줿��
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
������ե������ߡ��ǥ� |
|
| |
|
|
| |
��(��)�ǥ�(�ӿ�Ƿ����Ĺ�����θ���ë�Ծ���Į1��1)�ϡ�1�������Թ���˿�����������ե������ߤ�����
��Ʊ���ե����Ǥϡ�Ʊ�ҤαĶȡ����ѡ������ȡ����ij���IT�ʤɼҰ���1000�ͤ����������Ϥ��롣
��2��28���ˤ�������ե����ǡ�������ꥢ�ˤ�����Ʊ�Ҥμ���ȤߤξҲ�ڤӥ��ե����θ��ز��Ť��줿��
�����ϥ��ڡ����ֽ�(TSUDOI)�פǹԤ�줿������Ǥϡ��б����������ټ�ô���β�������������ꥢ�γ��פ�Ҳ𡣡ֿ͡�����ν����ϤǤ�������ǡ������ء��ܵҡ�¾�ȳ���ޤ�ѡ��ȥʡ��Ȥ�Ϣ�Ȥ����Ƥ���������ޤ�������ꥢ��6�������ä������������ץ���ȱ��Ĥ�2�����˽��뤷�����ɤ�����Ǥ⥢���������䤹���Ϥ����������������⳰�Υѡ��ȥʡ��Ȥζ��Ϥˤ�����ʵڤӥ���塼�����ο����ʲ��ͤ����߽Ф����Ҳ�˹����Ƥ����פ�������ե����λ�̿������������
���ޤ�Ʊ���ե����Υ��ץȤ�Ҳ�
�������Ϥ�¥��=���⳰��¿���Υ���ܥ졼���������߽Ф���
�������פζ��̲�=�Хå����ե�����ǽ��층��������Ψ����ޤ롣
�����ϰ�ؤι�=�ϰ�Ҳ鿮�ꡦ����������ϰ̤ΰ���Ȥʤ롽�ʤɤ�����������
�����θ塢����ˤ����륽�եȥ�������ȯ��AI���桦SoC��ȯ���ա��ɥХ�塼����������Ȥο�ʤʤɤˤĤ��ơ����줾�����Ǥ�Ԥ�����������
����������ե������ס�
��������=��105��0004������Թ��迷��4��3��1�����װ��ĥӥ�
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
��ݲ�Ĥǥ����ƥʥ֥��Ϣȯ������ޥ�ȯư�� |
|
| |
|
|
| |
����ޥ�ȯư��(��)(�Ų������ĻԿ���2500)��18��19���������ݥե������dz��Ť�������9���ƥʥ֥롦�֥��ɹ�ݲ��2025������ݤ���פ˽黲�ä����֡���Ÿ���˲ä���19���ˤ�Ʊ�Ҥ����ĸ���������б���ά����Ĺ�����β�Ĥǡ֥�ޥ�ȯư������ˤ�̤���Ĥʤ������ƥʥӥ�ƥ���ι�פԡ������ޤ����������å�����¾�ҤȤΥѥͥ�ȡ����ʤɤ�ͽ�ꤷ�Ƥ��롣
���֡���Ÿ���Ǥϡ�Ʊ�Ҥ�������1��Ǥ���⡼�������������YA��1�ס��������Х벽�θ�ư�ϤȤ⤤������������P��3�פμ�ʪŸ����(��)�إ��ܥˡ��Υ����ƥ����Ȥˤ�äƥɥ쥹���åפ��줿��ư�֤����λ���θ�Ÿ���ʤɤ�Ԥ���
��Ʊ��Ĥϡ��������Ϥdz����졢�������Х�dz������륵���ƥʥӥ�ƥ��Υ�������������ߥ�˥ƥ������٥�ȡ���³��ǽ������������ͥåȥ�������Ȥ��ƺǤ�Ĺ����ˤ���IJ�Ĥ�1�Ĥˤʤ롣
��Ʊ�Ҥϡ����٥�Ȼ��ä��̤��ƤɤΤ褦��Ʊ�Ҥ��ͤι����˹����Ƥ����Τ����ޤ������줫��ɤΤ褦�˿ͤι����˹��������Τ���ȯ�����롢�Ȥ��Ƥ��롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
̤������ѥץ�åȥե�������ܡ���������ѥӥꥪ�����������������ܥ� |
|
| |
|
|
| |
��(��)���ܥ�(����͵���Ĺ)��10����4��13��������塦̴���dz��Ť����2025ǯ���ܹ��������ˡ��ץ���ʥѡ��ȥʡ��Ȥ��ƶ�������ѥӥꥪ���̤����Իԡפǡ�̤��Ρ����ѥץ�åȥե�������ܥå�(Versatile��Platform��Robot)�פΥ��ץȥ�ǥ��Type��V�פȡ�Type��S�פ����������Type��V�����Ȥδ���̵�ͤ�¸�����ץ�åȥե�������ܥåȤ���������������ܥ���Ÿ���֡�����Hall��C���ߤ����Ƥ��ꡢ������̤��ο������ȤλѤ�ɽ�����롣
����������Ω����Ʊ�ѥӥꥪ�����ǥơ��ץ��åȤ��Ԥ�졢���ʤ���������Ĺ�������Ҥ���ɽ������������������Ĺ�ϡ�����Υ��ץȤ�̤��Ҳ�μ¸���Ǥ��롣̤���ԻԤǤϤɤ���ηä��������졢�ɤ�ʹ��������ޤ��Τ����䤿����ȤϤɤΤ褦���ηä�ƥ��Υ������Ǥ��μҲ������褷���ۤ��Ƥ����Τ��������䤤�˸�����³����1�Ĥ����������������˴���������������������λҤɤ⤿�����ޤ��и�˭������ͤ����ˡ����ƿ��äƴ����Ƥ��������������ʥ����ǥ������߽Ф���뤳�Ȥ���Ԥ��Ƥ���פȽҤ٤���
���ѥӥꥪ��̤����ԻԤϡ���Ĺ��150��ȥ������33��ȥ�ε���ʷ���ʪ�ǡ�����������֤ˡ�Hall��A�ס�Hall��B�ס�Hall��C�פ�3�������ʬ����Ƥ��ꡢ����Ÿ���ȶ��˶�������12�Ҥ��͡���Ÿ����Ԥ������ܥ���Ÿ���֡����ϺǸ��Hall��C���ߤ���졢������̤��ο������ȤλѤ�ɽ�����롣̤���³���Ƥ����ϵ�ȿͤ�ͥ�����ֿ������ȡפμ¸��ˤ����ơ�����̵�Ͳ��������ƥǡ�������Ѥ�����̩���Ȥ�Ϥ���Ȥ���Ķ���٤��㤤��������ˡ�γ�Ω��ơ��ޤˡ����Υ����ƥ��Υ������Ȥ������ѥץ�åȥե�������ܥåȤǤ���Type��V��Ÿ�����롣
��Ʊ��Ÿ���֡����Υ����ˡ��ˤ�����������Ĺ�ϡ֤��줫������Ȥˤ����ƽ��פ�����̤���̤��Υ��ץȵ���������Ǥ��Ҳ𤷤ޤ��פȽҤ١�Type��V�ˤ�����줿�١�����ä������ε��Τ������ȡ����ؤ�����꤬ʨ�������ä����طʤ����֤��줿�緿�������Ǥ�Ʊ���ܥåȤ�Type��S������̼���dz�������Ѥ�CG���˥�����DZǤ��Ф��줿��Ʊ��Ĺ�ϡ�Type��V�Ϻ�Ȥ˱����Ƽ��Τι⤵�������Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ���1���¿�������Ӥ˻��Ѥ��뤳�Ȥ���ǽ�����ޤ�����Υ��ܥåȤ��ߤ��˶�Ĵ���ƺ�Ȥ��뤳�Ȥˤ�ꡢ��Ψ�ɤ���Ȥ�Ԥ��פ����������ߤ⸦�泫ȯ���ʤ�Ǥ���Ȥ�������ܺ�Ԥ˳��ߤ����������Х뵻�Ѹ����Ǽ±�ǥ�γ��Ť�ײ�����ȽҤ٤���
��Type��V�����Ȥδ���̵�ͤ�¸�����ץ�åȥե�������ܥåȤ���������Ĺ�������ˤ��ä��̤ꡢ��ħ�ϡ���ʪ�������������ݤδֳ֡�������Ƥ˱����Ƽ��Τι⤵�����ʤɤ��ѷ����뤳�Ȥ��Ǥ����ƺ�Ȥ�Ŭ��������ץ���Ȥ�ư���դ��ؤ��뤳�Ȥǡ�1���¿�������Ӥ˻��Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
��������Ĺ�ϥ����ˡ���ΰϤ��ǡ����ؤ����Ҥɤ⤿���������������Ȥ�?�ȵ��Ԥ������졢�ֺ���ϸ��夫��ο����������Ȥ�������Ÿ������������Ͽʹ֤�ɬ�פʿ�������ˤ��Τꡢ�����٤������Ȥξ������˹ͤ��Ƥۤ����Ȥ�����å������פ�����������Ʊ�֡����Ǥ��祹��������Ѥ��ơ����ۤ����Ȥ�¸��Ǥ��륲����ʤɤ�Ÿ�����Ƥ��ꡢ�Ҥɤ⤿���˸�����̤�����Ȥ�ͤ��뤭�ä����Ȥʤ�ФȽҤ٤���
���ޤ�������̵�ͤ������Ϥɤ����餷��¸����뤫�ȿҤͤ���ȡ����Ƚ����Ԥ��Ĥ�ܤ�Ȫ�Τ��Ф˽��ޤʤ��Ȥ������������饤�ե������뤬���ޤ��ΤǤϤʤ����פ�������̤����ԻԤ��ۤ����ڤ�����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�դΤ������ܥ������ǿ��������Ȥ���ơ�����ÿ����ܥ� |
|
| |
|
|
| |
��(��)����ÿ����ܥ�(������Ĺ����̸��������Ժ�������5��2��36)��2��28����3��1����2���֡����ո���跴��¿��ή�̥����ǡ�¿�š����ꡦ�������3�ĶȽ��Ʊ���ޤ���3��5��6��2���֡����ڸ���ë����ƻ�αؤ����ͤ���������äפ��ǡ����ġ����Եܡ�������˧���4�ĶȽ��Ʊ�ˤ��Ÿ�����2025ǯ�դΤ������ܥ������פŤ�����
��Ʊ�Ҥ�2���4��ޤǴ�����Ϥǡ�2025�դΤ������ܥ������פŤ��Ƥ��ꡢƱ�Ҥ��䤷�ʤ��ICT����������塼��������Ƥ���ȤȤ�ˡ����ϰ�˹�ä�������Ҳ𤷡�¿�������Ȥ˺��ǽΨ�θ��塦���ϲ����бĵ��ϳ���ʤɿ��������ȤΥ���������Ƥ��Ƥ��롣
���ֽվ���������ˡ���1��Ⱦ������ɸã����4���٤μ��������˸����ơ��ɤ��������ȥ��å��夬�ڤ��Сפ���1�Ķ���Ĺ����2�Ķ���Ĺ��Ĺ���ᡣ��夲�λ���Ť���ΰ�ĤȤ���ƱŸ���������դ��롣
����ǯ�˰���³����2��28����3��1����¿�š����ꡦ�������3�ĶȽ�ˤ���Ʊ�dz��Ť���Ÿ�����ŷ���˷äޤ졢ξ���Ȥ�¿�������Ȥ��ͤᤫ�����赤����Ÿ����Ȥʤä���
�����ˤϥȥ饯��MR1000���Ŀ���NW8��DR6130�ʤɤ��緿���龮�����饹�������ޤǤ�Ÿ��������¾��ȵ����̤������ʤɤ���·������Ȥθ�Ψ�����㥳���Ȳ���¸����뵡����ǿ��ξ������Ƥ�����
����ǯ������Ʋ��ʤι�ƭ�ˤ�ꡢ���Ȥ��������Ф��������ߤϹ�ޤäƤ���褦�ǡ����Ǥ��Ѷ�Ū�˾��ʤ��ǧ����ô���Ԥ˼����ͤ�¿���ä���
����������Ƥ��äƤ���40��������ϡ�15�إ��������1�ͤǴ������Ƥ��롣����������餤�ʤɤǴ�������Ȥ��Ƥ���ͽ�ꡣ�������ˤ��㤨�ʤ���������˸������Ŀ���������Х��ȥ饯�����褿�פȤ�����
���ޤ������Ԥ�10�إ�������ΰ��Ƥ���40��������ϡֺ�ǯ���㤬�µ��ˤʤꡢ�ޤ���1�ͤ������������������ˤ��켺�Ԥ��Ƥ��ޤ����Ʋ���ƭ�β��äϼ������ʤ��ä��פȤ�������ǯ�������������ǹԤ����ᡢ�����Ϣ�ε�������ǰ�˥����å����Ƥ������ޤ������ܥå��Ŀ�����Ƴ����ͤ��Ƥ���Ȥ�����
��¿�űĶȽ����������Ĺ�ϡ������Ȥ������ι�����ߤ��⤤����ǯ�ϰ꤬����äƤ��饳��Х�����줿������ʤ��ȤϽ��ơ���ǯ�Ϥ���ȿư��������Ȼפä��������αƶ��ϴ������ʤ��פȡ�Ÿ����˿���������˸�������ꤳ�ܤ��Τʤ��褦���ä���ȥե��������Ƥ����Ȥ�����
���ޤ������ġ����Եܡ�������˧���4�ĶȽ��Ʊ�ˤ��Ÿ����γ��Ž����ϡ�ī���龮�����ߤ뤢���ˤ���ŷ���Ȥʤä����������ץ����¿�������Ԥ�����ä���������Ȥ�70��ν����ϡֱ��Ǥ�ط��ʤ�����ǯ���ڤ��ߤ���Ƥ���פȸ������������㤬�Ĥ�ȩ����ī�Ǥ⡢���ˤϳ赤�����դ줿��
�����������äƺǽ���ܤˤĤ��Τ����ޥ�������ɥ����顼�ȥ��硼�ȥǥ����������夷���ȥ饯�������β��ˤϡ���ǯ10���ȯ�䤷��NW80S������Υ���������Ŀ���������Ŀ������¤֡����������緿�ޤǼ��·�����ȥ饯�����ȵ��������������ʤɤΤۤ�������������������������˹�碌����С����֥�ץ饦�ʤɴ���ľ�Ť˴�Ϣ����Ƽ磻��ץ���Ȥ䡢�����dz�������ѥ���åȥ�����١���ʤɤ�饤�åפ������Ԥδ��Ԥ˱�������
������������Ǥϡ֥˥塼�٥��ޥ�����TA801N�פ����᷿���Ȥ���Ÿ������������ڤο��������б����뤳�Ȥʤɤԡ��뤷����
���Ƕ�μ���ư���ˤĤ���Ĺ����Ĺ�ϡּ�ư���ɤ�ICT��Ϣ�����˶�̣����Ŀͤ������Ƥ��뤳�Ȥ�´����Ƥ���פȤ���������μ��׳���˴��Ԥ��롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
������Ÿ�������������㥯�ܥ� |
|
| |
|
|
| |
��(��)���㥯�ܥ�(���ľ���Ĺ�����㸩����������Ļ����331)��7��8����ξ����Ÿ�����2025�դΤ������ܥ������פ��ƱĶȽ�Ǽ»ܤ������Ʋ��ǤϽռ��פ˸����ơ��Ѷ�Ū�ʸܵ��б���Ԥ����ܳʾ�������Ȥ����������ļ�Ĺ��Ÿ����ؤΰյ����ߤ亣���θ��̤��ʤɤ�ʹ���ȤȤ�ˡ����������š���㡢Ĺ����4�ĶȽ���ꡢ�ƽ�Ĺ���ष����
�������Ÿ����μ��⥳�ץȤȤ��ơ��ϰ�Τ����ͤȶ��˰���������Ȥ�!�פ�Ǥ���(1)������Ԥˤ�����۴ĤΤ���ο��������γ���(2)KSAS����ư���ɤ�Ϥ���Ȥ������ޡ������Ȥ�PR(3)��ǯ��꿷�����Ȥʤä����Ķ�����������Ķ�������Ϣ�Ȥ��ơ������ʳ��θ����ߤ����Ұ�ݤȤʤäƤμ��פ����(4)�����ѡ�ô�������ȤؤΥ��ץ������������˼���Ȥ।�٥�ȤȰ��֤Ť���������Ū�ʽ�������ȤߤȤ��ơ�����GS�ȥ饯���������Ŀ����ο�ʤ�ƻ��������Ÿ������ʵᤷ�������ʤ��褷���Ƶ�����Ϣ�Ȥ��������Ǥ�Ÿ����RTK���϶ɤ�PR���뤳�Ȥˤ�뼫ư���ɤο�ʤ����ѿ������ߤγ������ܻؤ���Ÿ����ˤ�����������ɸ�ϡ��ƱĶȽ��3���ٷײ��70%�����ꤷ����
�������ĶȽ�(�ߺ���§��Ĺ��ޤ�12̾���������ڱ�)�ϡ������Ÿ����Ǥ�ư����ɸ350�͡�������ɸ5250���ߡ�����¾��Τ�ͥ��������������Ȥ�¿���бĵ��Ϥ�Ŀͤ���ˡ�ͤޤ��͡�������Ǥ⡢�Ʋ��ξ徺�ǥ���Х����ư�����ɹ����ä����ޤ����������Ȥ��ꡢ���̤��椫��ˡ����äƤ��������פȤ��ä��ߺн�Ĺ������Ÿ����Ǥϼ�ư���ɤ俷����GS�ȥ饯������ʤ��롣�ֺ�ǯ�������Ȥδؿ��ι⤵���Ƥ��롣��ʬ�������μ������˴����Ƥ���Τǡ��ֽ���������ꡢ�ºݤ˻ȤäƤߤơ���������ä���Ƥ������פȽҤ٤���
����������������ܤϥȥ顦�����Ĥ�1�椺�ķ�3�椬��Ư���Ƥ��뤬���������˾ö�Ū�����Ȥ�¿�����ᡢ�����ӥ����Ϥ��������������ݤ��Ƥ������ˡ��ֺ�ǯ��Ժ���������̡������ӥ����ʼ�꤬�ɤ��ʤꡢ�����������夷�ơ����ʤ��Ϳ����б��Ǥ���褦�ˤʤä���ʷ�ϵ����ɤ��פȼ���������������
�����űĶȽ�(Ĺë��˽�Ĺ�ޤ�12̾������Խ��ն�)��ư����ɸ320�͡�������ɸ5200���ߡ���𤬥����ϰ�Ǥ��ä�������ݤ侮����лϤ����ǯ���Ʋ���ƭ������ơ�������ߤ��ޤäƤ��ꡢ���������Ƽ�ư���ɤ�GS�ʤɤΥ��ޡ����������ʤ��Ƥ������ޤ���Υ�����ƽ��ʤߡ��ĿͤǤ⡢20��30�إ������롢ˡ�ͤǤ����50��70�إ������뵬�Ϥ����Ȥ��ФƤ����緿�����ʤ�Ǥ��롣���ǯ��RTK���϶ɤ������Ǽ�ư��������3���Ƴ���˷�ӤĤ����塢�٤��Ȥʤꡢ��ǯ�ˤʤä�3��Ƴ���ȡ����������ᤷ����
��Ĺë���Ĺ�ϡ��Ʋ��ξ徺�䥻���륹�ˤ���ʵ�⤢�ä�������Ϥ꺣����絬�ϲ��ۤ����ˡ��������롣�±鵡���Ѱդ���PR���Ƥ��������פ��ä����ޤ���������Ⱦ���ʾ������3��4�إ������뵬�Ϥ����Ȥ��Ф����ȥ�ǥ�����ʥ�ʵ������ʡ��ϰ�Υ����ޥ�Ȥʤ�ô�������Ȥˤϡ����ޡ���������KSAS����Ƥ��Ƥ������ߤɤ�ο��������ƥ���ά�����ζ��Ϥ����ʤ��顢KSAS�˲������Ƥ��뤬�����Ѥ�����Ƥ��ʤ����Ȥ��Ф��Ƥο�ʤ�Ԥ�����������ܤϥȥ饯��2�桢�Ŀ���1�档������Ȥǿ�����Υ��ܥåȥ���Х���⡣�������֤��̤����μ��ν�����Ԥ��ʤ��饹�ޡ��������γ��Τ��ܻؤ��������ӥ��̤Ǥϡ������������������������������Ƥ��ꡢ�����˸�Ψ�褯���ʤ��������פ�Ĺë���Ĺ������δ����ġ���ǹ���������Ԥ�����Ȥκ����Ψ����ޤ롣
���Ǥ�⤤��嵬�ϤǤ������ĶȽ�(��������Ĺ�ޤ�20̾����������)�ϡ�ư����ɸ390�͡�������ɸ7910���ߡ����ݺ�ʪ���𤫤�̼�����Ʀ�����������ͥ��ʤ��������������륹���ʪ���ò������μ�����äƤ��롣Ÿ����Ǥϼ�ư���ɤ俷��GS�ȥ饯����KSAS�䥶��ӥ��ʤɥ��ޡ������ȴ�Ϣ���Ǥ��Ф������Ŀͤ�30�إ���������������MR���饹�Υȥ饯������������ؤ�¸�ߤ��롣�ֽ��Ƿбĵ��Ϥ����礷�������ʤ����Ǥʤ��������ʤˤⵤ���ۤꡢ���Ѵ���ʪ���ʤ��Ȥ������ȤΤʤ��褦��������ƿ�ʤ��Ƥ��������פ������Ĺ������ޤǵ���������������Ƥ������Ȥ⡢�Ʋ��ξ徺������äơ�������ߤϹ����Ȥ��ä�����ư���ɤϡ��±鵡���Ѱդ���ǯ����Ω��³����2��Ƴ������ޤ�ʤɡ����Ȥδ֤˿�Ʃ���Ƥ��Ƥ��롣
���ޤ������ݺ�ʪ�˱����ơ����������緿�ޤ��͡��ʵ������פ����뤿�ᡢ�������ˡ������ʤ��顢�ȥ饯����ʣ�����ͭ�������Ȥˡ����դ���ư���ɤο�ʤ�ԤäƤ��������ͤ����������˼±������ơ�20��μ��Ұ��ΰ�����Ʊ���˹ԤäƤ����������ӥ��ޥ������륹�ˤĤʤ��ĶȤƼ�ꥻ���륹��٤���ʤɡ������������ɤ���褫������ɸã���˿��Ϥ��롣
��Ĺ���ĶȽ�(��¼������Ĺ�ޤ�13̾)�ϡ�ư����ɸ470�͡�������ɸ4800���ߡ������ʤ��顢��Ʀ������ž��⡣ˡ�ͤ�¿�������Ϥ�30��100�إ������롣�ĿͤǤ�����20�إ������롣����ǯ���ˤ����ơ��Ƕ��к��ˤ����פǡ����ɵ������ե��åȥ⥢���������̵����ɥ�����ʤɤ�ư�������ޤ����ɥ�����β�Ư����¿�����ĶȽ�ˤϽ�����������Ԥ��ε��Τ��¤�Ǥ�������������ܤ�2���Ư����¼��Ĺ�ϡ�JA�����ˤ��������Ƥβ��϶�������ᤵ�ǡ�2��3000�ߤ������Ȥˤ�ꡢ����ʤ���״����ˤĤʤ��äƤ���פ��ä��������θ����������300�ͤ���줹�������֤ꡣŸ�������Τ��ʵ�ޡ��������Ȥ��ơ����������Ÿ����¾���������Ȥ�����͡��ʵ�����ڤ���¤١������ܤ�ľ�Ŵ�Ϣ�ʤɤ��Ѱդ�������ư���ɤ�������Ȥ���Ѥ���5������档����¾������GS�ȥ饯��������GS�Ŀ����⤹�Ǥ˺�ǯư���Ƥ��롣
�����������ϼ꤬��ʤ��ۤɡ��ۥӡ����Ȥ���ΰ����ޤᡢ�͡��ʰ��꤬���ब���٥ƥ������Υ����ӥ��ޥμ¤ʻŻ��DZĶȽ��٤��Ƥ��롣
�����ĶȽ�α���˶�դ������ļ�Ĺ�ϡ��Ʋ��徺������ƶ��Ӥ���Ĵ�Ǥ��뤳�Ȥ�����������ǡ�������ư���ˤ�äơ��Ļ벽����Ƥ��ʤ������ߤ�ФƤ���פȽҤ١�ô����˥ե���������������Ǥʤ������������Ȥμ��פ��ꤳ�ܤ��ʤ��������פ�Ȥ�����KSAS�����ˤ��̵�������ѤǤ���RTK���϶ɤϸ���13���ꡣ�����������䤹�ե���������ܹԤ������Ѿ���ؤؤΰ����夲��ǯ�ʹߤ�Ư��������ͤ�������ư���ɤ䥢������ܤʤɤΥ��ޡ��������Ͽͼ�����á������������㸺���Ķ�����㸺�˴�Ϳ���뵻�ѤȤ��ƴ��϶����ѤȤȤ��PR���롣
�����ο�ʤΤ��ᡢƱ�ҤΤߤɤ�ο��������ƥ���ά������KSAS�γ���ˡ���̳Ū������ʤɤΥ��ݡ��Ȥ������뤳�Ȥǡ����쥻���륹�ζ���ȤȤ�ˡ����ȤؤΥ��ݡ��Ȥ�ԤäƤ������ƹ���Ȥγ���ˤ�ꡢ���ǹ���夲�Ȥʤ�172��4000���ߤ�Ͽ��
��¾������������꤬���ʤ��桢��ǯ���顢�������濴�Ȥ������Ķ������ȡ��ƹ�ξ�����ߤ��濴�Ȥ�������Ķ������Ȥ��ȿ�ʬ���Ԥä����Ʋ��ξ徺�������͢���Ƥγ��ݤ����ʤäƤ���¦�̤⤢�롣���Τ褦���طʤ�����夲��������顢��������夲�������Υȥ�ץ�ã���Ȥ��������ʻ�ɸ�˥��եȡ��ƱĶȽ�Ĺ�ˤ�����˿�Ʃ���Ƥ�����
���ޤ������Ķ������Ǥϡ��Ķ����ˤȿ�ʺ��˲ä��ơ����鸦���ˤⵤ���ۤ롣���鸦���ˤ�ꡢ���ʤؤ�����ᡢ�������ä���ƤǤ����������ۤ��Ƥ��������Τ���λ��ߤȤ��ơ�NK�ե�����¼��˸������Ȥʤ�֥�����١����פ��ߤ����±鵡��ͳ�˻��ѤǤ���Ķ�������������������θ����Ǽ��Ұ��ξ�ֵ���θ������䤤���������ä�����Ǥ���褦���ݡ��Ȥ��롣
������ˡ����㥯�ܥ��餷�������㥯�ܥ���¸�߰յ������̤˽Ф���褦�ʡ�������������ά��������������Ϥ��̤��Ƹ��夵���Ƥ��������Ȥ�Ҥ٤Ƥ��롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�ȥ饯�������ȿ����Ĺ�˲��Ļ���ܥ���4��1���տͻ� |
|
| |
|
|
| |
��(��)���ܥ�(����͵���Ĺ)��14����2025ǯ4��1���տͻ���ȯɽ���������Ƥϼ����̤ꡣ
(2025ǯ4��1��)���̵�������������
�������������������Ĺ��������������������Ĺ����ͭ��
���̥ȥ饯����������
�����ȥ饯�������ȿ����Ĺ������͵��Ϻ
���̥����������
������������������Ĺ��ȬȨ�±�
���̷�����������
����������¤���̳��Ĺ����ƣ����
���̤���¾��
�������ܥ��Ρ�������ꥫ�����ݥ졼�����и�(�����������������Ĺ)����������
������������(�ɾ�ά)
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
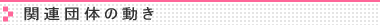 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�ϰ����ȡ������嵻�Ѥ��б����������������ȵ������ѥ��饹�������� |
|
| |
|
|
| |
�������������ȵ�����������(Ĺ��͵�ʽ�Ĺ)��7������̸��������Ԥ�Ʊ��Ϥʤ��ڥۡ���ǡ�����6ǯ�����ȵ������ѥ��饹��������Ť���(Webʻ��)����ĤǤϡ����ȵ������ѥ��饹������ư���ɸ�ಽ�����̲���ʰѰ������(����API�˴ؤ������Ȥ�)�䡢���饹�������ȴ�λ�������Ȥ���(1)�������б�����Х���(2)ξ�����Ŀ���(3)����κ��դ������ٱ礹���ǽΨ�����η�(4)��ޥȥ�����Ϻ�ȵ������ηϡ��γ�ȯ�˴ؤ���ȯɽ���Ԥ�줿���ޤ�������λ��ϡ�����ǡ�����鳫ȯ������Ÿ�����������Ԥ�줿��
������Ǥϡ�Ĺ���Ĺ���������Ĥ������������Ǥϡ����������塢�Ķ��б��������к��ʤɤε��ѳ�ȯ�ԡ��ɴ����äƿʤ�Ƥ����פȺ���μ���ȤߤˤĤ��ƽҤ٤���
�����饹������ư��̵ڤӼ�ǯ�ٳ�ư�������ϡ�������Ϣ�ȿ�ʼ����翹������Ԥ�������6ǯ�ټ»ܲ���Ȥ��ơ��ϰ����ȵ������ٱ祿���ס�=���������б�����Х���γ�ȯ������κ��դ������ٱ礹���ǽΨ�����ηϤγ�ȯ����ޥȥ�����Ϻ�ȵ������ηϤγ�ȯ����ä��礦���ϵ��γ�ȯ���ֳ��������Ѽ��Ѳ������ס�=���⼾��Ŭ������Х���γ�ȯ��������ư���ȵ����ѥХåƥ�ݻ������γ�ȯ���ּ�����������ѥ����ס�=��ξ�����Ŀ����γ�ȯ(6�̤˴�Ϣ����)���ڲ�����㪽��������դ��ݥƥȥϡ��٥����γ�ȯ���ֿ�����Ƴ�����̼¾ڥ����ס�=����������ˤ������Ȱ����μ¾ڸ��梦�۾���ݥǡ����ȴ���Ĵ���ǡ��������礷���ǡ�����ư������μ¾ڢ�����Ȱ������θ���������������Ȥˤ�����ꥹ���㸺���̤μ¾ڡ���Ҳ𤷤���
���ޤ���ɸ�ಽ�����̲���ʰѰ���(���ķ��װѰ�Ĺ)���(����API�˴ؤ������Ȥ�)������Ϣ�ȿ�ʼ������Ŀ�Ԥ������ĥ��С��Ȥ��ơ���������(���̼���ˡ�������������ൻ�Ѷ���)�����ҷ���(�����������������ȸ��楻��)�������(����������ڲ֤���������)����ë��(��ʪ������¢���߶���)��ƣ¼���(���̼���ˡ�����ܻ��߱�ݶ���)�������(���̼���ˡ���������ȵ������Ȳ�)��ƣ��δ��(���̼���ˡ���������ȵ���������)�γƻ����Ǥ�������Ȥʤɤ���𤷤���
�����ȵ������ѥ��饹�������ȴ�λ�������Ǥϡ�(1)�������б�����Х���γ�ȯ(��긩���ȸ��楻���������ȸ���ꡦ��Τ®Ϻ��)(2)ξ�����Ŀ����γ�ȯ(�����������ȵ�����������̵�Ͳ�����ȸ����ΰ衦����ʹ���)(3)����κ��դ������ٱ礹���ǽΨ�����ηϤγ�ȯ(���������ȸ��楻����������ڸ����ΰ衦����͵��)(4)��ޥȥ�����Ϻ�ȵ������ηϤγ�ȯ(���ո��������縦�楻�����Ȫ�ϱ�ݸ���ꡦ��ë���һ�)��4̾�ˤ��ȯɽ���Ԥ�줿��
���µ���Ÿ���Ǥϡ��������б�����Х���ϻ�ɩ�ޥҥ�ɥ�����(��)��������ϵ��ϥ��ޡ�������(��)����ޥȥ�����ϵ���(��)���֥��ȥ������������Ԥ�줿��
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ξ�����Ŀ����γ�ȯ��Ĵ������������6ǯ�ٸ������� |
|
| |
|
|
| |
������������6������̸����������̶�������������Ϥʤ��ڥۡ���ǡ�����6ǯ�����ȵ����������縦�������(����饤��ʻ��)������270̾�����ä����������ϡ����ӿ建�ʤ���ξ������ʤɤθ塢Ʊ����ε�����Ϣ�ȿ��������������������ǽ�����������ΰ衢̵�Ͳ�����ȸ����ΰ衢�����ƥ�������ظ����ΰ褬���줾�츦�泵�Ҳ��Ԥä��ۤ��������ʰ������������٤ʤɤΥȥԥå������⡢����˸��߿ʹ���θ��̸������ʤɤ��Ԥ�줿��
������ΰ�����Ω�ä�Ʊ�����Ĺ��Ĺ��͵�ʻ�ϡ��������Ϥ��Ƥ������ȤߤȤ��ơ�������������ư���������Υ����ץ�API�ʤɤ��������Τ��������ץ�API�ˤĤ��Ƥϡ���ǯ8�������API���̲�����������Ȥ������������Ȥߤ�Ĥ��ꡢICT�٥����������������Ȥ�Ϣ�Ȥ����ơ��ǡ��������Ѥ������������ä��ʤ��Ƥ���Ȥ�����
���ޤ�����ȯ���Ȥ��¤��礭����Ȥ�������Ȱ�����������5ǯ�٤�����Ȼ�˴���ΤˤĤ��Ƹ��ڡ������ȵ������ط������Τ�����˴�������Τ�3ʬ��2�����Ƥ��롣��������ӿ建�ʤȶ��Ϥ��ʤ��顢����Ȼ��Τ�Ĵ����������ȯ�����ƥ����ڡ�������ư�λٱ�ʤɤ�ԤäƤ���������ȤȤ�ˡ�4���Ͽ����ʴ��Ǥΰ�����������ʤ�뤳�ȤȤ��Ƥ��ꡢ����³��������Ȱ����к����ؤ�Ƥ����פȡ���˴���θ����˸���������ʤ����Ȥߤ˰��ߤ�����
�����ӿ建�ʤ���ϡ���ô�˼�����ݵ�����������Ĺ�亴���ֲܴ�ʹ��ȡ������ɵ�����ڲݲ�Ĺ�亴�ε��ܱѾ�����š��ֻܴ�ϥ��ޡ������ȵ��ѳ���¥��ˡ�γ��פ�ǧ�����ξҲ�ʤɤ��ܻ��Ʊˡ��Ƨ�ޤ������Ȼٱ祵���ӥ����ȼԤΰ�������ư��¥�ʤ�ߤɤ�ο��������ƥ���ά�ؤ��б��ʤɤ��줾����⤷����
�����θ塢�ط��Ԥδؿ����⤤������7ǯ�ٳ��Ϥο����ʰ������������١פȡ�ξ�����Ŀ�����ľ�����Ѥγ�ȯư���פ�2�Ĥ�ȥԥå����Ȥ��Ƽ��夲����ô���Ԥ��ܺ٤���������ȯư���ˤ����Ƥϡ�ξ�����Ŀ����ο��հ������٤���ȯ��ɸ�Ǥ����3����������ã���������Ȥ䡢ľ�����Ѥ���Ѥ�������Ψ������2ǯϢ³90%�ʾ�ˤʤäƤ��뤳�Ȥʤɡ����β��˸�����ư������������
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
����Ƿ��Ĺ���������������Ϣ���̾����� |
|
| |
|
|
| |
����������Ϣ��5��������������Υۥƥ����69���̾�����Ť�����Ϣ�εİƤ��̤�ķ衦��ǧ������Ǥ����λ��ȼ����������ȡ����θ��������ˤ����ơ�����Ƿ��Ĺ(��ɲ��������������Ĺ)������������ޤ�������Ĺ����¼����(����)���綶����Ϻ(ʡ��)��ξ�ᡢ��̳���������湨������Ǥ�Ȥʤä����������˵��Ĺ�ͺ(����)������Ǧ(������ʬ)��ξ���Ǥ�����̱ɼ�(�̳�ƻ)����潨��(����)��ξ��������Ǥ������
������ϡ���¼����Ĺ�γ���θ��դ�³��������Ĺ���������ġ��ϰ����Ȥ˲̤�����������Ȥ���䤬�����Ƥ���Ȥ�����ȯ�ʳ�ư��ƤӤ����������ФȤ��ơ����ӿ建�������ɵ�����ڲ���������к���Ĺ���ں�ε���˼���Ҥ١�Ʊ��μ���Ȥߤ˴��Ԥ�����
��6ǯ�٤ζ�Ʊ������Ȥ���ǯ��6��6%����5��6100���ߡ��ưʹߤΥۥ�������������ˤμ���������������������5���Ȥϡ�ʼ�ˡ�ʡ�硢ʡ����������ʬ������Ĺ�ꡣ
������ξ����ϡ����ž��Ȥ���徦�Ȥ���ǯ����39����Ȥʤä���
������λ��ϡ�2024ǯ�ٹ������ɽ�����Ԥ�졢�����ã���ȹ����ɽ���ơ���꾦�Ȥ�������ɧ����Ĺ��������5���Ȥ���ɽ����ʡ�羦�Ȥζ�����������Ĺ��������Ĺ���鵭ǰ�ʤ�£�褵�줿��
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���ϡ��㥳���ȵ��Ѽ¾ڡ�����������Ӹ�Ƥ��� |
|
| |
|
|
| |
��������ˡ�����ӿ建�����ʻ��ȵ��ѿ�������(ƣ�ܷ�����Ĺ)��5�������������Į������ڷ����(����饤��ʻ��)�ǡ�����6ǯ�ٿ������(�ݻ�������Ĺ)���Ӹ�Ƥ��Ť������ı�����٤�����ϡ��㥳���ȵ��Ѥʤɤμ¾����Ӥ���𤵤줿��
����Ƭ���������Ĥ�Ω�ä��ݻ���Ĺ�ϡֿ������Ͼ���47ǯ��ȯ������ǯ��53ǯ�ܤˤʤ롣���줫��⡢����Υˡ����ο�Ÿ��Ƨ�ޤ�������Ȥߤ�ʤ�Ƥ����פȽҤ٤���³���ơ����ФȤ������ӿ建����ô�˼�����������Ĵ�(��������)�κ�ƣ�»ᡢ���ޡ������ꥸ��ѥ�(��)������и�����줾��˼�����ƣ���Ĵ��ϡֿ����μ���Ȥߤϡ����������θ�ľ���ʤɤ�ԤäƤ��������ȵ����ˤ��Ƥ��롣���ȵ��Ѥι��ʿ�ಽ��ޤ뤿��ˤȤ�����ʤ�Ƥ��������פȽҤ١��и�����ϡֿ�����������ľ������桢���ı�����٤�����ϡ��㥳���ȵ��ѡ����������ѵ��Ѥγ�Ω�����̤��ڤ��ߤ��פȴ��Ԥ����
���ֱ��(1)�֤��줫����������ȿ������ȡ�=���ӿ建�������ɹ�ʪ�ݲ�Ĺ�亴(������ô��)�������ҹ���(2)�֥��ޡ������Ȼ���Τ�����ݡ�=�����������������Ǥ���������ܸ��ϻᡣ
��ʬ�ʲ��(1)�ֿ��ı�����٤�����ϡ��㥳���ȵ��ѡ����������ѵ��Ѥγ�Ω�פΤ����쥿�������6����ڤӻҼ��ѥȥ��������(2)�ֹ��ʼ������ղò�������ʪ�����������뵻�Ѥγ�Ω�פΤ������硢���ȥ��⡢�֥��å�����֥ɥ��ط�(3)�쥿���ڤӥ��ޥͥ������ܥ��㡢�ͥ����ι�Ʊʬ�ʲ�(4)�ִĶ���������θ�����������Ѥ�ɾ������Ω��(5)�־����������ü���Ѥγ��Ѥˤ������������ƥ�γ�Ω�ס�
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
��Ω60��ǯ�ε�ǰ��ŵ�����ĸ����� |
|
| |
|
|
| |
�����ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�(���и�������Ĺ)��11�������Ļ���Υۥƥ����Ω60��ǯ��ǰ��ŵ�ڤӽ˲��Ť����ϸ��ط��ԡ��ȳ��ط��Ԥʤ�80̾�ʾ夬������
����������������Ĺ�ˤ�볫���θ��դθ塢ʪ�μԤؤ�������������졢³������������Ĺ����ż��������š����Ԥ˼հդ�Ҥ٤��塢�־���39ǯ����Ω���졢��ǯ60��ǯ��ޤ����뤳�Ȥ����˴�����������������������ԥå��ι��ʵ��������椬ʨ��Ω�������¼�γ�¼�ʤɤ⤢�ꡢ���Ⱦ������礭���Ѳ���������ǡ��ܳ�Ū�����ȵ�����Ƴ���ˤ�ꡢ���ϲ����ȤλϤޤ�Ǥ⤢�ä����ȳ��Ǥ�������Ӥ���Ĺ�����Ʊ���ˡ�¿�ͤ���������������β��Τ���ζȳ����Τ��ȿ�����ɬ���Բķ���ä�����Ω����60ǯ��Ĺ���ˤ錄�ꡢ�����ȳ��ΤޤȤ���Ĵ����Ȥ��Ƥ�����ô�äƤ�������ǯ�ϲ����ط��Ԥζ��Ϥˤ�ꡢ������Ȥ��Ĵ�˿�ܤ��Ƥ��롣�ޤ������ư�ˤ��Ϥ����졢�����ô����Ȥʤ�ͺ�����Τ���θ����Ǥ���إ�����21����֡٤ˤ��ˤ��ߤʤ��ٱ�Ƥ�������ǯ�٤�Ʊ����֤˼�����������ߤ�������ѼԤΰ����ˤ��ư�������Ƥ��롣����ϥ��ޡ������Ȥ�ȯŸ�ˤ��Ϳ�Ǥ���褦�����Ū�Τʼ��Τ��ؤᡢ��ξҲ���̤��������Ҥ��ȹ���ȤȤ��ȯŸ�Ǥ����ȹ���ܻؤ������Ϥ�ŤͤƤ����פȸ�ä���
�����Фκ��ݷɵס����ĸ��λ��������ǽ��ĸ����ӿ建�������������Ѳݤ���ͧ������Ĺ����������Ϣ�δ���Ƿ��Ĺ�����������湨����̳���������ĸ��澮�������������ƣ߷������Ĺ�������Dz�ƣ������̳��Ĺ���˼���Ҥ١�60ǯ�θ��Ӥ�Τ��������оҲ�Ƚ�����Ϫ�θ塢ɽ���������վ���£�褬�Ԥ�줿��
��ɽ���������վ��μ��Ԥϼ����̤ꡣ(�ɾ�ά)
���������ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�Ϣ����Ĺɽ��=��������(���ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�������Ĺ)���������ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�Ϣ����Ĺ���վ�=���ؽ�§(���ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�����)�����ھ�(���ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�ƻ�)����ƣ����(���ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ��������̳��Ĺ)�����ĸ��кҶ��Ѷ�Ʊ�ȹ�����Ĺ���վ�=(��)���ĥ��ܥ���(��)�������������������Ź��ƣ������������߷����Ź��(��)�ò첰�Ȣ����ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�����Ĺ���վ�(��Ʊ������ȶ�����)=(��)�ۥ����Ľ��ıĶȽꡢ��ë����(��)���ıĶȽꡢ���ĥޥå��顼(��)��(��)�ݻ�����꽩�ıĶȽꡢ(��)�ڻΥȥ졼�顼����꽩�ıĶȽꢦ���ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�����Ĺ���վ�(��Ʊ������������ȹ�)=(��)���ĥ��ܥ���(��)ISEKI��Japan���̥���ѥˡ������ޡ������ꥸ��ѥ�(��)���̻ټ������̱Ķ������ġ�(��)����������(ͭ)����ݵ���Ź�����ĸ����ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�����Ĺɽ����(�ȹ��ͥ�ɿ���)=�г���Ƿ((��)���ĥ��ܥ��Ķ���������Ĺ)�������(Ʊ�Ķ���������Ĺ��ǽ���ŹĹ)�����Ľ�ʿ(Ʊ���ĶȽ�Ĺ)����δ��((��)��������)���������((��)���繩������)
����κǸ�ˡ��IJ�θ��դ����§����̳������̳�ᡢ����ƻ���Ԥؼհդ�ɽ���Ʋ���ӡ��˱�˰ܤä���
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�Ķ���θ�����߱�ݤ�¾ڡ����������ʤ� |
|
| |
|
|
| |
�����������Ϥ��Τۤɡ�Carbon��Xtract(��)���彣����(��)�������彣(��)�ȤȤ�ˡ�ʡ���ԤDz���dz�������Ѥ�Ǿ��¤��ޤ���������δĶ���θ�����߱�ݤγ�Ω�˸������¾ڻ��ȤϤ�����ȯɽ������4�Ԥ�ʡ���ԤΡ֥���������ץ������פ���������ͭ�κ��ť�ե�å�������ˤơ����߱�ݤˤ�����CO2���ѤȲò���2�Ĥ����֤��Ų�����CO2�ӽ��̺︺�˼���Ȥࡣ����Ū�ˤϡ�Carbon��Xtract����ȯ��Ρ�ʬΥ�ʥ�����Ѥ����絤�椫��CO2��ľ�ܲ�������ŵ�����CO2�������֡�membrane-based��Direct��Air��Capture�פ���ѡ�����ˤ�ꡢ�ϥ������Dz������CO2�Υϥ�����ؤζ��뤬��ǽ�Ȥʤ롣
���ޤ����彣���Ϥ�Ĺǯ�θ�������Ѥ��Ƥ����ҡ��ȥݥ���Ѥ������ò����ŵ��������֤����ѡ����������������ε��Ѥ��Ȥ߹�碌����Ŭ�ʺ��ݵ��Ѥ��Ω�����ޥ˥奢�벽���뤳�Ȥǡ�����Ū�����ȸ���ؤ�Ÿ�����ܻؤ��������彣�ϡ�Ʊ�¾ڻ��Ȥˤ�����к�����ɾ������ȥ�ǥ�θ�Ƥ������ô�����¾ڻ��Ȥ����̤�����˼Ҳ�����Ǥ���褦�ٱ礹�롣4�Ԥϻ��߱�ݤ��Ų���ʤ��̤��ơ��彣���ꥢ�Υ����ܥ�˥塼�ȥ��μ¸��˹����Ƥ����Ȥ��Ƥ��롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
����Ȱ����ơ��ޤ˥��ߥʡ������ȿ������ز��������� |
|
| |
|
|
| |
�����̼���ˡ�����ȿ������ز�(���ķ��ײ�Ĺ)��5������̸��������Ԥ������������ȵ�����������(������)�����ή����2���֤Ϥʤ��ڥۡ���פǡ����ȵ������ߥʡ�������Ȱ����θ����������Ƥ��줫���ͤ���פŤ���������Ȱ�����ơ��ޤ˷Ǥ�������Ȼ��Τμ��֤�����Ȱ����ιͤ��������ܥå������ˤ���������ʤɤˤĤ��Ƶ���������Ρ������ˤ�Ʊ���ˤơ�VR�ˤ������Ȼ����θ���Ⳬ�Ť��줿��
�����Ťˤ����ꡢ�����������IJ�Ĺ�ϡ����Ȥ����Ϥ��ꤷ�Ƥ�����ˤĤ�����ƥҥ��Ȥ��뤳�Ȥ��褯����ȸ�ꡢ���ѵ��������������Ჿ�Ȥ�����Ǥ����ΤΡ������礭�ʵ����ˤʤ�ȥҥ��Ȥ������ˤ��礭�ʥ����뤳�Ȥ�����Ȥ��������ϤȤƤ���פ��ȽҤ٤������Τ����ǡ��ɤ���ä�����Τ��ɤ��뤫�ˤĤ����͡��ʷ��������Ƥ����Τ����ȵ���������ȤˤȤä�ɬ�פʤ��ȤǤ��ꡢ�����Ϥ��ΰ���Ȥʤ�褦��ͭ�յ��ʻ��֤ˤ������ȴ��Ԥ����
���ޤ�����������Ĺ��͵�ʽ�Ĺ������Ȱ������������μ���Ȥߤν��פ���Ǥ��������������Ȼ�˴���ΤΤ������ȵ����ˤ���Τ�3ʬ��2�ȹ⤤�������Ƥ��뤳�Ȥ�Ƨ�ޤ������ȵ������Τ�Τΰ����������ȤȤ�ˡ����ȼԤؤΰ���������������פˤʤ�ʤɤȰ���������
��³���ơ������Ѷ��ʧ�ǡ����˴�Ť�����Ȼ���ʬ�ϤˤĤ���(�������ȶ�Ʊ�ȹ�Ϣ���������Ƿ��)������Ȱ����θ����ȿ����Ѥؤ��б�(�����������ȵ����������硦��ƣ����)�����ȵ����μ�ư���Ԥ˴ؤ�����������ݥ����ɥ饤��Τ��Ҳ�(���ӿ建�������ɡ�����һ�)�����ܥ��Υ��ܥå������ΰ��������ƥ�ˤĤ���((��)���ܥ���������Ϻ��)���ͤȥ��ܥåȤζ�Ĵ�����μ¸��˸���������(���ȵ������縦��ꡦ��˷�Ź���)����5�ֱ�ڤ�����Ƥ�Ĥ�»ܡ�
�����Τ�����ƣ�������7ǯ�٤�������������������ΰ����������ˤĤ��ƾҲ�Ʊ�����ˤ�(1)������������(2)��������֡��ե졼�ม��(3)���ܥåȡ���ư���������������ꡢ(3)�ϥ��ܥå�(�оݡ����ѥȥ饯�����Ŀ�������æ������Х���)�ȼ�ư������(��ư���ɵ�ǽͭ�ꡣ�оݡ�Ʊ)��ʬ����롣���Τ������Τ�¿�����ѥȥ饯�����Ф��붯���Ȥ��ơ�7ǯ�٤�ꥷ���ȥ٥�ȥ�ޥ�������������å����֡�����ƥ�����֤���������Ŭ�Ѥ����ʤɤȼ�������
���������ӻ�ϥ��ܥ��Υ��ܥå������ȳ���������ܤ�����������ƥ�ˤĤ��ƾҲ�Ʊ�ҤΥ��ܥå������ˤĤ��Ƥϡ���ư����٥�1��2�ޤ���ڤ��ʤ�Ǥ��ꡢ�ȥ顦�����Ĥμ���3�������Ƥǥ�٥�2���ܻ�ƻ롦̵�ͱ�ž��ǽ�ʥ��ܥå����������䤵��Ƥ��롣����������ܤ������������ƥ�ϡ�����¦�ǰ۾��Ƚ�Ǥ�����ߤ���4�Ĥε�ǽ(ž���ɻߤʤ�)���ͤˤ��ƻ뵡ǽ(��������⥳��ʤ�)���͡��㳲ʪ�������ʤɤ��������Τ����ǡ������Ÿ˾�Ȥ��ơ���ư����٥�3�α�ִƻ�ˤ�뼫ư����(��������)�������Τ���˥����奢���̿���͡��㳲ʪ�����ι��ٲ�������Ϥˤ������ǧ�����ݤʤɤ�ɬ�פȤ�������⼫ư����٥�3�¸��˸����ƿʤ�Ƥ����ʤɤȸ�ä���
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���ޡ����ġ��볫ȯ���Ի�����DX��ʥ��������ब����ݥ����೫�� |
|
| |
|
|
| |
���������������긦���˥å��Ի����ȸ�����¤Ӥ��Ի�����DX��ʥ���������(������ɽ���ء��������)��2��28������������Ԥ�����������ĥ����ѥ��ڤ�Web�ˤơ���������ݥ�������Ի����Ȥ�٤��륹�ޡ��ȵ��Ѥȥ��ߥ�˥ƥ��פŤ��������ӿ建������3ǯ����������άŪ���ޡ������ȵ������γ�ȯ�����ɡ��ȤǹԤä��������̤���𤷤���Ρ�
����1���ϡ��Ի�����DX��Ŭ���륹�ޡ��ȵ��Ѥγ�ȯ�פ��ꤷ�ơ����ޥۡ����ޡ��ȥ��饹���ɥ��������Ѥ�������ǧ���ˤ���������Ⱥ�Ȼٱ�ε��ѤˤĤ��ƾҲ𡣥��ޡ��ۡ���ǥ���(��)��������������ά���ε�����塢����͵������ƣ���顢�ܺ��һҤγƻ�ϡֲ���ǧ���ˤ������������Ȼٱ硽�Ի����ȸ������ޡ������ȥġ���γ�ȯ�ȸ��̸��ڡפ��ꤷ�ƹֱ餷����
��������ϥ��ޡ����롼�����Τγ��פ˿��줿�Τ���Ʊ�Ҥ⥢������ȤǼ���Ȥ�Ǥ��륹�ޡ������ȤˤĤ������������Ȥ�ᤰ���͡��ʲ�����褹�������Ȥ��ƴ��Ԥ���ޤ륹�ޡ������Ȥ������Ի����Ȥ�Ŭ�������Ѥ�¿���ʤ��Ȼ�Ŧ�������Ƨ�ޤ��ơ�Ʊ�Ҥ����褷�����ӿ建�ʰ������Ȥθ������֥ͥåȥ�����ߥ�˥ƥ�������Ѥ���DX��ʤˤ���Ի����ȿ����ȿͺ�����פˤ����ơ��Ի����ȸ������ޡ������ȥġ���Ȥ��ơ����ޡ��ȥ��饹���Ѥ�������Ȼٱ祷���ƥ�ֱ������ޡ��ȥ����ɡפγ�ȯ�ȡ����θ��̸��ڤ˼���Ȥ���ݤ�Ҳ𤷤���
���������ޡ��ȥ����ɤϥ��ޡ��ȥ��饹�ޤ��ϥ��ޥۤ��Ѥ������ȸ���ˤƤ��ΤޤȤ����ȥ����ɡ��Ȥ��失�ƺ�Ȥ�������ǡ������Ƚ�Ǥ䵭Ͽ����ͭ�ݡ��Ȥ��Ƥ�����Τǡ��鿴�Ԥ�̤���ϼԡ����ҡ��������鷺Ʊ���κ�ȼ»ܤ�ٱ礹�롣��Ƚ�Ǥ��¤鷺���Ϻ�Ȥ��ǽ�ˤ���ֽ���Ƚ��ע������ܤ�Ƚ�Ǥ����в١����̺�Ȥ�ٱ礹��ַ�������ע����������餯�餯��Ͽ����ǡ����ޥåԥ��ʤɤε�ǽ��ͭ������Ȼٱ�Τۤ������饹����Ԥ��ܤˤ�����Τ�Ͽ���Ƥ��������Ȥ��Ƥ���ѤǤ��롣�оݺ�ʪ�ϥȥޥȤ䥤�����ʤɤǡ��缡���礷�Ƥ���Ȥ������ʥ���֥ɥ��������������ˤ��������̻ٱ����ϻٱ硢����ͽ¬�ʤɤ��б�����AI�����ƥ��ȯ�������ν���Ƚ���Ǥ��ʼ��̤˥�ǥ��������뤳�Ȥǡ�����Ψ�θ�����ǧ�Ǥ����Ȥ������ޤ�����ư���Ʋ�������ʥ��βֿ������Ԥä����ڤǤϡ��ֿ���16��2%��ʿ�Ѹ����ʤɰ�������̤������Ȥ�����
��������Ϥ����Υ����ƥ��������褫��������ˡ��ͰƤ��뤳�Ȥǡ��Ի����Ȥθ���Ǥξ��ϲ��伫ư����ޤ뤳�Ȥ��Ǥ���������Ի�����DX�ˤĤʤ���ΤǤϤʤ����ʤɤ���Ƥ�����
������¾��������Ǥ�������ؤ���������ᡢ��۵�§��ˤ��֥ɥ�������������γ��ѡס�������ؤδ���ٱʻ�ˤ��ִĶ������������μ����Ȳ��ϡס��ιֱ餬�Ԥ�줿��
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�кѻָ������ǹ⡿����������ͻ���ˤ����˴ؤ���ָ��ʤ�Ĵ�� |
|
| |
|
|
| |
��(��)����������ͻ���ˤ�2��27�����־����ư��Ĵ��(����7ǯ1��Ĵ��)�פ�»ܤ������˴ؤ���ָ���Ϥ��ᡢ���ܤξ���ο���͢����Ķ�����θ��������ʪ���ù����ʤι����ˤĤ���Ĵ����Ԥ�����̤���ޤȤ�Ƹ�ɽ������ƱĴ���Ϻ�ǯ1������20��70����˽�2000�ͤ��оݤ˥����ͥåȷ�ͳ�ǹԤä���Ρ�
����̳��פ�ߤ�ȡ����˴ؤ���ָ��ϡ��ַк����ָ���45��6%(������1��4�ݥ������)��ʿ��20ǯ��Ĵ�����ϰ���ǹ�����к����Ż������5ǯ7��Ĵ������40%Ķ����³���Ƥ��ꡢ�⤤����ݻ����Ƥ��롣ǯ���̤ˤߤ�ȡ�20���40����礭���徺�������ַк����ָ��פ��������ͳ�ϡ�ʪ�����徺���Ƥ��뤫���(54��2%)���Ǥ�⤯�������ǡ�¾�ι����ʤ��Ȥˤ����Ȥ����������(8��9%)���־����Ϸ��Τ�������ߤ����䤷���������(8��8%)�ν���ä����ַк����ָ��פι�ư�ϡ֤Ǥ�������¤����ʤ�����ǹ�����(73��0%)���Ǥ�⤯�������ǡ֥������ݥ���ȥ�����������Ѥ����¤�������(56��0%)����ɬ�װʾ�ξ��ʤ�������ʤ���(39��4%)�ν�ȤʤäƤ��롣
���ޤ������ΤǤߤ������6ǯ7��Ĵ���˰���³���ַк����ָ��סַָ��סִ��ز��ָ��פ�3��ָ��ȤʤäƤ��ꡢ�ַָ���(44��0%��Ʊ0��8�ݥ������)�Ͼ徺���ִ��ز��ָ���(40��3%��Ʊ4��8�ݥ������)�ϡ�Ĵ�����ϰ������40%Ķ���Ȥʤä���ǯ���̤Ǥ����Ƥ�ǯ��Ǿ徺���������ä�70��(������9��7�ݥ������)��40��(Ʊ7��6�ݥ������)�ʤɤ��礭���徺������
���ޤ����ִ��ز��ָ��פι�ư�ϡ�����ʤ���ѡ�(44��3%)���Ǥ�⤯�������ǡ������ںڤʤɡ�Ĵ����ɬ�פ��ʤ���Τ�¿��������(29��5%)���֥��å���ڡ����åȥե롼�Ĥʤɤ���ѡ�(28��4%)�ʤɤȤʤä���
��3��ָ��μ���¿���Τϡ��ְ����ָ���15��2%���ּ���ָ��ڤӡ������ָ���13��6%���ָֹ���11��5%�ʤɤȤʤäƤ��롣
�������������ʤ��������Ȥ��˹��ʤ��ɤ�����ֵ��ˤ�����׳���66��0%(������0��3�ݥ���ȸ�)������Ĵ�����鲣�Ф��ǿ�ܡ�Ĺ��Ū�ˤϸ��������Ȥʤꡢ�ֵ��ˤ�����פΤ�ǯ�夬�⤯�ʤ�ۤɳ�礬�⤤�����Ǥ��ä���
�����ܤξ���ο���͢���ˤĤ��Ƥιͤ���ʹ���ȡ����¤�����׳���81��2%�ȹ⤤���¤�����Ȥ�����ͳ�ϡֵ�����ư�伫���ҳ���͢�й�ˤ����뿩�������˱ƶ���Ϳ����ɬ�פ�͢���̤���ݤǤ��ʤ��ʤ��ǰ�����뤫���(32��7%)����¿�Ȥʤä���
��¾��������ʪ���������Ķ�����θ��������ʪ���ɤ�����ֵ��ˤ����Ƥ���פȤ������42��1%�ǡ��Ķ�����θ������ˡ���������줿����ʪ�Ȥ��Ƥ褯���������Τϡ��ϻ��Ͼä�����ʪ��(51��0%)���Ǥ�⤯�ʤä����Ķ�����θ������ˡ���������줿����ʪ��������ͳ�ϡֿ��٤�ͤη���θ���Ƥ��뤫���(64��3%)���Ǥ�⤫�ä���
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
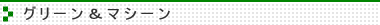 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�ӵ�Ÿ��10��5��6���˵ܾ븩�д��Ԥdz��š��Ӷȵ��������� |
|
| |
|
|
| |
�����̼���ˡ���Ӷȵ���������(�����ٽ���Ĺ)�ϡ���ǯ�Ρֿ��ӡ��Ӷȡ��Ķ�����Ÿ���±��פ�10��5��6��ξ�����ܾ븩�д��Ԥ����������(�д�����)�������϶�dz��Ť��뤳�Ȥ�ۡ���ڡ������ȯɽ����������ϡ֤ߤ䤮2025��48���������ספγ��ŵ�ǰ�Ի��Ȥ��Ƶܾ븩�Ȥζ��Ťdz������������Υ����������ȯ�����ɤ����ǿ��ε����䳤������͢����������������ǽ�Ӷȵ���������������ʧ�������Ӿ���������ʤʤ����������ʤ����Ȥߡ������ӥ��ԡ��뤹�롣����13�������Ÿ�Ԥ��罸�Ϥ��Ƥ��ꡢ��Ÿ�������ߴ��¤�4��11���ޤǡ�
���ֿ��ӡ��Ӷȡ��Ķ�����Ÿ���±��פϡ�����ͣ�줫�ĺ��絬�Ϥ��Ӷȵ���������Ÿ����Ȥ�������˹����Τ��Ƥ��ꡢ�������פε�ǰ�Ի��Ȥ��ƹԤ����緿���٥�ȤȤ������夷�Ƥ��롣
���ϡ��٥������ץ����å����ե�����Ȥ��ä�����ǽ�Ӷȵ�����Ϥ��ᡢ�������������ȼ֡��ں��˺յ����ɸ�����إ��åȤʤɤΰ������ʤ�Ÿ�����±餷��������ħ����ǽ�ԡ��뤹���ȤʤäƤ��롣
�����ӡ��Ӷȡ��Ķ���������ڤȤ��ΰ������Ѥ�¥�ʤ���Ū��1981ǯ���鳫�Ť��Ƥ��ꡢ��ǯ��10��20��21��ξ����ʡ�温�����ԤΥ���������ྡ���dz��š�80�δ�ȡ����Τ���Ÿ����1��9000�ͤ���졣�ǿ������Ÿ�����±顢����θ���ǥ�ȥ졼�����ʤɤ�̥λ������
�����Ǥ�̵�ͺ�ȼ֤�ŵ��α�������ƥࡢ�ɥ�����Ȥ��ä����줫����ӶȤ˷礫���ʤ����ޡ����ӶȤ����ʤ����Ȥߤ�Ҳ𤹤�֡�������Ω�����Х饨�ƥ����٤������ü���Ӷȵ�������Ʋ�˲����ޤ���������ǯ��¤�Ӵ�Ϣ������Ÿ���������Ƥ��Ƥ��ꡢ¤�Ӻ�Ȥ��ò�����¿��Ū¤�ӵ���ޥ���㡼�ʤɤ��¤����
����ǯ��10��˵ܾ븩�д��Ԥdz��š����Ų��������������˷�ޤä����Ȥ����Ӷȵ���������Ǥϡ���Ÿ��Ȥ��罸�Ϥ�����
����Ÿ���פ�Ʊ����ۡ���ڡ���https://www.rinkikyo.or.jp/news/view/173�˥��åפ��Ƥ��롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
5563���ߤ�4������5ǯ�ӶȻ��г� |
|
| |
|
|
| |
�����ӿ建����ô�˼��������2��28��������5ǯ�ӶȻ��гۤ�ޤȤᡢ��ɽ������
������ˤ��ȡ�ʿ��25ǯ�ʹ����÷����ǿ�ܤ��Ƥ����ӶȻ��гۤϡ�����5ǯ���������Ǻ����β��ʤ��㲼�������̤θ�����������ǯ�����229��7000���߸�������5562��5000���ߤȤʤä�����ǯ��Ǥߤ�ȡ�96��0%������������
�����гۤ������ϡ��ں�����3257����(������58��6%������ǯ��90��4%)�����ݤ��Τ�������2199��2000����(Ʊ39��5%��Ʊ106��4%)����ú����71��9000����(Ʊ1��3%��Ʊ112��5%)����������ʪ�μ�34��5000����(Ʊ0��6%��Ʊ59��9%)�Ȥʤä���
���ں������λ��гۤϡ�ʿ��25ǯ�ʹߡ����߽����幩�Ϳ�����Ĵ�˿�ܤ������Ȥ䡢���ؤδ�������͢���̤����ä������ȡ�������ǽ���ͥ륮����FIT��������Ƴ����ȼ�ä��ڼ��Х����ޥ�ȯ�Ť����Ѥ���dz���ѥ��å��Ǻ�������̤����ä������Ȥʤɤˤ�����÷����ǿ�ܤ��Ƥ�����
������������5ǯ���ں������ϡ���ǯ�����348���߸������������ӿ建�ʤǤϡ�dz�����å��Ǻ�������̵ڤӴ���͢���̤����ä����������߽����幩�Ϳ��θ����ˤ�ꡢ�������Ǻ�β��ʤ��㲼�������̤θ����ʤɤ��ƶ���������ʬ�Ϥ��Ƥ��롣
���������Ǻ���������ǯ��15��2%�����礭�����ष����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
��ư���Ρ��֥졼�ɤʤɿ����ʤ�2����ȯɽ����Ʊ���� |
|
| |
|
|
| |
����Ʊ����(��)(��Ԣ��Ϻ��Ĺ����긩�ִ��Լ����410)�Ϥ��Τۤɡ������ʤΡ���ư���Ρ��֥졼��e��SB81�פ���ӡ֥���С�����ȯ�ŵ�WG3000is�פ�ȯɽ������ȯ�䳫�ϤϤ������6��ǡ�4��1������ͽ��μ��դ�Ϥ�롣����������ñ��������פν��㵡�ǡ��鿴�ԤǤ⥹���å��������μ�������Ȥ�ʤ���롣�嵡�����ӵ���149Ω��������ζ���4�������륨����ܤ�ȯ�ŵ������̡�����ѥ��Ȥ�����������ŵ����פ˱����롣
����ư���Ρ��֥졼�ɡ�e��SB81�פϡ�Ʊ�Ҽ缴���ʤǤ�����㵡�κǷ��̵����ư�μ�ڤ�(�Ÿ��ϥ����å�1�ġ���®����®�ڤ��ؤ���������ڤ��ؤ��Ȥ�˥����å�1�ġ�®�٤ϥ�С��ΰ���ø��Ǵ�ñĴ��)������ʤ��顢30�����������ޤ��б��Ǥ��롣�ե뽼�Ť���60ʬ��Ư�������δ֤���֥��ڡ���36��ʬ(�����������10������ξ���)�ν����Ȥʤ�ǽ�Ϥ���äƤ��롣
��������פǡ��鿴�ԤǤⵤ�ڤ˥����å�����˻Ȥ����Ȥ��Ǥ����֥졼�ɤ����뤿��˼Ф�˳����ѹ�����ǽ�ǡ���®�˽��㡦ƻ�Ť��꤬�ʤ���롣�ޤ���ξ�����ɤΥ֥졼�ɤϹ���ʤ��Ǵ�ñ����æ��������������ڤ��ؤ����饯�ˤǤ��롣����ˡ��Хåƥ(������।��������)�μ�곰���ϥ���������������Υ�å������μ�Ǽ�κݤϥϥ�ɥ����ǥ���ѥ��ȡ��ϥ�ɥ��2�ʳ��ǹ⤵Ĵ���Ǥ���ȼԤ˹�碌����ʤɡ���갷���ϴ�ñ��������������伫�����־���㤫���˽������롣
��Ʊ���μ�ʻ��ͤϼ����̤ꡣ
����������ˡ=��Ĺ1410������810������890�ߥꢦ��������=70�������ϥ�ɥ�⤵(2�ʳ�)=86/91�������������=810�ߥꢦƱ�⤵=330�ߥꢦ�������=540ʿ����ȥ�/�����Хåƥ=����2��4������ɸ���Ȼ�����60ʬ��ɸ�ོ�Ż�����8����(100�ܥ���Ÿ�)�����Ѳ����ϰ�-20��20��C
���������˾������ʤ��ǹ���28��3800�ߡ�ȯ�䳫�Ϥ�6��1���ǡ�4��1������ͽ�������դ��롣
������С�����ȯ�ŵ��ο����ʡ�WG3000is�פϡ���ʽ���3��0kVA�ʤ������ν��̤�24��5������������ˡ��Ĺ510����300�߹�480�ߥ�ȷ��̡�����ѥ��Ȥ˻ž夲���������������ͤǡ����ʤ�Ķ������ǧ�Ĥ�������Ƥ��롣;͵��18����ڥ��ʾ�ǡ����̲��Ť�¿����ƻȤ��롣�ޤ������ޡ��ȥե���䥿�֥�åȤʤɤ�ľ�ܽ��ŤǤ���USB���ťݡ��Ȥ��������ܥ���1�ĤǴ�ñ�˿��̤Ǥ��륭��ꥢ�ϥ�ɥ�(��������ϥ�ɥ��PCV�����㥹����)�ǡ���ư���饯�ˤǤ���ʤɤε�ǽ��ͭ���Ƥ��롣
��dz���������̤�5��0��åȥ롢Ϣ³���ѻ��֤Ϻ���7��0���֡���ž������ѥͥ�Υޥ�������������ɽ�����إܥ�������Ȥǡ��Ű����������������ȿ���缡ɽ���Ǥ��롣ɸ����°�ʤ�ľή�Хåƥ�����ѥ����ɡ��ץ饰�������ɥ饤�С������礦��������ȷ����Ϣ���ή=ñ��100�ܥ��(AC30����ڥ�)��ñ��100�ܥ��(AC20����ڥ�)��2��ľή(�Хåƥ����)=DC12�ܥ�Ȣ�USB=DC5�ܥ�ȡ�2��4����ڥ���2��
���������˾������ʤ��ǹ��ߤ�27��5000�ߡ�
��Ʊ�Ҥϡ�����λŻ��������ʤ��͡��ʥ�����dz����Ǥ�����ǽ����������äƤ���Ȥ������Τ˰��ߤ��Ƥ��롣ȯ�䳫�Ϥ�6��23����ͽ����դ�4��1�����顣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Ȳ�μ�ξ�֥ץ�ƥ���ʡ����ܥ����ƥ२�˥���� |
|
| |
|
|
| |
�����ܥ����ƥ२�˥����(��)(�����ɻ���Ĺ��ʡ�����������ķ�Į����5��2��25)��1��顢�����ʡ��ӶȺ����Ȳ�μ�ξ�ץ�ƥ��פμ����б���ʤ�Ƥ��롣Ʊ���ϡ��������Ϥ���ΰ���������ȯ������Τǡ��������ݤ줫���äƤ����ڤ����ǽ����������֡�������8�ȥ�ʲ����淿�֤��Ѻܤ����饸�������ǰ����˴����ڤ���������Ȥ��Ǥ��롣
�������ﳲ�˵ڤ����긩���λ��л��ϡ��衹��Ⱦ�Фι߱��Ǥ褦�䤯���Фˤʤä��������ä���������ư�β����⳰���絬�ϻ��ӲкҤ����ͤ����Ƥ��뤬������ͽ�����֤Ȥ��Ƥ⡢�����ˤ�����(�����ꤽ����)���ڤ���դν����Ͽ�®�˹Ԥ��ʤ��ƤϤ����ʤ���
�������θ���ˡ������顢�ŵ��Υ饤�ե饤�������Ū�����߽Ф��줿�Τ��֥ץ�ƥ��ס��ޤꤿ���߳�Ǽ���Υ��������Ϲ⤵12��ȥ롢��ʿ9��ȥ���ϰϤǺ�ȤǤ�����ü�ˤ�Ʊ�ҳ�ȯ�Ρ֥ե��顼�Х���㥶���륹�פ����塢����åץ��ȡ�Ȳ�ݺ�Ȥʤ�1��5���Ư����̤����������ɻߤΰ�̣��ޤᡢ����Υ�줿���֤���饸����ǹԤ�����ξ�ˤϥ����ȥꥬ��(4��)����������Ȥΰ��������ݤġ�
������Ϲ���ȼ֤�Ȥä���������ȤǴ��������⤫�ä�����Ʊ���Υ����ƥ�ˤ��������ϳ��ʤ˸��塣����˥��ץ�����Ω�α��������ƥ�֥ƥ���Υ��饹�פ��Ѥ����Ͼ夫��α�����ǡ����ذ�������ݤǤ��롣
���ޤ�����Ǽ�����ˤ���Х����å����Ȥ�æ��ʤ������ԤǤ�����Ψ�褯��Ȥ�ʤ���������⤢�롣
�����ܼ�Ĺ�ϡ��ۤ������ϲ�Ҥ�����䤤��碌����Ƥ���Ȥ��ʤ��顢�ͼ�ǹԤäƤ�����Ȥ�Ʊ����ü���Ǽ�Ԥ���褦�˳�ȯ���Ѥ߽ŤͤƤ����С���������ӤϹ������Ÿ˾������μ��׳���˴��Ԥ�����Ƥ��롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�������ޥ���㡼��1���Ȳ�Τ�ʴ�ա��������� |
|
| |
|
|
| |
����������(��)(��ˬ��������Ĺ���Ų��������Ĺ��155��8)�����Ϥ�������ߤΥ��ƥʥ�Ȥ˺�Ŭ����ڤ�ޤäƤ����������ޥ���㡼��MVM��1000�פϡ�5��10�ȥ饹�ΥХå��ۡ���Ŭ�礹���ڡ��ݡ����ʴ�ա����赡��Ω�ھ��֤Ǥ�ʴ�դ���ǽ�ʤ��ᡢȲ�Τ�ʴ�դ�1��ε����Ǵ���Ǥ���������ɸ��ϤǤ��줾����б������ѿϤ˸����֤��פ餺��ȸ�Ψ����夵���롣
�����̤�400������Ʊ���饹����ǤϷ��̤ǡ��ں�����1000�ߥ�ȹ������ᡢ���ꤷ����Ȥȸ�ΨŪ�ʺ�Ȥ�ξΩ���ޤ��������ɻߥ��С��ˤ�ꡢ����ʪ�ˤ����Τ������㸺�����뤳�Ȥ��Ǥ��롣
���Ϥˤϡ��ں﹩��ˤ���Ѥ���Ƥ��륿���ƥ�ݤ���Ѥ��Ƥ��ꡢ���˹⤤�ѵ����������Ĺ���֤λ��Ѥ��Ѥ��롣���ѴĶ��ˤ��뤬���ܰ¤Ȥ��Ƽ�̿����1ǯ�ۤɡ�����ˡ��Ϥϥܥ�ȤǸ��ꤵ��Ƥ��뤿�ᡢ��������»���Ƥ⡢ϻ�ѥ�����Ŵ�ѥ��פ�Ȥäƴ�ñ�˸��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
��Ʊ���Τ���¾�λ��ͤϼ����̤ꡣ
����������ˡ=W694��D1290��H802�ߥꢦΩ������ľ��=120�ߥꢦ���Ѱ����ϰ�=160��180bar����Ŭ����=180bar������ή���ϰϡ�60��70��åȥ�/ʬ����Ŭή��=70��åȥ�/ʬ
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���ޥ���ġ���ȯ�䡿�����ۡ���ǥ�������ѥ� |
|
| |
|
|
| |
�������ۡ���ǥ�������ѥ�(��)(������ɧ��Ĺ������Թ������2��15��1)��2��28�����顢Ʊ�����ʽ�Ȥʤ륹�������å��ޥå����֥졼���б��Ρ�36V�����ɥ쥹�ޥ���ġ���CV36DMA�פ�ȯ��Ϥ�����Ʊ����36�ܥ�ȥ֥饷�쥹�⡼��������ܡ���٤��礭���ݺ�ʤɤǤ����Ǥ���ǽ�ǡ��֥졼�ɤο���Ѥ�4��0�٤˳��礷�����Ȥˤ������®�٤������ʸ����¸�������˥�С��������ǥ֥졼�ɤ���æ���Ԥ��빽¤�Ȥ����֥졼�ɸ��ưײ����������������å��֥졼�ɤ˲ä������������å��ץ饹���ʡ����������å��ޥå������ʤΥ֥졼�ɤ����Ѳ�ǽ�ˤʤä���
�����Τۤ���(1)2������LED�饤����ܤDz��˸������֥졼�ɤο���⸫�䤹��(2)��ư������ʬ6000��2������ϰϤǥ����������Ǥ���(3)�������ȳ�¦�Υϥ����å�������Τ�����餫���������魯�뤳�Ȥǿ�ư���㸺���ʤɤ���ħ�����롣
��������ˡ��Ĺ359�߹�130����88�ߥꡢ���̤�2��0���������Ż��֤���19ʬ(����)/��25ʬ(������)�����ӤϳƼ���������ǡ��ݥ��åȲù�����������������ʤɤ���Υ���ں�ʤɤθ���ʤɡ�
����˾������ʤ����̤�7��3800�ߡ�
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�ϥ�������ޤӤ������ܥåȤ�ͭ�������ԡ��롿����ѥ�եե��� |
|
| |
|
|
| |
�������������Υ���դκ�ŵ�Ȥ����른��ѥ�եե���2025��7��9��3���֡���������ͻԤΥѥ��ե������ͤdz����졢����եץ졼�䡼������վ�ط��Ԥʤ�¿�������Ԥ����襤��ߤ�����
���ȳ�����ϡ����������θ�Ψ�����ʿͲ����ܻؤ���Χ���Է��μǴ�����ϥ����С��ʡ����Υ�(��)(P���˥륽����ɽ������̸���ۻ�)�Ȥ�ޤӤ�����ѥ�(��)(���迭���Ĺ�����������)����Ÿ�����ؿ����
�����Ÿ�Υϥ����С��ʡ����Υ��ϡ������Υ磻��쥹���ܥåȼǴ�����CEORA546EPOS�פ�Ϥ���֥����ȥ⥢�ץ����ν�Ÿ�����ǡ������Ʊ�ҽ��Ƥλ�ߡ������ϥץ쥼��ơ�����ơ����Ȥ�������3��Ʊ�Ҥ����Ĺ�ƻ�����Ź�����դ��ϥ����С��ʡ����ܥåȼǴ�������ˡ��֥����ȥ⥢�פ�����������վ�γƥ��ꥢ��Ŭ���������ȥ⥢�������ƿ����ʤΡ������������Ѥ������ꥢ�磻��̵���Dz�Ư�����EPOS������פ���ħ������������
�����ꥢ��Ŭ���������ȥ⥢�ˤĤ��Ƥϡ�������ʿ��ʥ��ꥢ(�ե��������������ߥ�ա����)=CEORA(������㤤���åƥ��ǥå���°)�����ۤΤ���ʣ���ʥ��ꥢ(�ե��������������ߥ�ա���դʤ�)=Ʊ550EPOS��550�����ۤθ��������ꥢ(���ߥ�ա���դʤ�)=535AWD���줾��侩��EPOS������˴ؤ��Ƥϡ��������桢�����ȥ⥢��������������ե�����ơ��������Ȥ߹�碌�뤳�ȤǸ����鷺��������������٤Dz�Ư�Ǥ����������ȥ������ƥ�������θ�����߷ס������ǽ�ʥ��åƥ��ѥ�����ʤɤΥ��åȤ�����Ȥ��ơ��������ڳ���˴��Ԥ��������
����ޤӤ�����ѥ�ϡ��֥��ܥåȤ����塦��������������롡�ͼ����к������ϲ��к��������Ⱥ︺�˹����ޤ��פ�Ǥ����֥��������ܥƥ������饤��ʥåספ�(1)���ܥåȼǴ���RTK��ǥ�(2)Ʊ���嵡RTK��ǥ�ԡ��롣
��(1)�Ǥϡ�����������ɥ�ǥ�κ��������Ѥ�1��2000��2��4000ʿ����ȥ�ʤΤ��Ф���RTK��ǥ��TM��1050��4��5000ʿ����ȥ롢Ʊ2050��7��5000ʿ����ȥ롢�ޤ���(2)�ϥ���������ɥ�ǥ�RP��1200��3��ʿ����ȥ�ʤΤ����RTK��ǥ��RP��1250��4��5000ʿ����ȥ�ȳ��ʤ˥��åס�RTK��ǥ�Ǥϡ�����Υ��������Ԥ���ľ��Ū�ʥѥ�����Ǥ����Ԥ�¸���
������˥��ޥۤ䥿�֥�åȤ�Ȥ�WEB�����ƥ�ˤ�ꡢ���롦���Ťʤɤλؼ����������γ�ǧ�����顼���μ����ʤɡ������������夷�Ƥ��뤳�ȤĴ������
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�����������������٥륳������4��1��������ͻ� |
|
| |
|
|
| |
�����٥륳����(��)(��������Ĺ�������������������5��15�����֥饤�ȥ���5F)�ϡ�4�����Ťμ������ǡ�4��1��������ͻ�����ꤷ����Ǥ��������ˤ����о��(��������Ĺ)����Ǥ��������Ǥ���뼹������ϸ�����������ΰ�Ϻ��ξ�ᡣ��Ǥ�塢�����ϼ�����(6����ͽ��Ǹ���)��������(��)�������ݽ�μ�������Ȥʤ롣
����Ǥ��������������1969ǯ8�����ޤ졢55�С�1992ǯ3���������ؾ�������´�ȸ塢2004ǯ��Ʊ�Ҥ����ҡ��ޡ����ƥ����������Ķȴ����Ĺ����������Ĺ�ʤɤ�Фƺ�������˽�Ǥ���롣�Ѿ���̳�ϴ�������Ĺ�ڤӥ������Х�IT�����ƥ���ô����4��1���դμ�������������ȿ������Ѿ���̳���Ƥϼ����̤ꡣ
���������������ʿ������=���������������������ƺ�����ˡ̳������̳�ͻ���(���������Ķ��ɺҥ��롼����)�������������������������̳����ô����������������о�=������Ʊ���������=���졼����Ȥ����硢�ޡ����ƥ����������ι������ô���ڤ�Ʊ�����������졼��Ķ�����Ĺ��Ʊ�����ĵ���=���ե��������륹����Ĺ�ڤ��������������������Ķ��ɺҤ�ô��
������ε�ƣ������ʡ���ٹ���ξ���3��31����Ǥ
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
4����5�ټ������ˡ����Υ˥å���4��1�����ȿ����ԡ�������� |
|
| |
|
|
| |
��(��)���Υ˥å���(ƣ����Ϻ��Ĺ������Թ����쿷��1��9��1)��3����4��1���դ��ȿ������¤Ӥ�����������ɽ�������ȿ����ԤˤĤ��Ƥϡ��ղò��ͤ��ϽФ�������������̤�����³Ū����Ĺ��¸����뤿��˹Ԥ��Ȥ������Ԥ�6����(29��)4�ټ���������4����(18��)5�ټ������Ȥʤ롣�ޤ����ټҤϼ�Ĺľ���ȿ����Ѥ�ꡢ�ܼ��ȿ��ϵ�ǽ���ˤ����Ԥ�Ԥ���
���ټҤ������ܡ����졢�����������ܵڤӳ�����5�ټҡ�
����������ϼ����̤ꡣ
��(���å���ϸ�������̾�ɾ�ά)
������ɽ�������Ĺ=ƣ����Ϻ(��ɽ�������Ĺ)
�����������̳��������Ķȡ���ȯô��=���ְ�Ϻ(�������̳��������Ķ�����Ĺ)��Ʊ��̳����Ĺ=������Ϻ(Ʊ���ѡ������ӥ�����Ĺ)��Ʊ�бĴ��ô��=������Ϻ(Ʊ�бĴ��ô��)��Ʊ��������Ĺ=������Ϻ(Ʊ��������Ĺ)
����������=������ŵ(������)����������(������)
������дƺ���=��İ��(��дƺ���)���ƺ���=�һ���Ϻ(�ƺ���)
������̳�������(��)N��LOGI�ѡ��ȥʡ�����ɽ�������Ĺ=������Ϻ(��̳�������(��)N��LOGI�ѡ��ȥʡ�����ɽ�������Ĺ)��Ʊ�ټ����缼Ĺ=����Ϻ(Ʊ����ټ�Ĺ(��)����ټҴ�����Ĺ)
�������������������������Ĺ(��)�ꥹ���ޥͥ�������Ĺ=�ɿͼ�(���������������������Ĺ(��)�ꥹ���ޥͥ�������Ĺ)��Ʊ�ټ����缼��=������Ϻ(Ʊ�Ķ�����������Ĺ)��Ʊ��������������Ĺ(��)�ͻ���Ĺ(��)�����̥���Ĺ=��Ǯ��Ϻ(Ʊ��������������Ĺ(��)�ͻ���Ĺ(��)�����̥���Ĺ)��Ʊ��������������Ĺ=�˰���(Ʊ��������������Ĺ)��Ʊ�ټ����缼��=����Ϻ(ƱEX��Ĺ(��)�ץ�����Ĺ)��Ʊ��̳����������Ĺ(��)�����ӥ��ٱ���Ĺ=����Ϻ(Ʊ�����ӥ�������Ĺ)��Ʊ�����ܻټ�Ĺ=�����Ϻ(Ʊ�����ܻټ�Ĺ(��)�����ܻټҾ��ʴ�����Ĺ(��)�����ܻټҴ�����Ĺ(��)BPR��ʼ�����Ĺ)��Ʊ��̳����������Ĺ(��)������Ĺ=������Ϻ(Ʊ��������Ĺ(��)Ĵã��Ĺ)
���Ұʲ��Ͽ�Ǥ�����
����������������ټ�Ĺ=ʿ��Ϻ(�����ټ�Ĺ(��)�����ټұĶ���Ĺ(��)BPR��ʼ�����Ĺ)��Ʊ����ټ�Ĺ=�����(�ǡ����бĿ�ʼ�Ĺ)��Ʊ��ȯ����Ĺ=����(Ŵƻ��Ĺ(��)������Ŵƻ��ŹĹ(��)������Ŵƻ�Ķ���Ĺ(��)���ѳ�ȯ��Ĺ)��Ʊ��������Ĺ=����Ϻ(��������Ĺ(��)����������Ĺ)��Ʊ�ǥ�������ά����Ĺ=������Ϻ(�ǥ�������ά����Ĺ)��Ʊ�����ټ�Ĺ(��)����������ȯ��Ĺ=�����Ϻ(��������Ĺ(��)����������ȯ��Ĺ)
������Ǥ������Ϻ��������Ϻ��ŷƻ��Ϻ
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
��11�����濹�ϴ��ν����Ʒ6����������2025�Ӷȵ�����9�� |
|
| |
|
|
| |
������������(��������ɽ��������Ĺ)��10�����ָ�����������⿹�Ӻ������ס��̾Ρ����濹��(���¤���)���פ���11������Ʒ�Ȥ���6�����ꤷ��ȯɽ����ȤȤ�ˡ�2025ǯ�٤μ���ȤߤȤʤ���12��������Ȥ��罸��4��1�����鳫�Ϥ��뤳�Ȥ����餫�ˤ�����16��α�����椫�����Ф줿6�Ʒ�ˤϡ����1��4000���ߤ�������롣���줾�줬�ϰ�������Ƥ�����ͭ�β���ʤɤβ����ܻؤ��ȤȤ�ˡ����ȼ»������������ʤɤˤ����Ȥࡣ
��������⤬�ʤ������濹�ϴ��פϺ�����ο��ӻܶȤβ���Ǥ���ֻܶȽ��פ���½д�Ȳ���פμ���Ȥߤ˲ä������Ӥζ������Ѥ���ʪ¿���������˴ؤ�����Ȥʤɤ�����Ǥ���褦�Ƚ�������
������η���Ʒ�ϡ����л�����β�������Ʊ�ܶ����ϲ��ˤ��ϩ�������Ƚ۴ķ����ӻܶȤι��ۡ����ӥ����ӥ����Ȥˤ�뿹�ӷбĥ�ǥ�ι��ۡ����ޡ����ӶȤ���Ѥ����ޥ��Ӥ������ȳ��ѥ�ǥ�ʤɡ��ϰ褬�����������褷�Ƥ����ơ��ޤȤʤäƤ��롣������⡢�����̱ͭ�Ӥθ�������ȯ�������뤳�Ȥ��ܻؤ�����ư�ȤʤäƤ��롣
��16��α�����椫����줿6�Ʒ�μ»ܻ���̾�Ƚ����о���ϡ�ȯɽ��Ǽ����̤�ȤʤäƤ��롣
�������ۻԽ��ջ����л������Ķ�����ץ���������=�������������ȹ�(������)
������Ʊ�ܶ����ϲ��ˤ��ϩ�������Ƚ۴ķ����ӻܶȤι���(3ǯ�ֻ���)=�б����⿹���ȹ�(������)
��������̤�����϶�ˤ��������̱ͭ�ӡ��������ܥ�����������=�̤ʤ�����ȹ�(���㸩)
��������Ʒ����ܶȤȤ������ӥ����ӥ����ȡפˤ�뿹�ӷбĤΥ�ǥ빽�ۻ���=����α�����ȹ�(������)
����������ε����ӶȤ��˹��ۤ��롽�����å��ൡ�γ��ѡ�=���̼���ˡ�����¿��Ӵ�������(���ɸ�)
�������ɴֽ���Υ�奦���奦�ޥ����������Ѥ��ܻؤ������ޡ����ӶȤ���Ѥ����ޥ��Ӥ������ȳ��ѥ�ǥ���ȡ�(2ǯ�ֻ���)=���츩�����ȹ�Ϣ���(���츩)
�����Τ��������ɸ������¿��Ӵ�������μ���ȤߤǤϡ����ɸ�ģ��Ƴ�������������Υ����å��ൡ����Ѥ��ơ������ӶȤ�Ŭ������������ˡ��Ƴ������ȤȤ�ˡ�ô����ΰ������ϰ�ؤ���ڤ��̤��ƿ����ʵ����ӶȤι��ۤ��ܻؤ���
���ޤ������츩�����ȹ�Ϣ���2ǯ�֤λ��ȤȤ��Ƽ���Ȥ�֥��ޡ����ӶȤ���Ѥ����ޥ��Ӥ������ȳ��ѥ�ǥ���ȡפǤϡ��ˡ����ι⤤��奦���奦�ޥĤˤĤ��ơ�Υ�礫��Ȳ�Ρ��½С����䤹�륹������γ�Ω��ޤ�ȤȤ�ˡ��ޥ��Ӥ������ȳ��ѤȤ�ξΩ�������ǥ�ι��ۤ��ܻؤ���
���������νб����⿹���ȹ礬�ʤ��3ǯ�ֻ��ȤǤϡ��Ԥ��ʵ������������뻳�Ӥ�Ʊ�ܶ����ϲ����뤳�Ȥǡ�����ΨŪ��ϩ�����֤ηײ����������緿�ȥ�å����̹Բ�ǽ���Ӷ�����ƻ(��������)���������ϰ����Τ��½д�Ȳ�ʤɤ�¥�ʤ�ޤäƤ�����
���ޤ�����������ʻ����2025ǯ�٤�Ʊ����罸���ޤȤᡢ4��1������6��30���ޤǤ�»ܴ��֤Ȥ��Ʊ���Ϥ��롣��ǯ��2��˿�����̤�ȯɽ���Ԥ��롣
������ϡ���������տ�������������ȹ�Ϣ�������ᤷ��ɬ����ܤξ塢ƱϢ������Ф��롣
���䤤��碌�ϡ��������ȹ�Ϣ����ȿ���������(TEL03��6700��4735)�⤷�������濮�����(��)�Ķȿ����(TEL03��5281��1420)�ޤǡ�
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
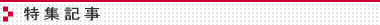 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�緿�������ޡ��Ȳ�����Ÿ�����졦�����ý� |
|
| |
|
|
| |
�����츩�������Ծ���絬�����Ȥ�����ȹ礬���줾��ǹ�ʻ����ư�������ꡢ�������緿�������դ��μ�ư�������֡��ɥ�����Ȥ��ä������β�ư������ȯ�ȤʤäƤ��롣�����ܤ������ε�ð��Ԥ��濴���絬�����Ȥˤ��������ʤ���������ԻԤΰ���Ǥ�1Į̤�������Ȥ����ߤ��롣24ǯ�٤��Ʋ���ƭ�����Ȥ����ޥ���ɤ��ޤ�ĤĤ��ä����������ְ찮����絬�����ȤˤȤäƤϡפȤ�������¿��������Ū����夲�����ʤ������Τ褦���طʤ��顢�����Ծ�ˤ�����ƼҤαĶȳ�ư�������̤ˤ��롣�ط��ƼҤ��ष����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
����ƼҤ��б����絬�Ϥ����˥��ԡ��롿���졦�����ý� |
|
| |
|
|
| |
��(��)��Φ�ᵦ���ܥ�(�����ϼ�Ĺ)�ϡ�2024ǯ1��12���������������ˤĤ��ơ����絡���⤹�굡���������̵��Ȥ��ä�����Ϣ�������夲����Ĺ������24ǯ���Ʋ���ƭ��ȼ�����Ŀ����Ȥ�����Ԥ��Ƥ�ľ�����䤹�륱�������������Ƥ��ʼ�����Ż뤹��褦�ˤʤä������Τ������Ҥε���Τʤ��Ǥ�����̵��β�ư������Ω�ä���
���ȥ饯��������Х����Ŀ����ˤĤ��Ƥ�23ǯ�٤���٤Ƥ��줾������١����Ǿ������������������絬��ô����������緿�β�ư������ȯ��������ۥ١����Ǥ����Ȥʤä�������Ķ����ξ���ʸ����Ĺ�ϡ��ϰ�ˤ��뤬�����塢�礭�ʱ����ȹ���絬��ô����˺�Ȥ����������㤬������Ȼפ������Τ褦��ô����ˤ��ä���ȥ��ץ������������פ��Ϥ����롣���ߡ��ȥ饯����60���ϡ��Ŀ�����8��������Х����4��6�Ȥ��ä����饹��������μ�ή�ȤʤäƤ��롣
���絬��ô���꤬�������������������뤹��Τ���������������Ϣ�ξ�������ô��������뤫���������ĶȤ��פȤʤ롣¾���αĶ�����Ʊ����������Ķ������ܼҤΥ���塼�����������Ϣ�Ȥ��ƺǿ��ξ�������ꤷ��ô����Ȥο�®�ʾ���ͭ��ޤäƤ��롣
���ޤ���24ǯ�ˤ�RTK���϶ɤ��������̡����졢����ò��5�ĤαĶȽ�˳��ߡ�����ˤ��Ƴ�����ʤ�GS��(ľ�ʥ������ȵ�ǽ���)����������ܡ��ɥ��������̩��Ȥ�¸����Ƥ��롣
���������֥��å�ô���ι��ݹ�����Ĺ�ϡ֤��줫����϶ɳ��ߤθ��̤��Ф�Ȼפ������Τʰ��֤��ݤä����ۺ�Ȥ���ư���ɤDz�ǽ�ʤ��ᡢ���ϥɥ�����η��ʤ�Ǥ���פȼ�������ä�����������֥��å�ô���λ���ͳϯ��Ĺ�ϡִ��϶ɤ�����ơ��ȥ饯����GS���ͤο����ʤ�ޤ��REXIA(�쥯������60��105����)�٤⤷�ä�����Ƥ������פ��ä���
����ǯ�ϥȥ饯����SL600(60����)�ڤ��Ŀ�����NW80S��PF(8��)�פ˸��դ��μ�ư�������֤��դ������츩�Υ��ڥ���뵡�Ȥ��ƳƱĶȽ�Ǽ±餷�Ƥ������ޤ�����ǯ��8ǯ�ܤȤʤ뻰�̰��γ�ư(���ܥ������ܥ������ꥵ���ӥ�����Φ�ᵦ���ܥ��Ȥ�Ϣ��)���̤��������ؤΥ��ޡ��������ο�ʤ����Ϥ��Ƥ�����
�����ޡ������ꥸ��ѥ�(��)�����ᵦ�ټ�(����ͭ�ټ�Ĺ)�μ������ϡ�����������ˤĤ���23ǯ4��9��(���)�ޤǤ϶������줿��������Ʊǯ8�������Ƥ��ϰ褫����Ƥ������ʤ��夬��ΤǤϡפȤ�����ʹ����������ä��絬�����Ȥι�����ߤϹ�ޤ�ĤĤ��ä�������ή���10�����������������Ϲ�ž��ư����ߤ���12��ˤ�����夤����
�����츩�����礹��ᵦ�Ķ����ε����Ұ���Ĺ�ϡ��Ʋ��ξ徺�������������������ߤ˲Ф�Ĥ��뤫���狼�롣���������Ƥ����ʤϾ夬��ɡ����������˻��ʤ����Ȥ���������ä����Τ���¡פȸ������������ä���
�����Τ褦�ʾ����Τ�ȡ�24ǯ4��12��ˤ��������3����β�ư���Ϸײ�ˤϻ��ʤ��ä����������ȥ饯����25ǯ3��ޤǤ��̴��Ǥߤ�ȡ�24ǯ�¤ߤ������֤��ȸ����ࡣ�ȥ饯����50��60���ϡ��Ŀ�����6��8��������Х����4�ʾ�Ȥ��ä��Ȥ���������μ�ή�ȤʤäƤ��롣
�����줫���3��1����ȯ�䤷��������ܤΥ饸��������YW500RC'AE�פγ��Τˤ����Ϥ��롣23ǯ��ȯ��Ρ�YW500RC�פĴ�ʲ�ư����ߤ���ʤ���������ܤο����ʤ����������饨����ư�Ǥ����ޤ���ï�⤬���䤹�����Ǥ��ꡢ���ܤ�Ƥ��롣������Ĺ�ϡ֤����ͤ����ɾ�����ɤ��פ��Ϥ����롣�ޤ��������Фʤ��ȹ�ɾ�Υǥ��������������YDP802(Ŭ�����ϡ�50��120)�פμ±��Web�Ǽ����դ��Ƥ��ꡢ����γ��Τˤ����Ϥ��Ƥ��롣
�����٥�Ȥ�2��14��15���˸���(��Ṿ��)��21��22���˸���(���Ż�)�ȸ���(�黳��)��3��Ź�ˤ�Ÿ����š�³����3��7��8���ˤϸ���(Ĺ�ͻ�)��Ĺ��(Ʊ)��Ź�ˤ�Ÿ����Ť�����Ÿ����Ǥ�4�������ʲ��ʲ���ι��Τ�ޤ�ơ��ϰ��Ŭ�����ȥ饯����YT������ڤ��Ŀ����ˡ���������������ɤ굡���夫�������żﵡ�Ȥ��ä��վ��ʤ���Ƥ�̴��˹Ԥä���
��(��)ISEKI��Japan��������������ѥˡ�(�����Ĺ)�ǤϺ�ǯ��������Ǿ����浬�Ϥ�������Υ�����ʤ�ʤ����Ʋ���ƭ�Ȥ�������⤳������Ȥˤ϶�������������ǯ�Ȥʤä���
���Ʋ���ƭ�����������������������ʤ��������ι�ƭ��³�������Ȥ⤢�ꡢ���Ʋ����夬�ä��Ȥ����ǡġפȤ�������¿�������Τ褦�ʾ����Τ�ȡ�24ǯ1��12�������ˤĤ��Ƥϡ�23ǯ��Ʊ��������٤ƥȥ饯������ǯ�¤ߡ��Ŀ����ȥ���Х���ϸ��Ȥʤä�(����١���)��
�����������츩ȯ�Ρ֤ߤ������ߡפ�֤���ߤ����פȤ��ä��ʼ�δ���������������Խ��8����ܤ����ݤ��ˤʤ�ʤ�������ӥ��դ��Υ���Х���Ÿ�������ǯ��5������ư���⤢�ä����ޤ����Ŀ����֤��ʤ�PRJ8(8��)�פ������夬��ǹ�Ĵ�����Ԥ���ߤ��Ƥ��롣
������Х����������HFR�������4042(4��/42��1����)��4050(4��/50��3����)����ɾ����Ƥ��ꡢ����³����ʤ��Ƥ���������Ķ������ܳ��Һ���Ĺ�ϡ֤���饳��Х���ˤ�Ω�ΤΥ���֥��Ȥ��ä������ʤ��դ��Ƥޤ�����������ץ뤫�ĥ���ѥ��ȤǴ������������¤��Ƥ��롣�浬�Ϥα����ȹ�Ȥ��ä��ؤ˲����̤ǤΥˡ����˹��פ��Ƥ���ΤǤϡפȴ��Ԥ��롣
���絬��ô����ؤ��б��ˤĤ��Ƥϡ����������֤���Ʊ�Ҥ��絬�ϴ�輼�ˤơ�����ơ��絬�����ȤȤϡפ�������ơ���������ƤϤޤ����Ȥ�������������Ƴ�ư��Ԥ����ޤ�����˾��¿���ȥ饯��������Х����Ŀ�������ŵ����Ծ�˽в�餺�����䤬���ʤ�����������¾���αĶȽ�Ⱦ���ͭ�ʤ����б����Ƥ�����������
�����٥�Ȥ�2��14���ˡ֥����ꥸ��ѥ�ե�����in����פ�ɧ������ǡ�3��7��8���ˤϡֽդ���Ÿ����פ�Ʊ�Ҥ�ε������(���츩������)�ˤƳ��š��ȥ饯����BF������פ�ե��ǥ���������֥���������ܡ�IGAM2�ס����ռ�ư�������֡�CHCNAV�ס��֥饸���ѥ������⥢�פʤɤ�PR������
�������ư���ˤĤ��ơֿ��ߤ��絬�ϴ�輼���̤��ƥ�����Ȥ��Ƥ�¸�ߴ����˥��ԡ���Ǥ��뤫���������ΤȤʤ롣����³�����ϲ��ȹ��Ψ�ˤĤʤ�����Ƥ���ƻ�˹Ԥ������פ��ܳ���Ĺ���Ϥ����롣
�����컰ɩ��������(��)(ʡ�ʾ�ͳ��Ĺ)�ϡ�24ǯ��(1��12��)����������ˤĤ��ơ�23ǯ�٤���٤ƥȥ饯���ڤӥ���Х�����������Ŀ��������Ȥʤä�(��ۥ١���)�����������Ѥδ������ʤ��ɽ�����192%������������饸�������ʤɡ����Ϣ������155%�ȡ����줾���ۥ١�������夲����Ĺ������
����ǯ���Ʋ���ƭ�αƶ��⤢�ꡢ������θܵҤ��������ޥ���ɤ�夬�ä�������������Ʊ�Ҥȼ��츩��ɩ��������ǯ10��˳��Ť��빱�㥤�٥�ȡּ����������ɥե�2024�פǤ���ǯ�ʾ�����襤��ߤ������٥�Ȥ���夲��23ǯ����ä������������Τۤ���Ʀ�����������絬�����ȤˤȤäƤϡ�10��12��ˤ����Ƽ��Ϥ�������Ʀ������Ȥʤꡢ�Ʋ���ƭ��������Ǵ�٤ʤ������ˤ�ʤä���
������3����ˤ����뺣ǯ�٤�����θ��̤��ˤĤ���ʡ�ʼ�Ĺ�ϡ�24ǯ����Ӥ��ƾ����������ʤꤽ�������Ҵ���Ǥ����Ͻ��Ѥ�ư�����ߤޤä��褦�˻פ�����������Υ�����ɤ�ɤ�ʤ�����Τ�ȡ��絬�����Ȥ佸������ι�ʻ���Ƥӿʤफ�⤷��ʤ��פ��ä���
������ޤ����ߤ��Ƥ�������(�ܵ�)���絬�����Ȥ˵ۼ�����뤳�Ȥǡ�������Ȥ˹��פ�����������ϲ���ľ�뤹����������ơ����Ҥʥ��ե��������ӥ�������ޤǰʾ���ᤵ���褦�ˤʤ롣ʡ�ʼ�Ĺ�ϡ֤��Τ褦����Ƥȥ����ӥ����궯�����Ƴ�ư���Ƥ����פ��Ϥ����롣
������Ū�ˤϡ��ȳ��ǹ�®�ο����դ����ԡ��ɤ�ؤ��Ŀ�����XPS(�������ԡ�����)�����(6��8��)�פ䡢�̤����Ȥ��®�ǹԤ����Ψ��ȵ��Υǥ������ϥ�����KUSANAGI�פʤɡ������ܤ�Ƥ��뻰ɩ�ޥҥ�ɥ����ʤ���ƻ�˼±餷�����Τ�ޤ롣
���ޤ������������Ȥˤϥϥ������̼���Ǥ�Ȥ��뿷���ʤΥȥ饯����X(������)S�����(18��20��23��25����)�פ�PR���롣����ϡ���ɩ�ޥҥ�ɥ���������Ԥ���ͽ��Υȥ饯����XS������פ��ɲû��͡���2�ƤΡ�KUSANAGI�פγ��Τˤ����Ϥ��롣�֥ȥ饯���ϥե륯�����ͤ��ȵ��ȹ�碌�Ƥ��ä���ȿ�ʤ��Ƥ��������פ�ʡ�ʼ�Ĺ�ϰյ����ࡣ
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���ԳƼҤ��б���ˬ��ȼ±�����ϡ����졦�����ý� |
|
| |
|
|
| |
�����ޡ������ꥸ��ѥ�(��)�����ᵦ�ټ�(����ͭ�ټ�Ĺ)�ϵ��Դ����ư���ˤĤ��ơ�����3����β�ư���ϼ��츩��Ʊ���褦�ʾ����ǿ�ܤ������������ּ�����⸷���������פȵ�����Ĺ���ä������塢���Τ���60%�ʾ�����������Ȥ�����(���)�ϡ��������濴���絬�ϲ��˸����ƽ��Ѥ��ޤ��ޤ��ʤ�ΤǤϤʤ�����ͽ¬���롣
������������Ǥϥͥ����濴�Ȥ���Ȫ���Ĥ�ô����俷�������Ԥ�ư������ȯ�����Ƥ��ꡢ�����ؤˤ���������ơ����ޡ����ʤ�PR��ޤäƤ��롣����Ū�ˤ�����ư�ͤ��ܿ�����PW10'N�ס����Ѥͤ�ʿ���ܿ�����PH20A'NHD�ס��ͤ����ϵ���HL10�פȤ��ä����ʤǤ��롣
���ä�1���Ρ�PW10'N�פ�7���ͽ���Ĥ���ܤǤ�����ȼԤ���Ĥ����Ȥ⼫ư�ǿ����դ���Ȥ�Ԥ���Ʊ���ϼ�ư�ǿ�ʿ���椹�뤿�ᡢ���ջ����������ݤġ��ޤ�������̵�ʳ�Ĵ��ϥ�ɥ�ˤ�ꡢ���ϰϤ˳�������Ǥ��������ϤǤγ���Ĵ����ñ�ˤǤ��롣Ʊ���γ�����С��ϼ긵�˽��椷�����֤���Ƥ��뤿�ᡢ�����˳ڤȤ����Τ���ħ��
��2020ǯ�٤����ȿ������ز�γ�ȯ�ޤ���ޤ���1��Ρ�HL10�פϡ���ͥ��μ��Ϻ�Ȥ������˷�ϫ�����롣��ͥ��μ��Ϥϡ�(1)��������(2)������(3)����(4)����Ȥ�(5)��«����«��5�Ĥι��������롣Ʊ���Ϥ����1��ǹԤ������ο�ʿĴ��(��ưUFO)�ˤ����ܷ�����ǽ�ˤ������ޤ����������פǥ������ؤ�ķ�;夲�Ⱥ����β��֤����Ǥ�����Ȼ��������Ĺ��820�ߥ�û�����Ƽ�Ǽ�Ǥ��롣
��������Ĺ�ϡָܵ�ˬ��ȼ±���̤��ơ��ƴ�Ϣ���ʵڤӤ������ں��Ϣ���ʤ⤷�ä�����ơ����Τ��Ƥ��������פ��Ϥ����롣
��(��)ISEKI��Japan������������ѥˡ��ε��ԱĶ���(����������Ĺ)�ϡ�24ǯ1��12�������ˤĤ��ơ�23ǯ�ξʥ��ʹ�Ϣ��������Ȥ����ߡ��������̵��䴥�絡���⤹�굡�Ȥ��ä������β�ư����24ǯ��2��ޤ����˳�ȯ�Ȥʤä���
��2��ʹߤϤ���ȿư���������������ϸ������ʤꡢ23ǯ��(1��12��)����٤ƥȥ饯���ϲ��Ф����Ŀ����ڤӥ���Х���������Ȥʤä�(����١���)��
��������Ĺ�ϡ����Ҥ������϶�ǯ�ޤ�ˤߤ��ۤΤ�Τǡ������⿽����������Ϥܼۤ������줿�����αƶ����鿷�����������˾�������Ȥ�����¿���ʤä�������ۤ������Ͻ��פ�����̤����Ƥ���פ��ä���
�������ܴ���Ǥϥȥ饯����25��35���ϡ��Ŀ�����4��(���)��5��⤷����6��(�絬��)������Х����3�Ȥ��ä����饹����ή�ȤʤäƤ��롣�����Υ��饹�����ˡ����줫��ϥȥ饯���Ⱥ�ȵ�(�����ɤ굡��ǥ������ϥ����ʤ�)�μ±�����Ϥ��Ƥ������ޤ������դ���ư�������֡�CHCNAV�פ���ɾ�Τ�����Τ��ؤ�롣
����ǯ�٤��������ε�ð��Ԥ����ߤ����絬�����Ȥ˾��������ƱĶȳ�ư��³���롣�����ȼ�������Ȥ��������μ���˭�٤��絬��ô������б�����٤�������³�����Ұ��˵��Ѹ�����Ԥ����ޤ�����������¿�����浬�����Ȥˤϸ��̼±��Ԥ���ˬ���ư��³���ʤ����ؾ��ʤ�PR���롣
��������Ĺ�ϡ֥ȥ饯����BF�������RTS5�������±鵡�Ȥ��������CHCNAV���ȵ������դ����ϰ�˹�ä���ƤƤ��������٥�Ȥ�3��1��2����ð��ĶȽ�dz��š���ˤ��絬�����Ȥ˸������إ���ѥ���ե������٤�Ʊ��dz��Ť����ȥ饯�����ò�����PR��ޤ�פ��Ϥ����롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
JA�����������ܵ����ٸ���ء����졦�����ý� |
|
| |
|
|
| |
��JA��������������������ȵ�����(��������Ĺ)��2024ǯ9��ޤǤξ���ˤĤ��ơ���������������ʲ��ʤβ���ʤɤ�ƶ����������ζ���˶��路�������κ�ؿ�(24ǯ��)��ʿǯ�¤ߤ�100�Ǥ��ä������ּ����̤Ϥ���ۤ�¿���ʤ��פȤ����ȹ�������⤢�ä��褦����
��������桢24ǯ9��ʹߤ��Ƥβ��ʤ��徺�����줬�ȹ�������������Ф�����ߤ��ᡢ����ޤ������ι�����α�ޤ餶������ʤ��ä����������ˤ��֤��ε���ƨ�����������褦�פȤ�������Կ�������������ʤ�������Τ������Ⱦ�����ư���ϳ�ȯ���������Բ�Ĺ�ϡ��Ʋ��Ⱥ�����������ߤ�Ϳ����ƶ��������礭���פ��ä���
��24ǯ4��12��β�ư���Ǥߤ�ȡ���ǯƱ��������٤ƥȥ饯���Ϲ�Ĵ�˿�ܤ���126%�����Ȥʤä�(����١���)���Ŀ���������������ˤ��24ǯ�٤����ʲ��ʲ�������23ǯ�٤˹������꼡������(Ʊ)������Х����172%���礭����Ĺ����(Ʊ)��
����ǯ6���ȯ��Ϥ����ֶ�Ʊ��������Х���(4��48����)�פϡ�������絬�����ȤˤȤäƾ��������饹�Ǥ��롣�������Բ�Ĺ�ϡֿ���̤ˤ����ơ�Ʊ����Х����絬�����ȤȤ�����η����Ȥʤꡢ��������4��ʾ���緿����Х������Ƥ���ʤɡ����̤�ʤ�뤦���ǤΤ��ä����ˤ�ʤä��פ��ä�����ǯ�����ѥ���Х������夲�����Ƥ��롣
������̤Ǥ������Ԥ���˾��Ĥ��ि�ᡢ�ȥ饯��������Х����Ŀ����ι����Ԥˡ�����Ĵ���פ��ꤷ�������Ȥ�24ǯ4���»ܡ�����ˤ�������Ԥ��ܲ���õ�ꡢ��˾�ˤ��ä���ȱ������ʳ�ư�����Ϥ��Ƥ��롣�ޤ������ʳ������ܤ˴�Ϣ�����ȵ�����Ƥ������������˴ؤ����ٶ����ԤäƤ��롣
��4���ϥȥ饯����Ϥ��ᶦƱ��������Х���ο�ʡ�������1ǯ�֤�3�Ť��빱���Ÿ������̤��ơ������������������פ���Ƶڤӡָܵ����ٸ���פˤĤʤ����ư��Ԥ���������
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���Ծ��ȡ�������Ȥ���ɸã�������졦�����ý� |
|
| |
|
|
| |
�����������ȵ������ȶ�Ʊ�ȹ�(����͵����Ĺ��20�ȹ��)�ϡ�2024ǯ2��19������78���̾���������������ۥƥ���ԤˤƳ��š�����6ǯ��(����6ǯ1��12��)�λ�������ڤӷ軻�ط����ྵǧ�η����7ǯ�٤λ��ȷײ�ڤӼ���ͽ������η�ʤ���7�İƤĤ���������⾵ǧ���ķ褵�줿��
��24ǯ�٤ζ�Ʊ������ȤǤϡ������Ÿ�����ꥢ���ᤪ��(�����ܵ�����)��2��7��˳��š��Ʒ�Ȥ⻲�å������ޤ���100�ͤ�Ʊ���ˬ�졢���襤��ߤ�����
��������Ȥ���ɸ�ۤ���ã����������23ǯ����Ǥϸ��Ȥʤꡢ�ָ��������������;夬��αƶ������Ȥθ����⤢�ꡢ������������³���Ƥ���פȹ�����Ĺ�ΰ�����������ä���
���������ȤǤϡ�JA�������Ԥ�ð�����������ˤơ����ȵ���������ǽ����ιֽ����24ǯ1��˳��š�Ʊ��27���˼µ���������˳زʻ��Ԥ������η�̡�1�鵻ǽ�Τ�4̾(���Ψ57%)��2�鵻ǽ�Τ�2̾(Ʊ22%)����ʤ�����
������ˤĤ��ơ��͡����װ�������Ǹ������������ȿ����Ĥ�ͤ���ȡ�����ǯ������٤Ƹ��ߤξ��Ȥ�¸�߰յ������ƹͤ��롣����Ͼ��ȤȤ��Ƥ���ޤ��ݤäƤ������Ȥ�褫�������Ȥ�¸�ߤ�ޤ��̤�ݻ����뤳�Ȥ��������פˤʤ�Ȼפ��פȰ�����Ĺ���ä���
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
�Ѥ����������˵��Ѥ��б����Ŀ��������Ĵ�Ϣ�����ý� |
|
| |
|
|
| |
���������Ʋ���ƭ��Ϣ����ƻ�����ʤɡ��Ƥؤδؿ�����ޤäƤ����桢�ơ�����ᤰ���������Ѥ�����Ȥ��Ƥ��롣���ӿ建�ʤϡ�����9ǯ�٤���ο��������θ�ľ�����������Ǥ��Ф�������ο���ž��Τ�������Ƥ���Ƥ������ȤȤ������Ʋ���ƭ���Ƥ�������ή�����������������Ƥ����С�������ư�ˤ����������경�ʤɡ�¿���β��꤬���餫�ˤʤ��桢�Ƥ˴ؤ���ư�������ܤ���Ƥ��롣�Ƥ˴�Ϣ����������
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
��������ͭ����ˡ���硿�Ŀ��������Ĵ�Ϣ�����ý� |
|
| |
|
|
| |
�������������ȵ������������7������̸��������Ԥ��������dz���������6ǯ�����ȵ������ѥ��饹��������ǡ�ξ�����Ŀ����������Ÿ��������
��ξ�����Ŀ�����ľ�����Ѥϡ����ͭ�����ݤ��оݤȤ�����Ρ��Ŀ����κ��������ľ�������ˤ��Ĥ����ưܿ��������֤ˤ����Ū�ʽ����Ԥ�ľ�����Ѥ���Ƥ���ȤȤ�ˡ����ν�����ˡ���ǽ�Ȥ���ݥå���ξ�����Ŀ�����ߤΤ뻺��(��)�ȶ�Ʊ��ȯ(��ȯ��ɸ�����հ������١�3���������)����������ˡ��Ŀ������Τ����̤Ǥ���ޥå���ξ�����Ŀ����λ����������
�����ӿ建�ʤ����ꤷ���ߤɤ�ο��������ƥ���ά�Ǥ�2050ǯ�ޤǤ�ͭ�����μ���Ȥ����Ѥ�100���إ�������˳��礹����ɸ���Ǥ����Ƥ��롣������ͭ�����ȼ������Ѥ�2��5���إ����������٤Ǥ��뤳�Ȥ��顢�����ʳ��礬ɬ�פǤ��롣���ѳ���ˤ���������1�Ĥ������ɽ��Ǥ��ꡢ�������Ѥ��礭�ʿ��ˤ����Ƹ�ΨŪ�ʻ����ɽ����Ѥ��Ω���뤳�Ȥ����פǤ��롣
�������ɽ����ѤȤ��Ƥϡ���˵������𤬻��Ѥ���Ƥ��롣�����������������������Ū�˺��Ѥ����֤��Ф��ơ�����ؤ�»������Τ�������Ū�ʥ졼������Ȥ虜������ʤ����֤ǤϽ�����̤��㤤���Ȥ�����ȤʤäƤ��롣�����̤�¿�����Ǥϼ��Ĥ����������ꤹ��ɬ�פ����ꡢ���ѳ�����˳��װ��ȤʤäƤ��롣
�������ǡ����֤Ǥ����Ū�ʽ��𤬲�ǽ��ľ�������ηϤ���Ƥ���ȤȤ�ˡ������¸�����ξ�����Ŀ����γ�ȯ��ԤäƤ��롣ξ�����Ŀ������Ŀ����κ��������ľ�������ˤ��Ĥ�������������ΤǴ����ܾ����Ĥ�ܿ��Ǥ����Ŀ����Ǥ��롣����ˤ�ꡢ���������Ŀ����κ�����������Ǥʤ�������ľ�������ˤ��Ȳ�ǽ�Ȥʤꡢ���֤ν�����̸��夬���ԤǤ��롣ξ�����Ŀ����γ�ȯ�Ǥϵ������ν�����������Ĥ��ܿ����뤿�ᡢ���հ������١�3����������ȯ��ɸ�Ȥ�����
�����饹�������Ȥˤ����ơ��ߤΤ뻺��(��)�ȶ�Ʊ�ǥݥå���ξ�����Ŀ����γ�ȯ��Ԥä������١������Υݥå����Ŀ���(RXG800D)�ϡ����֤��ѹ��Ǥ���HST(����̵����®����)��������Ƥ��롣RTK��GNSS�����������������¬�̾�����ˡ������ޤ���ɸ���٤Ȥʤ�褦��HST����®���Ĵ�������տޤ������֤��Ĥ�ܿ�����ξ�������浻�Ѥ�ȯ�����������ȶ��˻�����ܤ�������°����ǹԤä����հ������ٻ�Ǥ���ɸ�ͤ�ã�����뤳�Ȥ��ǧ������
���ޤ����ݥå���ξ�����Ŀ����γ�ȯ��ʿ�Ԥ��ơ�ξ�����Ŀ�����ľ�����Ѥμ¾��Ѥˡ��ݥå����Ŀ����ȼ��Τ����̤Ǥ��륯�ܥ������ޥå����Ŀ�����١����ˡ��ޥå��������Ŀ����λ�����������ޥå��Ļ��Ǥ���ɸ�Ȥ��뿢�հ������٤�ã���Ƥ��ꡢ������ϤǼ»ܤ��Ƥ���ľ�����Ѥμ¾ڻ�ǻ��Ѥ���Ƥ��롣
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
���������ʤɤ�����ݥ����ࡢ����ٱ祢�ץ곫ȯ���Ŀ��������Ĵ�Ϣ�����ý� |
|
| |
|
|
| |
�����������彣�������ȸ��楻����2��26����ʡ�����Υ쥽��ۡ���ڤ�Web�ˤơ���άŪ���ޡ������ȵ������γ�ȯ������/͢�г���Τ���ο����ѳ�ȯ�־��Ͻ��𡢰��������ο���ͭ�������ηϤμ¾ڤȻٱ祢�ץꥱ�������ȯ����������Ť�������άŪ�������ץ���������SA2��106R�ֿ���ͭ�����ȡץ���������Ȥζ��š�����4��6ǯ�٤˼»ܤ����ץ��������Ȥ����̤Ȥ��ơ�ͭ���ơ�ͭ����Ʀ��͢�Ф˴ؤ������ư�������Ѥ����ٱ祢�ץꡢ�뤵���³���˶�������ʼ��ȯ���Ѥθ��ϼ¾ڻ�η�̤ʤɤ��Ҳ𤵤줿����������Ʊ������ߧë������Ĺ�ϡ���άŪ�������ץ��ǿ���ͭ�����Ȥβ���������������濴�Ȥʤ��ʤ��Ƥ����аޤ�������Ϥ�������������Ԥ��Ȥ�������ͭ�����Ȥ�����������˻뤳�Ȥ���Ԥ�����
�������ǡ�Ʊ�ץ��������Ȥγ��ס�ͭ���ơ�ͭ����Ʀ��͢�Ф˴ؤ������ư�������ݵ��ѡ��³����ɽ����ѡ����ϼ¾ڻ�ˤĤ��ƹֱ�ڤӼ������Ԥ�줿���������ݵ��ѤǤϡ�(1)ξ�������۾�ˤ������ǽΨ����(2)ͭ���ѻ������˴�Ť����������������(3)ͭ�������ݤˤ�����ͭ���������������벽���ץ���Ѥ��������̤�Ŭ����(4)�ӿ���������ڤŤ���Τ����������ݵ��ѡ�����𤵤줿��
��(1)�������������ȵ�����������̵�Ͳ�����ȸ����ΰ��Ū��ȵ�����ȯ���롼��鸦������ž���������������ͭ�����ݤε�������ˤơ����ֽ�����̤�夲��٤�ξ�������浻�Ѥ���ܤ����Ŀ��������ưľ�ʡ���ư����ξ�����Ŀ���(���ϴޤ�)�ε�ǽ����ܤ����¾ڤ�Ԥä��Ȥ��������հ������٤ϸ���3����������ã����ľ�����䲣�����ν��������»ܤˤ�������̤����夷������Ψ90%�Υץ�����������ɸ��ã�����ǧ�Ǥ�����
��������(3)�����������彣�������ȸ��楻�������ܻ������ΰ�����������롼�ץ��롼��Ĺ�亴���Ų쿭��ֱ顣������������ȯ����������ͭ����������������벽���ץ�ˤĤ��ƾҲ𤷤��������Ȫ�������̤ˡ�����ʵ��������ͭ����������Ѥ����ݤΡ�ͭ�������ͳ���������ʬ(���ǡ�����������)���ɤ����ٶ��뤵���Τ����Ф��������ǽ��������ʬ�̤�ͽ¬�Ǥ����Τǡ����������������ھ�����٥�ȥ�ץ����Ȥ�̵���������Ƥ��롣Ʊ���ץ��ͭ�������ݻ�Ǽ¾ڤ����Ȥ��������Ԥ�ͭ�����ݶ�Ǽ��̤��㤫�ä��Ȥ����ۤɡ����ץ�ͭ���¾ڤˤ��������뷹�����ߤ�줿�Ȥ�����Ʊ���ץ����Ѥ��ƻ����߷פ�Ԥ��������������㸺��ޤ뤳�Ȥ��Ǥ���ȽҤ١��²��ʲ���ʵ��������������������ʤ���������ι⤤ͭ���������Ȥ߹�碌�뤳�Ȥ����������
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ľ���Ŀ�����ͭ�������ޡ������Ⱦ���顿�Ŀ��������Ĵ�Ϣ�����ý� |
|
| |
|
|
| |
�����ޡ������ȿ�ʶ��IJ�ڤ����������彣�������ȸ��楻����1��16�������츩����Ԥ�(ͭ)������١����ˤ���ޤʤɤǥ��ޡ������ȿ�ʶ��IJ���5������ڤ��������Ӻ���Ĥˤ������ǯ���ޡ��Ȳ������ٶ���Ť���(����Webʻ��)��Ʊ�����ڤ�Ʊ�Ҥʤɤ��֥�����١����ˤ���ޥ��ޡ������ȼ¾ڥ���������פȤ��Ƽ���Ȥ�����¸�ǯ�٥��ޡ������ȼ¾ڥץ��������Ȥ����̤ʤɤ���𤷤��ۤ������ޡ��������μ±��Ԥ�줿����α�ƥ��ƥ��ץ饶�ǹԤ�줿�����Ǥϡ����������ˤ�륹�ޡ������ȿ�ʶ��IJ�ڤӥ��ޡ������Ȼ��߶��ѥץ��������Ȥ����������ӿ建�ʤˤ�륹�ޡ������ȿ�ʻܺ����������Ԥ�줿�ۤ��������ޡ������Ȥηк���ɾ���ȥ��ޡ�������Ƴ���ٱ祵���ӥ��ο��(�ե����ࡦ�ޥͥ����ȡ����ݡ�����ɽ�����ܲ���)���������ȥ��å��Ի�ʡ���Ԥ������ޤ�뿷�������ޡ������ȵ��ѤΤ��Ҳ�(ʡ�������ӿ建���������ݡ�����ͪ�ᡢCarbon��Xtract(��)��(��)�����ʥå������ƥࡢSACMOTs)���ե��������åȤ���Ѥ������ȥǡ���Ϣ�Ȥμ����ˤĤ��ơ�����������AI��ͭ�����ѡ�((��)�ե����ࡦ���饤�����ޥͥ����ȡ������·ɻ�)����3�ֱ餬�Ԥ�줿�������Ǥϡ����ܻ�ιֱ鳵�פΰ�����ߤ롣���ܻ�ϥ��ޡ������Ȥηк���ɾ���ȡ�Ƴ���ٱ祵���ӥ��ο�ʤˤĤ��ƾҲ𤷤������Ԥ����¸�ǯ�٤��餳��ޤ�����217�϶�Ǽ¾ڤ�ԤäƤ��륹�ޡ������ȼ¾ڥץ��������Ȥ����̤���ޤȤ����𡣥��ޡ��������ˤ�����̤ξ��ϸ��̤ˤĤ��Ƥϡ����ܥåȥȥ饯���ζ�Ĵ��Ȥˤ����ϲ�(ϫƯ���ֺ︺)��30%����ˤʤꡢľ�ʥ��������Ŀ�����Ʊ11%���٤ȡ���ư���ɵ�ǽ�Ǥ����ξ��ϲ���¸��������ޤ�����ư����������ƥ����7�为�������ʺ︺Ψ��ߤ������������б����ΤǤߤ�ȡ����ޡ������ȵ���Ƴ���ˤ����ϫƯ���֤Ȱ����̤��Ѳ���ߤ��Ȥ����Ƽ¾��϶�ˤ�������ϫƯ���֤�ʿ��9%�︺�����ñ����ʿ��9%����(������ʿ��)�Ȥʤä�������˼¾��϶����3��ˤ����ơ�10%�ʾ��ϫƯ���֤κ︺���̤�����줿�Ȥ������ޤ���ñ�����äϡ����ǡ������˴�Ť����ѻ���䡢����˲ä����ʼﹽ���������߷פ���������϶�ˤ����Ƹ����˸��줿�Ȥ������ޤ������ޡ��ȼ¾ڻ��Ȼ�������ˤ�����ˡ�ͷбġ��ĿͷбĤ����ס��������Ѳ���ߤ�ȡ��¾ڷбĤμ¾���(ʿ��30ǯ)����¾ڸ�(����3ǯ)�ˤ����Ƥηбļ��٤��Ѳ��Ǥϡ�ˡ�ͷбġ��ĿͷбĤȤ���������ס����������ä��Ƥ��롣Ƴ�������褫���줿���ޡ�������Ƴ���θ��̤ˤĤ��Ƥߤ�ȡ�(1)����̼��̥ǡ����γ������ˤ����ñ���ȼ������ä�ã��(2)���ޡ���������Ƴ���ȹ�碌�����ݲ�����������Ū����ˤ�ꡢϫƯ�Ϥ����ä����뤳�Ȥʤ����ϳ��硦�������ä�¸����ʤɤ�������줿�����Τ�����(1)�ˤĤ��ƾܺ٤�ߤ�ȡ�Ʊ�бĤǤ�2000ǯ�ʹߵ��ϳ��礬�ʤߡ����������������桢100�إ��������Ķ���뺢������ñ�����㲼�����礭������ˤʤäƤ����������ǥ��ޡ������ȼ¾ڻ��Ȥ˻��褷�ƾ��ϲ���ʤ��ȤȤ�ˡ����̥���Х����Ƴ����������̼��̥ǡ���������������Υǡ����Ⱥ��ݻٱ祷���ƥ����Ѥ�������̤��ʼ��������֤������ѻ���ˤ���������������å���ޥåפ˴�Ť����ѻ����»ܤ������ޤ����������ǤϺ����ô���礭����������Ͼ�ά����Ƥ��������ɥ�������Ѥ��ơ���������˱�����������ѹ������������μ���Ȥߤη�̡������̤ϺƤ����á�����2ǯ�ˤϡ����ϳ���ȹ�碌�������������̤�33%�����ã���������ޤ���(2)�λ���Ǥ�ʿ��30ǯ�˸������Ͻ��ѻ��Ȥ˻��衣����ήư�����ʤ�����ˤ��ä����Ȥ⤢�ꡢ�б����Ѥ�30ǯ��32�إ������뤫������3ǯ�ˤ�106�إ�������ޤdz��礷�������Τ褦�ʾ����Τ�Ȥǥ��ޡ������ȼ¾ڻ��Ȥ˻��ä������ܥåȥȥ饯������ư��ž�Ŀ�����ľ���������Ŀ����������ٱ祷���ƥ�������Ѥ������ϲ��ȡ��������Ƥ��ʤ����Ȱ��κ��ǽΨ�����ޤ뤳�Ȥ�ײ衣���ϳ��礬�ʤ���ǡ�ϫƯ�Ͽ���4�ͤ���5�ͤؤ�1̾�����äΤߤ���70�إ�������ε��ϳ�����б������Ȥ��������ϳ����ȼ��������礭�����ä��������μ��̤ϡ������ҥ�����㲼���Ƥ��뤬�����������ޤ��ϡ����ѳ���ˤ⤫����餺���ä���������˥��ޡ���������Ƴ���˲ä������ù��ľ�ź��ݤ��������á����Ϥν�����ư��ž�Ŀ������μ�ư���ɵ�ǽ����Ѥ����㤤���Ȱ��ε�ǽ�θ��塢�ʼ����֤θ�ľ���ʤɺ����̡�������̤Ǥβ�����ʻ���Ƽ»ܤǤ�����
|
|
| |
���ۡ��������� |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
