| |
|
|
| |
農経しんぽう |
|
| |
令和7年3月24日発行 第3544号 |
|
| |
|
|
| |
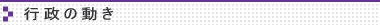 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
基本計画の目標示す/農林水産省・農政審企画部会 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は14日、東京・霞が関の農林水産省講堂で、食料・農業・農村政策審議会企画部会(第118回)を開き、新たな食料・農業・農村基本計画の本文(案)を議論した。農林水産省からは、食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する2030年の目標が示され、食料自給率の目標は、カロリーベース45%とするほか、摂取熱量ベースで53%の目標を提案した。
基本計画本文の「まえがき」では、「今回策定する食料・農業・農村基本計画は、激動する国際情勢や人口減少等の国内状況の変化等の中にあっても、平時からの食料安全保障を実現する観点から、その計画期間を5年間とし、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進めることとする」と位置付けを述べ、その実現に向けて「基本計画の実効性を高めるため、国内外の情勢を含めた現状の把握、その分析による課題の明確化、食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標、課題解決のための具体的施策及びその施策の有効性を示すKPIの設定を行うこととし、少なくとも年1回、その目標の達成状況の調査・公表、KPIの検証によりPDCAサイクルによる施策の見直しを行い、おおむね5年ごとに基本計画の変更を行うこととする」とした。
国内の農業生産の増大に向けた2030年の目標としては、食料自給率について、カロリーベース45%、摂取ベース53%、農地面積は412万ヘクタール、49歳以下の担い手数は、現在の水準の4・8万経営体(2023年)を維持、労働生産性・土地生産性については、1経営体当たり生産量を1・8倍、生産コストの低減については、米は15ヘクタール以上の経営体で、1万1350円/60キロから9500円/60キロに低減、麦・大豆は2割減(現状比)―などを掲げた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
令和7年産主食用米の作付意向/農林水産省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は19日、令和7年産の水田における戦略作物等の作付意向について、第1回中間的取組状況(令和7年1月末時点)を公表した。それによると、各都道府県の主食用米の作付意向は合わせて128万2000ヘクタールで、令和6年産実績と比べて2万3000ヘクタールの増加となった。10〜12万トンの増収と試算される。
都道府県別の意向では、増加傾向が19県、前年並みが24県、減少傾向は4県となっている。増加は北海道、東北全県、北陸全県、関東など東日本での意向が強い。
戦略作物等の作付意向は、加工用米は4万7000ヘクタール(対前年比3000ヘクタール減)。増加傾向8県、前年並み12県、減少傾向24県。新市場開拓用米(輸出用米等)は1万2000ヘクタール(対前年比1000ヘクタール増)。増加傾向8県、前年並み17県、減少傾向13県。米粉用米は6000ヘクタール(対前年比同)。増加傾向8県、前年並み24県、減少傾向14県。飼料用米は8万5000ヘクタール(対前年比1万4000ヘクタール減)。増加傾向0県、前年並み11県、減少傾向35県。WCS用稲(稲発酵粗飼料用稲)は5万7000ヘクタール(対前年比1000ヘクタール増)。増加傾向7県、前年並み26県、減少傾向13県。
麦は10万1000ヘクタール(対前年比2000ヘクタール減)。増加傾向11県、前年並み21県、減少傾向13県。大豆は8万1000ヘクタール(対前年比3000ヘクタール減)。増加傾向9県、前年並み9県、減少傾向27県。備蓄米は2万6000ヘクタール(対前年比4000ヘクタール減)。増加傾向4県、前年並み11県、減少傾向13県―となっており、戦略作物の減少分がほぼ主食用米にシフトした格好。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
国産大豆テーマに勉強会/関東農政局 |
|
| |
|
|
| |
関東農政局は18日、みどりの食料システム戦略勉強会(第29回)をオンラインで開催した。1〜3月のテーマは「役に立つ!有機農業の栽培技術」。その最終回となる今回は、農研機構中日本農業研究センター有機・環境保全型栽培グループの田澤純子氏が登壇し、関東地域における大豆の有機栽培技術研究について紹介した。
田澤氏はまず、国内に流通している有機大豆の約9割が外国産であるというデータにより国内生産量が大きく不足している現状を示し、国産有機大豆の栽培推進の必要性を強調した。
続いて、有機大豆の栽培体系について、慣行栽培と比較しながら検討。(1)有機栽培に適した品種の選択(2)播種時期を遅くする(3)早期中耕培土の実施―という3つのポイントをあげ、それぞれの詳細を説明した。
(1)有機栽培に適した品種については、中〜晩生、小〜中粒、多莢であることをあげた。品種別の慣行栽培との収量比較では「納豆小粒」が91%、「フクユタカ」が76%などの研究結果を報告。また「在来品種は晩生が多いので、様々な品種で有機栽培を試してみてほしい」と勧めた。
(2)播種時期は、慣行栽培の場合は6月中旬〜下旬だが、有機栽培では7月初旬〜中旬を目安に播種時期を遅らせることで、慣行栽培の6〜7割の収量が期待できるとした。また、播種時期をずらすことで開花時期も遅れるため、カメムシなどによる吸汁害被害が3割程度軽減されたという研究結果も示した。
(3)中耕培土の実施時期については、慣行栽培では播種後3〜4週間で行うのが通例だが、有機栽培の場合は播種後10日〜2週間と早期に実施することを推奨。これにより、雑草量の抑制に大きな効果があることを示すデータを提示し、特にホソアオゲイトウやメヒシバなど、初期の植物体が大豆より小さい1年生雑草に対する抑草効果が高いとした。さらに、株元までしっかり土を掛けることが効果的だとし、水田転換畑にはディスク式中耕培土機の使用を勧めた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農機メーカーが取り組み/令和6年度「農作業安全対策全国推進会議」から |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は2月26日、東京・霞が関の農林水産省講堂(Web併用)で、令和6年度「農作業安全対策全国推進会議」を開き、令和7年度の農作業安全対策の推進方針の決定や、農業機械メーカーなどからの取り組み事例報告などを行った(既報)。7年度の重点推進テーマは「学ぼう!正しい安全知識〜農業機械作業研修・熱中症対策研修の拡大と充実、未熟練農業者への研修実施」。この中から、メーカーの発表概要をみる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
イチBizアワードでハタケホットケが最優秀賞/内閣官房 |
|
| |
|
|
| |
内閣官房が主催している、地理空間情報を活用したビジネスアイデアコンテスト「イチBizアワード」において、(株)ハタケホットケ(日吉有為代表、長野県塩尻市)の水田雑草対策ロボット「ミズニゴール」が2024年度最優秀賞に輝いた。
同表彰制度は地理空間情報を活用したビジネスアイデアの発掘や人材育成・コミュニティの形成を行うプロジェクトで、第3回目となる今年度は、昨年度比1・7倍の合計172件の応募があった(アイデア部門101件、ビジネス部門61件、地域部門10件)。1月31日に東京ビッグサイトの「G 空間EXPO2025」会場内で開催された表彰式にて、ノミネートされた45件から最優秀賞や各部門の優秀賞、みちびき賞など各賞が選出され、表彰が行われた。最優秀賞の表彰では、有識者審査員の庄司昌彦氏より日吉代表に賞状とトロフィーが贈られた。
最優秀賞に輝いた「ミズニゴール」は、GPSを搭載し、水田を走らせるだけで除草作業の自動化を実現する水田雑草対策ロボット。ロボットが水田を自動走行し、泥をかき混ぜ水を濁らせることで雑草の光合成を遮断し、米の有機栽培の最大のネックである草取りの手間を軽減する。準天頂衛星システムみちびきのCLAS(センチメータ級測位補強サービス)対応受信機を搭載することで位置情報を高精度化した他、ロボットを複数の農家でシェアレンタルする仕組みを検討するなど、地域連携による産地化を支援していることなども評価された。
庄司審査員からは選定理由として、「草取りにGPSという発想が興味深い。なぜロボットで草取りの手間を減らす必要があるのかというコンセプトがしっかりしており、米の売り方についてもよく考えられている。モーターの開発が困難であるが知財を取得済みという点への評価や、デバイスの生産力と安定供給がカギとの声もあった。ビジネスが正のスパイラルに入るまで頑張ってほしい」とのコメントが寄せられた。
ハタケホットケはこのほど、ミズニゴールの2025モデルのリリースを決定。同機の利用希望を募集しており、利用希望者は3月〜4月中旬まで開催しているオンライン説明会への参加を呼び掛けている。ミズニゴールのサービス詳細や、オンライン説明会の申込みは同社ホームページ(https://hhtk.jp/)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
令和6年度エネルギー安全保障セミナー開催/外務省 |
|
| |
|
|
| |
外務省は4日、都内新宿区のコモレ四谷タワーコンファレンス及びWebにて令和6年度アジア・エネルギー安全保障セミナーを開催した。
これはエネルギー安全保障における日本の取り組みや国際連携の必要性等に関する理解促進を目的として同省が毎年開催しているもので、今年度は「エネルギー移行におけるエネルギー安全保障」をテーマとして、クリーン・エネルギー移行に不可欠な重要鉱物などを取り上げ、各国のシンクタンク・国際機関の専門家と議論を行った。
開会あいさつした同省経済局審議官の林誠氏は、今回はクリーン・エネルギー移行が進む世界において、エネルギー安全保障がどう変わるのか議論を深めたいと説明。世界のエネルギー安保をめぐる状況は複雑化しており、各国とも気候変動対策のためネットゼロ実現に向けクリーン・エネルギーへの移行を加速しているが、一方でエネルギーは国民生活や経済活動の基盤であり、安定供給を損なわないよう安全で秩序あるエネルギー移行を進める必要があると述べた。
石油・天然ガスといった従来のエネルギー源確保は今後も重要であり、地政学的リスクに注意を払うと同時に、クリーンエネルギーへの移行が求められ、太陽光・風力などが導入されるにつれ、エネルギーの安定供給など新たな課題も出てきている。電力インフラに対する安全確保や、クリーンエネルギー移行に不可欠な重要鉱物のサプライチェーンの強靭化の重要性も高まっているという。エネルギー安保をめぐる状況が転換期にある中で、今日はこれからの課題と国際社会の取り組みについて議論を深め、現在及び将来におけるエネルギー安保に対する理解を深めることを期待したいなどと述べた。
その後、登壇者によるプレゼンテーション及び議論が行われた。
プレゼンでは、▽国際エネルギー機関(IEA)シニアアナリスト・ローナン・グラハム氏▽米国戦略国際問題研究所(CSIS)エネルギー安全保障・気候変動プログラム・シニアフェロー・ジェーン・ナカノ氏▽東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)エネルギー政策局長及びアジア・ゼロエミッションセンター長・ヌキ・アギャ・ウタマ氏▽日本エネルギー経済研究所(IEEJ)資源・燃料・エネルギー安全保障ユニットガスグループ研究主幹・柳沢崇文氏がそれぞれ講演した。
そのうち、グラハム氏はエネルギー安全保障における伝統的課題及び新たな課題と題して講演。グラハム氏はまず、IEAについて世界のエネルギー安全保障の確保を基本的な使命としていると紹介。そのうえで、従来のエネルギーである化石燃料の動向について、石油の生産は2030年に向けてOPEC(石油輸出国機構)の生産能力の増大により増産すると見込まれ、ガスについてもLNG(液化天然ガス)の液化能力の向上により増産が見込まれるとし、ある程度は供給断絶のリスクが緩和されているとした。しかし、運輸にあたりマラッカ海峡やホルムズ海峡を通過する中東からの供給割合が多いことから、アジア輸入国にとって地政学的リスクが避けられないと指摘。今後の石油・ガスはアジア太平洋地域など、新興国・発展途上国において消費量が著しく増加し需要を牽引するため、それらの国々におけるエネルギー安全保障や緊急時対応がますます重要になると述べた。
一方で、環境問題対応などを背景に「電気の時代」に移行するにつれて、従来の需要に加えてEVやデータセンター、ヒートポンプなど新しい技術の電力需要も増え、世界の年間電力需要が著しく増加していると説明。それに伴い、電力の安全性が最も重要になると述べ、世界的に膨大な追加発電能力が必要となり、太陽光発電や風力発電などクリーンエネルギーに対する投資が増加しているものの、膨大な電力の安定供給を実現し、安全性を確保するには、短期的・季節的な柔軟性が必要になるという。また、多くのクリーンエネルギーの製造業や、エネルギー関連の重要鉱物は、中国をはじめとした数カ国に集中していることも安全保障における課題などと指摘した。
他方、柳沢氏は「エネルギー安全保障とエネルギー転換に関する日本の視点」について講演。柳沢氏は日本政府が今年2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画について触れ、同計画では、2021年以降、日本を取り巻くエネルギー情勢が劇的に変化しており、日本のエネルギー安全保障に不確実性が高まっていることを指摘。これに対処するため、日本は2040年度に向けて様々なエネルギー需要シナリオを準備する必要があると述べ、特に長期LNG契約が重要な役割を果たすことに期待が傾けられているが、あらゆるエネルギー源及び供給国には長所と短所、不確実性があるため、万能薬ではないと説明した。
日本は同盟国であるアメリカとエネルギー協力を強化することが予想されるものの、米国への過度依存は日本のエネルギー安全保障の脆弱性を招くことから、日本はエネルギー源及び供給国の双方において多様化を継続的に追求するとともに、企業活動のみでは解決できない困難には日本政府の支援や関与の必要性もあるなどと述べた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
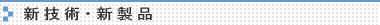 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
「スーパーうね草取りまーVA」発売/アイデック |
|
| |
|
|
| |
(株)アイデック(伊東潤弥社長・兵庫県加西市北条町栗田182)は、刈払機アタッチメントの雑草粉砕ブレード「スーパーうね草取りまーVA」を今年1月に発売。同品は現行機種「うね草取りまーPRO」の改良新モデルとして雑草を削って粉砕する特徴を継承しつつ、ギヤヘッド部に角度可変機構を搭載。従来機よりも性能や耐久性、使いやすさが向上した。
スーパーうね草取りまーVAの主な特徴は以下の5点。
(1)手持ちの刈払機に取り付け可能(2)10センチ程度の雑草を立ったままで素早く削り取る(3)強力な小型ハンマーナイフで削った雑草は粉砕するため、集草の手間が不要(4)雑草の生長点から削り取るので、雑草発生の抑制効果がある(5)角度可変ヘッド採用。様々な現場で最適なアングルで使用可能(水平90〜180度)―など。
畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内など、従来の機械では狭くて難しい場所でも、ヘッドの角度を効かせたスポット除草により効果的な作業ができる。また、同品にはラバー製カバーを搭載しており、取り外しが簡単にできる。取り外しが楽なため、中に入り込んだ土や小石をスムーズに取り出せる。これにより除草中の土の付着や石詰まりを大幅に軽減。騒音吸収効果や飛散防止の効果も期待できる。
スーパーうね草取りまーVAは、付属の取り付けキットにより、ほとんどの刈払機に取り付けができる。
製品動画や詳細は、同社Webサイトで確認できる。問い合わせは同社(TEL0790・42・6688)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ラジコン草刈機「アイラボ」、省人化に貢献/オカネツ工業 |
|
| |
|
|
| |
オカネツ工業(株)(和田俊博社長・岡山県岡山市東区九蟠1119の1)は、2024年5月にハンマーナイフ型ラジコン草刈機「AIRAVO(アイラボ)」を発売。以来、人手が足りない中山間地域における草刈り作業の軽労化と省人化を実現していると好評を博している。
なお、同機は「第35回読者が選ぶネーミング大賞」にてアイデアネーミング賞を受賞した。
アイラボはラジコン操作のため、離れた場所から操作ができ、広範な平地や人の入りにくい場所の草刈りのみならず、傾斜など危険を伴う場所での草刈りに最適である。刈り幅は700ミリ、車速は約0〜4キロ。刈取部はエンジン駆動で走行部はモーター駆動のハイブリッド式となっている。走行部にはクローラを装備し、最大角度30度の急斜面での作業が可能。
送受信機と同社が開発した制御システムにより、リニアレスポンスな操作性を実現した。
刈り取りはハンマーナイフの採用で、150センチの草でも数センチ程度のチップ状にし、集草作業時の煩わしさを解消する。また、刈刃配列を螺旋状にすることで刈り取り抵抗を軽減、耐久性に優れ連続作業時間の向上を実現した。なお、アイラボは軽トラに積載できる。
同社はこれまで電動ミニ耕うん機「CURV0(くるぼ)」、エンジン式2馬力車軸耕うん機「ほっテ」、一輪クローラ伝動運搬車「HaC0VO(はこぼ)」、山岳用運搬車「NoVoRo(ノボロ)」、サスペンション搭載の軽量型耕うん機「DC2S」、アイスクリームブレンダー「BJ」など、自社ブランド製品を果敢に開発・製造し、ヒットを飛ばしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
スーパーソル推進/古河産業 |
|
| |
|
|
| |
古河産業(株)(伊藤啓真社長・東京都港区新橋4の21の3新橋東急ビル)の新規事業創出部が農業分野への普及を図っている「スーパーソル」は、廃ガラスびんを原料に破砕↓粉砕↓混合撹拌↓焼成発泡の工程を経て製造した人工の軽石で、比重や吸水率をコントロールできるため、用途に合わせた製造が可能。鉱物由来のため周辺環境に影響を与えることがなく、安心して使える資材。農業では土壌改良材、暗渠資材としての活用が期待できる。
スーパーソルは、絶乾比重0・25〜0・5、吸水率20%以上のL1から、同1・0〜1・6、5%以下のL4まで4規格があり、農業の土壌改良材にはL1、暗渠資材には同0・35〜0・5、20%未満のL2が適格。 農業以外では、スポーツ施設やゴルフ場の排水資材、グリーンの床材、雨水貯留システム資材として動力を使わずに水質を維持する災害対策用、また、浄水場の土壌脱臭装置のフィルター資材、伊勢エビの養殖施設における濾過材など、様々な現場で使われている。
農業関係では、▽圃場の透水性を高める効果=土壌改良材▽高設栽培における軽量資材の効果=イチゴ栽培などの軽量土壌で混合使用▽排水資材の効果=暗渠用排水資材▽水分の蒸発を抑え土の表面温度を適切に保つ効果=マルチ資材▽牛舎における牛の転倒防止効果=敷料(滑り止め)―といった用途で使われている。
同社は、先に東京ビッグサイトで開かれたアグロイノベーション/みどりの食料システムEXPOに出展。「スーパーソルが農業を変える」をキャッチフレーズに、排水性、保水性、通気性に優れ、多孔質、エコの特徴を持つ同製品をSDGsにマッチした環境資材と位置付け、農業分野でのさらなる利活用をアピールした。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
土壌データを見える化/横山商会 |
|
| |
|
|
| |
(株)横山商会(横山信太郎社長・石川県白山市横江町5377)は2月20日から、土壌データを見える化する「らくらく実りくんスマホ版」の販売を開始した。
同製品はハウス・畑・果樹などに専用の土壌センサを埋め込むことで、土の中の状態を簡単に確認できる土壌モニタリングシステム。
土の中の水分率・温度・EC値を測定し、パソコンやスマホなど各デバイスでデータを確認できるようになっている。本機に電池を入れてから1年以上動くため、種まきから収穫の段階までをカバーする。
年度ごとの収穫量とデータを比較することで、収穫量アップにつなげ、水分量や肥料管理の量・タイミングを見える化し、若い農業従事者への継承にも役立てる。
今回発売したスマホ版は、本機とスマホ・タブレットを接続し、iOS版アプリでデータを確認する。自動計測・リアルタイム計測機能を搭載。計測データの共有機能も付いている。溶液のECを測定することも可能。定額料金不要で、運用コストは電池のみ。
販売価格は9万8000円(税抜き)。購入は横山商会のECサイト、よこやま商店(https://yokoyama-ec.shop/)にて。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ロッカー型無人店舗を新発売/ISEKIトータルライフサービス |
|
| |
|
|
| |
(株)ISEKIトータルライフサービス(玉置茂喜社長・東京都荒川区西日暮里5の3の14)は3月末から、冷蔵機能を搭載した「ロッカー型無人店舗」を発売する。すでに同社は無人販売機「セルフベンダー」の供給で農家の野菜販売などをバックアップしてきたが、今回の新製品はロッカータイプになったことで様々な形状の商品に対応でき、また、要望の多かった冷蔵機能の装備により、さらに幅広い品目を販売できるようになった。農業・農家の変化が著しい昨今、直販部門を設けるなど多様化する営農を支える商材として、「ロッカー型無人店舗」の今後の普及拡大が期待される。
ロッカー型無人店舗は、最大40種類の商品の販売が可能。オプションとしてキャッシュレス端末を用意しており、現金を持たずに買い物をする各世代にも対応でき、また、高額商品の販売でもキャッシュレスなら安心というメリットがある。
各商品を置く部屋のサイズは工具不要で簡単に変更でき、その内容(収納部屋内寸、耐荷重)は次の通り。▽スモール=幅200×奥行330×高90ミリ、3キロ▽ワイド=同400×330×90ミリ、5キロ▽トール=同200×330×195ミリ、10キロ▽ラージ=同400×330×195ミリ、20キロ。販売可能商品は、各内寸から5〜10ミリ小さい寸法の物になる。また、部屋割りは8パターンの組み合わせが可能。
無人店舗で懸念される商品アピール力については、外扉の商品パネル(A4サイズ)で各商品の魅力、特徴を分かりやすく詳しくアピールできるのに加え、外扉を開けると見えるディスプレイウインドウで実際の商品を目視で確認できるようにしている。
同製品を使って商品を購入する人は、商品パネルで品物を確認し、外扉(ドア)を開けて実物を確認。テンキーで品物を選んで支払った後に内扉を開けて商品を取り出す―手順になる。決済が完了すると選択した商品の内扉だけロックが外れて取り出せる仕組みだ。
商品販売時に想定されるトラブルを防ぐために、▽売切スイッチ=商品の大きさに関係なく最小重量50グラムから売り切れを検知する。これにより従来の自動販売機では扱えなかった小さな商品も販売できる▽空売り防止=一度販売した部屋は売り切れを認識。このため販売済みの部屋を重ねて購入してしまう問題を防ぐ▽商品閉じ込め防止(リトライ対応)=購入商品を取り出す前に扉を閉めても、商品が売切スイッチの上に載っていれば再度扉を開くことができる―機能を搭載している。
ロッカー型無人店舗(メーカー=富士電機(株))の主な仕様は次の通り。
▽外形寸法=高1854×幅1785×奥行620ミリ(設置必要奥行650ミリ)▽定格消費電力=178ワット▽設置条件=屋内専用、直射日光不可、設置時の傾き±1度以内▽本体ユニット製品質量=350キロ▽電源=単相100ボルト(コンセント容量=15アンペア)▽決済ユニット製品質量=70キロ▽使用貨幣=10、50、100、500円硬貨、1000円紙幣(新紙幣対応)▽価格設定=10〜9990円(10円単位)▽電子マネー=オプション
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
粒・粉・ペレットが撒ける電動散布機/和コーポレーション |
|
| |
|
|
| |
(株)和コーポレーション(今井猛詞社長・兵庫県三木市福井2の11の41)は、4月1日に電動散布機「撒きざんまいプレミアム」を発売する。
従来の肥料散布機は粒状肥料の散布には適していたが、湿った堆肥や粉状の石灰などの散布には困難が伴い、ユーザーにとって大きな課題となっていた。また、肥料や堆肥の散布には、それぞれ専用の機械を購入する必要があった。
同社は多くのユーザーからの要望に応え、有機石灰、消石灰、堆肥(含水率50%以下)、もみ殻、燻炭など、多様な肥料を効率的に散布できる電動散布機「撒きざんまいプレミアム」を新たに開発した。
同機は、粉状・粒状・堆肥類まで、これ1台で全て撒くことができる。拡販用と散布用の2種類のモーターを装備。アジテーター(攪拌棒)は粒状・ペレット状用と粉状用の2種類あり、モーターからワンタッチで脱着可能なため簡単に変更できる。散布幅調整レバーで、散布幅を40センチから5メートルまで調整可能。また、均等撒き調整ノブにより、散布物を均等に撒くことができる。動力となるリン酸鉄リチウムバッテリーは高い安全性を誇り、2〜6時間の連続運転が可能である。
また同機は、様々な運搬車等への取り付けが可能な取り付けタイプのマルチ散布機。オプションの様々な取り付けアタッチメントで、現在所有している運搬車や軽トラックなどに装着可能となっている。
併せて発売する電動運搬車「KT―8FK2」は、鉛蓄電池24ボルトを搭載し、約8〜10キロの走行が可能。「撒きざんまいプレミアム」を搭載すれば、肥料散布の省力化、効率化に貢献する。また、電動運搬車は、通常の運搬車としても使用可能。重さ120キロまでの作物や資材、農機などを運ぶことができる。
〈撒きざんまいプレミアム KT―MK2仕様〉
▽寸法=幅620×長さ950×高さ845ミリ▽重量=24キロ▽ホッパー容量=60リットル▽散布範囲=40センチ〜5メートル(速度・散布品による)▽バッテリー連続運転時間=2〜6時間(散布物の負荷により変動)
〈電動運搬車 KT―8FK2仕様〉
▽寸法=幅620×長さ1560×高さ1205ミリ▽重量=66キロ▽最大積載量=120キロ
問い合わせは同社(TEL0794・82・6588)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
スクミッチをPR/大栄工業 |
|
| |
|
|
| |
大栄工業(株)(干川量也社長・佐賀県三養基郡みやき町白壁1964)は、ジャンボタニシ撃退製品として誘引トラップ「スクミッチ」の普及を進めている。
気候変動による高温推移が続く中、稲に大きな被害を及ぼすジャンボタニシは北上しながら被害を拡大させている。こうした状況下、同社は生研支援センターのイノベーション創出強化研究推進事業でジャンボタニシ誘引トラップ「スクミッチ」を開発、特許を取得した。同製品は、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の誘引剤とスクミリンゴガイ捕獲器をセットし、田んぼで化学農薬を使わずにスクミリンゴガイを捕獲し、生息密度を減らすもの。とくに有機農業など環境負荷への低減に取り組む生産者には大きな支援器具となる。
使い方は、捕獲状況が分かりやすい半透明の捕獲器の中央に水溶性で自然への影響がない誘引剤をセットし、フタをして田んぼに置くだけ。効果の半径が約15メートルなので、10アール圃場の場合は水の出入りがある場所とジャンボタニシが繁殖しやすい場所の中心に合計3個程度設置することを推奨している。田植え後、水が入った後に設置し、誘引剤(スクミッチフード)は1週間程度で交換する。また、継続設置すると越冬個体が減少し、さらに効果は高まる。
スクミッチのサイズは幅500×厚250×高100ミリ、重量は1400グラム。素材はポリカーボネートで軽く、持ち運びしやすいよう把手付き。また、スクミッチジャンボは同740×375×360ミリ。誘引剤「スクミッチフード」は1個30グラム。ほかに交換時期が倍の2週間程度の「スーパースクミフード」があり、スクミッチ用は1個105グラム、ジャンボ用は1個120グラム。こちらは紙管入りで、同器にセットするとジャンボタニシが直接紙管を食べて剤が溶出する。
同製品の使用により、被害軽減・増収で生産者の収入アップが図れ、また、これまでの防除剤よりも経費削減につながるとともに、環境に優しい手法ともなる。同社は先に東京ビッグサイトで開かれたアグロイノベーション/みどりの食料システムEXPOに出展、同製品のPRに努めた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
捕獲動物を楽に運搬/オンサイテック |
|
| |
|
|
| |
オンサイテック(株)(西澤久友社長・長野県松本市和田3967の10)は、鳥獣害防止対策の一環でイノシシなどを捕獲した現場からジビエとしての食材を提供する加工センターまでの間を結ぶラジコンの冷却・運搬装置「EV自走式冷却搬送機(SSCBOX)」の普及に努めている。西澤社長は、同機が農林水産省の補助事業対象機(2分の1助成)となったことから、今後は導入に弾みがつくと期待を向けている。
山間地など足場の悪い地域で捕獲した場合、斜面の移動が困難、処理場までの間に肉質が劣化するなどの問題点が生じやすく、その解消策として同機には不整地に強いゴムクローラの足回り、冷却機などを備えた。また、害獣駆除ではハンターの減少や高齢化が進み、その要因として、足場の悪い場所での動物の運搬といった重労働を嫌い、後継者ができにくい事情があるという。
そうした作業環境を改善するため、捕獲した動物は布等(ストレッチャー)で包んで同機に備えているウインチで引き出し、同機に積み込んで冷却した動物を広い場所で待機する軽トラ(冷蔵庫装備)まで自走で運搬、アルミブリッジを使って車両ごと軽トラに積載といった流れで処理場まで運ぶ。
同機の操作はリモコンで行い、ポータブル蓄電池を電源として冷却する。最高速度は時速6キロ。航続時間は約4時間、機体サイズは長1700×幅870×高1000ミリ。左右は約45度、前後は約30度の傾斜まで対応する。
西澤社長は、同機の発展系として、稲作関係の副産物を処理する機械を開発中とし、より広い市場での需要づくりに意欲をみせている。同社は先に東京ビッグサイトで開かれたアグロイノベーション/ジビエ利活用・害獣被害対策展2025に出展し、同機のPRを進めた。
同社の連絡先はTEL026・266・0072。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
散布幅可変スプレーヤを全国展開/ロブストス |
|
| |
|
|
| |
(株)ロブストス(高垣達郎社長・群馬県みどり市笠懸町久宮191の108)は今年から、畝間の除草剤散布を正確に速く行うことができる農機具「アジャスタブルスプレーヤ」の全国展開を進めている。同機は農家の協力を得つつ開発した現場ニーズ対応型製品で、本機を4輪の手押し車としているため、前進も後進もただ転がすだけの簡単操作。2021年に発売されており、今年から本格的な全国対応に乗り出している。
アジャスタブルの名称通り、ハンドルの開閉動作と散布幅が連動し、作業しながら散布幅を変えられるため、株元に合わせて正確に散布できる。また、一定の散布幅に固定して使うこともでき、可変モードと固定モードはノブネジををひねるだけで切り替えできる。散布部は、ビニールフィルムとパッカーで前・後・右・左・上の5面をカバー。風速5メートルの中でも飛散なく使え、散布ノズルは上下・回転・水平の各方向に動いて首振りできるため、散布方向は360度調整が可能。
そのほか、(1)散布幅・フレーム幅・ノズル位置・サイドカバー高さ・ハンドル高さ、すべての調整を手動で行うことができ、圃場で工具が必要になって困るようなことはない(2)基本仕様で散布幅を40センチから100センチまで伸縮できる。中央の連結パイプの長さを変えればそれ以上にも拡張が可能(3)総重量は約6キロと軽く、マルチの上にタイヤを乗せてもマルチが破れることはない(4)適応作物はネギ、トウモロコシ、ナス、ブロッコリ、エダマメ、アスパラガス、レタス、サツマイモ、カボチャ、パイン、黒大豆、小菊など、現在でも全国各地の50品目以上で活用されている―などの特徴がある。
単独での除草剤供給源はバッテリー式もしくはエンジン式の背負動噴になるが、同社HPでは、圃場わきを走行するブームスプレヤーのノズル部と複数の作業者(同機)をパイプで結び、複数の畝間を同時作業する様子も紹介されている。
同社は、「一次産業作業機械特注部品製造」をうたっており、様々なニーズに応える企業として技術力を発揮している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ストローチョッパーNSCシリーズ/松山が新発売 |
|
| |
|
|
| |
松山(株)(松山信久社長・長野県上田市塩川5155)はこのほど、麦の残稈処理・緑肥の細断に最適なニプロストローチョッパー「NSC」シリーズを5月から北海道で先行発売、本州では7月から販売すると発表した。従来機の「MECシリーズ」を全面改良し、カッティング軸の安定した高速回転により作業性能が向上、大規模圃場における安定した細断作業が可能となった。3型式をラインアップし、適応トラクタ馬力は55〜150馬力。
NSCシリーズは、作業幅230センチのNSC2300RV(55〜80PS)、250センチのNSC2500V(75〜100PS)、290センチのNSC2900RV(100〜150PS)の3型式をラインアップ。
今シリーズよりカッティング軸やフレームのパイプ径を大きくし、強度とバランス性能が向上。回転時の振動が軽減したことと、Vベルト4本(NSC2900RVは5本)による駆動で、カッティング軸はPTO540rpm時、1944rpmの高速回転を実現。大規模圃場における安定した細断作業が可能となった。また、爪は従来機(MECシリーズ)より硬度を上げたフレールモアを採用し、耐摩耗性が約20%向上している。
取り扱いの面では、シールドの開閉が可能となっている。開度は6段階(デフレクターを付けた場合は5段階)に調節が可能で、固定はロックピン式で工具が不要。シールドの両サイドにガススプリングを採用したことで、片手で楽に開閉が可能だ。さらに、細断物を後方へ均一に飛散させるためのデフレーターは取り外し可能で、様々な条件に対応する。
トラクタへの装着は、クラッチ付きプーリーの採用によりワンタッチ化を実現。JIS標準オートヒッチ(2形)の4L/3L/0Lと、2点クイックヒッチの2Lに対応し、トラクタへの着脱が簡単。また、4L/3L/0Lは格納に便利なキャスター付きスタンドを標準装備している。
【特徴】
(1)カッティング軸はPTO540rpm時に1944rpmの高速回転を実現。
(2)カッティング軸やフレームのパイプ径を大きくしたことで、バランス性能が向上。回転時の振動を抑え、安定した高速回転が可能となった。振動の軽減は機体の破損や故障を防ぎ、より長く使用できる。
(3)ローラの採用で安定した刈高さを実現。ボルトの差し替えで4段階の刈高さ調節が可能。
(4)シールドの開閉にはガススプリングを採用し、片手で開閉が行える。開度は6段階の調節が可能で固定はロックピン式のため工具が不要。
(5)従来機より硬度を上げたフレーム爪を採用し、耐摩耗性が約20%向上した。
(6)高速回転するフレーム爪と、カバー内部に取り付けられたスタティックナイフにより草を粉砕。同時に、ウィンドブレードで風圧を上げることにより粉砕された雑物を勢いよく排出する。爪は自由にスイングする形で取り付けられており、障害物に当った際は衝撃を逃がし、爪や機体へのダメージを防ぐ。
〈仕様〉▽型式=NSC2900RV―2L[Z]▽機体寸法=全長1400×全幅3270×全高1165ミリ▽質量=994キロ▽作業幅=290センチ▽適応トラクタ馬力=73・5〜110・3キロワット(100〜150PS)▽作業速度=3〜8キロ/時▽作業能率=3〜8分/10アール▽爪本数=60本▽刈高さ=0〜12センチ▽爪軸回転数=PTO540rpm時1827rpm▽駆動方式=ベベルギヤVベルト5本掛▽装着方法=2点クイックヒッチJIS2形
〈希望小売価格(税込み)〉NSC2300RV―0L=176万円〜NSC2900RV―2LZ=204万6000円
▽発売時期=北海道2025年5月、本州2925年7月予定
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
除草剤塗布器「電動パクパク」で手の負担軽減/サンエー |
|
| |
|
|
| |
移植器やパイプ抜き差し器などを製造販売する(株)サンエー(滋賀県草津市新浜町431の3)は、大豆やテンサイ圃場、また公園などで難防除雑草を駆除するための除草剤塗布器「パクパクシリーズ」に、モーター駆動方式の「電動パクパクPK89M」をラインアップに追加した。北海道では野良イモの防除にも使用されているという。
従来製品は除草剤を塗布する際に持ち手部分を握り手動で操作したが、ユーザーからの「回数が多いと手が疲れるので電動式にしてほしい」という要望を受け改良した。使用方法は、操作ボタンを押すと、ノズル先端から定量の薬液が泡状となって吐出し、それを雑草の茎葉に塗布する。軽く押す操作で使用でき、握りやすいベンドグリップと体感重量を軽減するリストループが付き、手の負担軽減を追求した。ショートノズルとロングノズルを標準装備し、雑草の草丈に合わせて使い分けが可能。電源は単3電池5個、またはニッカド、ニッケル水素DC7・2ボルト充電池を使用。
〈製品仕様〉
(ロング本体)▽寸法=幅35×長さ860×高さ125ミリ▽重量=475グラム▽薬液ボトル容量=500ミリリットル▽使用薬剤=グリホサート系除草剤タッチダウンiQ▽使用薬量=雑草1株当たり1〜3カ所
▽希望小売価格(税込み)=3万9160円
▽製品問い合わせ=同社(TEL077・569・0333)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
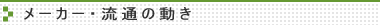 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ふくいスマート農業推進大会開催/NOSAI福井など |
|
| |
|
|
| |
スマート農業の導入を推進する「ふくいスマート農業推進大会」が12日、福井県産業会館(福井市)で開催され、35の団体や農機メーカーがブースを出展、農業従事者など約400人が訪れた。
開会に先立ち、福井県副知事・鷲頭美央氏は「県では令和元年からスマート農業の推進を始め、導入面積は今年度末までに7600ヘクタールを見込んでいる。スマート農業は、農業に携わる多様な人材の裾野を広げる。今回は女性農業者の活躍を通じてスマート農業の推進について考えることをテーマとし、更なる経営の発展と新しい可能性の発見につながることを期待している」と挨拶した。
同副知事が述べたようにステージに女性の農業者が登壇し、どのようなスマート農機を仕事に活用しているかを紹介するコーナーなども設けられた。
主催に名を連ねる福井県農業共済組合(NOSAI福井)は、県内全土をカバーするRTK基地局を運営しており、それを利用したスマート農機のデモンストレーションも会場の屋外広場で行われた。
まず各販売会社がトラクタなどの大型機を実演した。ヤンマーアグリジャパン(株)は直進アシストトラクタ「YT357RJ」を使用し高度な機能性をアピールした。
また、(株)北陸近畿クボタはトラクタ「SL350GS」にRTKアンテナを装着し、三角コーンの間を手放し運転で進むパフォーマンスなどを披露。
そして(株)ISEKIJapan関西中部カンパニーは、田植機「PRJ8」とロボットトラクタ「TJV985R3」で無人運転やリモコンによる操作を実演した。
ドローンのプロモーションにも力を入れており、ステージでは機体を展示しながらプレゼンテーションが行われ、屋外ではデモフライトも実施された。デモフライトはヤンマーアグリジャパンをはじめ、(株)NTT e―Drone Technology、(株)石川エナジーリサーチなどが自動航行などの機能性をアピールし、見学した人たちが熱心にスタッフに質問する姿が見られた。
会場にいた県の担当者に話を聞いた。
農林水産省が2020年に発表した農業センサスによれば、福井県の販売農家数は約1万戸。いずれ最新の農業センサスが発表されるが、農家数は約30%以上の減少が見込まれているという。県では農家数が減少しても農地を確保し、生産額を維持することを目的としており、スマート農業を推進することで規模を拡大する農家をサポートしている。
また、スマート農機による軽労化は女性の活躍に合致すると考え、女性農業者を応援する取り組みも推進しているとした。
同担当者は「農業が法人化して従業員を雇うという流れになったのはここ10年ほど。それまでは家業という色合いが強く、女性は雑用をし、男性がトラクタなどの機械を操作するという風潮で、他分野に比べ女性の参入は遅れをとっている。しかし、今後はいかに農業従事者を増やすか、または減少を食い止めることが課題なので、女性の活躍は重要だ」と述べた。
同イベントは今年で5回目となるが、例年よりも女性の参加者が目立つように感じると同担当者。女性へのサポートが奏功し、農業を盛り上げることにつながれば、と期待をにじませた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ヤンマーブランドアセットデザインを設立/ヤンマーHD |
|
| |
|
|
| |
ヤンマーホールディングス(株)(山岡健人社長)は、さらなるブランド認知、価値の向上を目指し、ヤンマーのブランド・デザインノウハウを活用したコンサルティング、およびブランドコンテンツ・アセットの創出、開発を行う新会社「ヤンマーブランドアセットデザイン(株)」を4月1日に設立する。
ヤンマーグループでは、1959年の誕生以来長く愛されているマスコットキャラクター「ヤン坊マー坊」や2025年4月から地上波での放送が決定しているヤンマーオリジナルアニメ『未ル わたしのみらい』など、ブランディングにつながる多様なコンテンツを有している。
また、トラクタなどの農業機械や建設機械など、世界中で活躍するヤンマー製品も、大切なブランドコンテンツのひとつ。これらのコンテンツをグッズや玩具などに展開し、IP(知的財産)としての価値を高めるとともに、創出したアセットを活用し、ヤンマーが目指す「わくわくできる心豊かな体験に満ちた社会」の実現に向けたさまざまな取り組みを進めていく。
〈新会社概要〉
▽会社名:ヤンマーブランドアセットデザイン(株)▽所在地:大阪府大阪市北区茶屋町1の32YANMAR FLYING―BUILDING▽代表取締役:長屋明浩▽設立日:2025年4月1日▽事業内容:(1)グループ内外へのブランドコンサルティングおよびデザインコンサルティング(2)ヤンマープロダクトやキャラクターなどのブランドコンテンツ・アセットの活用、開発(3)ヤン坊マー坊、未ルなどのキャラクターグッズ、トラクタ・建機などのプロダクトグッズの企画など▽持ち株比率:ヤンマーホールディングス(株)100%
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
RAKUtAをリニューアル/クボタ |
|
| |
|
|
| |
(株)クボタ(北尾裕一社長)の子会社である(株)クボタクレジット(田中伸明社長)は、WEBサイトからトラクタなどの農業機械のリース契約を申し込むことができるサービス「RAKUtA(ラクタ」について、対象商品のラインアップを大幅に拡充し、リース期間を選択可能にするなど、より便利に利用できるようリニューアルした。
同社では今回の刷新の背景とねらいについて次のように述べている。
クボタでは、多忙な農業従事者が時間や場所を問わずに農機のリース契約を申し込みできるよう、2024年3月にリース申込サービス「RAKUtA」を開始した。利用者から多くの申し込みや問い合わせをいただく中で、対象商品のラインアップ拡充への要望をいただいた。この度、ラインアップの拡充に加え、リース期間の選択も可能にすることで、さらなる利便性の向上を図り、利用者のニーズに寄り添った多様な農業機械導入方法の提案を一層強化していく。
〈リニューアルの内容〉対象商品のラインアップ拡充=トラクタは、従来の1シリーズから13・5〜106馬力までの11シリーズへとラインアップを大幅に拡充した。また、新たに田植機とコンバイン(各1シリーズ)を追加した。
〈リース期間の選択が可能に〉
利用者のニーズに合わせ、リース期間の選択が可能になった。トラクタは4〜7年、田植機・コンバインは4年または5年から選べる。
〈「RAKUtA」(ラクタ)についてその他の特徴〉WEBサイトから、商品の詳細やリース料金、概算納期が確認できる。顧客自身でリースの申し込み手続きが行える。製品や契約についての質問や相談は問い合わせフォームや専用電話から可能。農業機械の納品やアフターサービスはクボタのディーラー・販売店が対応する。
リース期間終了後は、顧客が「残存価格にて買い取り」か「物件を返却」を選択できる。詳しくは下記URLへ。
https://webshop-agriculture.kubota.co.jp/
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
2025年の農政と農機関係の注目事業/クボタWEBセミナー |
|
| |
|
|
| |
(株)クボタ(北尾裕一社長)は5日、「2025年の農政と農業機械関係の注目事業」と題したWEBセミナーを開催した。同社機械統括本部兼担い手戦略推進室の半田淳氏が「改正食料・農業・農村基本法」の概要と「スマート農業技術活用促進法」の概要について説明。2025年の主要な農業機械関係の補助事業を紹介した。セミナー要旨は次の通り。
◇
「食料・農業・農村基本法」は、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図ることを目的に、農政の基本理念と政策の方向性を規定しており、「農業の憲法」とも称されている。1999年の制定後、初の改正となり、日本の農業は大きな転換期を迎えている。
今回の改正では、世界の食料需給、環境問題、日本の農業就業人口の減少などを背景に、基本理念を見直し、関連する基本的施策が定められた。
国民一人ひとりの「食料安全保障」を基本理念の中心に据え、「環境と調和のとれた食料システム」を新たな基本理念に加えた。▽人口減少下における農業生産の方向性▽農村の地域コミュニティの維持▽「食料システム」の位置付けと関係者の役割―を明確化し、改正基本法に基づく食料・農業・農村基本計画を策定。
基本法は具体的な規制や制度を定めるものではない。理念や施策の具体化は個別の法令に基づく制度や予算事業によって推進される。これから策定される基本計画や関連予算がより重要となることを留意しておきたい。
今後注目すべき動きを6つ紹介する。
(1)食料・農業・農村基本計画の策定(今年3月まで)。基本法の理念実現に向けた施策展開のプログラム、果樹振興基本計画等関連計画の改定。
(2)各地における地域計画の策定(同)。今後、地域計画実現に向けた取り組みを強化。
(3)合理的な価格形成に関する仕組みの法制化(今年度中の法案国会提出を予定)。合理的な費用を考慮した価格形成のため、認定団体による指標作成、関係者の努力義務などが検討されている。
(4)土地改良法制の見直し(今年2月に国会提出済み)。基幹的用排水施設の更新手続きの簡素化など。
(5)水田政策の見直し(2027年目途)。
(6)環境関係交付金の見直し(同)。
次に「スマート農業技術活用促進法」について説明する。農業者減少等の農業を取り巻く環境変化に対応して、農業の生産性向上を図るため、▽開発供給実施計画▽生産方式革新実施計画―の2つの認定制度を創設。
「開発供給実施計画」とは、スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画のことで、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等の開発及び当該スマート農業技術等を活用した農業機械等またはスマート農業技術活用サービスの供給を一体的に行う。
「生産方式革新実施計画」は、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産方式の導入に関する計画で、スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産方式の導入をセットにして相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させる必要がある。
▽法律に金融、税制等のメリット措置が規定されている▽ポイント加算等の優先採択等の優遇措置が受けられる―といった計画の認定メリットがあり、生産方式革新実施計画を策定して農林水産大臣の認定を受ける必要がある。
生産方式革新実施計画におけるスマート農業技術は次の(1)〜(3)までに適合した技術と規定。
(1)農業機械、農業用ソフトウエア、農業用の器具並びに農業用設備または農業用施設を構成する装置、建物及びその附属設備並びに構築物に組み込まれて活用されるものであること。
(2)情報通信技術(電磁的記録として記録された情報を活用する場合に用いられるものに限る)を用いた技術であること。
(3)農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断または動作に係る能力の全部または一部を代替し、補助し、または向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減または農業の経営管理の合理化を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するものであること。
新たな生産方式の導入とは、スマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じて次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生産方式の導入に取り組むものと規定されている。
(1)スマート農業技術を活用した作業効率の向上に資する圃場の形状、栽培または飼養の方法、品種等の導入。
(2)スマート農業技術の活用による機械化体系に適合した農産物の出荷方法の導入。
(3)スマート農業技術で得られるデータの共有等を通じた有効な活用方法の導入。
次に2025年の主要な農業機械関係の補助事業について。農業機械導入が可能な農林水産省補助事業のうち、一般の農業者でも取り組みやすい事業を3つ紹介する。
1つ目は「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業」。農業者の高齢化・減少が進む中で農業の持続的な発展を図るため、スマート農業技術の現場導入と生産・流通・販売方式の転換、これを支える農業支援サービス事業体の育成や活動の促進等の取り組みを総合的に支援する。
スマート農業の普及に向けた100億円の大型予算であり、新規に開始する人だけでなく、すでに事業を行っている人もサービス拡大の目途であれば対象になる。
農作業の受託は農業支援サービスの一種であり、個人の事業者にとっても取り組みやすい。▽専門作業受託(農作業受託)▽機械設備供給(リース・レンタル)▽人材供給▽データ分析―といった農業支援サービスがある。
サービスに利用する農業機械は、スマート農機か否かにかかわらず半額補助で、スマート農機を導入する場合は補助上限がアップ(補助上限額は事業タイプ等により1500万円、3000万円、5000万円)。農業支援サービスに必要な農業機械と一体的に導入するセーフティローダー等の専用運搬車も補助対象。 なお、この事業は3月14日まで広域型の第2次公募が行われた。予算の執行状況によっては第3次以降の募集も想定される。地域型については各都道府県に問い合わせを。
2つ目は「農地利用効率化等支援交付金」。事業要望調査の、国への提出期限は過ぎたが、来年度以降の申請準備の参考に説明する。
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援するとともに、農地引受力の向上等に取り組む場合の支援を充実させる。個人経営者も活用でき、トラクタ、田植機、コンバイン等全ての農業機械が対象。補助上限は、地域農業構造転換支援タイプが1500万円。融資主体支援タイプが300万円(目標年度の経営面積により600万円)。
3つ目は「新規就農者総合対策のうち経営発展支援事業」。49歳以下で新規就農する人の就農後の農業機械等への初期投資の取り組みを支援する。全ての農業機械が対象で、本人負担は4分の1(国2分の1、県4分の1、本人4分の1)。本人負担分について金融機関からの融資を受けていること。国費上限500万円(経営開始資金交付対象者は250万円、地域計画早期実現支援枠は600万円)。
このセミナーのアーカイブ配信視聴はこちら。 https://agriculture.kubota.co.jp/event/webinar/20250305-nousei/archive.html
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
組織改正も/三ツ星ベルト・4月1日付人事 |
|
| |
|
|
| |
三ツ星ベルト(株)(池田浩社長・兵庫県神戸市長田区浜添通4の1の21)は、2025年4月1日付の人事異動及び組織改正を内定した。
組織改正は、同社が掲げる2030年度の「ありたい姿」の実現に向け、機能の強化と効率化を目的に行う。内容は以下の通り。
(カッコ内は旧職、敬称略)
【執行役員の異動】
▽執行役員コーポレートコミュニケーション本部長(執行役員社長室長)=辻政嗣
【部門長人事】
▽コーポレートコミュニケーション本部社長室長(社長室秘書広報担当次長)=山口兼司▽コーポレートコミュニケーション本部IR企画室長(サステナビリティ推進室次長)=森永拓次郎▽コーポレートコミュニケーション本部サステナビリティ推進室長(サステナビリティ推進室長)=後藤和生▽産業資材営業本部海外営業推進室長(産業資材営業本部長付部長職位)=安尾孝雄
【組織改正】
社長室及びサステナビリティ推進室を統合し、「コーポレートコミュニケーション本部」を新設、産業資材営業本部に「海外営業推進室」を新設する。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
「神刈RJ1016」新発売記念キャンペーン/アテックス |
|
| |
|
|
| |
(株)アテックス(村田雅弘社長・愛媛県松山市衣山1の2の5)のハイブリッドラジコン草刈機「神刈RJ1016」はプロ仕様として、刈幅1016ミリ・最高時速5キロで広い範囲をスピーディーに刈取りできるため、草刈り作業の効率化・省力化の実現に貢献。発売以来多くのユーザーから好評を得ている。
同社は、これから本格的に稼働する季節に合わせ、4月1日より「神刈RJ1016新発売キャンペーン」を開催する。
期間中に「神刈RJ1016」を購入した人にもれなく、草刈り後の機械清掃や圃場清掃に役立つ、ブロワをプレゼントする。ブロワは純正バッテリーと充電器付きで、吹き飛ばしと吸引どちらにも対応できるもの。重さ1・4キロ、長さ505ミリで、電圧10・8ボルト、最大風量2・6立方メートルと高性能の本格ブロアとなっている。
ハイブリッドラジコン草刈機「神刈RJ1016」は、刈幅が1016ミリと、より広い刈幅を実現。刈幅だけでなく最高速度も時速5キロとアップし、作業効率が従来の2倍以上となった。従来モデルの良さは各所に継承しながら、同機はガードチェーンと防水プロポが標準装備となっている。また、クローラ接地長を1・175ミリに設定したことで安定した走行を実現し、オペレータがストレスのない、快適な作業を行えるようになった。
神刈アプリに対応しており、緊急時にはスマホでの走行操作が可能となる。
傾斜地では最高速度を自動調整し、作業場所の角度に応じて3段階で調整される。神刈は会社や工場の緑地管理などに使用されることが増えており、草刈り作業をより安全に、より効率的に行える草刈機として期待されている。
〈主な仕様〉▽機体寸法=長さ1890×幅1450×高さ995ミリ▽機体重量=660キロ▽刈幅=1016ミリ▽刈高=35〜240ミリ▽使用最大傾斜=45度▽最高速度=時速5キロ▽最大出力=20・8馬力(ネット値)▽エンジン=カワサキFS691V搭載
〈キャンペーン概要〉
▽期間=2025年4月1日〜6月30日
▽内容=対象商品購入者に「ブロワ(純正バッテリー&充電器付き)」をもれなく1台プレゼント
▽対象商品=ハイブリッドラジコン草刈機「神刈RJ1016」
キャンペーン及び製品に対する問い合わせは、同社(TEL089・924・7162)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
新社長に松下高士氏/大竹製作所 |
|
| |
|
|
| |
(株)大竹製作所(愛知県海部郡大治町中島郷仲265)は、2月21日開催の定時株主総会並びに取締役会において、松下高士氏が代表取締役社長に就任した。代表取締役社長の大竹敬一氏は取締役会長に就任した。松下新社長は、大竹会長の甥にあたる。
社長に就任した松下高士氏の経歴は以下の通り。
▽1998年青年海外協力隊音楽隊員としてドミニカ共和国にて2年活動
▽2000年帰国後、武者税理士事務所、奥村税理士事務所勤務
▽2006年監査法人トーマツにて会計監査に従事
▽2013年より独立行政法人国際協力機構ベトナム事務所にて企画調査員として勤務。産業・人材育成を担当
▽2018年大竹製作所入社、取締役就任
▽2025年代表取締役社長に就任。
1976年生まれ、49歳。
松下氏は社長就任にあたり「農家の高齢化と離農が進みつつある中、国内中小稲作農家向けに農業機械を生産販売する弊社は非常に厳しい環境にある。しかし米作りを中心とした農業は、我が国の文化や生活に根差した重要な産業であると、米価高騰の影響の大きさからも再認識した。農業を支え、継続可能な事業体制への変革を進めたい」と抱負を述べている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
レーザー除草ロボを参考出品/フタバ産業 |
|
| |
|
|
| |
フタバ産業(株)(魚住吉博社長・本社=愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1の1)は、11〜14日に東京ビッグサイトで開かれたみどりの食料システムEXPO2025に出展。施設園芸用の燃焼式暖房機の排ガスに含まれるCO2をリサイクルし、作物の光合成促進のために施用する「アグリーフCO2システム」を紹介したほか、開発中の製品として、「レーザー除草ロボット」「エネルギー循環システム」を参考出品した。
「レーザー除草ロボット」は、畝立て後1〜2週間で表層に出てくる雑草をAI画像処理で識別し、雑草の生長点にレーザーを照射して除去する完全自律型の除草機。農薬やマルチを使わず、自動化で人手不足への対応や生産性向上に寄与する。市販は2026年度末を予定している。
「エネルギー循環システム」は、葉や茎などの農業残渣をリサイクルし、施設園芸で活用できるCO2や熱、肥料に活かそうというもの。
2017年に市販を開始した「アグリーフCO2システム」は、夜間に暖房した際のCO2を回収・浄化・貯留し、日中にそれを植物の株元に局所施用する装置。日中も暖房機が稼働している場合は、CO2の貯留と施用が交互に行えるため、より多くのCO2を施用できる。
CO2施用のための燃料費がかからずコストが軽減できるほか、局所施用(灌水チューブを利用)でムダなくムラのない施用が可能になる。また、局所施用のため植物群落内の風通しがよくなり病害の減少が期待できるなどのメリットがある。加えて、暖房機を使わない時期は空気施用(送風)が可能で、年間を通して利用できる、環境・作物・人に優しいシステムとなっている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
チップソー専門、オンラインショップで拡販強化/トリガー |
|
| |
|
|
| |
(株)トリガー(静岡県磐田市匂坂中1600の22)は、チップソー製造に特化したメーカーで、企業への製品供給のほか、オンラインショップなどを通じた自社ブランド製品の拡販にも力を入れている。先に東京ビッグサイトで開かれた除草ワールドに出展し、その幅広い製品シリーズをアピールした。
いまの売れ筋として推奨するのは、(1)雑草刈りや下刈りに適応する「隼(はやぶさ)」(2)笹刈り、小枝刈りにも使える「刈らまいかUタイプ」および(3)「刈らまいか軽量タイプ」など。
(1)は、高い耐久力と飛び石対策を施した高品質チップソーで、刃袋をなくすことで石飛を低減し、超微粒子超硬の採用で、同社比2倍以上長持ちする点が特徴。縁石沿い、フェンス際、道路脇などの狭い場所から、通常の草刈り、下刈りまでオールラウンドに使えるチップソー。
(2)は両端の尖ったU字型のチップを採用したことで秀逸の切れ味を誇り、刃袋をなくすことで草が絡む頻度を最小限に抑えた。また、安全性、作業性を考慮し軽量化台金を使用し、埋め込み型チップおよび日本製高品質銀ロウの採用により、最高品質の強度を実現した。特許取得の特殊形状は、U字型のチップとの相性がいい。また、軽量タイプも同様に高い強度と抜群の切れ味を誇っている。
このほか、直径40〜50ミリの小径雑木まで対応する「やまかりくん」「エコチップソー」「村正(むらまさ)」「斬れすぎ君―山林」、芯が硬いお茶の木の切断を可能にした「おちゃかりくん」などを揃えている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
新動画の配信開始/山本製作所 |
|
| |
|
|
| |
(株)山本製作所(山本丈実代表取締役・本社=山形県天童市、東根事業所=山形県東根市大字東根甲5800の1)は、同社のYouTubeチャンネルで、面白くてタメになるライスセンター情報を随時発信している。
中でも日本各地のライスセンターを紹介する「ライスセンターツアー」は、それぞれのライスセンターの様子や業務の流れ、機器の使い方など様々な情報を提供しており、今後のライスセンターづくりのヒントや、良い発見があると好評を得ている。
このたび同ツアー第29弾目となる、山形県東根市の(株)ティスコファームを取材した動画の配信を開始した。
【取材先概要】
▽社名=(株)ティスコファーム
▽水稲作付面積=30ヘクタール▽乾燥機=50石×4台▽籾すり機=6インチ
今回は、もともと産地直売所だった既設の木造建屋に、乾燥・調製・精米の3ラインをコンパクトに詰め込んだライスセンターを紹介。
既存施設にライスセンターを建てる様子、施設の内部、そしてシリーズ初となる稼働中のライスセンターの様子を紹介するなど、内容盛りだくさんの動画となっている。
詳しくは、山本YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@1918yamamotoSS)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
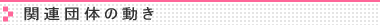 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
スマート農業の展開探る/日農機協が農業機械化フォーラム |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本農業機械化協会(菱沼義久会長)は14日、都内の馬事畜産会館で2024農業機械化フォーラム「スマート農業のこれまでの取組と今後の展開」を開催した。昨年のスマート農業技術活用促進法の施行により同技術の開発や普及が加速される素地が整い、同技術が今後より多くの地域かつ広範な面積での利活用へと展開していくにあたり、これまでの取り組み事例などを検証するとともに、今後の展開方向について検討した。菱沼会長は今後農業と食料安保を進めるにはスマート農業が必要だとし、データ駆動によって農業の経営や生産を変えていくイノベーションが起こるなどと展望した。
開会あいさつした菱沼会長はスマート農業はまさにこれからだと述べ、農業の担い手急減が確実である中で農業と食料安全保障をいかに進めていくのかが最大のテーマになるとし、そこでいよいよスマート農業の出番になると説明。スマート農業は単なる省力化機械ではなく、データ駆動により農業の経営や生産を全て変えていくイノベーションであると語り、期待を寄せた。
次いで来賓として農林水産省技術普及課生産資材対策室長・土佐竜一氏が挨拶。いつでも安く食料が手に入る時代が変わり、様々な環境変化に対応できるよう新しい基本計画を審議していると述べ、スマート農業もその重要な施策の1つであり、現場導入を後押ししていくなどと語った。
続いて講演に移り、ファーム・マネージメント・サポート代表で元農研機構理事の梅本雅氏が「スマート農業の展開と今後の展望」を基調講演。国内の人口動態と農業構造の変化、スマート農業に関する研究の推移を振り返った後、現在の普及状況について、データを活用する経営体が年々増加し、団体経営体では昨年62・7%に達したと説明。日本農業法人協会によると半数以上の法人がスマート農業技術を導入し、特に農薬・肥料散布や生産管理支援システムなど作業・営農支援の関連機器が導入されているほか、水稲作では大規模層でドローンの所有が増えているという。
これを踏まえて、今後の方向性は、省力化を図りつつ収量・品質を向上させると同時に、環境負荷も軽減させる・非熟練者でも効率作業ができる技術対応が求められると指摘。経営で求める効果をいかに達成するかという機器選択が重要になるとし、今後はスマート農機において▽さらなる知能化▽収穫以降の行程を改善する新たな仕組み▽労働安全の推進―などが求められるとともに、技術以外の部分においても農業全体の改善を図るべく▽新たな品種や作目構成、栽培用式、栽培方法の導入など生産方式の革新▽中山間地における圃場の大区画化―などが重要になると強調。スマート農業の推進と合わせて生産方式の革新を同時に実施することが求められるなどと語った。
次いでスマート農業実証事業に取り組む事例など話題提供として、農事組合法人神崎東部農場長・青野雄太氏による「発酵の里 こうざきにおけるスマート農業技術の導入事例」、岩見沢市情報政策課長・谷口正行氏による「産学官連携によるスマート農業の推進」、農業DX推進研究所所長・打田欽也氏による「衛星画像×AI分析で農作物をモニタリング」の3講演が行われた。
パネルディスカッションでは、講師に質疑応答を行った後、北海道大学大学院農学研究院長・教授・野口伸氏が「スマート農業のこれまでの取組と今後の展開」と題して自らの研究紹介を含めた総括コメントを述べた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農作業事故防止の中央推進会議を開催/日農機協 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本農業機械化協会(菱沼義久会長)は14日、都内中央区の馬事畜産会館にて、令和6年度農作業事故防止中央推進会議を開催した。
「農作業での熱中症を防ぐには」をテーマに掲げて、国内全般の熱中症対策に関する情報共有を図るとともに、農業における熱中症対策の高度化に資するため、農作業事故対策の関係者による同推進会議を実施した。
冒頭、あいさつした菱沼会長は、農作業死亡事故のうち熱中症による死者は年間30人程度と増加傾向にあり、対策が重要になっていると指摘。また、先に報道された厚生労働省による職場の熱中症対策の義務化について触れ、農業法人も対象になるため、今後情報収集のうえ発信していくなどと意向を示した。
次いで農林水産省農産局技術普及課課長補佐・土岐俊雄氏が来賓挨拶を行い、令和5年の農作業事故死亡者数は236人と前年比2人減だったものの、熱中症による死亡者は37名と同8名増えており、国としても現場の取り組み事例を紹介しながらしっかりと事故防止の対策をしていくなどと語った。
その後、6講演が行われた。土岐氏は「農業の熱中症被害と農林水産省の取り組み」を講演。5年の農作業死亡事故における15・7%が熱中症であり、機械・施設以外の作業に係る事故で最も多くなっていると指摘。日本の夏季の気温が上昇傾向にあり、それとともに熱中症も増加していることから、機械とともに農作業安全対策を考えていく必要があると述べた。そこで同省では7年度農作業安全対策推進方針において、5〜7月を熱中症対策研修の実施強化期間に位置付け、既存の集会などに熱中症に係る内容を追加する「+熱中症対策」の研修を進めていくなどとした。
一方、日本農業機械化協会指導部長・東城清秀氏は「熱中症対策アイテムの農業機械士によるモニター調査」と題して、昨年実施した同調査の結果概要を報告。
報告によると、全国の農業機械士協議会に協力をあおぎ、全国14府県の農業機械士27名に7月から60日間連続で熱中症対策アイテムを身に着けてもらった。対策アイテムは(1)ファン付き作業服または(2)冷却ベスト(3)ネッククーラー(4)カナリア(深部体温を推定し熱中症リスクを警告する機器)など。
その結果、(1)は重さが割とあるものの、涼しく使いやすい、快適などと高評価を得た。(2)は使用開始時は涼しいが長時間もたない、身体全体を冷却できないなどのコメントがあった。また、作業別でみると、草刈りや稲刈りなどが作業時間が長く、(4)の警報が鳴る回数が多かったなどと示された。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
広がる農の安全教育/農業技術革新フォーラム分科会 |
|
| |
|
|
| |
農研機構、経団連、日本農業法人協会は3月21日まで「農業技術革新・連携フォーラム2025」をオンラインで開催した(既報)。同フォーラムでは12日、分科会「農業の安全教育の現状と課題」をWeb開催し、事前に150人以上の視聴登録が集まった。
分科会では、▽農業者教育の推進に関する方針と施策(農林水産省農産局技術普及課生産資材対策室・土岐俊雄氏)▽農作業事故体験VRを活用した体験型教育について(全国共済農業協同組合連合会全国本部農業・地域活動支援部・和泉崇之氏)▽実機を用いた体感型教育((株)クボタ農機国内アフターマーケット事業推進部・稲垣勇一氏)―の3講演及び総合討議が行われた。
そのうち、稲垣氏はクボタの農作業安全教育の取り組みとして、(1)実機を用いた大型トラクタの死角体験(2)トラクタ傾斜角装置を用いた転倒角体験(3)ミニチュア農機を用いた模擬体験(4)VRゴーグル活用研修―などを紹介。北海道農作業安全運動推進本部のオホーツク地区本部が主催した研修会において、クボタ及び北海道クボタが実施した実機研修を紹介した。
(1)実機を用いた大型トラクタの死角体験では、135馬力の大型トラクタに実際に乗ってもらい、座席の前方及び左後方に設置した子供パネルがどの程度見えるか体験してもらった。これにより、予想以上に死角があることを確認してもらい、「もしこの死角に子供や孫がいたら」と想像をめぐらせ、見える範囲の予測と実測との差異を考察したという。この体験については、比較的準備するものが少なく手軽に行えると説明した。
また、(2)は小型トラクタがゆっくりと右側に傾斜するトラクタ傾斜角装置を用いて、傾斜角20度までを体験。7度あたりからシートから尻が浮く感覚を体験できるという。実作業においては作業機がついており、走行面の凹凸や加速度もあることから、傾斜角20度では実際に転倒するという危険をリアルに体験できるものとなっている。研修では「実作業において傾斜角20度は危険行為であり、常にシートベルト装着が必須である」と説明。また、ボンネットとトラクタ後方にスマホ角度計を設置し、体験角度をリアルタイムで目視可能にする工夫も施した。
その他、(3)全ての農機を準備することは難しいため、16分の1スケールのミニチュア農機を用いて、実際に起こったトラクタ横転事故を再現したり、(4)VRゴーグルを活用した乗用型トラクタ転倒の疑似体験などを行い、受講者により多くの事故事例をリアルに伝える研修を進めた。稲垣氏は農作業安全は農業経営の土台であるとし、グループ一丸となって今後も邁進していくとした。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
クボタに学会賞/日本機械学会 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本機械学会(山本誠会長)は14日、2024年度日本機械学会賞などの受賞者を決定した。農機業界からは、日本機械学会賞(技術)に「無人自動運転コンバインの開発」で(株)クボタの林壮太郎、藤田敏章、吉田脩、湯浅純一、江戸俊介の各氏が選出された。日本機械学会奨励賞(技術)に「内燃機関におけるアンモニア燃焼技術の開発」でヤンマーホールディングス(株)の松永大知氏が選ばれた。
学会賞などの表彰式は、4月24日午後3時半より都内港区・明治記念館にて開催される同学会の2024年度(第102期)定時社員総会にて行われる予定。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
未来の農担う若手や女性を表彰/未来農業DAYs |
|
| |
|
|
| |
農業の未来を担う若手や女性農業者の優れた取り組みを表彰し、広く社会に発信する「未来農業DAYs」が6日、都内文京区の東京大学弥生講堂一条ホールで開催された(未来農業DAYs実行委員会主催、農林水産省後援)。女性農業者らの活躍を称える「令和6年度農山漁村女性活躍表彰式」及び、農業に関心のある若者の革新的アイデアを表彰する「第9回大地の力コンペ」が開かれた他、今年度は初めての取り組みとして、「未来の農林水産業に向けて―これまでの挑戦、これからの挑戦―」をテーマに受賞者等による取り組み発表・トークセッションも開催された。
開会にあたり主催者挨拶した納口るり子実行委員長(筑波大学名誉教授)は、同会について「農業の楽しさ・奥深さを理解してもらうための取り組みの1つ」と位置づけた。そのうえで、分かりにくい・排他的とみられがちな農林水産業界において、実際に携わる人々は国民に理解してもらおうと様々な取り組みを行っていることを踏まえ、本会にて第一線で活躍されている関係者や今後農林水産業を活性化するであろう応募者を表彰すると述べ、本日の開催により農林水産業や関連産業がさらに輝かしい発展を遂げることを願うなどと期待を寄せた。
続いて「令和6年度農山漁村女性活躍表彰」表彰式及び審査委員講評、受賞者等による取り組み発表・トークセッション、「第9回大地の力コンペ」のファイナルプレゼンテーション、コンペ結果発表などが行われた。農山漁村女性活躍表彰のうち、農林業関係の受賞者は次の通り(敬称略)。
【農林水産大臣賞】(1)女性地域社会参画部門/徳永順子(個人、福岡)、大田原市農業委員会(組織、栃木)▽(2)女性活躍経営体部門/農業生産法人(株)よしだや(青森)▽(3)若手女性チャレンジ部門/小林千歩(栃木)
【経営局長賞】(1)/横田友(個人、埼玉)、公益社団法人大野市シルバー人材センター(組織、福井)▽(2)/(株)カネイファーム(徳島)▽(3)/和田梢(大分)▽(4)地域子育て支援部門/ONE SLASH(株)(滋賀)
【林野庁長官賞】(1)/特定非営利活動法人SCR(組織、宮城)
【全国農業協同組合中央会長賞】(1)/佐藤美登子(個人、北海道)
【農山漁村男女共同参画推進協議会長賞】(1)/福嶋求仁子(個人、熊本)、三浦悦子(個人、宮城)、山梨きら星ネット(組織、山梨)▽(2)/(株)アグリシアJAPAN(千葉)▽(3)/合同会社十色(埼玉)
受賞内容の一部をみると、大臣賞を受賞した徳永氏は、2002年に農業委員、2016年に福岡県内で女性として2番目となる農業委員会会長に就任。遊休農地を解消するため、景観作物である菜の花栽培を推進、その菜の花を利用した「菜の花オイル」を地元JAへ働きかけて開発した。また、2013年には市の環境審議会委員に就任し、生ごみをメタン発酵するバイオマスセンター「ルフラン」で生成される液肥の農業への活用を進め、資源循環のまちづくりに寄与した。
さらに2022年からは、土地改良区理事に就任し農地中間管理機構関連農地整備事業を活用して、全国屈指の約60ヘクタールの大規模区画整備に取り組み、地元特産品「山川みかん」の産地承継に尽力していることなどが高く評価された。
審査委員長の岩崎由美子氏による講評では、令和6年度事業は16道府県及び9市町村、17団体から計35事例の応募があり厳正な選考を行ったと説明。最優秀賞など受賞者の取り組みを紹介したうえで、紹介した事例以外にも素晴らしい活動が数多くあり、農業・農村の持続性を高める上で女性たちの取り組みはかけがえのない価値を生み出しており、こうした取り組みを広く発信していくことの重要性を改めて認識したと女性農業者の活躍を褒め称えた。
その後、取り組み発表・トークセッションならびに「第9回大地の力コンペ」などを開催。未来の農業の中心となる若者・女性の活動やアイデアを広く発信した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
炭素貯留量の簡便算出法を開発/農研機構 |
|
| |
|
|
| |
農研機構は12日、日本産業規格の分析値を活用して、バイオ炭の農地施用による炭素貯留量を簡便に算出する手法を開発したことを発表した。秋田県立大学、立命館大学、和歌山県工業技術センターとの共同研究によるもの。同手法により、原料の種類に関係なく炭素貯留量を簡便かつ正確に計算でき、バイオ炭の普及促進や炭素クレジット創出の効率化が期待されるとしている。
バイオ炭は、バイオマスを燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350度C以上で加熱して作られた固形物。バイオ炭の施用による土壌の炭素貯留量の増加は、CO2削減のクレジット化の手段としても注目されているものの、これには土壌へ施用する炭素量に加え、炭素の固定効果を評価する必要がある。従来の土壌炭素貯留量の算出手法は、投入バイオ炭の重量、同バイオ炭の有機炭素含有率及び100年後の炭素残存率を用いて計算するが、用いる原料の種類や炭化温度によってこれらのデフォルト値が異なるほか、炭化温度が不明なものの場合はデータを取得するために元素分析などの測定が必要となり、時間と費用がかかっていた。
その点について、今回開発した新手法では、元素分析を行う代わりに、石炭の品質評価に用いられる日本産業規格(JIS M 88126)を応用し、バイオ炭の工業分析値を用いて、炭化温度や農地施用による炭素貯留量を算出する。この手法のJISに基づく工業分析は日本国内の公的機関で実施可能であり、測定精度が確保されている。さらに、この算出式を原料ごとに研究機関等が作成・共有することで、バイオ炭の品質評価プロセスの効率化が進み、結果としてバイオ炭による炭素クレジット創出の効率化も期待される。
農研機構は同手法は国内で未利用の農業残渣などを原料としたバイオ炭の評価だけでなく、アジア地域における多様なバイオマス資源への適用が期待されるとした。これにより、バイオ炭の施用が持続可能な資源循環や温室効果ガス削減の促進に一層寄与することが見込まれる。一方で、同手法は現時点では正式なクレジット計算方法として採用されていないため、今後、J―クレジット運営委員会への提案・議論を進めることが重要になるなどとしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
畑作体系の可変施肥でスマート農業技術検討会/北海道農業研究センター |
|
| |
|
|
| |
農研機構北海道農業研究センターは11日、オンラインで令和6年度スマート農業技術検討会「畑作体系における可変施肥」を開催した。農林水産省によるスマート農業実証プロジェクトの成果の横展開を進めるべく、畑作体系における可変施肥について同プロジェクト終了後も継続して取り組んでいる事業者などが実証の成果や普及に関する情報提供を行った。
開会あいさつした農研機構みどり戦略スマート農業推進室・川嶋浩樹氏は、250名以上の参加登録があったことに謝意を述べた後、令和元年度からスタートした同プロジェクトでは全国217地域で実証が行われたが、本日はこれらの実証成果の社会実装を加速する目的で実証事例や普及に関する情報を共有すると趣旨説明。本日の議論が、環境負荷低減や農業者減少など地域の課題の解決の一助になることを願うなどと語った。
次いで講演が行われた。まず同機構同推進室・長澤幸一氏が「『スマート農業実証プロジェクト』における畑作体系の可変施肥実証の事例」の全体概要を説明。可変施肥実証は概ね北海道にて行われ、可変施肥ブロードキャスタの活用が多く、作目は小麦やキャベツ、玉ネギなどであったとした。一方で畑作の可変施肥は地形や礫、輪作体系などの影響により、水田に比べて難しいとの声があり、作業面積の拡大や可変施肥機以外のスマート農業技術との組み合わせなどの検討が必要などと示した。
一方、(株)ズコーシャ・横堀潤氏は「北海道における窒素肥沃度のセンシングによる可変施肥」と題して、鹿追町で行った実証について報告。土壌中の窒素肥沃度の高低が作物生育に影響することから、ドローンによる圃場の撮影画像データと、実測の熱水抽出性窒素を照合して肥沃度を計測し、さらに堆肥や残渣などの有機物施用履歴を掛け合わせて、土壌肥沃度ベースの可変施肥マップを作成。同マップをもとに施肥設計を行い、ブロードキャスタにて可変施肥を行ったところ、テンサイ・バレイショともいずれの圃場でも減肥かつ増収を達成できた。特にテンサイでは、肥料55%減かつ収量10・3%増を達成した圃場もあったという。コスト面もこれら可変施肥を実施したことにより、肥料削減と増収により、10アール当たりで平均1万5612円の経済効果があったとした。 さらに同社は、可変施肥効果の高い圃場の識別方法として、圃場の衛星画像を使用して、表層の土壌腐食含量並びに作物生育を示すNVDIとの相関を検討し、可変施肥効果が高い圃場を抽出する方法を開発したなどと紹介した。
その他、JAつべつ・有岡敏也氏による「北海道における小麦、玉ねぎの可変施肥実証〜土層改良施工との組合せによる効果〜」、滋賀県農業技術振興センター・片山寿人氏による「滋賀県における大麦の可変施肥実証および最近の取り組み」などの報告と、北海道から道内の畑作地帯の可変施肥の普及について、農林水産省からスマート農業推進について情報提供が行われた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
米価上昇受け入れ/日本政策金融公庫が米の購入意向調査 |
|
| |
|
|
| |
(株)日本政策金融公庫は13日、先に実施した「消費者動向調査(令和7年1月調査)」のうち、特別調査「米の購入について」の結果を取りまとめて公表した。同調査は今年1月、全国の20〜70代の男女2000人を対象にインターネット経由で行ったもの。
調査結果によると、令和6年8月以降の米の価格上昇に対する考えは「価格上昇には納得していないがやむを得ない」46・1%が最も高く、次いで「価格上昇は厳しいが納得している」28・1%、「大きな影響はなく気にしていない」14・5%、「価格上昇は受け入れられない」11・3%となった。年代別にみても、全ての年代で「価格上昇には納得していないがやむを得ない」が4割を超えて最多となっている。
また、昨年秋以降の家庭における米の購入量については、米不足が話題となる前の昨年7月以前と比較して「変化していない」64・7%が最も高く、次いで「減少した」16・6%、「一時的に減少したがもとに戻した」9・7%の順となった。同居家族人数別では、「減少した」と回答した割合は「1人暮らし」で22・0%と最も高くなった。
米の購入量が「減少した」と答えた人に減少がどのような形で生じたか尋ねたところ、「米を食べる頻度を減らした」(72・6%)が最も高かった。米を減らした代わりに食べる量や頻度を増やした食品があるか尋ねたところ、「めん類」(60・8%)が最も高く、次いで「パン」(54・1%)の順となった。
また、米の価格上昇を「気にしていない」「納得している」と答えた人にその理由を聞いたところ、「米を食べることが習慣になっているから」42・5%とした割合が最も高く、次いで「米を食べることが好きだから」35・5%、「物価上昇により米以外の他のものの値段も上昇しているから」28・4%の順となった。
米の生産者に期待することについて聞いた質問では、米の生産について、今後生産者に期待することは、「より安心・安全な米の生産が行われること」51・2%が最も高く、次いで「よりおいしい米の生産が行われること」31・9%、「米不足にならないよう生産量を増やすこと」29・0%の順となった。
また、米にまつわる生活全般の質問については、米を食べる頻度は「1日2食」43・0%が最も高くなった。年代別では、「1日3食」は20代で最も高く「1日1食」は70代で最も高くなった。米の購入手段については、「スーパーや生協の店舗で購入」69・2%が最も高く、次いで「農家から直接購入」17・2%、「ドラッグストアで購入」16・5%―などの順となった。
また、米を購入する際、どのようなことが決め手になっているかを尋ねたところ、「価格」65・6%が最も高く、次いで「銘柄」39・0%、「産地」29・2%、「精米時期」10・5%―などの順となった。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
20代の農業に対する意識・実態調査/JA共済連 |
|
| |
|
|
| |
JA共済連(村山美彦代表理事理事長)はこのほど、農作業安全研修実施強化期間にあわせた「20代の農業に対する意識と実態調査」の結果を取りまとめて発表した。全国の20代男女を対象に、昨年11月にオンラインアンケートを行ったもの。
それによると、20代男女1万人に将来農業をやってみたいか聞いたところ、「そう思う」が21・4%、「ややそう思う」が30・6%となり、合計52・1%と20代の約半数が「将来農業をやってみたい」結果になった。特に、効率重視の昨今だが、「タイパ疲れ」を実感している20代では将来農業をやってみたい人が60・2%と多い結果になった。
日常生活の価値観に関する調査では、20代1万人のうち75・6%が「効率性は重要」、74・3%が「タイパ(タイムパフォーマンス)は重要」と回答する一方で、半数を超える56・1%が「タイパ疲れ」を実感。そして、タイパ疲れを感じる20代は、あえて手間をかけたり自給自足をしたり、自然の中で働くことや地方移住への関心が高いことが示された。
「自給自足をやってみたい」回答は、20代全体では41・9%だったのに対して、タイパ疲れの20代は49・7%と自給自足への意向割合が高い。また、「自然の中で働きたい」も全体が40・9%だったのに対してタイパ疲れの20代は48・9%。「地方移住しても構わない」も全体47・6%に対してタイパ疲れの20代は53・3%となり、あえて手間をかけて自分の手で生活し、自然の中で暮らしたいという意向が強くなっている。
次いで、将来農業をやってみたいと回答した20代男女700人(大学生200人、ビジネスパーソン500人)を対象に、農業に対する意識や実態を調査した。彼らに農業の魅力を聞いたところ、「自然と向き合える」38・4%、「自分と向き合える」30・0%、「成果や過程が目に見える」27・6%、「自分なりの創意工夫ができそう」25・6%などが上位の結果となった。JA共済連はこの結果について、「農業をやってみたい20代は、農業が自然と向き合い、自分自身とも向き合うことができる、結果だけでなくプロセスに深く関わり、自分の手で創意工夫していく仕事であることに魅力を感じている」と分析している。
また、将来目指したい農業ライフについて聞いたところ、「農業と自分のしたいことを両立したい」33・0%、「別の仕事をしながら農業をする半農半X的な働き方をしたい」「家族や仲間と協力しながら、家庭的な農業を楽しみたい」がともに28・6%、「地域と連携しながら、コミュニティに貢献する農業を行いたい」22・7%などといった意見が多い結果となった。
実際に何歳ぐらいで農業を始めたいかについては、「40代頃」と答えた人が20・4%と多く、40代までに始めたい人が合計で41・5%と約4割を占めている。
一方、将来、農業を始めることに備え準備として行っていることがあるかを聞くと、「準備あり」56・0%と過半数を占めた。具体的な準備内容としては、「農業に関する情報収集」32・7%や「資金を貯めている」30・4%、「農業をしている人や農業を始めた人からの話を聞く」28・6%、「農業や農業をしている人のブログや動画、SNSなどの定期的な閲覧」26・8%などがあげられ、まずは身近で取り組みやすいことから始めているようであった。
さらに、今後農業について学びたいことを聞くと、「農家経営について」26・6%や「土壌や作物の栽培方法など」24・0%、「起業のための補助金や補助制度など」21・9%などが上位にあがった。「農作業事故の事例や安全対策」について学びたいと答えた人は、17・7%だったが、農作業でのケガや事故を防ぐプログラムを体験したいかと具体的に聞くと、78・9%と大多数が「体験したい」と答えた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
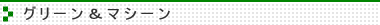 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
安全装備品導入を支援/農林中金助成事業 |
|
| |
|
|
| |
農林中央金庫(奥和登代表理事理事長)は14日、2015年度から林業の労働安全性向上を目的に実施してきた「林業労働安全性向上対策事業」を2025年度も引き続き実施、労働安全対策に取り組む森林組合等を対象に、林業用の安全装備品の一部購入費用の助成を行うことを発表した。上期募集を4月1〜30日、下期募集を9月1〜30日を実施期間として行い、助成対象である(1)一定の防護機能を有する安全装備品(2)熱中症対策商品(ファン付きジャケット等が対象、インナー類は助成対象外)、防虫・防獣用品(3)割賦利用対象商品の購入に対して3割助成で支援していく。
森林組合等に対する林業用安全装備品の購入費用の助成を行う「林業労働安全性向上対策事業」は、2015年度に開始された。安全装備の普及率向上を図ることで、林内作業の安全性向上、林業従事者の安全を確保するのが狙い。2025年度は、「林業従事者が使用しており、1年を目途に消耗・買い替えを要する装備・用品で、直接的な労働安全性の効果が認められるものに限定して3割助成」(農林中金)で実施する。
助成対象となる商品は、チェンソー防護ズボン、同チャップス、同ブーツ、安全靴・安全長靴・安全地下足袋、林業用ヘルメット、林業用手袋、林業用ジャケットなどの装備品をはじめとして、かかり木処理器具・伐倒補助器具、その他労働安全性向上に資する用品から、防中・防獣・救急用品、熱中症対策および防寒用品などの各種用品に拡充されている。
農林中金によると、2015〜2023年度までの9年間で合計4266件、7億700万円の助成が実施されており、林業の安全性向上はもちろん、伐倒補助器具などの普及による労働環境の改善に大きく貢献している。
この助成事業の実施前である2014年度と比較すると、チェンソーなどの起因による「切れ・こすれ」事故はマイナス195件と減少。また、2019年8月からは下肢防護衣の着用が義務化されており、防護ズボン、チャップスを助成対象とする同事業へのニーズも高まっている。
このように同事業での効果が認められ、林業における労働災害の発生率(死傷年千人率)は低下傾向にあるものの、依然として全産業の平均である2・4と比較すると高い水準にあることから、「林業従事者の確保のためにも労働安全性の向上は必須の課題となっている」(同)として、助成事業の役割を確認している。
申請書の送付先は、申請者が組合の場合は各都道府県森林組合連合会(東京都森組、大阪府森組を除く)、連合会の場合は全森連。直接助成は、農林中央金庫営業企画部森林グループあてとなっている。
事業に対する問い合わせは、Eメールでshinrin_eigyodai5@nochubank.or.jpまで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
林業イノベーション現場実装シンポジウムの動画を公開/林業機械化協会 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人林業機械化協会(島田泰助会長)はこのほど、2月5日に開催した「令和6年度林業イノベーション現場実装シンポジウム」の動画公開を開始した。同協会ホームページにアップしている。別掲のURLを入力すると視聴することができる。
2月5日に行われた令和6年度の同シンポジウムは、第1部=木質系新素材の開発・実証の現状、第2部=林業機械の開発・実証、第3部=新しい林業経営の事例、第4部=パネルディスカッションの4部構成。それぞれ現在進められている事業での成果、機械開発の現状や今後の展開などが報告された。
また、ファシリテーターに酒井秀夫氏(東京大学名誉教授)、パネリストに宇都木玄(森林総合研究所研究コーディネーター)、佐川賢司((有)佐川運送代表取締役)、辻佳子(東京大学教授)、坪野克彦((株)フォレスト・ミッション代表取締役)、山田壽夫(一般社団法人日本木材輸出振興協会会長)の5氏を招いて行われたパネルディスカッションでは、「―技術は林業の未来を変えるか―」テーマに、現代林業における技術の果たす役割を掘り下げた。
各部のURLは次の通り。
【第1部】 https://youtu.be/C_Xa-VT5MeY
【第2部】 https://youtu.be/7JV1w6NhnjM
【第3部】 https://youtu.be/cVMstXpGItY
【第4部】 https://youtu.be/fLb0ySCOmK4
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
「創意工夫」表彰行事、大江町光林会に優秀賞/大日本山林会 |
|
| |
|
|
| |
公益社団法人大日本山林会(永田信会長)は14日、令和6年度の林業経営「創意工夫」表彰行事の受賞者を決定し、発表した。それによると、第15回となる同表彰行事の優秀賞は、山形県の大江町光林会が取り組んだ「スマホを持って所有林を探しに行こう―研修会の開催等による所有山林の相続登記・森林整備の推進」が受賞。奨励賞には、和歌山県の(株)はぐくみ幸房代表取締役の大谷栄徳氏が進めた「大型ドローンの安全な運搬体制に向けたルールづくり」が選ばれた。
優秀賞に輝いた大江町光林会の創意工夫は、所有者不明の山林が増加している問題解決に向けて、スマートフォンの地図アプリに地籍データを表示させて所有林の境界を明確化する方法や、山林相続の基礎知識を学ぶ研修会の開催。マニュアルを作成して一般の森林所有者への普及活動も行った。
また、奨励賞の大谷氏は、林業用運搬型ドローンの開発や人材育成などを行っていく中で、業務の中で蓄積されたデータを活用して、大型ドローンの安全な運搬体制を構築するルールづくりを行った。
表彰式は、5月28日開催予定の同山林会の令和7年度定時総会で行われる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
「アスパイア」5機種発表/ハスクバーナ・ゼノア |
|
| |
|
|
| |
ハスクバーナ・ゼノア(株)(パウリーン・ニルソン代表取締役・埼玉県川越市南台1の9)は4月から、コンパクトなガーデンツール「Aspire(アスパイア)シリーズ」5機種(チェンソー、トリマ、ヘッジトリマ、ブロワー、バリカン)の発売を順次進めていく。いずれもボタン1つ・電源のオン/オフで稼働/停止ができるお手軽ツール。世界の主要メーカーが加盟する18ボルトバッテリーシステムを採用しており、100種類以上の電動工具、園芸機器などとバッテリーを共用できる。
「アスパイアシリーズ」は、すでに昨年プルーナを市販しており、今回の新製品を加えて6機種のラインアップとなる。また、全国発売に先んじて同社キーショップでは先行発売を実施、チェンソーC15Xは14〜31日、トリマ、ヘッジトリマ、ブロワー、バリカンは4月7〜21日にその機能を確認することができる。
各機種ともグレーを基調に操作部、脱着部は目立つオレンジ色とし、直感的に操作できるデザインを施しているほか、アスパイア保管システムに対応しているため収納は場所を取らず、万が一製品を放置した場合でも180秒自動シャットダウン機能で自動的に電源オフで安全など、シリーズ共通の特徴を有している。
機種ごとの特徴などは次の通り。
▽チェンソーC15X=軽量・コンパクトながらパワフル。X―プレシジョンガイドバーとSP11Gチェンによる高精度な鋸断性で最大径15センチまでの枝を正確かつ滑らかにカットする。工具を使わずバー、チェンの着脱、調整ができ、チェンブレーキを搭載。本体質量(バッテリーガイドバー、チェンなし)は2・2キロ。本体価格は税抜き3万円。
▽トリマT28=効率的で美しい仕上がりとなるデュアルナイロンカッターは、オートフィード機能で自動的に繰り出され、ループハンドルは4段階の位置調整が可能、快適に作業できる。本体質量(バッテリーなし)は2・6キロ。本体価格は税抜き2万円。
▽ヘッジトリマH50=葉受け板で刈り取った枝葉の処理が容易。50センチの長いカッティングブレードで広い範囲を効率的に作業できる。優れた切断能力と美しい仕上がりをみせ、ガイドが刃よりも長く高い安全性を確保。片刃・両刃兼用。本体質量(同)は3・1キロ。本体価格は税抜き2万3000円。
▽ブロワーB8X=風量は3段階調整、デリケートな花壇から芝生上の濡れ落ち葉まで作業に合わせて選べる。風管はワンタッチで簡単着脱、作業や収納が容易。本体質量(同)は2・0キロ。風力は80N、風量10立方メートル/分。風速40メートル/秒。本体価格は税抜き2万1000円。
▽バリカンS20=工具を使わずアタッチメント交換、バリカンとヘッジトリマを簡単に切り替えられる。タイヤ装着で作業性が向上。ポール装着で立ったままの作業も可能。バリカンの刃寸法は12センチ、ヘッジトリマは同20センチ。本体質量(刃付き、バッテリーなし)はそれぞれ1・1キロ、1・2キロ。カッティングスピードはバリカンが1400カット/分、ヘッジトリマが2800カット/分。本体価格はバリカン(ヘッジトリマアタッチメント含む)が税抜き2万円、バリカン+ポールが同3万円。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ハイパーフリー好調/ツムラ鋼業 |
|
| |
|
|
| |
津村鋼業(株)(津村慎吾社長・兵庫県三木市別所町巴46)が製造する刈払機用のチップソーと刈刃は「角鳩印ブランド」として知られ、農林業の従事者のみならず、草刈りのシーンで一般のユーザーにも好んで使われている。昨今は充電式刈払機に最適なチップソーと三日月刃の「ハイブリッドカッターW型」が好評だ。
さらに、チップソーと並び好調な売上げをみせるのが、同社のモア刃「ハイパーフリーシリーズ」だ。同品は、畦草刈りや斜面刈りのシーンで最高のパフォーマンスをみせ、従来のバーナイフに比べて基盤を挟んだ上下2段刃の構成で、これが鋭い切味をみせる。
切れ味に加え、フリーという名の通り、上下の刃が自由に動く。そのため草刈り時に石などの硬質異物に当たっても刃が逃げる。これにより機体本体への衝撃を抑え、機体に負担をかけにくいという特徴がある。
上下2段刃は草を細かく粉砕し、基盤の「草巻き付き防止コブ」により草が巻きつきにくい。そのため作業後の後処理が楽になる。さらに、基盤と上下2段刃を固定するボルトはそれ自体が回らない構造で、ボルトが回らず基盤取付穴が大きくならないので安全だ。
シリーズは、500SP、600・700・757・1300WM、600・700GCと7種類を揃える。
問い合わせは同社(TEL0794・82・0771)まで。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
地域内エコシステムの実証事業/躍進2025林業機械(10) |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会(酒井秀夫会長)はこのほど、令和6年度の林野庁補助事業「『地域内エコシステム』技術開発・実証事業」の成果を報告書にまとめ、ホームページにアップ、情報発信している。一般社団法人ゼロエミやまなしが取り組んだ「皆伐再造林と連動した枝条残材チップ製造・供給システムの開発」と(株)森の仲間たちが進めた「寒冷地に適した小型薪ボイラーシステムの開発(2)」の2つ。事業効果などを明らかにしている。
令和6年度の「地域内エコシステム」技術開発・実証事業で一般社団法人ゼロエミやまなしが山梨県北杜市を事業実施場所として進めた取り組みは、「皆伐再造林と連動した林内枝条チップ製造・供給システム(フェーズ2)」だ。
枝条のバイオマス活用を前提とした皆伐再造林システムの最適化と、地域内の小規模熱利用にも供することができる、安定的なチップ品質とコストの実現を目的としたこの実証事業では、次に6項目に取り組んだ。
(1)レーザー測量による森林資源量の解析及び解析精度を検証する。
(2)バイオマス利用を前提としてハーベスタ造材を実施し枝条集積の最適化等を調査実証する。
(3)枝条集材オペレーションの効率化に向けて、グラップルフォークやバイオマスフォワーダの運用の方法と運搬効率を調査実証する。
(4)車載型チッパー・コンテナ車適用によるチップ製造を実施し生産効率を検証する。
(5)運搬車両を簡易改良し、燃料チップの品質向上について調査実証する。
(6)チップ製造・供給原価を試算する。
現場での調査・実証の結果、グラップルフォークやバイオマスフォワーダの運用では、林内における枝条の集材や運搬効率の向上、枝条残置率低減、枝条運搬量の定量化が期待できることを確認。また、車載型チッパーとコンテナ専用車の適用によりチッパーの稼働率及び生産効率が向上すると指摘。汎用性・実用性のある簡易スクリーン機構を開発しチップの品質向上にも寄与。製造原価としてキロ当たり19円以下の実現を目指した。
一方、(株)森の仲間たちが事業者として取り組んだ「寒冷地に適した小型薪ボイラーシステムの開発(2)」は、欧州製の先進的な薪ボイラーと同水準の性能を有する燃焼技術開発を目指した。岐阜県大垣市と青森県五戸町を事業実施場所として開発を進めた。
薪ボイラーの新しい普及の局面をつくることで、地域内分散型需要エコシステムを拡大し、地域内エコシステムをより増強していくことを目的に掲げる、この取り組みでは、(1)完全燃焼対策(2)ブリッジ対策(3)放熱対策の3つの開発を行い、青森県五戸町で寒冷地での実証を進めた。
より完全性の高い燃焼の実現を目指した3つの対策を施して、(1)燃費向上により製品高を克服(2)欧州製の薪ボイラーと同等の魅力を有する製品により国内を維持・拡大、海外市場も視野に(3)国産で85%以上の効率を有する燃焼機器開発は業界の技術底上げ―を実現させる。これにより、大きな需要の見込まれる寒冷地での市場開拓が可能になるほか、開発ノウハウの水平展開並びに薪ボイラーによる木材需要開拓と地域内分散型エコシステムの構築が期待される。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
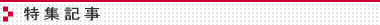 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
勢いに乗り春需取り込む/熊本県特集 |
|
| |
|
|
| |
世界最大級のカルデラを有する阿蘇や豊富な水資源、温暖な気候など自然溢れる熊本県。昨年2月、世界最大の半導体メーカー・台湾積体電路製造(TSMC)が、日本初進出となる熊本工場(菊陽町)を本格稼働させた。当初懸念された農家への影響は今のところ道路渋滞程度でそれほど大きくない。一方、米価や野菜価格の上昇で該当する作物を栽培する農家を中心に購買意欲も高まっているが、収穫時期の違いによって、米の買取価格に地域差も生まれており、今後の市場の動き次第との声もあった。そんな県内の様子をお伝えする。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
市場の概況:農業産出額5位堅持/熊本県特集 |
|
| |
|
|
| |
熊本県は平坦地から高冷地まで恵まれた立地条件を活かして、多彩な農業を展開する全国屈指の農業県だ。2023年農業産出額は3757億円で、7・0%増加し、前年同様全国5位を堅持。そのうち、畜産で1371億円(全国7位)、野菜1365億円(同3位)、果実391億円(同7位)など、食料生産基地として重要な役割を担っている。生産農業所得は1554億円で前年の4位から2位に浮上。上位10品目は、1位が肉用牛435億円。2位以下は順に、トマト(400億円)、米(328億円)、生乳(317億円、豚(265億円)、ミカン(191億円)、イチゴ(160億円)、鶏卵(146億円)、メロン(127億円)、スイカ(118億円)と続く。酪農・畜産から稲作、施設園芸、果樹、野菜と多様だ。農産物の中で日本一の生産量を誇るものには、トマト、スイカ、不知火(デコポン)、宿根カスミソウ、い草などがあり、この他にもナス、葉タバコ、クリ、ショウガなどが全国的に高い順位を占める。
県内水稲農家は米価の上昇で好影響が出ているものの、地域によって差が出た。阿蘇産のコシヒカリは概算金で1俵当たり2万2020円と前年比で7500円増、過去20年間で最高額となる一方で、収穫が早めの天草地方では米価が上がり始めた時期での出荷であったため、その恩恵が少なかったなど、地域によって明暗を分けた。
また、認定新規農業者数が全国1位。認定農業者数全国2位(いずれも令和3年3月末時点)。認定新規就農者数は1万772経営体で、前年比625経営体減少した。
県は農業人口減や次世代農業者の育成が急務との危機感から、スマート農業推進にも力を注ぐ。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
各社の対応:スマート農機の実演強化/熊本県特集 |
|
| |
|
|
| |
(株)中九州クボタ(西山忠彦社長)の2024年実績は前年に対し横ばいであった。主要3機種は台数的には決して楽観できる状況ではなかったが、大型化が進んでおり、トラクタで60PS以上、コンバインで4条クラス、田植機は4条がメーンながら、6条以上も増加している。「農家1軒ずつが大規模化している。一方で、離農も進んでおり、販売台数減少、大型化の傾向」と内田信二常務は話す。
昨年の展示会開催は例年通り各拠点での実施と全社統一で2回開催。春先と秋に本社で開催し、好評だった。実演も積極的に実施。スマート農機を中心にGSや自動操舵とともにニーズに合わせて作業提案を行い、関心の高さを感じた。また、担い手を中心に地道な推進活動を継続的に実施した。
昨年夏以降続く米価上昇で、今年の栽培面積を増やすという稲作農家もみられ、購買意欲も高まっている。今年の出足はクボタ製品のみならず、乾燥機や色彩選別機、フレコンなど、米関連商品含め、需要は上々。「現状では米価も野菜価格も高いが、これが継続するかは不透明。それでも、離農を撤回し、もう少し続けてみようという農家が出ているのは確か」(内田常務)とも述べた。
今年の展示会は1〜3月と夏に拠点ごとに実施予定。全社実演試乗展示会も含め行っていく。担い手に対しての接点活動は継続し、KSASやGS、自動操舵等のスマート農業関連を推進する。ドローンについては、更新需要を確実に押さえていきながら、中山間地の労力軽減を支えるべく、その地域でのドローン推進も進める考えだ。
アフターサービスは順調に拡大。点検活動から整備受注へつなげながら、サービスセンターでの入庫点検も行う。中古機も高い需要に応えるべく、買い取りを強化しながら、販売へのサイクルを回していく。
ヤンマーアグリジャパン(株)九州支社(増田広次支社長)南九州営業部における2024年実績は前年並みとなった。主要3機種は、コンバインが好調に推移し、トラクタと田植機は苦戦した。米価の上昇で、乾燥機や籾すり機は例年より突発的な需要がみられた。米価上昇の恩恵を受けた農家には、税金対策のため大型コンバインの更新をするケースもあった。一方で、「良かったのは米だけ。裏作の麦、大豆は良くなかった。そういう地域の特需は見込めていない」と熊本南部ブロックの松本秀和エリアマネージャーは振り返る。とはいえ、米や野菜の価格は良いので、このまま価格が維持されれば、今年は農機需要に期待したいと述べた。
昨年の展示会は春と夏に開催。加えて酪畜向けのトラクタや輸入作業機の展示会も実施。近年はそれが定着している。実演は各地域の特性に合わせた作業機を用意し、集落ごとに提案した。松本氏は「酪畜は依然として厳しいが、底は脱した。酪農家によっては機械投資も出てきている」と話す。
今年は3月決算に向け受注促進に注力している。「以前は補助事業頼みの側面が強かったが、補助事業が少なくなってきている。他方で、米価が上がっていることを踏まえて、今後は収量、品質を向上させる機械提案は顧客メリットが高い。レーザーレベラーや色彩選別機など推進していきたい」(松本氏)と述べた。
今年も実演や展示会で昨年の流れを継続しながら、担当地域の担い手を全て訪問して接点強化を図る。例えば、甘藷農家の集まる地域での栽培体系提案とともに自動操舵を推進するなど、地域特性に合わせて、きめ細かい推進を行っていく。スマート農業の知識やスキルの向上を図って提案力強化にも注力する。ドローンへの関心も高いため、そのニーズにも確実に対応すべく、点検整備の態勢も拡充している。
アフターサービスや中古機については、下取りから整備、販売の流れを速くし、在庫を滞留させないようにする。稲作地域と裏作のある地域では、整備需要が異なるため、農閑期地域の拠点に整備を回すなどの工夫もしながら、より効率的な対応を行っている。
(株)ISEKI Japan九州カンパニー(中谷清社長)中部営業部の昨年実績は前年比120%を超え好調に推移した。中でも井関製品が伸長。コンバインは米価上昇を背景に堅調だった。トラクタ、田植機を含めた主要3機種の販売台数はほぼ横ばいながら、高馬力帯の売れ行きが良く、売上高アップに貢献。加えて作業機などの関連商品も前年を超え、総合的に実績を拡大した。「大規模農家だけでなく、中小規模の個人農家でも馬力アップが進んだ。関連メーカーの皆さんのご助力にも感謝したい」と蔵野伸也部長は振り返った。
上期は2月のグランメッセ熊本で開催した展示会で下地をつくり、4月以降、推進で実績を積み重ね、米価決定以降はその波に乗った。11月にも中部営業部で中規模展示会を行い、突発的な購入に結びつけた。「生産者の中には、予想以上の収入となり、税金対策で購入するケースも見受けられた」と蔵野部長は話す。
今年も2月に展示会を開催し、会期中の実績で前年を上回った。今のところ、田植機が大小とも伸びている。実演は昨年、BFトラクタと自動操舵をセットで推進し、好評だった。今年も継続しながら、大規模農家に向けアピールしていく。
米以外の麦や大豆、ニンジン、サツマイモなども堅調。関連機械をPRしていく。乾田直播も昨年から一部農家の協力のもと普通作とWCSで試験栽培を開始。良好な結果を得ている。それを踏まえ、大規模農家へ提案も行っていく。
アフターサービスには、より一層力を入れる。人員増強や育成で、受け入れ態勢を強化。点検案内の送付などで周知活動を徹底することで、収益を伸ばしている。
三菱農機販売(株)九州支社(松尾秀二支社長)熊本管内の実績は昨年12月時点で前年比109%、計画比101%と好調に推移。
幸村義一支店長は「トラクタが好調。KUSANAGIも前年比400%の伸び。管理機や草刈機、作業機も良かった。一方、コンバイン、田植機が苦戦した」と振り返る。KUSANAGIのPRにはかなり注力し、ほとんどの実演を同機に費やした。JA熊本県経済連の夏の大展示会でもPRした。「社員が真面目に取り組んでくれたおかげで、よくカバーしてくれた」と話す。米価上昇で、11月以降、乾燥機や保冷庫などの受注が増加している。
今年の出足は、一部メーカーの商品が入ってこないことなどもあり、若干落ち込み気味。最小限のマイナスで抑えて、見通しのある3月で挽回していく。今年度の着地も計画達成の見込み。
KUSANAGIの実演は今後も継続し、単協の展示会でも漏れなくアピールし、興味をもった農家全てを実演につなげていく。また、25年度は新型のXPSのトラクタや田植機もPRしていく。
独自技術である紙マルチ田植機は、興味、関心をもつ農家をホームページで募って実演を行う。また、実機は阿蘇農業高校(現・阿蘇清峰高等学校)で使用されており、今度更新もされる予定。みどりの食料システム戦略が施行されて以降、興味を持つ農家が出てきている。また、ペースト施肥田植機も施肥機の装着率が上がってきている。肥料価格の高騰の影響は少ない。「ペーストの良さを理解して使ってくださる農家がほとんど。三菱の独自技術が時代の流れとともに評価されてきている」と幸村支店長は述べている。
アフターサービスは、内容を詳細に明示して請求し、一目瞭然でわかりやすく対応し、収益を確保していく。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
JA熊本経済連:共同購入コンバイン計画達成/熊本県特集 |
|
| |
|
|
| |
JA熊本県経済連の今年度実績は、1月末時点で前年比100%、年度末着地は若干割り込む見通しである。米価の上昇による影響は、昨年末に駆け込み需要で、保冷庫、乾燥機、色彩選別機に動きがあったが軽微だった。主要3機種はトラクタ、田植機は前年比2割減。一方でコンバインは5割増となった。台数の減少が続いているという。「機械価格がどんどん上昇しており、生産者にとっては更新が厳しい。米価が上がっているとはいえ、肥料や農薬などの営農コストも上がっていて、今回の米価上昇が単年のものとの見方もあり、様子をみているのでは」と堀内健児農業機械課長は見解を述べた。
7月に60回記念として開催した大展示会は計画を達成。計画比で110%。動員も7400名が来場した。堀内課長は「イベントの中身を新しくし、昨年に比べて1300名ほど来場者が増えた」と述べた。
また、同じく7月にスマート農機の実演会を実施。直進機能付きのトラクタや田植機、後付け自動操舵、ドローンなど、15台を取り揃え、圃場を借りて、法人や大規模農家向けに行った。「農家さんは興味をもたれている。100名程度が参加し、関心も高かった」(堀内課長)という。自動操舵システムは、CHCナビ製を主に推進していく。
2025年度の重点施策としては、整備士の育成に力を入れ、人材確保に努めていく。「農協の整備士も高齢化が進んでいる。若手の育成と確保が課題。10年後を見据えて、嘱託の整備士にも協力いただいている」と話す。その他にも、大口買い取りによる価格の低減、農業法人組織への推進強化、夏の大展示会へ向けての推進等も行っていく。実演会も年1回、時期は未定ながら継続していく考えだ。鹿児島、宮崎とともに、南九州3県でトラクタの共同仕入れを行っており、九州全域化へ向けた話し合いもなされている。
共同購入コンバインは2024年度10台の計画に対し、11台を受注した。3年間の合計で35台を計画する。「熊本では4条は主力機。もう少し上のクラスでも良いが、4条刈であれば、上下両層での供給が可能。3条刈を使っていた方から、低価格で作業効率が上がったという喜びの声も寄せられている」と堀内課長。また、推進施策として、7月の展示会向けにオリジナル動画を作成中。購入者のインタビューなどをまとめたものを発表する。2025年度も10台の計画で、さらなる飛躍を目指す。
アフターサービスでは、格納保守点検について、周知を高めるべく昨年、新たにチラシを作成。また、再販できる中古が減少している中、3月に大分、熊本の各商組と35回目となる合同中古農機展を開催。しかし、展示台数が過去に類をみないほどの少なさだという。「少ないとはいえニーズは高まっているので、どうにか開催して、少しでも生産者を支えられれば」と堀内課長。
機械を購入した生産者がケガをした際に、お見舞金を出しているが、その件数が増加している。堀内課長は「高齢の方を中心に多い。大展示会でもコーナーをつくって、安全講習として刈払機の使用方法、熱中症対策などを行い、啓発に努めている」と話した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
県の取り組み:農家減少に危機感/熊本県特集 |
|
| |
|
|
| |
熊本県におけるスマート農業の取り組みを、農林水産部生産経営局農業技術課普及振興企画班の楠田倫主幹、香月みなみ主任技師、同課農業革新支援センター産地づくり支援班の山並篤史主幹に取材した。
まず、2021年2月、県の食料・農業・農村基本計画でのスマート農業の取組方針に、4年計画として「ロボット技術やICT技術に加え、栽培環境や農作物の生育状況など多種多様なデータを見える化し、スマート農業をフル活用することで、大幅な省力化や生産性の飛躍的向上、高品質な農作物の安定生産を実現する」と記載。指標としてドローンを活用した土地利用型農業防除面積の割合を2019年の5%から2023年目標13%と設定し、その結果、実績14%と目標を達成。着実に農業のスマート化を前進させている。取材時点(2月末)は、来年度より始まる新たな取り組みを策定中であった。
スマート農業の取り組み事例としては、(1)農作業の効率化(2)収量・品質の向上(3)技術の見える化―の3点をあげた。
(1)は、ドローンを用いた農薬散布が、水稲で増加してきている。これを果樹でも応用できないかということで、柑橘やクリなどで検討した。また、自動操舵システムやロボット農機の実証なども水稲栽培において行った。(2)では、環境モニタリング装置を活用した若手農業者の栽培技術の向上を図るべく、イチゴハウス内の環境データを見える化し、ベテラン農家のデータを新規就農者と共有することで、技術向上に役立てる。(3)は、ベテラン農家の管理作業を動画で紹介し、管理のポイントを見える化、マニュアル化。これは昨年3月、大玉スイカの栽培マニュアルとして冊子にまとめ、農業者を含む県内関係者限定で配布した。普及指導員からは、新規就農者への教育ツールとして、非常に使いやすいとの評価を得ており、今後の活用が期待される。 また、スマート農業推進に向けた県の新たな取り組みとして、(1)農業者と企業のマッチング(2)指導者向け研修会の開催(3)アドバイザー派遣の3つを令和6年度に行った。(1)は、農業者の要望や課題等を事前調査した上で、それに合致する企業を選定し、県から呼びかける形で参加企業を募り、農家と企業をマッチングするというイベントを実施。ありそうでなかったコンセプトだったこともあり、参加企業や参加できなかった農家からはまたやってほしいという声も聞かれた。
(2)は、市町村の職員や普及指導員、農協職員など指導する側で、現場に即したスマート農業を推進できる人材を育成する目的で大規模な研修会を10月と2月に開催した。10月は全般的なスマート農業の導入事例について、実証プロジェクトに関わった担当者を招いて講義をした。2月は、モニタリングデータの読み取り方として、実際の数値をどう読み取って、どう指導につなげるかをレクチャー。いずれの回も実習の時間を設け、10月は生成AIの使い方、2月はデータ分析を行った。(3)は、現場で困っている人に専門家を派遣し、アドバイスをするという取り組み。初回は、スマート農業全般に詳しい専門家を招いてレクチャーした。
楠田主幹は「熊本に限った話ではないが、急速な農業人口の減少に危機感を感じている。このままでは農地の維持も難しくなってくるという実感から、スマート農業機器を活用した省人化や効率化にどうしても取り組んでいかなければならないし、若手農業者にも早く一人前になっていただきたい。その思いが正直なところ」と述べた。
これらの話を聞き、現場の実情や声に対して真摯に向き合い、誠実に対応していることが垣間見えた。このような地に足のついた地道な取り組みが県農業の活性化につながっていくことだろう。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
品揃え充実、販売促進へ勢いに乗る/草刈機・刈払機特集 |
|
| |
|
|
| |
草刈機・刈払機は、今年も市場ボリュームアップが見込める期待機種の一つにあげられている。彼岸が終われば、夏の草刈りシーズンに向けて草刈機・刈払機商戦も熱を帯びてくるが、計算できる刈払機の他にもスマート農業との絡みで人気を博している遠隔操作型をはじめ、ハイスペックな商品となる自律走行型など、この先の需要獲得に期待が高まる機種が目白押し。販売サイドの意気込みと品揃えの充実などとがあいまって視界は良好だ。引き続き各種草刈機は勢いのある商品の一つにあげられるなど、まさに売り時。拡販のチャンスが到来しており、現場も活気づいている。今週は更なる高みにステップアップしている草刈機・刈払機に焦点を当てて、最近の動向をフォローしてみた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
スマート農業の推進と草刈機:省力化い貢献する遠隔操作型/草刈機・刈払機特集 |
|
| |
|
|
| |
基幹的農業従事者数は、今後20年間で4分の1にまで減少し、30万人になることが見込まれている。そのような状況になっても、生産水準を維持できる生産性の高い食料供給体制を確立するためには、スマート農業技術の活用と、それに合わせた生産方式の転換が欠かせない。
そこで、昨年10月に施行されたスマート農業技術活用促進法では、(1)スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)(2)スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)―という2つの認定制度を創設した。
(1)生産方式革新実施計画は、スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産方式の導入をセットで行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動を認定するもの。(2)開発供給実施計画は、特に必要性が高いスマート農業技術等の開発や、それを活用した農業機械または技術活用サービスの供給を一体的に行う事業を認定するもの。いずれも、農林水産大臣に申請を行い認定を受ける流れとなっており、認定を受けた農業者や事業者は、税制や金融等の支援措置を受けることができる。
施行から約半年を経て、認定件数は(1)生産方式革新実施計画が10計画(3月7日時点)、(2)開発供給実施計画は8計画(2月27日時点)となっている。
農業分野におけるICT、ロボット技術の活用事例の1つに、リモコン草刈機があげられる。農林水産省では事例として4社の製品について取り上げて、農林水産省ホームページのキーワードにある「スマート農業」にアップし、それぞれ特徴を次のように紹介し、効率性や傾斜地対応能力など高いポテンシャルを発信している。
◆三陽機器(株)「AJK600」
▽概要=アーム式草刈機の技術と油圧・マイコン制御の技術を組み合わせ、リモコン操作可能な草刈機を開発▽特徴=(1)人が入れない場所や急傾斜(最大傾斜40度)のような危険な場所での除草作業もリモコン操作で安全に実施可能(2)軽量コンパクトで、軽トラでの移動が可能(3)作業効率は慣行作業の約2倍。
◆(株)アテックス「神刈RJ705」
▽特徴=(1)最大45度の急傾斜でも遠隔で安全な草刈りが可能。また、45度の傾斜角度を検知すると一旦停止する機能を装備(2)傾面での作業で、機械が谷側に逸れるのを自動で調整する斜面補正システムを搭載(3)草刈りはエンジン、走行は電動のハイブリッド仕様で、作業場所やトラックまでの移動が静か。
◆和同産業(株)「KRONOS(ロボモアMR―301)」
▽特徴=(1)草刈りをしたい場所にエリアワイヤーを設置、エリア内をランダムに走行しながら草刈り(2)超音波センサーで障害物を検知(3)刈取負荷に応じて走行速度を制御(4)バッテリー残量が少なくなったら自動で充電ステーションへ帰還(5)緩斜面(最大20度)の除草作業が可能。
◆(株)ササキコーポレーション「smamo(スマモ)」
▽特徴=(1)草刈りアタッチや走行ユニットなどのアタッチメントにより、様々な用途に使用可能な電動リモコン作業機(2)全高40センチなので人が作業しにくい場所や機械が入ることができない場所の草刈り作業を行うことが可能(3)最大35度までの傾斜地で除草作業が可能(4)作業時間は約2時間 (草刈りアタッチ・バッテリー2個並列接続時)(5)バッテリーは家庭用コンセントで充電でき、充電時間は約2時間。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
草刈機を取り巻く動向:推進に諸条件揃う/草刈機・刈払機特集 |
|
| |
|
|
| |
現在の草刈機・刈払機市場は、前回の特集記事で紹介した、農林水産省が進める「みどり投資促進税制」の草刈り関係の対象機を見て分かるように様々な機種がラインアップされているのが大きな特徴だ。改めて確認してみると、ラジコン草刈機、電動リモコン草刈機、オフセットモア、ブームモア、リモコン式小型ハンマーナイフモア、傾斜地草刈機、オフセットシュレッダー、トラクタ用アーム式草刈機など現在販売されている各種製品が認定対象機種として名を連ねている。1機種だけではない。様々なタイプが揃っている。
これまで草刈機・刈払機市場は、普及台数、販売台数ともに群を抜いている刈払機を核として、手押し式、自走式、乗用式からトラクタやバックホウをベースマシンとするインプルメント式、さらには技術革新に伴い脚光を浴びているリモコン・ラジコンの遠隔操作型から自律走行するロボット型までバリエーションが広がってきていると指摘してきたが、使う側にとってより最適な機種が選択できるような商品構成、品揃えとなっている。
最近の草刈機・刈払機市場のユーザーニーズは、より省力、より快適、そして効率的に作業を済ませることにある。これに草刈り作業を進める上で忘れてはいけない安全作業面も当然、クローズアップされてくる。
このため、作業能力に優れる自走式や乗用式が台頭し、安全問題との絡みから、離れた位置で作業のできる遠隔操作式が注目されるようになっている。ラジコン式草刈機は、農林水産省が展開するスマート農業という点でも、構成機種の1つに位置付けられている。様々な実証プロジェクトにおいて全国の事業体が試験し性能評価が進展、現地検討会の実施などとあいまってラジコン草刈機の普及啓発、需要拡大に一役買ったのは周知の通りである。
さらに草刈り作業に関わるのは、農林業分野だけではなく、面積的には拡大基調にある、都市部の造園・緑化、グリーンメンテナンス関連の市場があるのは忘れてはならない。
ともに現在の悩みの種となっているのが作業員の人員確保、いわゆる人手不足問題である。このため、作業能力に優れるハイスペックな機械が求められ、安全な作業を実現する点で、離れた場所から作業のできる遠隔操作型への要望が高まってきている。機械による現状の打開、問題解決が進められようとしている。
各種機械ともに持ち味、特徴がある。これをユーザーにどう勧めていくのか。販売サイドの腕の見せどころである。しかも市場環境としては、先に指摘した通り、機械での効率的な作業の実現に対してニーズは高い。商品の品揃えの充実に購買意欲の高まり、草刈機・刈払機はいま売り時、拡販のチャンスが到来している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
刈払機の市場展望:手堅く需要獲得/草刈機・刈払機特集 |
|
| |
|
|
| |
数ある草刈り用機械の中にあって、最も普及し、年間の販売台数が最も多いのが手持ち式の刈払機だ。最近、自律走行のロボット式、離れた場所から作業のできる遠隔操作式、さらには作業能力の高い乗用式、自走式、また、同じ手持ち式でもバッテリー式と競合機種が年を追うごとに増えていく中でも堅実な実績を残している。
日農工が部会統計をもとに取りまとめている「2025年1月分の農機生産出荷実績」によると、1月の刈払機の生産台数は、5万9516台(国内向3万8708台、輸出向2万808台)で前年同月に比べ98・3%、出荷台数は2万6692台(国内向1万7289台、輸出向9403台)で同89・9%とやや低調な出足となっているが、これからの需要期本番に向けてどのような上昇カーブを描くのか目が離せない。
日農工刈払機部会は、部会長の2025年見通しとして、更新を見送ってきた需要が徐々に回復し、堅調に推移すると見込んでいる。引き続き安定した需要を予想している。刈払機は、コンパクトで持ち運びにも便利、あらゆる作業形態に応対できる柔軟性に買い替えやすい価格帯などがあいまって手堅く、安定した需要を獲得してきたが、この構図は今年も大きく変わることはないとみられる。
販売する側に立っても草刈り用機械のファーストチョイスとして頭に浮かぶのは手持ち式刈払機。最新タイプは新機能を搭載し安全作業への対応がより進んでいる他、ユーザーの広がりによって誰でも簡単に使えるように軽量、コンパクト化が進展しているのが大きなトレンドとなっている。売れ筋をしっかり捉えての販売推進が求められてくる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
刈払機の安全使用に向けて:基本の順守、励行を/草刈機・刈払機特集 |
|
| |
|
|
| |
刈払機のシーズン本番を迎えるに当たって心しておきたいのが安全使用の徹底だ。正しい使い方、安全への装備など改めて確認しておく必要のある事柄だ。
日農工刈払機部会(久保浩部会長)では、「『刈払機の正しい使い方』を紹介する安全啓発動画やチラシを日農工のホームページで公開し、農業従事者のみならず、地方自治体やシルバー人材センターなど幅広いユーザー層へ、安全講習用ツールとして提供している」とした上で、昨年、国民生活センターから出された「刈払機の作業中の事故に注意!」と題する安全啓発強化の要望書を受け、事故防止に向けた取り組みをさらに推進してしていく姿勢を示している。
では、刈払機を安全、かつ適切に使っていく上で何が求められるのか。刈払機部会が作成したパンフレット「刈払機の正しい使い方」からみてみよう。
刈払機には、「肩掛式」と「背負式」とがあり、ハンドルの種類によって「ツーグリップタイプ」「ループハンドルタイプ」「U(両手)ハンドルタイプ」があるが、用途や作業場所に最も適した機種、そして刈刃を選択していくことが大切だ。特に刈刃には、チップソーやナイロンコードなど多くの種類が揃っており、作業する場所や地形、刈る草の種類や状態など、対象物に合った製品を選ぶことができる。
また、ナイロンコードについて日農工刈払機部会では、(1)柔らかい草や作業場所が塀の側や障害物に接近した作業の場合は、キックバックが生じないナイロンコードカッターの使用を検討する(2)使用時にはコードを伸ばしすぎないようにする。取扱説明書に指示された長さに切り揃えてから作業する(標準で10〜15センチ)(3)ナイロンコードカッターは必ず純正品を使用する―などと指導。
ただし、チップソーで作業するときよりもエンジンの回転数を上げる必要性があること、刈刃からの飛散物が多くなることがあること、そしてナイロンコードカッターを装着できない機種があることなどを示し、注意を喚起している。
刈払機の作業中に気をつけなければいけない主な事故といえば、キックバックがある。回転する刃に障害物や地面が当たった場合、回転方向と反対側に刃が跳ね返ってしまうことが起きる現象のことで、跳ねた刈刃が作業者や周囲の人に当たると重大な事故につながりかねない。刈払機部会では、右側で草を刈らない、往復刈りではなく刃の左側のみで刈るように要請。また、作業者の周囲には近づかないようにする、と注意している。
巻き付きも要チェックの項目だ。刈払機は作業中に草や落ちていた紐などが刈刃に巻き付いて止まることがある。このときにエンジンを切らずに取り除こうとすると、刃が再び回り出して手を切ってしまう事態になりかねない。刃はあくまでも巻き付いたものの抵抗で止まっているだけなのだ。だから巻き付いたもの、絡んだりした草を取り除く際には、必ずエンジンを止めて作業する必要がある。
さらに飛散物。作業場所に何が隠れているのかよく分からない。空き缶やゴミ、障害物があるかもしれない。刈刃に当たった場合、高速で飛散し、作業者はもとより、周囲の人の負傷にもつながりかねない。このため、事前の作業場所の確認、飛散物防護カバーの適切な位置での取り付けなどとともに、保護眼鏡、フェイスシールドなどの防護具の装備を徹底するよう求めている。
日農工刈払機部会では、刈払機の正しい使い方として、別表の通り16項目を示し、励行するよう呼びかけている。こうした基本的な事項を順守、励行し安全で快適な作業現場を実現させていこう。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
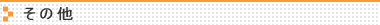 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
降車状態での事故も/2024年報道のトラクタ死亡事故 |
|
| |
|
|
| |
昨年のトラクタによる死亡事故の報道件数は46件で一昨年の45件とほぼ同じになった。即死と報道された事故のみをカウントしているため農林水産省のデータより少なくなる。今回は「転落転倒」を国際基準の定義に合わせ「横転」:走行地面上で横倒し(Tip Over=90度を超えない横転)と、「転落」:走行地面より下方に機体が落下し反転(Roll Over=90度を超えて反転)した事故の2種類に分けた。事故分類では横転が7件、転落19件、挟まれ1件、轢かれ11件、巻き込み8件で、相変わらず横転と転落で過半数を占める。ただ昨年の特徴は、運転者がエンジンを掛けたままトラクタから降り(または落車し)トラクタに巻き込まれる事故が多発している。他人を巻き込んだ3件を除けば20件(43%)は運転者が乗車した状態でなく、地上で死亡事故に遭っている。安全作業に関する教育では転落防止とともにエンジンを掛けたままの降車や収穫作業での微速無人運転を禁じる指導を徹底することが必要である。事故被害者の年齢層は85歳以上が7人、75〜84歳まで21人、65〜74歳まで10人であり、事故を起こした人の82%が65歳以上の非生産年齢者層である。高齢者の農作業事故を減らすためには、農地や農業施設といったハードの基盤整備だけでなく、農地法の改正も含め中山間地の農地売却を容易にするソフト面の施策が必要となる。そして65歳以上の高齢農作業者が働き続けなくても生活できるような年金制度や医療・福祉制度の見直しも必要ではないだろうか。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
