| |
|
|
| |
農経しんぽう |
|
| |
令和7年8月11日発行 第3563号 |
|
| |
|
|
| |
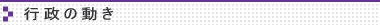 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
米の増産に舵切る/米の関係閣僚会議 |
|
| |
|
|
| |
第3回米の安定供給等実現関係閣僚会議が5日開かれ、今般の米の価格高騰の要因と対応の検証等について小泉進次郎農林水産大臣から報告を受けた。検証の結果、「需要量に対し生産量が不足していた」ことが明らかとなり、石破茂首相は「米の増産に舵を切る」ことを指示した。増産に向けては、農業経営の大規模化・法人化やスマート化の推進などを通じた生産性の向上に取り組む方針を示した。農林水産省が会議に提出した検証結果の資料によると、農林水産省は、人口減少等による需要のマイナス・トレンドの継続を前提として、翌年産の需要量の見通しと生産量の見通しを作成(令和4年秋・令和5年秋)したため、家計調査やインバウンドによる需要増等の実態を踏まえた直近の消費動向を考慮してこなかった。また、生産量の見通しにおいても、精米歩留まりが低下していることを考慮しなかった。他方、実際の生産量及び在庫量から計算した需要量(玄米ベース)は、令和4/5年と比較して、令和5/6年、6/7年は増加。また、精米とう精数量から推計した需要量(精米ベース)でも、令和4年産と比較して、令和5・6年産は増加。その要因は、高温障害等により精米歩留まりが悪かったことから、玄米ベースでの必要量が増加したこと(供給面の要因)に加え、インバウンド需要や、家計購入量の増加など1人当たり消費量の増加によるものと考えられる。この結果、生産量は需要量に対し令和5/6年:40〜50万t程度(需要量比:6〜8%程度)、令和6/7年:20〜30万t程度(需要量比:4〜5%程度)不足し、民間在庫を取り崩し、需要量に見合う供給量を確保せざるを得なかった。民間在庫は、多くが既に売り先が決まっているものであり、緊急事態に対応できるバッファーになり得ない状況。民間在庫の減少に伴い、流通段階では、次年度の端境期に米が不足するとの不安から競争が発生。卸売業者等では、新規の調達ルートを開拓したり、同業者間で取引するスポット市場を通じて、比較的高い価格の米を調達した。これらが米価高騰の要因となる中、農林水産省は、生産量(玄米ベース)は足りているとの認識の中で、1.流通実態の把握に消極的であり、マーケットへの情報発信や対話も不十分、2.政府備蓄米についても、不作時に備蓄米を放出するというルールの下、放出時期が遅延。こうした対応の下で、卸売業者等の不安感を払拭できず、更なる価格高騰を招いた、と分析した。米増産に向けた今後の方向性としては、1.需給の変動にも柔軟に対応できるよう、官民合わせた備蓄の活用や、耕作放棄地も活用しつつ、増産に舵を切る政策への移行、2.農地の集積・集約、大区画化や、スマート農業技術の活用、新たな農法(節水型乾田直播等)等を通じた生産性の向上、3.米国の関税措置による影響を分析しつつ、増産の出口としての輸出の抜本的拡大、4.精米ベースの供給量・需要量や消費動向の把握等を通じた、余裕を持った需給見通しの作成と消費拡大、5.流通構造の透明性の確保のための実態把握や流通の適正化を通じた消費者・生産者等の納得感の醸成、6.作物ごとの生産性向上等への転換、環境負荷低減に資する新たな仕組みの創設等を通じた水田政策の見直し(令和9年度)などを推進する。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
今年上期の農産物輸出8097億円で15%増/農林省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は4日、2025年1-6月(上半期)の農林水産物・食品の輸出実績を公表した。それによると、同期の農林水産物・食品の輸出額は、8097億円となり、前年同期比で15.5%、1086億円の増加となった。米(援助米を除く)の輸出額は67億7500万円で、前年比22.6%増となった。農産物は5231億円(対前年同期比14.4%増)、林産物は371億円(対前年同期比17.7%増)、水産物は1994億円(対前年同期比20.1%増)、少額貨物は501億円(対前年同期比8.2%増)。輸出先は1位が米国(前年1位)、2位が香港(同2位)、3位が中国(同3位)で変わらず。これに台湾、韓国、ベトナムなどが続く。今年上半期の状況は、多くの国向けが対前年同期比でプラスを記録した結果、対前年同期比15.5%増と前年同期を大きく上回った。4月から関税措置が導入された米国向けについても、ホタテ貝、緑茶、ブリなどが大きく増加した結果、対前年同期比で22.0%増となった。1-6月の輸出額としては、品目別では牛肉、緑茶、ブリなどが、国・地域別では米国、台湾、韓国などが過去最高を記録した。関係者からの聞き取りでは、日本食レストランの増加、日本食への関心の高まり、インバウンドの増加による日本食の認知度向上、健康志向の高まりなどが輸出増加の主な要因とみられる。品目別では、米(援助米を除く)は67億7500万円、前年比22.6%増、パックご飯等は9億6100万円、43.8%増。イチゴは53億円、22.2%増。果実は、リンゴが47億4000万円、27.6%減など全体的に減少している。牛肉は325億7200万円、15.5%増、豚肉は13億3700万円、28.3%増など好調を維持した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
3県で「やや上回る」/7年産水稲・西南団地の早期栽培 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省統計部は6日、「令和7年産水稲の西南暖地における早期栽培等の10a当たり収量の前年比見込み(7月15日現在)」を公表した。それによると、10a当たり収量の前年比見込みは、徳島県、宮崎県、鹿児島県の早期栽培で「やや上回る」、高知が「平年並み」となっている。農林水産省では、「西南暖地における早期栽培等の生産は良好。今年の主食用米の生産見込み(対前年56万t増)に向け順調なすべり出し」としている。気象データ(降水量、気温、日照時間、風速等)及び人工衛星データ(降水量、地表面温度、日射量、植生指数等)から作成される予測式に基づき予測した。令和7年産水稲の西南暖地の早期栽培及び沖縄県の第一期稲の10a当たり収量の前年比見込みは、徳島=やや上回る(対前年比105%〜102%)、高知=前年並み(対前年比101%〜99%)、宮崎=やや上回る(対前年比105%〜102%)、鹿児島=やや上回る(対前年比105%〜102%)、沖縄=やや下回る(対前年比98%〜95%)となっている。西南暖地の早期栽培においては、気温、日照時間ともおおむね前年を上回って推移した一方、沖縄県の第一期稲においては、4月から5月の気温が前年を下回って推移したため。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
令和6年度食料・農業・農村白書をみる(終) |
|
| |
|
|
| |
農林水産省がまとめた令和6年度の「食料・農業・農村白書」は、特集と5つのトピックス、本編7章立て((1)世界の食料需給と我が国の食料供給の確保(2)農業の持続的な発展(3)農林水産物・食品の輸出促進(4)食料安全保障の確保のための持続的な食料システム(5)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮(6)農村の振興(7)災害からの復旧・復興や防災・減災、国土強靭化等)の構成となっている。最終回の今回は、本編の第4〜6章の内容をみていく。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
水稲への影響懸念/渇水・高温対策本部 |
|
| |
|
|
| |
既報の通り、農林水産省は7月31日、農林水産大臣を本部長とする「農林水産省渇水・高温対策本部」を設置した。現在、少雨傾向により、東北、北陸、近畿等の一部地域において、渇水・高温による水稲の生育等への影響が懸念されている。同日開催された本部会議では、小泉進次郎農林水産大臣から、次の通り指示があった。現在、少雨傾向により、東北、北陸、近畿等の一部地域において、渇水・高温による水稲の生育等への影響が懸念されていることから、今後の対応について、以下の3点を指示する。1つ目は、渇水・高温に関する情報の収集・発信や節水の働きかけ等について。国土交通省、都道府県等と連携して、渇水・高温に関する情報を収集・発信するとともに、現場への節水の働きかけや応急ポンプの貸出し等を的確に行うこと。2つ目は、渇水対策に係る補助事業(水利施設管理強化事業)の積極的な活用について。本年度からの新たな取り組みとして、現場における渇水時のポンプの調達・運転等に係る諸経費を補助することとしているので、渇水傾向の地域にプッシュ型で働きかけ、地方公共団体等と連携して、本事業を積極的に活用すること。3つ目は、高温や斑点米カメムシ類に対する被害防止の徹底について。8月は、高温や斑点米カメムシ類による被害防止に向け重要な時期であり、地方公共団体等とも連携して、被害防止に向けた技術指導や防除の徹底を図ること。特に斑点米カメムシ類について、追加的に一斉防除を実施する際の支援を検討すること。また、今後も高温傾向が継続した場合も対応できるよう、高温耐性品種への切り替え等、高温に強い産地形成に向けた施策を検討すること。これらにより、限られた水資源の有効利用や対策技術の励行に努め、渇水・高温による被害の軽減に注力してもらいたい。農林水産省は今年度からの新たな取り組みとして、「水利施設管理強化事業」によって、現場における渇水対策のためのポンプの調達・運転や番水等に係る諸経費を補助することとしている。水利施設管理強化事業(公共)は、令和7年度予算概算決定額で33億7500万円(前年度27億3500万円)を措置している。農業水利施設は、食料安全保障の確保の基盤であり、また、国土保全や健全な水循環の維持・形成に寄与していることから、自然的・社会的・経済的情勢の変化を踏まえて、施設管理者への支援を充実し、施設機能の適切な発揮を図る。同事業のうち、「渇水・高温対策」の対象施設は、渇水・高温対策に取り組む農業水利施設。対象経費は、渇水対策BCPの策定、ポンプの調達、設置、運転等に要する費用。国庫補助率は2分の1。国土交通省によると、7月28日現在の渇水状況は、14水系17河川で渇水により取水制限等の対策をとっている。中国地方整備局、東北地方整備局では、渇水対策本部を設置している。また、令和7年の斑点米カメムシ(イネカメムシを含む)の注意報・警報の発表状況(7月30日現在)は、27道府県で33件の注意報が発表されている。警報の発表はまだない。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
サステナアワード2025を募集/農林省 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、「みどりの食料システム戦略」を推進している。その一環で、消費者庁、環境省と連携し、「あふの環2030プロジェクト」を実施。同プロジェクトにおいて、食や農林水産業に関わるサステナブルな取り組み動画を表彰する「サステナアワード2025」の募集を開始した。特に優れた作品には、農林水産大臣賞、環境大臣賞、消費者庁長官賞及びAgVenture Lab賞を授与する。募集期間は10月31日まで。食や農林水産業に関わるサステナブルな消費、環境との調和、脱炭素、生物多様性、資源循環など、サステナブルな生産やサービス・商品を扱う地域・生産者・事業者の取り組みに関する動画作品を募集するもの。優秀な作品を表彰し、あふの環プロジェクトホームページや農林水産省公式YouTubeチャンネル(maffchannel)で紹介するとともに、農林水産省、消費者庁、環境省の様々なイベント等で発信する。また、特に優れた作品は、英語版の動画を作成し、国際会議の場などを通じて世界に広く発信することにより、持続可能な生産・消費の拡大を目指す。主催は、あふの環2030プロジェクト〜食と農林水産業のサステナビリティを考える〜。共催は一般社団法人AgVenture Lab。事務局は農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ地球環境対策室(協力‥消費者庁、環境省)。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
農業とスポーツが連携/農林省が勉強会 |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は1日、「農業界とスポーツ界との連携に関する勉強会(第1回)」を開催した。我が国の農業者が減少する中で、農業が成長産業として持続的に発展し、食料の安定供給を担っていくためには、様々な分野から農業人材の呼び込みと定着を推進することが必要となっている。一方、従来にはみられない動きとして、スポーツ界から農業に参入するアスリートも現れてきている。アスリートの引退年齢の平均が20代といわれる中、農業に対して、セカンドキャリアとしての期待、プロチームの経営基盤の強化といった期待が寄せられている。他方、農業の知識・人脈がないアスリート等にとっては、就農のハードルが高く、アスリートのセカンドキャリアとして農業が意識されることが少ないのが実態。これらを踏まえ、農業界とスポーツ界がより連携を深め、Win―Winの関係となるような方策を検討するため、農業界とスポーツ界との連携に関する勉強会を開催した。勉強会は農林水産省経営局が主催し、スポーツ庁が協力する。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
開発供給計画2件認定/農林省がスマ農活用促進法で |
|
| |
|
|
| |
農林水産省は7月31日、スマート農業技術活用促進法に基づく開発供給実施計画を2件認定した。今回は北電興業、ジャパンプレミアムベジタブル(いずれも申請代表者)の計画が認定された。これにより、認定された同計画は累計41計画となった。認定された計画概要の一部をみると、北電興業は搾乳作業において、デジタルツイン技術を活用して非熟練作業者の搾乳作業をウェアラブル端末等からの情報に基づき解析し、その結果を踏まえ、熟練作業者の動作との比較によりリアルタイムに作業を最適に指示・提案する多言語対応のシステムの開発及び供給を行う。搾乳作業の最適化に向けた指示・提案を行う多言語対応システム。これにより、特定の作業者の行動を記録し、次の動作を「ウェアラブル・マニュアル」に反映することで、人の認知能力を拡張し、作業効率を向上させる。生産性向上の効果は労働時間20%削減を目指す。また、ジャパンプレミアムベジタブルは既存ハウスの改造により初期投資を低減しながらイチゴ・トマト等の周年栽培を可能とし、植物体のモニタリング等を通じて強制換気、細霧冷房等を効率的に運用することで投入エネルギーを低減する環境制御システム等を開発及び供給する。イチゴ・トマト等の周年栽培を可能とする環境制御システム等のトータルパッケージの実現でハウス内外の気温・湿度等を基に強制換気や細霧冷房等を効率的に運用するなど投入エネルギーを低減。付加価値額20%向上に資する技術を目指す。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
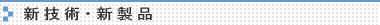 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
コンビラップマシーン新発売/タカキタ |
|
| |
|
|
| |
タカキタはこのほど、コンビラップマシーン「VCW1350N」(公道走行対応)を新発売した。梱包からラップまで1台で、高品質なサイレージを素早く作製する。ネット専用・ベルトタイプ芯巻き・ロールたておろし標準装備で、ベールの規格は直径120〜130cm×幅118cm、適応トラクタは73.6〜110.3kW(100〜150PS)、作業能率は5〜10分/10a。希望小売価格は1628万円(税込み)。主な特徴は次の通り。(1)梱包とラッピングを同時に作業=梱包とラッピングを同時に行うため効率よくベールを作製することが可能、トラクタ1台で作業できるため省力化にもつながる。また、梱包後土に触れずに素早くラッピングできるためより高品質なサイレージに仕上がる。(2)芯巻きの可変径ロールベーラタイプ=ロールベーラ部は可変径の芯巻きタイプになっている。ベール成形には耐久性に優れた2本の幅広ベルトを採用しているため、芯づくりから安定した作業が行え、隙間からのこぼれも低減する。(3)たておろし装置=たておろし装置によりベールはフィルムの厚い部分を下にして放出されるため破れを抑制することができる。また、ベールグラブでつかみやすい向きとなるためスムーズに次工程の作業を行うこともできる。移動時は折りたたんで移動。(4)全自動モード=ネット巻きからラッピング、放出までを自動で行う全自動機能を搭載。ベール作製に必要な操作を削減し、より簡単に作業を行える。また、ネット巻き後のチャンバー開閉とラップ巻き後の放出は手動操作にも切り替えられるため状況に合わせて作業を行うことができる。(5)コントロールボックス=コントロールボックスはタッチパネル式のカラー表示で見やすく、操作も簡単。ベール放出やチャンバーの開閉操作のほか、ベール径、ネット・ラップ巻き数、作製したベール数も表示する。全自動モードの切り替えも行える。(6)その他=バックカメラを搭載しているためラップの様子をトラクタから確認できる。また、機体側面に予備フィルムを保管可能で、フィルム切れの際も次のフィルムを素早く用意できるため、長時間の連続作業もスムーズに行える。〈主要諸元〉▽型式=VCW1350▽全長=6490(6980<作業時>)×全幅2460×全高2790mm▽重量=4050kg▽適応トラクタ=73.6〜110kW(100〜150PS)▽ベール寸法=直径120〜130×幅118cm▽適応フィルム=500mm×2本▽駆動方法=複動2系統/単動1系統▽作業能率=5〜10分/10a
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
アンテナ一体型GNSS受信機/ニコン・トリンブルが発売へ |
|
| |
|
|
| |
ニコン・トリンブルは、米国PTx Trimble社の農機向けGNSSガイダンス・自動操舵システムGFXシリーズ対応のアンテナ一体型GNSS受信機「NAV-960」を今秋、国内発売を開始する予定。PTx Trimble社は2024年4月より米国で創業したAGCO社とTrimble社の合弁企業。これまで20年以上研究開発を続けてきたTrimble社のスマート農業技術を引き継ぎ、GNSSガイダンス・自動操舵システムをはじめとした精密農業ソリューションの提供を行っている。これまで高精度な位置情報を用いた農機の自動操舵には、RTKやVRSなどのサービス利用に加え、必要機材の購入や通信契約などの事前準備が必要だった。「NAV-960」は、みちびき(準天頂衛星システム)のセンチメータ級測位補強サービス(=CLAS)に対応しており、CLAS利用時における前記の事前準備が不要になることから、より手軽に自動操舵を利用できるようになる。加えて、誤差数センチレベルの高い作業精度で自動操舵を可能にする新しい機能も備える。同製品は現在、製品化されている農機向け後付け自動操舵システムとしては、業界初となるCLASに対応。事前準備やキャリア通信網の範囲内でのみ利用可能なRTKやVRSに比べ、CLAS利用時は国内どこでも無償での自動操舵の利用が可能となる。従来機と比較して5倍以上の処理能力を持つCPUの搭載によって、精密な自動操舵を可能にするProSwath(プロスワス)機能を実現。位置測位や自動操舵アプリケーションの演算処理が効率化され、作業線(AB線)への進入や自動操舵中のライン上における位置精度と安定性が、従来比で最大50%向上する。CLAS利用時においてもRTKレベルの作業精度による自動操舵が可能。ファームウエアには、近年GNSSガイダンス・自動操舵システムの利用に影響を及ぼしてきた太陽フレアに対応するIonoGuard(イオノガード)機能を搭載。太陽フレアの影響を軽減し、自動操舵の安定利用を可能にすることで、限られた期間内で作業が求められる農業現場において時間的なプレッシャーを軽減する。なお、この機能は今後国内リリース予定のファームウエアにおいて従来機にも搭載される予定である。その他にも、頑丈なアルミボディの採用による剛性強化や経年劣化防止、従来機と同一のコネクタを採用し、更新もしやすい。対応ガイダンスディスプレーは、「GFX-350」、「GFX-1060」、「GFX-1260」。通常GFXシリーズとセットで購入する「NAV-900」は、在庫がなくなり次第販売終了となる(「Track-Guide3」は「NAV-900」とのセットで引き続き販売する)。同製品は、トラクタメーカー各社の全国にある販売代理店を窓口として、今秋より販売開始予定だ。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
導入進む電気乾燥機/大紀産業の新製品 |
|
| |
|
|
| |
大紀産業は、新製品の電気乾燥機「E-20HD-S(標準品)」および「E-20HD-PRO(全自動型)」の2機種を2025年5月から発売し、好評を得ている。同社が開発・製造・販売する電気乾燥機は、野菜や果物、お茶、和・洋菓子、海産物など幅広い食材を独自技術により効果的に乾燥させ、付加価値のある新たな食品を産出している。最近ではジビエやペットフードの分野でも導入が進んでいる。新製品は乾燥室内温風を従来の片側吹出方式から両側吹出方式に変更し、かつ熱効率を追求した熱源ユニットを搭載。消費電力を従来製品から約1割削減した。また、操作ボックスは全てデジタル表示にした。全自動型は新製品の液晶タッチパネルPROを搭載。これには同社独自の作物別12種類のオリジナル乾燥プログラムが標準搭載されており、最大30パターンまで記憶する。その他の主な特徴は以下の3点。(1)静音設計で低騒音シロッコファン採用(2)より操作しやすく、見やすいダンパー調整(従来品は乾燥機側面にあった)(3)自由に移動しやすいキャスターを標準搭載―など。同社は新製品の開発コンセプトについて「最近の電気代高騰を踏まえ、従来の電気乾燥機40kgタイプを、さらにランニングコストを低減するべく、乾燥室内温風構造を見直した。これにより省電力化と乾燥時間短縮化の両方を実現した」とし、新製品の販売想定先として「三相200ボルト仕様で規格外品の農産物を利用し、大量に乾燥物を作りたい大規模農業生産者、農業生産法人、食品加工メーカー向けに対応した商品です」とする。6次産業化に取り組む個人・大規模農家や食品メーカーによる導入が進み、高い技術に裏打ちされた同社の製品は国内のみならず東南アジア、米国、中国、スーダン、ケニアなど、海外でも好評で普及が進んでいる。希望小売価格は、「E-20HD-S(標準品)」が100万円(消費税・運送費別)、「E-20HD-PRO(全自動型)」が130万円(消費税・運送費別)。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
蒸れ防ぐ大量輸送袋人気/田中産業 |
|
| |
|
|
| |
田中産業が供給する穀物大量輸送袋「スタンドバッグプロスター」は、容量1300L、1700L、1900Lの3種類。オールメッシュで蒸れにくく、ホルダーレスで輸送がラクラク。スタンドバッグシリーズの中では、人気ナンバー1のプロ仕様製品。グラスファイバーロッドを使って自立し使い勝手がよく、収納の際はひねるだけで折りたたみ・コンパクトで場所を取らない。また、投入口が全開できるため、投入がラク。排出はボタンを押すだけで、スピーディーに作業が進められる。米以外では、麦、大豆、小豆、子実トウモロコシ、ソバ、飼料用米の収穫作業に活用されており、メッシュ素材の蒸れない袋資材としてロングセラー商品になっている。スタンドバッグプロスターRC用の規格は、直径1200×高さ1260mm、同1300×1260mm、同1380×1260mmの3種類となる。このほか同社のメッシュ大量輸送袋にはスタンドバッグスター(容量800〜1700Lの5種類)、スタンドバッグ角プロ(1300、1700L)、スタンドバッグ角スター(1300、1700L)、食品衛生法JIS規格適合品のコンテナバッグ(3段積み対応、最大充填量1080kg、大豆の流通保管に最適)、コンバイン袋DXライスロンがある。また、籾を一時貯留する際などに蒸れを防いで良質な状態を保つ「モミクーラー」も重宝されている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
うね成形機と谷あげ成形機好評/小川農具製作所 |
|
| |
|
|
| |
小川農具製作所のうね成形機と谷あげ成形機が野菜作の効率化機器として好評だ。【台形うね成形機(KSD型)】モデルチェンジを行い、耐久性能が向上し、加えて適応ロータリ幅を1100〜3000mmまで拡大した。また、「成形部 ワンタッチ差し込み機構」は継続して搭載しており、多様な畝作りを手軽に実現できる。例えば、4畝から2畝に変更する場合や、2畝を同時にマルチ作業する場合など、成形部を取り換えるだけで行える(マルチ作業にはオプション機が必要)。従来のうね成形機は本体と成形部が、ほぼ結合しており、故障などの修理時にのみ取り外すことが多いが、同製品は成形部の着脱はワンタッチ。別売のポイントマーカーを装着すると、畝立てと同時に植付け位置をマーキングできる。希望小売価格(税込み)=30万1400円〜/ポイントマーカー(PMS型)15万40円〜【谷あげ成形機(TAS型)】白ネギの植え付け溝を作るのに最適。トラクタのロータリに後付けできる成形機。特徴は(1)「ダブル鉄製平尾輪」を搭載。溝底をしっかり踏み固め移植苗が倒れにくい(2)平尾輪の間にやわらかい土溜りができるので苗を挿しやすい(3)「成形部 ワンタッチ差し込み機構」を採用。うね成形部が着脱できるので多様な畝作りを実現。▽希望小売価格(税込み)=34万5400円〜
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
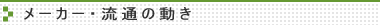 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
売上高1兆4549億円/クボタ2025年12月期第2四半期決算 |
|
| |
|
|
| |
クボタは6日オンラインで会見し、2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信(IFRS=国際財務報告基準)を発表した。それによると当中間期(2025年1月1日〜2025年6月30日)の売上高は前年同期比1247億円(7.9%)減少して1兆4549億円となった。国内売上高は機械部門、水・環境部門の増収により前年同期比266億円(8.7%)増の3323億円となった。海外は機械部門の減収により前年同期比1513億円(11.9%)減の1兆1226億円となった。また農機・エンジン部門の国内売上高は1578億円で198億円(14.4%)増となった。通期の連結業績予想は売上高2兆8800億円(前回発表予想(2025年4月13日発表)は3兆500億円)、営業利益2200億円(同2800億円)、親会社の所有者に帰属する当期利益1420億円(同1960億円)と下方修正した。会見には花田晋吾代表取締役副社長執行役員機械事業本部長、鶴田慎哉エグゼクティブオフィサー(EO)農機国内本部長、横溝敏久農機国内企画推進部長、若園真理恵同マーケティング推進課長が出席した。冒頭花田副社長が決算概要について次のように説明した。第2四半期の実績は売上高1兆4549億円、営業利益1430億円、親会社帰属純利益925億円。為替の影響を除くと売上高が1100億円、営業利益が477億円減収となっている。日本市場では前年同期比で売上げが188億円増加した。これは売上げに関して、米価上昇に伴い農機市場が好調に推移し、農家人口減少にもかかわらず数年ぶりに回復に転じ、製品を遅れなく供給することで昨年を大幅に上回る売上げを達成。建機に関しても、建設工事や都市再開発向けの需要は工事の遅延で若干スローながら概ね順調に推移した。北米では前年比1267億円の減収。建機市場はインフラ向け需要に支えられ堅調に推移したものの、住宅需要は年初から陰りが見え、前年の在庫住宅の反動や上半期の景況感減速により売上げが大きく減少した。個人向けレジデンス市場は低迷したが6月頃から下げ止まりが見られる。農業市場は穀物価格下落で縮小が続くも、畜産関係は牛肉価格安定で縮小幅が穏やかであり、中型プラット分野での新機種導入によりシェアが大きく上昇した。欧州では前年比157億円の減少となったが、建機市場は第1四半期より回復傾向が見られる。トラクタは主要市場で弱含みだが、牛乳価格上昇で酪農家の売上げが増加し、回復への期待が出ている。アジア全体では前年比9億円の減少となった。タイでは稲作向け市場が干ばつからの脱却で回復を見せる一方、畑作向け市場はキャッサバー価格下落で低迷し苦戦したが、トラクタ新機種導入で減少幅を抑えた。インドは昨年の豊作に加え十分な降雨もあり、市場環境は非常に好調で、冬の収穫に向けた作付けも順調に開始されている。〈コスト対策と今後の業績見通し〉営業利益は前年比643億円の減益となった。主な要因として、為替変動による166億円の減益(円高進行)、サプライヤー支援やリスク対応に伴う仕入れ部品価格上昇によるネット24億円の減益、固定費・人件費・減価償却費の増加など経費増による181億円の減益、相互関税の影響による41億円の減益があげられる。一方で、北米での政策調達金利低下やクオリティプログラム抑制によるインセンティブで58億円の増益、製品値上げ(北米中心)で210億円の増益があった。2025年通期の業績予想は売上高2兆8800億円、営業利益2200億円、純利益1420億円であるとの予測が示され、上半期の北米の追加関税影響による景気後退への懸念や減反影響が残ることから、期初計画と比べて厳しい見通しとしている。これに対し、短期的には小売状況を見ながら卸売をコントロールする在庫管理の徹底、関税対策としてインセンティブ見直し、製品価格改定、材料費・固定費削減で対応する。年末に向けて卸売資産を確実に減少させ、特に北米の金融債権を減少させるべく、北米事業の構造転換に取り組む方針とした。〈機械部門の概況〉売上高が前年同期比9.7%減少して1兆2674円となり、売上高全体の87.1%を占めた。国内売上高は前年同期比12.1%増の1741億円となった。主に農業機械及び農業関連商品の増加により増収となった。海外売上高は前年同期比12.4%減の1兆933億円となった。質疑応答では、国内コンバインの供給不足については、「想定超の受注と在庫削減方針が要因。現在は契約済み顧客を最優先、限られた生産能力を有効に割当てる」(鶴田EO)。建機の社内での位置づけについては、「過去10年間で建機事業の成長ペースが農機を上回っているため、自社を農機メーカーであると同時に機械メーカーと位置づけ、双方の事業を伸ばしつつ、短期的には成長性の高い建機事業へより多くの社内リソースを注ぐ方針」(花田副社長)とした。また、今年の関税コストについては、「インセンティブ見直しや固定費削減による自助努力で対応。今後も必要に応じた迅速な価格見直しにより、来年以降のコストアップもカバーしていく」(同)とした。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
クボタが9月1日付人事と機構改革 |
|
| |
|
|
| |
"クボタは5日、9月1日付の機構改革・人事異動を発表した。内容は次の通り(敬称略)。(2025年9月1日)『機構改革』【機械事業本部】1.「研究開発本部」北米研究ユニット(1)「北米研究開発部」を新設し、「シリコンバレー先端技術研究部」(廃止)の機能を移管。『人事異動』〔アセアン統括本部〕▽アセアン統括本部(クボタベトナムCo.,Ltd社長)小林望〔機械カスタマーファースト品質本部〕▽機械カスタマーファースト品質推進部長 三木田大祐▽機械カスタマーファースト品質本部(機械カスタマーファースト品質推進部長兼製品法規統括部長)朝田晃宏〔研究開発本部〕▽北米研究開発部長(シリコンバレー先端技術研究部長)丸山一人〔品質保証本部〕▽製品法規統括部長 大野雅治〔その他〕▽韓国クボタ社長 岡本真宜▽韓国クボタ出向(韓国クボタ社長)鈴木務▽クボタベトナムCo.,Ltd社長 山本昇平"
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
YANMAR CAFEが開店/ヤンマーホールディングス |
|
| |
|
|
| |
ヤンマーホールディングスは2日、東京・八重洲の複合施設「YANMAR TOKYO」1階のヤンマー米ギャラリー内に、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏がプロデュースしたカフェ「YANMAR CAFE」をグランドオープンした。日本酒アイスクリームやノンアルコールの甘酒などを販売し「HANASAKA(ハナサカ)」のもと、日本の食文化や農業の魅力・可能性を発信していく。YANMAR TOKYOは「人の可能性を信じ、人の挑戦を後押しする」という同社の価値観「HANASAKA(ハナサカ)」のもと、日本の食文化や農業の魅力・可能性を発信する拠点として、2023年1月に開業した。ヤンマー米ギャラリーでは、米づくりの歴史と現状を学び、未来の米づくりのあり方について考える体験型コンテンツを提供しており、これまでに延べ約19万人が来場している。今回オープンしたYANMAR CAFEはテイクアウト中心のカフェ。店内では、YANMAR TOKYO内の日本酒アイスクリーム専門店「SAKEICE Tokyo Shop」を運営するえだまめ(東京都渋谷区)が手掛ける日本酒アイスクリームに加え、産地や製法にこだわったノンアルコールの甘酒などを販売している。東京駅へのアクセスが良いので気軽に立ち寄れる。ゆったり過ごせるイートインスペースも設置した。ヤンマー米ギャラリーでは今後、米に関するオリジナルメニューの開発やイベント開催などを通じて、米の魅力を再発見できる新たな価値提供を目指す。【カフェの概要】▽住所=東京都中央区八重洲2の1の1 YANMAR TOKYO 1階(ヤンマー米ギャラリー内)▽営業時間=午前10時〜午後5時▽定休日=月曜日(営業時間と定休日はヤンマー米ギャラリーの休館日に準ずる。月曜が祝日の場合は開業し、翌日が休業となる)。メニュー例は次の通り。日本酒の旨味たっぷりの「日本酒アイス」(計12種)500円(税込み)、北海道産の酒米100%で造った麹の甘酒「いつでも甘酒」200円(税込み)、鳥取県の新ブランド米「星空舞」を使用した甘酒「星空舞 糀甘酒プレーン」350円(税込み)、フローズンタイプの甘酒「ライスブリューミルク」(計3種)450円(税込み)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
TICADエクスポに出展/ヤンマーアグリ、ヤンマーエネ |
|
| |
|
|
| |
ヤンマーアグリとヤンマーエネルギーシステムは、20〜22日の3日間、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で開催される「TICAD Business Expo&Conference」に初出展する。これは第9回アフリカ開発会議(TICAD9)の併催イベントの一つで、TICAD9に参加するアフリカ各国の首脳や閣僚、財界リーダーに向けて日本企業の商品や技術、サービスを発信する場。ヤンマーグループは、190社以上の日本企業や団体が参加する「Japan Fair」にブースを出展し、グループ会社のHIMOINS製可搬式バッテリーシステム「EHR」と汎用コンバイン「YH700」の実機を展示する。また、21日のイベントステージにはヤンマーアグリの所司ケマル社長が登壇し、西アフリカにおける農業機械化推進の取り組みについて紹介する。ヤンマーグループはアフリカ市場での事業を拡大しており、今年5月にはコートジボワールの販売代理店ATC Comafrique(アーテーセーコマフリック)とヤンマーアグリが農業発展に向けた協業に合意している。HIMOINSはアフリカに4つの現地法人を持ち、代理店も設置している。今後もアフリカ各国の農業をはじめとする産業に貢献するソリューションを提供していく。同展示会は日本貿易振興機構(ジェトロ)が主催し、アフリカビジネス協議会(JBCA)が共催。経済産業省、外務省が後援している。【出展概要】▽名称=「TICAD Business Expo&Conference」▽会期=8月20〜22日▽会場=パシフィコ横浜ホールB・C(ヤンマーブース=A30)【イベントステージ】(1)ヤンマーホールディングス主催「Yanmarの西アフリカにおける農業機械化推進活動について」▽日時=8月21日午後1時〜同1時45分▽場所=イベントステージ Stage C(2)ジェトロ主催「トルコと日本企業のアフリカ・第三国ビジネス連携の今」▽日時=8月22日午後12時30分〜同1時15分▽場所=イベントステージ Stage B
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
愛媛県から感謝状/井関農機 |
|
| |
|
|
| |
井関農機は7月30日、同社の砥部事業所(愛媛県伊予郡砥部町)が令和7年度献血運動推進協力団体などに対する愛媛県知事感謝状を受けたことを明らかにした。 同事業所は、長きにわたり献血の啓発活動や継続の取り組みを推進しており、その功績が認められ表彰された。贈呈式は、同日、愛媛県庁で執り行われ、開発製造本部長の代理として総務部の松山総務グループ長が感謝状を受け取った。同事業所は、今回の表彰を励みに、引き続き献血等の社会貢献活動を行っていくと、改めて取り組みの継続意志を示した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
KOMECTがKSASと連携/サタケ |
|
| |
|
|
| |
サタケが提供するライスセンターや精米工場向け生産支援システム「KOMECT(コメクト)」は4日より、クボタの営農支援システム「KSAS」と機能連携した。「KOMECT」はライスセンターや精米工場などでDX(デジタル・トランスフォーメーション)を活用し、生産情報の収集・活用や生産性の向上、顧客の利益改善などを図る生産支援システム。「Kome(米)」と「Connect(接続)」を組み合わせた造語で、米に関わる様々なもの(情報・知見・人・機械など)をつなぐという意味を持つ。サタケは、KOMECTの第一弾として、収穫から乾燥、調製、計量までの工程を見える化することができるライスセンター(RC‥主に大規模生産者)用サービスを4月1日より販売開始していた。「KSAS」は、クボタが提供する農業経営課題の解決をサポートするインターネットクラウドを利用した営農支援システム。パソコン・スマホを利用して電子地図を用いた圃場管理、作業の記録、進捗状況の把握など農業経営を「見える化」する。今回の連携により、KSASに登録済みの圃場データをKOMECTに取り込むことができるようになる。KOMECTの新規利用に当たって、KSASの利用者は圃場データの二重登録が不要となり、稲の生育や施肥の管理などのプレハーベストの工程から、乾燥や調製、計量などのポストハーベストの工程まで幅広い工程のデータを、1つの圃場データに効率的に集約することができるようになる。クボタが提供するデータ連携ツール「KSAS API」を用いてKSASで管理されている圃場データをKOMECT側へ取り込むことができる。取り込む圃場データの項目は「圃場名」、「作付品種」、「地番」、「面積」の4項目。「KSAS API」が提供する情報を使用して、前記圃場データを生成しKOMECT側に取り込む。なお、KSAS APIの連携料金(税別)は1万2000円(1年間、毎年更新、KOMECT、KSASの利用料金は上記に含まれない)。サタケは、今後もKOMECTの導入推進を図り、ユーザーの利益改善や生産性の向上などに貢献していくとしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
TICADエクスポに籾摺精米プラント出展/サタケ |
|
| |
|
|
| |
サタケは20〜22の3日間、パシフィコ横浜で開催される第9回アフリカ開発会議「TICAD9」の併催イベント「TICAD Business EXpo&Conference」で開催される「Japan Fair」で、海外向け事業ブランドの「REACH」をパネル出展する。アフリカ開発会議(TICAD)は、アフリカの開発をテーマとする国際会議。1993年以降、日本政府が主導し、国連や国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)と共同で開催され、例年アフリカ各国の首脳級をはじめとする要人や関係者が参加する。横浜開催は2019年以降、今回が4回目となり、同会場ではアフリカビジネスに関する最新情報の紹介や来場者との交流を目的とした「TICAD Business EXpo&Conference」も併催。「Japan Fair」というイベントでは、日本企業による最先端の製品・技術・サービスを紹介する。今回サタケは、同イベントに、長粒種用加工機械の事業ブランド「REACH」をパネル出展。同ブランドは、主に海外の中規模事業者(ミドル層)を対象とした籾摺精米プラントで、東南アジアや南米、アフリカなどで販売しており、従来プラントと比較して、コスト効率に優れ、短工期・高品質を特徴としている。なお、出展ブースはホールB・C内フードバリューチェーンカテゴリーブース番号G03で、開催時間は10時から18時まで(初日は11時から。最終日は17時まで)。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
売上高11.8億円/タカキタが2026年3月期第1四半期決算 |
|
| |
|
|
| |
タカキタは1日、2026年3月期第1四半期決算短信(2025年4月1日〜2025年6月30日)を発表した。それによると、売上高は11億8100万円(前年同期比25.2%減)、営業利益は9300万円の損失、経常利益は7800万円の損失、四半期純利益は5600万円の損失となった。通期予想は売上高72億円(前期比2.7%増)、営業利益3億5000万円(同1.5%増)、経常利益3億8800万円(同2.9%減)、当期純利益2億5400万円(同55.2%減)と、4月30日に公表した予想を据え置いた。決算概要は次の通り。農業機械事業は、米価高騰による水田市場での需要が回復基調にある一方で、主力である畜産・酪農市場では、輸入飼料や肥料、燃料費の高止まりなどを背景として機械投資が低調に推移した。国内売上高は、有機肥料散布機の受注が堅調に推移したものの、国産飼料増産に寄与する牧草梱包作業機や細断型シリーズなどのエサづくり関連作業機の受注は低迷し、前年同期比で減収となった。海外についても、欧州および韓国市場における需要停滞が続いており、減収となった。以上により、農機事業全体の売上高は、前年同期比3億6900万円減少し10億8200万円(前年同期比25.4%減)となった。軸受事業においては、得意先からの受注減少により、売上高は前年同期比2800万円減少し9800万円(同22.6%減)となった。以上の結果、当事業年度の売上高は、前年同期比3億9800万円の減少となり、11億8100万円(同25.2%減)となった。損益面においては、売上高の減少とそれに伴う生産量の減少が売上原価率を押し上げ、営業損失9300万円(前年同期は営業利益8000万円)、経常損失7800万円(前年同期は経常利益9300万円)、四半期純損失は5600万円(前年同期は四半期純利益4400万円)となった。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
2日間で成約6億円/JA全農かながわが農機展示予約会 |
|
| |
|
|
| |
JA全農かながわは1、2の両日、神奈川県平塚市の全農かながわ田村事業所で「農業機械展示予約会」を開催した。会場内には共同購入コンバインYH448AEJU(51.5PS、4条刈)を展示したほか、関東6県JAグループスペシャルトラクタYT357RJ、YGQH、県独自の推奨型式21品目などを並べた。来場者数の目標を1800人、成約計画は5億4000万円と設定。それに対して2日間で1555人が来場し、実績は速報値で6億900万円となった。開催翌週いっぱいをフォローアップ推進期間とし、さらなる実績アップにつなげるねらいだ。中尾信二農産部農機・自動車課長は「晴天には恵まれたが、台風接近で風が強い中での開催となった。来場者数は目標には届かなかったが、購入意欲の高い生産者に来てもらえた。今回はコンバインや田植機、米関連の機械の動きが良かった」と振り返った。会場で注目を集めていたのは、草刈機コーナー。実演を行うメーカーもあり、来場者が機械の特徴や性能について担当者に熱心に質問していた。夏場の草刈り作業の効率化・省力化のために欠かせない草刈機は、需要が伸びている。米価高騰の影響で生産者の購買意欲が全国的に高まっており、神奈川県内でも好調を維持している。スマート農機はラジコン草刈機や自動操舵に動きがあり、カメムシ被害が増えていることから動力噴霧器なども人気だそうだ。「米価高騰の良い影響が出ているが、いずれ反動が来てしまうのではないかという不安もある。機械導入に対する案内をどれだけ周知していくかが課題。農機価格の高止まりで先が見えない中、価格低減の取り組みもしていかねば」と中尾課長。中古農機コーナーにはトラクタや田植機、管理機など20種類が並んだ。リーズナブルな値段で手に届きやすいとあって中古需要も旺盛だという。この他、クボタアグリサービス、ヤンマーアグリジャパン、やまびこジャパン、丸山製作所、静岡製機、カンリウ工業、ネポンなどが、独自のブースを出展し、自慢の製品を紹介した。連日開催したミニ講習会では、ウルトラファインバブルや管理機の安全作業、スマート農業技術、刈払機の安全講習、ディーゼルエンジンのセルフメンテナンスについて、各メーカーの担当者らが解説した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
大型インパクトレンチ下取りセール/空研 |
|
| |
|
|
| |
空研は「大型インパクトレンチ下取りセール」を8月21日から始める。セール期間は2025年12月31日まで。期間中、対象機種を購入すると、手持ちのエアツールが下取りされる。対象機種は、同社の25.4mm角ドライブインパクトレンチの全機種。G、GS、GLR、GLSアンビルおよびP型も対象機種に含む。下取り機のメーカーは問わないが、25.4mm角以上のインパクトレンチに限る。対象機種の詳細は以下の通り。(1)25.4mm角・N型大型レンチ=KW-3800P(-5/PS)、同4500P(PS)、同3800proXGL(GLR/G/GS/GLS)、同3800 ISO-GL(GLS)、同4500GL(G/GS/GLS)。(2)25.4mm角・D型とその他大型レンチ=KW-380P(PS)、同385GL(GLR/G/GS/GLS)、同420GL(G/GS/GLS)、同40P(PS)。セール期間中に(1)の対象機種を注文し、25.4mm角以上の下取り機があれば、1台当たり1万5000円の下取り値引きを実施する。(2)の場合、25.4mm角以上の下取り機があれば、1台当たり1万円の下取り値引きを実施。また、これら下取りセールに加え、追加特典として「空研オリジナル防寒ブルゾン」が1着進呈される(製品に同梱して出荷)。同社の大型インパクトレンチは、大型自動車のタイヤ脱着作業をはじめ、建機の分解整備や組立て作業などに威力を発揮する。プロ仕様の整備用機械器具として整備現場の作業者はもとより、業界関係者から好評を博している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
温水除草応用し防虫効果実験/ケルヒャージャパン |
|
| |
|
|
| |
ケルヒャージャパンは沖縄県古宇利島で、「温水除草システム」を活用した外来種「ヤエヤママドボタル(オオシママドボタル)」の防除実証試験に協力した。今回の試験は、沖縄県環境部自然保護課の委託事業「令和7年度外来種対策事業(昆虫類・クモ類対策)」の一環で実施。薬剤を使わず高温水のみでホタルの個体数を抑制する効果検証が行われた。「温水除草システム」は、100度C近い高温水を散布して雑草の生長や繁殖を抑制する技術で、今回は昆虫防除に応用した。事前実験では、ヤエヤママドボタル幼虫に温水を直接散布、全個体(12個体)が異常個体化し死亡。幼虫は3〜5秒の散布で効果が確認された。また、植物への影響では、草本はしおれたものの色彩は保持。木本植物では茶変がみられたが、枯死には至らなかった。この結果から、同システムは環境への影響を最小限にしつつ、ホタル防除効果が期待できることが示唆されている。ヤエヤママドボタルは、近年、生息地域の拡大で在来生物の減少や生態系バランスの崩壊が懸念されている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
熱中症対策商品を提案/アクティオがセミナー |
|
| |
|
|
| |
アクティオは7月30日、千葉県市原市の同社プラント営業課で「暑さ対策体験型プレスセミナー」を開催した。同社はかねてより、猛暑日が増加する近年の気候変動を受け、建設など屋外の現場で働く人々の健康と安全を守るための包括的な熱中症対策に積極的に取り組んでいる。近年の夏の異常な高温傾向により、労働現場における熱中症対策の重要性が高まっている。さらに6月には改正「労働安全衛生規則」が施行され、全ての事業者に対して熱中症の重症化を防ぐための具体的な防止措置の実施が義務付けられた。今回のプレスセミナーでは、連日の猛暑の中で過酷な建設現場等に従事する作業員の健康を守る同社の暑さ対策商品が紹介された。夏の暑さから現場を守る商品として、4つの特徴を持つ商品が示された。(1)近場・近辺を冷やす商品▽ポータブルスポットクーラー充電式「エコやん」=工事不要でコンパクトなため持ち運びが簡単。バッテリーユニット・AC100V・DC電源で使用可能。吹出口で周囲よりマイナス8度Cの冷却効果▽「冷える〜む2」=循環式クーラーを使用し効率よく室内を冷やす。テントは少人数で簡単に組み立て可能。収納がコンパクトでキャスターがついているため移設が簡単。(2)広範囲を冷やす商品▽移動式エアコン「クールキャノンエコ」=10m先まで届く大風量(60Hz地域では12m)。扇風機/冷風扇/冷風扇+クーラーの3モード。水の気化を利用し冷やされた空気を熱交換器でさらに冷却することで消費電力が少ない▽移動式エアコン「スーパークール」=外気温から最大-13度Cの冷風が500m先まで届く。屋外や半開放空間でも使用可能。(3)体内から冷やす商品▽業務用かき氷機「Blizzastar J」=家庭用電源(100V)やポータブル発電機でも使用可能。(4)現場環境を管理する商品▽熱中症リスク判定AIカメラ「カオカラ」=外部環境×生体データで個人ごとに顔画像をAIカメラが高精度判定。判定撮影は最大3秒。リスク判定データは一元集約し管理者は全体及び個々の状況をいつでも把握可能。同社は他にも数多くの熱中症対策商品を保有し、猛暑の中での過酷な労働現場における熱中症対策への貢献を目指す。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
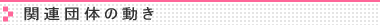 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
アフリカ農業の機械化推進/JICA・AFICAT事業 |
|
| |
|
|
| |
JICA(独立行政法人国際協力機構)はアフリカ地域に日本の先進的な技術の導入や農業機械化を推進するため、AFICAT(日・アフリカ農業イノベーションセンター)を立ち上げ、その一環で7 月28日から8月1日にかけて、重点支援5カ国の1つであるコートジボワールにて、有識者・メディア関係者による現地視察を行った。一行は現地でAFICATを推進する同国農業省などの機関を表敬し、水田圃場における農機作業を確認。さらに精米所や米流通業者協会における農機の活用状況を視察、本邦農機メーカー販売店並びに本邦企業を訪問するなど同国における稲作と農業機械化、本邦企業の同地進出の実情などを見て回った。AFICATは、JICAが推進し、アフリカ諸国における先進農業技術の導入促進を官民連携で実施する事業。2019年8月に開催されたTICAD7(第7回アフリカ開発会議)を契機に検討が開始され、アフリカでビジネス展開を検討する本邦の農業関連企業を対象にアフリカ進出を支援しており、アドバイス、展示、実証等の支援を行い、アフリカ諸国における先進農業技術の導入促進を図るもの。2022年2月からタンザニア・コートジボワール・ナイジェリア・ガーナ・ケニアの5カ国にて順次稼働し、昨年2月より新フェーズとして引き続き活動している。AFICAT対象各国では、本邦企業への各種支援、現地の農業関係者からの問い合わせ対応など、現地活動の実施部隊としてAFICAT委員会を順次、設立。コートジボワールでは、農業省の機械化担当局・稲作局に加え、コメ政策の実施機関であるコメセクター開発機構(ADERIZ)、民間セクターの代表としてコートジボワール商工会議所(CCI-CI)を主要機関として、その他国立農業研究センターや農村開発支援公社など様々な機関が参加している。今回の視察ではAFICATコートジボワール委員会の官民主要機関である、農業省、ADERIZ、CCI-CIを表敬。各機関の取り組みや、解決すべき課題などについて意見交換を行い、AFICATの重要性を確認し、日本の技術への期待が示された。また、生産現場視察では、同国中央部のヤムスクロ近郊の灌漑圃場にて中国製(東風井関農業機械)の歩行型耕うん機による耕うん作業の様子を視察。ヤムスクロの北にあるサカスでのCORISAK(サカスコメ農家組合)視察では、広大な灌漑水田にて、ヤンマーミニコンバインによる刈取り風景を視察した。同地区では、壊れて作業が中断していたヤンマー製・クボタ製のコンバインも確認し、故障の実態を聞き取りした。CAFREX(農機サービスプロバイダー)では、中国製による精米プラントの稼働状況を確認した。最大都市アビジャンにあるコートジボワール・コメ流通協会では、JICAが進める技術協力プロジェクトPRORIL2(国産米振興プロジェクトフェーズ2)で導入したサタケ製の光選別機、カンリウ工業製の石抜機の稼働状況を確認。米品質が確実に向上したとの現場からの評価を得た。クボタ・ヤンマーの農機販売代理店の訪問では、日本農機の販売戦略やその実績、評価などをヒアリング。いずれの日本農機も農業現場から高い評価を受けていることを確認した。また、本邦企業(コマツ・伊藤忠商事)の訪問においては同地進出の実態や課題などを詳しく聞いた。その他、PRORIL2事務所やJICA事務所なども訪問した。農政当局をはじめ、生産から加工の現場、農機販売店までさらった中身の濃い視察であったが、総じて感じたのは、農業機械が圧倒的に足りておらずポテンシャルが大きいということだ。同国の米の需要は高く、安い輸入米に頼りがちな現状を打破すべく、当局も増産に力を入れており、その一環で機械化を官民一体となって推進している。そして日本の技術への期待も高い。日本農機が役立てるチャンスも様々あるように感じるものの、農業や商取引をめぐる環境・習慣・仕組みの違いなどで課題も大きい。次週以降からコートジボワールの農業と農業機械化の実情について、詳しくみていく。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
コートジボワール有識者視察で報告会/JICA |
|
| |
|
|
| |
JICA(独立行政法人国際協力機構)は5日、食と農の協働プラットフォーム(JiPFA)アフリカ農業分科会/日・アフリカ農業イノベーションセンター(AFICAT)有識者会合コートジボワール視察報告会をオンラインで開催した。AFICATはJICAが推進し、アフリカ諸国における先進農業技術の導入促進を官民連携で実施する事業。今回、7月28日から8月1日にかけてAFICAT重点支援5カ国の1つであるコートジボワールにて、有識者・メディア関係者による現地視察を行ったことを踏まえ、この報告並びに、有識者からAFICAT活動への提言が行われた。開会挨拶したJICA上級審議役・山口博之氏は、AFICAT事業のこれまでを振り返り、有識者による現地視察について、まず2022年にタンザニアの農業機械化を視察し、その後様々な場面で対象5カ国の情報発信がされたことで企業からの問い合わせも増えたと述べた。そして、今回はコートジボワールであり、対象国5カ国のうち物理的な距離やフランス語圏であることなどを要因に関心がまだ低いと述べ、今回の視察を広く発信してもらうことで日本企業が西アフリカに目を向けるきっかけの1つにしたいなどと語った。次いでJICAコートジボワール事務所・中川氏が「コートジボワール農業分野の概要」を説明。同国はGDP787.9億ドル、経済成長率6.4%の西アフリカの経済大国。主要産業の農業ではカカオ・カシューナッツが生産量世界1位で、消費量が増加している米は約半分を輸入に依存している。米など食用作物は生産性が低く、農家の生産投資不足、機械化の遅れ、灌漑システムを含む施設の整備・修繕・適切な管理の欠如が生産性の低さにつながっているなどとし、それに対する日本の支援方針とJICAの取り組みを紹介した。有識者の視察結果報告では、かいはつマネジメント・コンサルティング・弓削田高大氏による視察の概要説明の後、有識者4名・メディア2名の報告が行われた。そのうち日本農業機械工業会専務理事・石井伸治氏は、機械化の課題として、消耗品・修理部品の迅速な供給と修理体制の構築、オペレータ・修理技術者の教育、精米所における停電による稼働ロス、生籾の安定的な調達などを示した。日本農業機械化協会専務理事・藤盛隆志氏は、品質・歩留まり向上による稲作収益増には直播と機械乾燥の実証・普及が鍵になるとし、また、圃場・農道の整備や排水性向上などインフラの課題解決も重要だと述べた。さらに課題として、コンバインを中心とした農機のアフターサービス(修理整備体制、スペアパーツのアクセス)等も提示した。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
世界の飢餓人口6.7億人/FAOがSOFI発表イベント |
|
| |
|
|
| |
FAO(国連食糧農業機関)駐日連絡事務所は1日、「世界の食料安全保障と栄養の現状(SOFI):2025年報告」発表イベントをオンラインで開催した。「世界の食料安全保障と栄養の現状(SOFI)」は、FAO、IFAD(国際農業開発基金)、UNICEF(国連児童基金)、WFP(国連世界食糧計画)、WHO(世界保健機関)の国連5機関が共同で作成する主要な年次報告書。世界の飢餓の撲滅、食料安全保障の達成、栄養の改善に向けた進捗状況などについて、毎年、モニタリング・分析を行い報告している。2025年版では「食料安全保障と栄養のための高騰する食料価格インフレへの対応」をテーマに、2030年までに飢餓、食料不安、栄養不良をなくすという持続可能な開発目標(SDGs)2.1および2.2の達成に向けて、食料価格の上昇がもたらす課題を分析。さらに、近年の食料価格インフレの要因や、それが食料安全保障や栄養に及ぼす影響、そして、これらの影響を防ぎ緩和するために必要な政策対応について取り上げた。開会挨拶に立った外務省経済局審議官の小林出氏は、同報告書を「飢餓撲滅、食料安全保障、栄養改善等に関する客観的なデータに基づく分析を提供し、国際社会がこれらの課題に取り組むベースとなる貴重な資料である」としたうえで、国際機関などと密接に連携し、同報告書を活用して、世界の食料安全保障の強化に引き続き貢献していく旨を述べた。続いてFAOのチーフエコノミストであるマッシモ・トレロ氏が、同報告書のポイントを解説。まず、2024年の世界の飢餓率は8.2%で、2年前に比べて0.5ポイント減少しているものの、いまだに6億7300万人が飢餓状態にある現状を報告。このままいけば、2030年に飢餓に苦しむ人は5億人以上にのぼると推計され、飢餓ゼロの目標達成にはほど遠い状況であると危機感を示した。また、2025年版のテーマである食料価格のインフレについては、食料安全保障と栄養の最大の脅威の1つであると述べ、パンデミック以降、全体のインフレ率を上回るペースで食料価格が上昇し、特に発展途上国に大きな打撃を与えていると指摘した。一方で、同報告書の主要なメッセージの1つとして「食料価格インフレは喫緊の課題ではあるが、克服できないものではない」と明言。課題克服のためには、国や分野、機関を超えた協業が重要で、投資の継続、政策協調の活用、透明性の向上、制度の革新が不可欠であるとした。そして、これらの政策的教訓は、食料価格インフレが食料安全保障や栄養に及ぼす即時的な影響の対応と、SDGs目標2の達成、さらには全ての人が手頃で健康的な食事を実現するという包括的な目標に向けたロードマップを示しているなどと述べた。そして「今こそ、アフリカへの支援に注力すべき。アフリカにおける農業システムの改革を実現できれば、飢餓をゼロに近い水準にまで減らすことができる」と自信をのぞかせた。その後、共同発行機関からの報告として、WFP、IFAD、UNICEF、WHOの各担当者が発言。このうち、WFP日本事務所代表の津村康博氏は、同機関について「国連の食料支援機関として、紛争や自然災害の影響を受けた地域に対する迅速かつ柔軟な食料支援を提供している。また、学校給食や土地の再生、生産者たちのマーケットへのアクセスなどの支援を通じて、地域社会の自立とレジリエンスを支えている」と説明。そのような活動を通じた現状として、パレスチナのガザ地区やアフリカのスーダンでは、紛争などにより安全やアクセスの確保が難しいため十分な支援ができず、深刻な飢餓状況に陥っていると報告。これらの地域で安全に支援できる環境が整えば、飢餓人口を減らすことができると強調した。そして「世界は食を通じてつながっている。今回の報告書が、日本と世界の食の問題を考える機会になれば」と期待を寄せた。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
秋の農作業安全啓発ポスター/日農機協が作成 |
|
| |
|
|
| |
一般社団法人日本農業機械化協会はこのほど、令和7年秋の農作業安全啓発用ポスターを作成した。同ポスターは農林水産省による昨年度の農作業安全ポスターデザインコンテストの入賞作品を使用して作成した。同協会では、このポスターを地域における秋の農作業安全の啓発活動に広く活用してほしいとしている。ポスターサイズはB2判(728×515mm)、価格は1枚160円(消費税、送料別)、購入枚数に応じて値引きあり。ポスター下部の空白部分に啓発活動実施機関名等の印刷可能。印刷費用はモノクロで、300枚以下は1万5000円(税別)、300枚を超える場合は1枚につき14円を加算。1000枚以上は2万4800円(税別)。カラー印刷は別料金。このポスターは同協会でのみ作成しているもので、農林水産省からの配布はない。購入申し込みは申込書に必要事項を記入のうえ、同協会までFAXまたはメールで送付する。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
国産国消PRでサイト更新/JA全中 |
|
| |
|
|
| |
JA全中はこのほど、乃木坂46の協力を得て展開している「国産国消」の特設ウェブサイトを更新した。全中では、特に若年層に向けて、日本の食や農業の現状を知ってもらい、より一層、国産農畜産物を手に取ってほしいという思いから、乃木坂46の協力を得て、令和2年12月から特設ウェブサイトを基点にメッセージ発信を行っている。6年目となる今年は、料理や食事をより意識したビジュアルへと更新し、消費者に国産農畜産物のおいしさや調理の楽しさを感じてもらえる内容となっており、「推し食材」を担当するメンバーを一部入れ替え、順次動画やクイズなどを展開する。動画の内容は、乃木坂46メンバーが好きな食材を使ったレシピに挑戦。実際にキッチンに立ち、料理する姿を他のメンバーがにぎやかに実況している。メンバーならではの自然なやり取りとともに、国産農畜産物のおいしさや調理の楽しさを感じられる内容となっている。新たに野菜担当となった井上和は「私はキュウリが好きですが、皆さんの推し野菜は何ですか?おいしくて、安心安全な野菜が食べられるのも農家の皆さんが心を込めて作ってくれているからこそですね!新鮮な野菜を毎日食べて農家の皆さんを一緒に応援しましょう」とコメントしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
山野会長が来年3月に辞任意向/JA全中 |
|
| |
|
|
| |
JA全中の山野徹会長は1日の定例会見で、来年3月をメドに、会長職を辞任する意向を表明した。新Compass-JA事業の損失発生に端を発した諸課題への対応に一区切りがついた時点で辞任する考え。定例会見の要旨は次の通り。7月23日に、米国の関税措置に関する日米協議が合意に達したことが日本政府より発表されました。合意内容の詳細を待つ段階ではあるものの、厳しい交渉が続く中、農業を犠牲にするような交渉はしないとの方針を堅持し、日本側の農産品の関税引き下げを回避したことについて、赤澤経済再生担当大臣をはじめ交渉にあたられた関係者の皆様のご努力に敬意を表します。米についても、合意内容は、既存のミニマムアクセスの範囲内で米国から調達割合を増やすものであり、主食用米として流通することはない、と小泉農林水産大臣は明言されています。合意内容の詳細や運用について、我が国の米の生産や需給に影響を与えることがないよう、引き続き注視してまいります。一方、15%の相互関税が、我が国の農畜産物の対米輸出に与える影響について、精査するとともに、輸出に取り組む産地や事業者への万全な対策の措置を引き続き求めてまいります。さて、8月1日の理事会において、JAグループとして、「令和8年度農業関係予算に関する要請」を決定しました。参議院選挙が行われ、政局は不安定な中ではありますが、8月末にかけて、令和8年度予算概算要求が行われる見通しであります。食料安全保障の確保が明記された、改正基本法および基本計画にもとづき、農業構造転換集中対策を推進するため、農業関連予算総額の抜本的な拡大が必要であり、8月1日に決定した要請にもとづき、働きかけを進めてまいります。最後に、全中が進めてきた新Compass-JA事業の損失発生に端を発した諸課題への対応について、職責を全うして難局を乗り切っていくことが、私に課された責任であると考えておりますが、その対応について組織として決定いただく時点を一つの区切りとして会長の職を辞することを、8月1日に開催した本会理事会、および、全国のJA中央会会長が集まるJA中央会・全国機関会長会議で表明いたしました。その時期については、令和8年3月になろうかと思います。会員から理解と納得をいただくため、十分な時間をとって協議を進めているものを「JA全中刷新プラン」として決定いただくのが令和8年3月の臨時総会となることから、また、全中会長の選出には、諸手続きおよびそれにかかる一定の時間が必要であることからも、その時期を想定しております。「JA全中刷新プラン」の実践は、新しい方に牽引していってもらうこととなりますが、それまでの間は、引き続き、会員の声をよく聴き、組織内外にJAグループを代表した発言を行いながら、職責を全うして難局を乗り切っていくことで、しっかりと全中会長としての責任を果たしてまいります。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
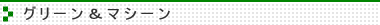 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
芝刈機など電動化促進事業に採択/やまびこ |
|
| |
|
|
| |
やまびこの子会社であるやまびこジャパンが販売するロボット芝刈機など電動農業機械3機種5型式が、令和7年度「農業機械の電動化促進事業」の補助対象機種として採択された。同事業は環境省および農林水産省が共同で推進する農業機械の電動化促進を目的とした補助制度。全国の農業現場における電動農業機械の導入を支援し、CO2排出削減や生産性向上に資するモデルケースの形成を目的としている。今回の採択は同社製品の環境性能と実用性が高く評価された結果で、農業分野における脱炭素化の推進に大いに貢献するとみられる。採択された対象機種は、ロボット芝刈機「TM-1000/TM-1050」、「TM-2000/TM-2050」、電動高所作業機「KCEB250/R」、電動作業機「KWE103」、「KWE104」の3機種5型式。ロボット芝刈機「TM-1000/TM-1050」、「TM-2000/TM-2050」は無人管理で昼夜問わずフルタイムでの稼働が可能。常に刈り続けることで芝を伸ばさず、刈り揃った状態を維持する。高所作業機「KCEB250/R」は走行クラッチが不要で軽快かつ滑らかな走行が可能な電動モデル。モーター駆動により作業音は非常に静か。早朝や住宅地付近でも周囲に配慮した作業が行える。電動作業機「KWE103」は棚下作業から運搬作業まで1台でこなす。春先の剪定、誘引作業から収穫まで座ったまま作業可能。シートを外せばコンテナ6個を運べる運搬台車としても使える。同社は「人と自然と未来をつなぐ」という企業理念のもと、自然環境や社会課題の解決に資する製品開発に注力してきた。今後も電動製品のラインアップ拡充を進め、農業現場の脱炭素化と作業効率向上に貢献していく。補助対象機種の登録事業者は同社販売子会社であるやまびこジャパン。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
新施工計画支援ソフトリリース/コベルコ建機 |
|
| |
|
|
| |
コベルコ建機はこのほど、クレーン施工計画を策定する支援ソフト「K-D2 PLANNER」の最新バージョンアップ版(AJ1、4、1.2版)をリリースし、4日から体験版を提供した。今回体験版として提供する同ソフトは、直感的なクリック操作でクレーンの吊り荷姿勢を作成し、その姿勢での負荷率や平面図、断面図などを作成できるシミュレーションソフト。エビデンスを残しながら3D、施工ステップ図を作成できるため、現場とのイメージ共有が的確にでき、最適なクラスのクレーン選定が可能になるなど、施工計画の精度向上、策定時間の短縮、コスト削減に寄与する。また、画面上でクレーンの玉掛と玉外しの姿勢を設定するだけで運搬経路の工程を自動生成する機能を新たに搭載している。さらに、干渉領域とのクリアランス(離隔距離)を設定すれば、障害物を避けた運搬経路を作成可能。加えて吊り荷位置を任意に指定できる機能を搭載し、重心が形状の中心にない吊り荷でもフックを重心位置に合わせられるようになり、利用するクレーンの能力や運搬経路の確認がより的確にできるようになった。同製品に対する問い合わせ先は同社コーポレートコミュニケーショングループ。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
建土セル特価販売/レンタルのニッケンが発表 |
|
| |
|
|
| |
レンタルのニッケンは5日、物流の適正化と生産性向上を目的とした自主行動計画を策定し公表した。物流に関わる各主体(第1種荷主、物流事業者、第2種荷主など)が共通して取り組むべき事項を整理し、改善策を実施することで持続可能な物流体制の構築を目指している。計画は(1)第1種荷主・第2種荷主に共通する取り組み事項(物流体制の効率化・合理化、運送契約の適正化、輸送・荷役作業等の安全の確保)、(2)第1種荷主としての取り組み事項(物流業務の効率化・合理化)、(3)第2種荷主としての取り組み事項(同)、(4)建設機械器具賃貸業の特性に応じた独自の取り組み―からなる。(1)では入荷にかかる荷待ち時間および荷役作業にかかる時間の把握、その時間が2時間以内の場合はさらなる短縮に努める、物流管理統括者の選定、パレット等の活用、システムや資器材の標準化、運賃と運送以外の役務などの対価である料金を別建てで契約、下請け取引の適正化、荷役作業時の安全対策などを掲げた。また(4)では協力会社が荷主事業者の場合は(1)〜(3)について対応することを要請し、荷待ち時間、附帯業務の内容を規定した。一方、同社は9月末までの間、同社とトラスト中山の共同開発商品「建土セル」のサマーキャンペーンを実施し、通常1万5340円(税別)の同製品を1万円(税別)で販売する。「建土セル」は現場の巡回などの際に便利なオールインワン仕様のバッグで、工具・文房具・タブレット端末などをまとめて管理・携行できる。特徴は荷物の重みで倒れない縦置き自立型で、取り外し可能な工具収納キャリー(裏面は図面入れやボード機能)、背面セキュリティポケット、タブレットポケット、工具収納ベルト、スプレー缶ポケットが付く。また止水ファスナーなど防水対策を施し、底面は防水・防汚仕様で泥だらけの地面にも置ける。サイズは縦190×横285×縦435mm、重量は980g。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
ミニショベルガイド公開/日本キャタピラー |
|
| |
|
|
| |
日本キャタピラーは、農業から土木までユーザーの希望に適う油圧ミニショベルを選ぶのに便利な「Catミニ油圧ショベル機種選定ガイド」を公開し、購入やレンタル機の決定に役立てている。ガイドでは(1)0.5〜2t級 後方超小旋回機、(2)3〜5t級 後方小旋回機、(3)3〜5t級 超小旋回機の3分類に分け、▽作業時に必要となる教育・資格/排ガス規制・低騒音▽主要諸元▽機種選定のポイント▽ワークツールの各項目に対応する内容を記載。各ユーザーの現場で最も機能を発揮しやすく、使いやすい製品の選択に役立つ内容としている。一部を具体的に見ると、次世代ミニ油圧ショベルの301.7CRおよび302CRは、機体質量3t未満で技能講習不要で運転可能、国交省第3次基準値排出ガス対策および超低騒音型建設機械に適合。機体や作業に関わる諸元が細かく示され、運転席はソフトキャノピ脱着可能な2柱、ROPSキャノピの強固な4柱、ROPSキャブエアコン装備のいずれかを選べる。ブレーカ配管仕様(オプション)は、ブーム中央部まで内蔵配管、ブーム中央部からアーム先端まで配管、スライド右親指スイッチ+右ペダル操作、流量調整機能、コンティニュアス(連続)フロー機能を記載。ワークツールはバケット、ブレーカ、オーガ、コンパクションホイールそれぞれの仕様を明示している。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
各種草刈機揃える/丸善工業 |
|
| |
|
|
| |
丸善工業は、油圧ショベル搭載型草刈機の拡販に力を入れている。供給機には(1)円盤式草刈機GC-600-1=硬い草や雑木、竹の刈り取りに最適、(2)フリー刃仕様草刈機GC-300F-1=幅広い種類の草刈り、(3)ヘッジトリマー式草刈機GC-1000/1500=剪定作業がメーンの場合に、(4)マルチャーMVM-1000=草・木・竹をまとめて処理―があり、それぞれ用途に合わせて選択できる。各機の特徴をみると、(1)は標準装備が40枚刃だが、刈刃は4種類から選べ、刈刃の交換によって雑木や竹、軟らかい草にも対応可能。(2)は刃の付け替えなく軟らかい草から硬い草、約φ30mmの小枝にも対応できるオールラウンダータイプ。(3)は飛び石の発生が非常に少なく、安全性が求められる道路脇や住宅街など飛散リスクを避けたい現場に最適。絡みやすいつる草もスムーズに刈り取る。(4)はタングステン刃のついたドラムを回転させ対象物を粉砕する機械で、草・木・竹をその場で粉砕し専用機械を揃える手間やコストが省け、高い作業効率を誇る。粉砕物はそのまま堆肥化でき、後処理がラクというメリットもある。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
第19回トップセミナーを開催/全森連と農林中金 |
|
| |
|
|
| |
全国森林組合連合会と農林中央金庫は7月31日、8月1日の2日間、第19回森林組合トップセミナー・森林再生基金事業発表会の模様をライブ配信した。これは、森林組合系統の経営層などを対象に、最新の林業情勢への理解と先進的な経営マインドの醸成を目的として、毎年開催しているもの。今回は、ネイチャーポジティブについての基調講演、部下の育成をテーマにした特別講演、そして第10回農中森力基金事業の成果報告が行われた。最初に、主催者を代表して中崎全森連会長と北林農林中金理事長が挨拶。中崎会長は、全国各地で発生した林野火災の被災者に向けてお見舞いを述べるとともに、1日も早い復興と森林再生に努めていきたいと述べた。また、2024年度から、基金による助成対象が従来の森林整備に加え、空間利用や生物多様性にも広がったことを受け、地域課題の解決に向け、さらなる応募の検討を呼び掛けた。基調講演では、東北大学グリーン未来創造機構/大学院生命科学科教授の藤田香氏が「ネイチャーポジティブの動向と森林の関わり」と題して講演。「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動を取る」というネイチャーポジティブの世界的取り組みを説明。我が国でも2024年3月に「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」が策定され、企業のネイチャーポジティブ経営が進んでいることを示した。自然保全を重要課題と位置付け、自然への貢献を最大化する同経営は、株価向上などにつながりビジネス機会にもなることから、2030年には日本の市場規模が47兆円にまで拡大することが予測されている。今年4月には林野庁が「森林の有する多面的機能に関する企業の自然関連財務情報開示に向けた手引き」を発行。近年は森林由来カーボンクレジットの人気が高まっているとし、その理由として、森林には脱炭素だけでなく、水源涵養、生物多様性向上の機能もあり、国連が求めるネイチャーポジティブ経営を進められることなどをあげた。将来的には、水や生物多様性のクレジット化への広がりも想定され、ネイチャーポジティブにおいて、森林は多くの可能性を秘めているとした。その後2日間にわたり、農中森力基金事業発表会が行われ、▽ICTを活用した被災森林復興(苫小牧広域森林組合・北海道)▽松くい虫被害地の森林機能の再生(遠野地方森林組合・岩手県)▽鳴子温泉「雫の森」再生プロジェクト(大崎森林組合・宮城県)▽山林火災からの速やかな森林再生(西白河地方森林組合・福島県)―など、全国7事業の取り組み成果が報告された。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
高品質の生産称える/全国乾椎茸品評会 |
|
| |
|
|
| |
日本椎茸農業協同組合連合会と全国椎茸生産団体連絡協議会は6日、都内新宿区のホテルグランドヒル市ケ谷で、第72回全国乾椎茸品評会表彰式を開催した。今回の地区予選会への出品点数は、昨年より13点少ない1384点。一方、出品地区は2県増えて9県だった。この中から、農林水産大臣賞5点、林野庁長官賞20点などが選ばれた。表彰式で挨拶に立った全国乾椎茸品評会会長の阿部良秀氏は、原木椎茸の生産量が10年間で半減している現状に危機感を示し、生産者が心配なく生産できるよう、原木椎茸を未来につなげる活動に努めるなどと述べた。団体の部では、昨年に続き大分県が優勝。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
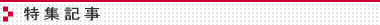 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
県発の農機で生産に貢献/岡山県特集 |
|
| |
|
|
| |
晴れの国おかやま。温暖な気候に恵まれた岡山米は米の食味ランキングで最高ランクの特A取得の「きぬむすめ」や「にこまる」をはじめ、中北部では「あきたこまち」や「コシヒカリ」、南部ではすし米など、業務用として需要が増加する「朝日」や「アケボノ」などが盛んに生産されている。また、県発の良質な作業機や草刈機メーカーが、岡山県のみならず全国の作物生産に貢献している。 (取材は6月下旬〜7月初旬)
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
出荷台数が大幅伸長/岡山県特集・市場の概況 |
|
| |
|
|
| |
県内の農機市場は米価の高止まりの影響を少なからず受け、県南の大規模農家による農機投資が活発化している。一方、県内に点在する兼業・小規模農家は、農機が全壊した場合に離農を選択せざるを得ず、厳しい状況が続く。そんな中、後述する農機メーカー販売会社ではトラ・コン・田の荷動きが過去に例をみないほど台数ベースで大幅に伸長するといった動きもあった。4月および7月からの各農機メーカーによる製品値上げを見越した、いわゆる”駆け込み需要”のような動きも、今年前半に多少あった。度重なる値上げについて、購入する側はもとより、売る側からも「我々としてもこれ以上製品価格を上げてほしくない。農家に説明するのが大変だ」といった本音が漏れる。兼業・小規模の農家の離農に歯止めがかからない状況下で、各社は大規模法人向けに的を絞り、営業・実演活動を行う傾向にある。全農や各農機メーカーともに、農機のセルフメンテナンス研修に注力しており、農機の点検・整備の充実を図っている。農機更新の難しい農家に、少しでも営農を続けてほしいという想いだ。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
担い手の更新が増加/岡山県特集・各社の対応 |
|
| |
|
|
| |
中四国クボタは、管内における農機需要が今年3月頃から高まり出した。拠点で開催した展示会では例年に比べて若い担い手の参加が目立ち、展示会での売上げも昨年に比べて大きく伸ばした。岡山営業部長の伊藤生希氏は「昨年の稲刈りが終わった時期に玄米低温貯蔵庫のキャンペーンを張ったところ、これが、すごく売れた」と話す。県の中・南部ではアグリロボ田植機「NW80SA(8条植え)」4台と、アグリロボトラクタ「MR1000H(100馬力)」1台が売れるなど、大型自動運転農機を導入する機運が高まっている。この背景には、昨年来の米価の上昇が少なからず影響している。飼料用米の生産から主食用米の生産に舵を切る農家もいるようだ。2025年1〜5月の本機(トラ・コン・田)の荷動きは前年同時期に比べてトラクタは微増、田植機、コンバインは大きく伸ばした。トラクタは60馬力、田植機は6条植え、コンバインは4、5、6条刈といったクラスが管内の主流となっている。全体の売上げは前年比127%で推移した。KSASの入会状況は岡山県で210軒(6月27日時点)、中国地方では一番の入会状況となっている。RTK基地局は津山東部、蒜山、岡山、邑久の4営業所に設置。農家からは「特に田植機の自動操舵で効果がある」と好評を博している。状況をみながら、同社は基地局をあと1カ所増設することを検討している。イベントは10月の末頃にスーパーマーケット「PLANT-5鏡野店」の駐車場にて大展示会を開催する予定。同会では大規模担い手に向けてクボタ製品をアピールしていく。営業面では整備工賃が全体の売上げのなかでも大きなウエートを占めており「農閑期に農機の整備をいかに徹底していただくか、これが肝となる。昨今の若い担い手は休日を農作業以外で費やすことが多い。従って日頃からの整備を徹底しておけば、お客様も我々も安心できる」と力を込める。ヤンマーアグリジャパン中四国支社は管内の動きについて、昨年来の米価の高止まりの影響もあり、大規模担い手による農機更新が増えている。一方、1町歩未満の小規模、3町歩未満の中規農家については引き続き厳しい状況にあり、農機の更新が後回しになる傾向である。2024年度(24年4月〜25年3月)の主要3機種の荷動きは、前年度に比べてトラクタは前年並み、田植機は微減、コンバインは微増であった。県内の総農家数の約45%が自給的農家という構成で、田植機の売上げを少なからず牽引してきたこの層の離農が続くなか、田植機はやや苦戦した。トラクタは県北で25馬力、県南では40〜50馬力、田植機は6、8条植え、コンバインは4条刈といったクラスがボリュームゾーンとなっている。岡山事務所の田上靖浩エリアマネージャーは「管内の自給的農家は農機の更新ができなくなると離農して田んぼを売るという事例が非常に多くなったと感じる。しかし売った田んぼは維持するのが難しく、その結果、耕作放棄地が点在する。この状況下では離農を踏みとどまる当該農家層と大規模農家のお客様をしっかりと維持せねばならない」と話す。実演は新製品のトラクタ「YT225Aリミテッド仕様(25馬力)」に注力、各種作業機を付けて展開している。現在はこの新製品のほか、セル仕様の管理機、草刈機を軸に提案を行っている。セル仕様となったラジコン草刈機「YW500RC」はその操作性の良さで管理機とともに好評を博しており、その他の草刈り関連製品を含め、堅調な荷動きをみせている。田上マネージャーは「今後もヤンマー製品およびスマート農機による省力・省エネの実現を目指したい。お客様の資金計画に沿ったファイナンスプランなども用意しているので、営農全般、お気軽にご相談いただきたい。また、時期前後の修理・整備の体制を充実させ、農繁期にお客様の手を止めず、今後も選ばれる会社であるよう心掛けたい」と力を込めた。ISEKI Japan中四国カンパニーのこれまでの動きについては、2025年3月以降から主要3機種の荷動きが例年以上に活発化した。特に田植機とコンバインは昨年の倍ほどの荷動きとなった。岡山営業部の小林純一次長は「2月頃まで苦戦したが、1〜6月をみると、全機種ともに前年同時期と比べて台数・金額ベースで飛躍的に伸びた」と力を込める。同社の岡山営業部では毎年3月中旬の3日間、「スプリングフェア」を同営業部の敷地内で開催していた。しかし今年は県下に点在する顧客を考慮し、拠点ごとにイベントを開催。地の利を活かしたこれらの催しが地域の農家を動かし、農機更新の機運を高めた。小林次長は「7月の製品価格改定を睨み、前述のイベントを含め、5月以降の値上げに係る『告知チラシ』を全顧客に配る動きに注力した。これらの地道な取り組みも大幅な売上げをみせた要因かと思う。一方、7〜8月は踏ん張りどころになると予測する。来る11月には岡山営業部に集約した『農家とヰセキの秋祭り』を開催するので、ここでしっかりと拡販したい」と話す。トラクタは25〜30馬力、田植機は4条植え、コンバインは4条刈といったクラスが主流となっている。そして管内におけるこれまでの農機更新は台数を大幅に伸ばしているのが特筆だ。小泉道也部長はこれまでを振り返り、「私としては各営業所の所長自身が自発的に企画・立案・実行できる環境づくりに専念した。これに呼応する形で各所長は緻密な企画を立ち上げ、獅子奮迅の働きをした。上期の瞠目に値する販売実績はこの流れによるものと考える」とし、「近年まれにみるほど個人農家による農機更新が際立ち、とても印象深い」と総括した。作業機および草刈り関連機も、メーカー各社との同行推進や実演会を着々と行い、その結果、これら商品も堅調な売れ行きをみせる。7月11日には自動操舵装置、作業機、草刈機のメーカーを岡山営業部に招聘し勉強会を実施。特に若手社員を中心に、今後の実演会で農家への提案がスムーズにできるよう見聞を広めた。三菱農機販売西日本支社は、昨年来の米価の高止まりが続くなか、管内における生産者の高齢化と後継者不足、離農といった課題が常態化している。7月は三菱マヒンドラ農機製品の価格改定を行ったものの、いわゆる「駆け込み需要」のような動きは過去に比べて少なかった。農機製品はもとより物価高が続くなか、管内では中古農機の需要が非常に高まっている。しかし供給が追いつかない状況だ。岡山支店の正金宗一郎支店長は「特に中古トラクタ(20〜30馬力帯)の引き合いが多い。希望されるトラクタがない場合は、それに類似の実演機や新品を一度試乗していただくことを心掛けている。もっとも購入の動機が中古価格のため、なかなか難しい」と話す。同社の主要3機種における2024年度(24年4月〜25年3月)の販売実績は、前年度に比べてトラクタおよびコンバインは減、田植機は伸長した。モデルチェンジ前のトラクタ「GSシリーズ(18〜25馬力)」の拡販に注力した結果、23年度は大きな売上げをみせた。この反動からモデルチェンジした「XSシリーズ(18〜25馬力)」の販売に苦戦した。田植機は業界最速の植え付けスピードを誇る「XPSシリーズ(6、8条植え)が好調な売れ行きをみせ、紙マルチ田植機「LKE60AD(6条植え)」、ペースト施肥田植機「LE50〜80AD」も売上げを牽引した。ペースト施肥田植機について三菱マヒンドラ農機は、2023年から全国規模で地道に実証試験を重ねており、導入した生産者からは「雨天でも田植えができ、一発施肥で生育と食味が良くなる」と好評を博している。今後について正金支店長は「農家の高齢化が進むなか、広大な水田での作業は負担が大きい。この課題解決のため、加えて時短作業を実現するために、三菱の中〜大型トラクタ、これに付けるKUSANAGI(ディスクハロー)、高性能コンバイン、そして高速田植機のXPSシリーズが開発された。これら農機を軸に、三菱製品の拡販に取り組みたい」と力を込める。倉敷河上農機は今年2月14日に創業100周年を迎えた。同日の午後から倉敷市内のホテルにて関係各社を招待し、記念式典を執り行った。年度開始月の2月から6月における主要3機種の販売実績は、2024年の同時期と比べて3機種ともに100%を超え、伸長した。特に田植機は台数ベースで2桁増の売れ行きをみせ、好調に推移した。同社は2月から5月にかけて「100周年記念特別セール」と銘打った紙面展示会をDMで打ち出し、紙面でラインアップした農機の販売状況を同社HPと連動させるなど工夫を凝らした。これが功を奏し、特に実演機や在庫品(今後に旧型となるトラクタなど)の荷動きが活発化、売上げを伸ばした。管内ではトラクタは30馬力前後(大規模担い手は60馬力以上)、田植機は4条植え、コンバインは3条刈といったクラスが主流となっている。山部社長は「コンバインは2条刈が大分減った。田植機は主に若手農家が直進キープ機能付きのものを求める傾向にある。笠岡市内の干拓地にある畑地で後付けの自動操舵装置の活用が増えている」と話す。7月25〜26日の両日はコンベックス岡山の中展示会場にて「クボタ農業応援!2025大商談会」を開催。農機販売のほか、農機の補助事業の講習会、コンバインのメンテナンス研修会を行った。また、昨年に続き、トラクタが転倒する角度を体感できるコーナーを設けて、シートベルト着用による安全運転を啓発し、来場者の耳目を集めた。山部社長は今期の見通しについて「現時点では米価が高止まりしているため、農機市場は良い状況かと思う。これに乗じて農機の更新をしっかり加速させたい」とし、「おかげさまで弊社は創業100周年を迎えることができた。これもひとえに担当地域の農家の皆様、各農機メーカー様のお力添えによるもの。引き続き、農業者の良きパートナーとして、安全な農機とこれに関連するサービスを提供し、地域農業の発展に貢献したい」と思いを新たにしている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
組合員との交流密に/岡山県特集・商組の動き |
|
| |
|
|
| |
岡山県農業機械商業協同組合(53組合員)は、農家のみならず組合員の高齢化を背景に、農機需要の減少に歯止めがかからない状況となっている。昨年来の米価の高止まりによる恩恵は、一部の大規模米農家にもたらされたものの、厳しい状況に変わりはない。自身も農家である事務局長の石原靖久氏は「離農という状況がいかに深刻か。私の住む農村(赤磐市東部)では用水路の清掃や溜池の管理といった重労働を伴うインフラ整備は、私を含めて5人ほどで行っている。ひと昔前は30〜40人でやっていた。いかに大変か分かるでしょう」と苦笑する。24年度(24年2月〜25年1月)の購買事業の実績は、計画目標額1億4100万円に対して1億3606万円(96%)。24年度は主にクローラと保冷庫、育苗土の荷動きが目立った。25年2〜5月は前年同時期に比べて112%で推移した。25年度の重点目標は、(1)定期訪問による組合員との情報交換(2)購買事業分量の確保(組合員別の目標設定と利用分量配当金の分配)(3)技能士の資格取得(講習会の開催)。「第41回中古農機モデルフェア」は昨年と同じく、紙面展示会の方式で組合のHPにて開催している(8月1〜31日)。石原事務局長は「昨今の酷暑と熱中症対策の強化(労働安全衛生規則の改正)、中古農機の品薄などを鑑み、屋外での開催はもはや難しい」とし、「今後も月1回は組合員を訪問し、情報交換をしながらコミュニケーションを図る」と話す。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
共同購入コンが好調/岡山県特集・JA全農岡山農機事務所 |
|
| |
|
|
| |
JA全農の岡山農機事務所は、これまでの動きについて、農機メーカー各社が今年から実施する製品価格の改定前の駆け込み需要の高まりや、米価の高止まりの影響などもあり、前年に比べて好調な滑り出しをみせる。なかでも各種のインプルメントや乾燥調製機の荷動きが目立った。トラ・コン・田における2024年度(24年4月〜25年3月)の供給実績は、前年度に比べて3機種ともに減となった。特にトラクタの供給に苦戦した。これは20〜26馬力帯のトラクタを導入する小規模農家への供給が、ままならなかったという背景もあった。難波所長は「コンバインは共同購入機(ヤンマーアグリ・YH448AEJU)がおかげさまで好評のなか、現時点で12台の受注がある。これ以外にも2台の契約がまとまりそうだ。また、他メーカーの低価格コンバインの荷動きも良い」と、生産コストを抑えるコンバイン供給の手応えを話す。主な活動については、県下のJA職員と生産者に向けて、農作業の安全に関する啓発活動および簡易にできるセルフメンテナンス研修を大々的に展開していく予定だ。セルフメンテナンスは前述の共同購入コンバインを使い、ヤンマーアグリジャパンの担当者が、JA職員および生産者に、自分で行える整備方法を解説していく。また、草刈機のメーカーと組み、果樹の生産者を対象にした草刈機、スピードスプレヤー、高所作業機の使用説明および安全講習、簡易な清掃・整備の研修も行う予定である。今期の見通しについて「今年度は良いスタートが切れた。しかし、後半がどうなるか。米価の動向は供給実績につながる大きな要因の1つになるだろう」と難波所長は展望。同事務所の守安俊之氏は「これから各JAが開催する展示会で、組合員がどう反応するか。米価を注視しながら秋商戦にしっかりと備えたい」と力を込める。11月28〜29日は最上稲荷で恒例の「農機フェア2025」を開催し、共同購入機をはじめとして、多様な農機をアピールする構えだ。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
林業活性化に向けてリード役担う/林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
林業の現場で林業機械が果たす役割は年々大きくなっている。林業事業体の期待も強い。素材生産でのハーベスタ、プロセッサなどの伐倒作業機械はもちろん、架線用での油圧集材機や最新機能を備えた架線式グラップルなどの導入が進み、高い作業性をいかんなく発揮し、期待に応えている。生産性向上はもちろん、労働負担の軽減・省力化、就労条件の改善、安全作業の実現など様々な役割を果たしており、林業の活性化の牽引役を担っている。特に最近では、遠隔操作や自動化、ICT、IoTさらにはAI搭載といったようなハイスペックな先進機種も登場し、機械化林業を新たなステージへと導いている。今週はそんな林業機械の現状を開発・実証、現場での導入事例や研究成果などを交えてフォローした。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
林野庁7年度事業の機械開発課題/林業機械特集 |
|
| |
|
|
| |
林野庁は7月24日、「令和7年度林業機械・木質系新素材の開発・実証に関する林野庁補助事業の実施事業者及び取組概要について」まとめ、公表した。このうち7年度の当初予算である「林業デジタル・イノベーション総合対策」のうち「戦略的技術開発・実証事業」で進められる「自動運転フォワーダの実用化に向けた多対多コントロールシステム等の開発」(実施主体=代表・パナソニックアドバンストテクノロジー、共同・諸岡、国際電気通信基礎技術研究所、国立研究開発法人森林研究・整備機構、東京農工大学)と「急傾斜地に対応した遠隔操作式植栽機械の開発」(実施主体=松本システムエンジニアリング)の2課題の開発・実証内容をみる。【自動運転フォワーダの実用化に向けた多対多コントロールシステム等の開発】開発目標は、先山・土場等の複数個所から複数台のフォワーダに自動運転表示や遠隔操作を行うための多対多コントロールシステムや、異常発生時のリカバリー機能の開発により、実用化に必要なユーザーインターフェイスを構築する、を掲げる。開発・実証内容は次の3点。(1)多対多コントロールシステムの開発=自動運転指示や目視内遠隔操作の機能を実装し、予防安全機能や遠隔監視機能と連携した多対多コントロールシステムを開発する。(2)異常発生時のリカバリー機能の開発=自動運転時のフォワーダに、外的要因による運行不可能状態やセンサー異常による車両走行停止等が発生した際に、オペレータに通報しリカバリー方法をガイドする機能を開発する。(3)林内通信システムの運用性向上技術の開発=林内通信システムの性能向上、省電力での運用を可能とする機能の実装のために、構成機器の見直しや制御の最適化を行う。林野庁では、期待される事業効果に、自動運転フォワーダの現場実装を可能とすることにより、丸太運搬時の労働災害リスクを回避し、林業の労働生産性を向上させることをあげる。【急傾斜地に対応した遠隔操作式植栽機械の開発】開発の目的は、植え穴の掘削から植え付け、側方転圧までの作業ができる植栽用アタッチメントとともに、アタッチメントを装着する建設機械には、スタビライザー装置、アシストウインチ、遠隔操作機能、立体視映像システムを搭載し、急傾斜地でも安全に作業できる機械を作ること。開発・実証内容は、次の3点。(1)植栽用アタッチメントの開発=植え穴の掘削、植え付け、側方転圧までの一連の作業を苗木1本当たり約30秒で行うアタッチメントを開発する。150〜300ccのコンテナ苗に対応する。(2)急傾斜地への対応=35度の傾斜地でも鉛直に植栽できるよう、アタッチメントを装着する建設機械に後付けで装着可能な、スタビライザー装置とアシストウインチを開発する。(3)遠隔操作への対応=遠隔操作システム、立体視映像システムを装備することにより、キャビン内と同じ感覚で遠隔操作できる機械を開発する。期待される事業効果について林野庁は「これまで人力で実施されていた植栽作業を機械化することにより軽労化を図るとともに、遠隔操作を可能とすることにより急傾斜地での作業の安全性向上」をあげる。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
無人で丸太を積載/林業機械特集・森林総研の研究成果 |
|
| |
|
|
| |
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所が先に発行した令和7年版研究成果選集2025では、林業機械に関連した研究成果として、「全面機械地拵えでトドマツの下刈り回数を大幅に削減」と「ロボット技術を活用して荷台への丸太積載を無人で行うことに成功」の2つのを取り上げ、紹介している。「全面機械地拵えでトドマツの下刈り回数を大幅に削減」は、森林総研植物生態研究領域の原山尚徳氏と北海道支所の菅井徹人、津山幾太郎、北尾光俊の3氏が取り組んだ研究。トドマツの造林地で大型機械による全面地拵えを行った結果、ササの再生が抑制され、下刈り1回でも苗木は良好に生育し、従来の筋状施業に比べ、地拵え+下刈りの費用を最大40%削減できることが分かった。研究では、大型機械による「クラッシャ地拵え」や「バケット地拵え」を造林地の全面に適用することで、ササの再生を抑えて下刈り回数を減らせるかを試験した。植栽後4年間は下刈りをせずに放置したが、ササの再生は抑えられ、代わりに落葉樹の植生が繁茂したという。特に施業費を比較すると、地拵えと1回当たりの下刈り費用は筋状施業の方が安価だが、全面機械地拵えは下刈り回数を大幅に減らせる。トドマツ再造林のコスト削減に有効であることが分かる、としている。一方で植栽場所を機械走行する際には、天候や地形、走行回数を考慮し、過度な踏み固めを避けることが重要、と注意している。一方の「ロボット技術を活用して荷台への丸太積載を無人で行うことに成功」は、同研究所林業工学研究の伊藤崇之、有水賢吾、中込広幸、猪俣雄太の4氏とモリトウの鬼武正行氏が担当した。研究では、レーザー計測技術や人工知能(AI)による画像処理技術、ロボット制御技術を統合し、丸太を荷台に自動で積載する制御システムを開発。グラップルローダに対し電子制御が可能なように、機械の各関節に角度センサーを取り付けるとともに、関節を駆動する油圧シリンダーや油圧モーターを電気信号で制御するための電磁比例弁を取り付けた。また、カメラ画像から深層学習を用いて丸太を検出する技術とグラップルに取り付けた2DLiDARでグラップル直下の丸太位置やグラップル爪先の挿入位置を検出する技術等を開発し、機体に取り付けた。現場での検証では、開発した機械で丸太の自動積載が可能であることを確認するために群馬県内の森林で実際に作業を実施。一連の動作を自動で行うことができることを確認。今後は、成功率と動作速度の向上を目指して研究を続けていく、としている。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
国産材供給量2009万立方m/林業機械特集・6年木材統計から |
|
| |
|
|
| |
既報の通り、農林水産省大臣官房統計部が7月29日に公表した「令和6年木材統計」によると、素材供給量のうち、国産材は2009万立方mで前年に比べて55万7000立方m減少、輸入材は271万4000立方mで同30万8000立方m減少と前年実績を下回った。前年対比で国産材2.7%減、輸入材10.2%減となった。これにより素材供給量に占める国産材の割合は88.1%となり、前年に比べて0.9ポイント上昇した。上の表は、都道府県別の国産材の需要量をとりまとめたもの。各都道府県別の素材需要量は、製材工場等への工場入荷量であり、特に同調査においては山元段階の調査が困難であることから、工場入荷量の入荷元の都道府県ごとに集計したものをもって当該都道府県における素材生産量としている。このため、都道府県の素材需要量と素材生産量は一致しない場合があるが、国産材の場合、2009万立方mの内訳は、自県材1432万6000立方mに対して他県材576万4000立方m。需要部門別国産材の素材生産量は、製材用1195万8000立方m(構成比59.5%)、合板等用426万2000立方m(同21.2%)、木材チップ用380万立方m(同19.3%)。また、同統計では、普通合板及び特殊合板、LVL、木材チップ、集成材及びCLTの生産量をまとめている。令和6年の実績は以下の通り。普通合板生産量は、250万6000立方mで前年に比べ2万6000立方m減少、特殊合板は48万7000立方mで同3万2000立方m減少。対前年比は前者が99.0%、後者が93.8%となった。LVLの生産量は20万8000立方mで前年に比べ2万立方m減少。対前年比91.2%。木材チップ生産量は448万8000tで前年に比べ77万2000t減少、対前年比85.3%。これに対して集成材生産量は175万1000立方mで前年に比べ7万6000立方m、CLT生産量も2万1000立方mで同3000立方mとそれぞれ増加した。対前年比では集成材104.5%、CLT116.7%と伸長。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
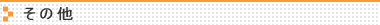 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
稲作問題の本質を探る/浦秀俊氏緊急寄稿 |
|
| |
|
|
| |
米価格の高騰が昨年より大きな問題となっている。生産量の不足、流通での滞留、販売業者や消費者の買い溜め等、種々の原因が議論されているが本質的な原因を探るべきである。そこで日本で販売されている短粒米(ジャポニカ種)に近い中粒種(カルローズ等)を年間168.5万t生産するカリフォルニア州に着目し、その農法の違いや経営状況を米国農務省(USDA)の公表データを基に分析した。【カリフォルニア州の稲作】米は麦、大豆やコーンといった穀類として扱われる。1920年代頃に南部州(アーカンソーやルイジアナ他)で長粒米の商業稲作が始まった。カリフォルニア州では中粒米を主体に作付けが拡大してきた。2022年のUSDA農業センサスによれば、全米経営体数はわずか3824で、収穫面積が92万ha(日本:約130万ha)、収穫量が777万tと日本とほぼ同量で大半が長粒米。2025年1月の調査報告書によれば、日本米に近い短粒米(ジャポニカ種)は全米の98%(12.1万t)、中粒米(カルローズ等)は65.9%(183.7万t)がカリフォルニア州で収穫されている。稲の栽培には粘土質の土壌と大量の灌漑水が必要であり、サクラメント川流域の7郡(サクラメント、シュッター、ユバ、コルサ、グレン、ビュート、サンウォキン)に集中。耕起はプラウ、砕土はディスクを使うため200HP以上のブルドーザーやクローラトラクタが牽引に使われる。平均収穫面積は137haで運営費はギリギリカバーできているが、償却費や固定費を加えた全算入生産費では平均耕作面積以下の経営体だと赤字経営である。【日米の稲作農家の比較(2023年産米)】ミシシッピー川流域の稲作面積は全米の約85%を占めるが、単価の低い長粒米が主流でしかも経営規模が平均240haと大きいので、中粒米が主流のカリフォルニア州の2023年産米データ(カリフォルニア NASS Crop Production 2024 Summary(January 2025))を使用した。農薬と地代以外の多くの費目でカリフォルニアが日本より安いことがわかる。特に種籾・播種費は日本の57%、肥料は62%、総労働費は25%とかなり安い。カリフォルニア州の時間賃金は21.50ドルと農林水産省の1500円より高いにもかかわらず労働費が少ないのは高速作業の効果である。日本は、米国人からカタツムリに例えられるロータリー耕うん、育苗や田植え作業が労働時間を延ばし労働費を押し上げている。日本の個別経営体のデータも参考に並べたが、比較にならない程の金額であり、やはりこれまでのやり方に何か問題があると考えざるを得ない。米国では採算が成り立たない規模の稲作農家は年々自然淘汰され、2022年現在で僅か3824の経営体(日本‥57万)に減少している。日本では3ha以下の稲作農家の大半が農業収入で赤字となっているが、農家としてまだ存続しているのは農外収入のおかげである。戦後の農地解放で小作農民を小規模地主に仕立て上げ、長年にわたって支援と保護を続けてきた政治の弊害であることは否めない。表2は表1の数値を用いて損益計算したもので、137haの経営体でも全算入生産費6万9509円を出荷額6万8813円でカバーできず696円の赤字である。これに対して日本の組織法人経営体では出荷額が10a当たり10万9501円(1万3038円/60kg)と高額なおかげで、全算入生産費が9万9462円(1.6倍)でも1万39円(9.6%)の利益が出ている。さらに「経営所得安定対策交付金」3414円が加算されるので、補助金を含む農業所得は10a当たり1万3453円となり、出荷額に対する利益率は12.3%になる。カリフォルニアの反収は952kg(組織法人経営体:503kg)で日本の2倍近く、60kg当たりの出荷金額は4356円(組織法人経営体‥1万3038円)と日本の3分の1であり如何に日本の値が高く付けられているかがわかる。これは個人経営体56万戸の赤字体質を補うためとしか考えられない。筆者が2000年に住んでいたジョージア州マリエッタの日本食材店のカリフォルニア産中粒米(錦)の今年の小売値が5ポンド(2.3kg)13.99ドル、コシヒカリが4.4ポンド(2kg)16.99ドル、コシヒカリ系プレミアム米(TAMAKI GOLD)が4.4ポンド19.99ドルで販売されており、農家出荷額が日本の30%であることを考えると流通マージンがかなり多いことがわかる。カリフォルニア米の食味は粘り気が少なくさっぱりした食感で、おにぎりや寿しに適した日本晴れに近い味だった記憶がある。【進化する米国の直播方式】稲の反収が高く、生産性が高いのは多収穫品種と高速農法によるところが大きく、生産性を上げるため品種改良と直播技術の改善を続けてきたからである。カリフォルニア州での聞き取り調査(2018年)で次の点がわかった。今まではディスクプラウをブルドーザーで牽引していたが、近年ゴムクローラトラクタとチゼルプラウ(不耕起農法)に置き換わりつつある。チゼルプラウに取り付けたガス圧入機で肥料を地中に圧入する省エネ農法である。稲の栽培に適した粘土質の田では水分が多く機械が入り難いため、サクラメント川流域の米作地帯では、グレンドリル(条播機)を用いた乾田直播から航空機による播種や薬剤散布となり、主流だ。稲が列状に根付くよう均平整地後にK型ローラーで152mm幅の溝をつけ、水を張った後に発芽籾を撒き水抜きすれば籾が溝の底に列状に集まる。米国の土地分割は2マイル(3.2km)四方が一般的で正方形の区画を4、8、16等分し長方形区画にしている。往復飛行による播種では長方形区画(600〜800m×200m)を横に並べた区画配置が効率的なため多い。散布幅15m、時速160kmで作業すれば旋回と種籾補給時間を入れても約1時間で100〜120haの作業ができる。航空散布用の小型機用滑走路が水田地帯に常設されている。【課題解決に向けて】国内稲作を守るためには、米の輸入阻止でなく安く作る米国のアイデアを輸入し生産費を下げ国際競争力のある米を生産することである。近代稲作の先進国、米国を手本に全ての国民に公平・公正な「生産費(出荷単価)の低減」及び「プロ農家支援」対策が必要である。農業構造改善に関して“規模拡大”とか“増産”を唱えるが、損益分岐点が極端に高い現状では赤字額をさらに増やすことになりかねない。本質的な問題である低い限界利益率を上げるためには(1)高収量の稲を開発することと(2)労働生産性を上げることに尽きる。高速作業で労働時間を短くすれば時間当たりの相対賃金が上がり労働生産性は上がる。時間を掛けて安い時間給で働くのではなく、短い時間で多くのアウトプットを得て高い時間給を得るやり方が米国の「高速耕うん+航空播種」である。カリフォルニアは日本の10倍の速度で作業をするがそれでも経営規模が小さいと赤字経営になっている現状を踏まえ、面積規模に見合った支援が必要である。米国の支援策の柱はあくまでも平年収穫量に基づく基準出荷額に対して、実出荷額が天災や市場異変で大きく下がった場合にその差額を補填するもので、農家の経常赤字を直接補償するものではない。米国の連邦支給は種々あるが小規模の副業的農家の恒常的な赤字改善を目的としていない点で日本と違い国民に平等で公平な施策と言える。日本も米国を見習い区画統合や面積拡大を進め出荷単価を米国並みに下げる努力をしている稲作事業者をもっと支援すべきである。中山間地の土地保全型の小規模個人経営体に対しては「農家」としての補助でなく「自然環境・国土保全」に対する貢献度に応じた礼金として支払うのが望ましい。アメリカのカリフォルニア大学のデービス校では日本の3割から5割低い生産コストをさらに下げる研究を続けている。日本でも埼玉の農業法人がグレンドリルを用いた節水直播方式で75円/kgを目指しているが、「食料・農業・農村基本計画」での“水田作の技術体系の将来像”では「ドローンを用いた播種を2040年に実現」と15年も先に考えている。米価低減が喫緊の課題であるにも拘わらずそのスピード感覚の鈍さに呆れる。せめて5年先の2030年に今のアメリカ並み(72.6円/kg)の生産費まで下げる施策がほしい。繰り返しとなるが、無人運転や自動運転等の機械費をさらに上げるスマート化より、機械費を上げずに少時間作業につながる農法と農業機械の研究開発に予算を割くべきである。
|
|
| |
|ホームに戻る| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
